初めて収益物件を探すとき、「本当に府中でいいのか」と迷う人は少なくありません。都心ほど賑わってはいないものの、府中は再開発が進み人口も底堅く推移しています。さらに賃貸需要が安定しているため、適切な物件を選べば長期にわたり堅実な家賃収入が期待できます。本記事では、府中で収益物件を購入するときに押さえておきたい立地の選び方、資金計画、制度活用までを具体的に解説します。読み終えたころには、自分に合った投資戦略が描けるはずです。
府中が投資家に選ばれる理由
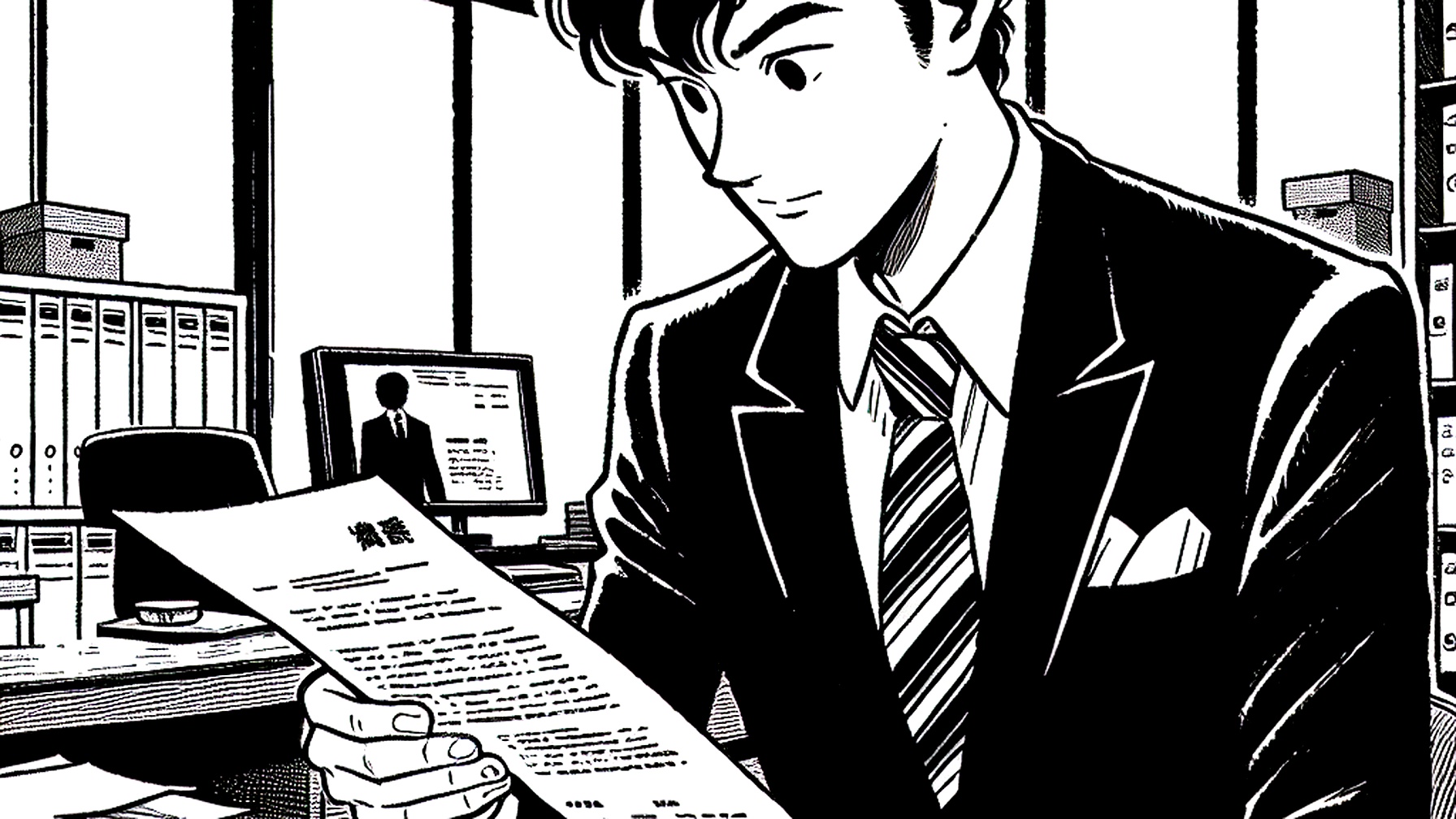
重要なのは、府中市が示す安定した人口動向と交通利便性です。東京都都市整備局の推計によると、府中市の総人口は2035年まで微増傾向にあり、若年層の転入も目立ちます。この背景には、京王線とJR南武線の二本立ての交通網が大きく寄与しています。新宿や渋谷に30分以内で到達できるため、都心勤務の単身者やファミリーの居住ニーズが継続的に見込めるのです。
一方で、同じ多摩エリアでも日野市や八王子市と比べると、府中市の空室率は3〜4ポイント低い水準で推移しています。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の2024年度調査では、府中市のワンルーム平均空室率は6.8%にとどまり、都心五区の7.1%と肩を並べる結果でした。賃料水準も安定しており、供給過多のリスクがまだ小さい点が投資家を惹きつけています。
また府中駅前では2024年に完成した大型複合施設「ル・シーニュ」が賑わいを創出し、飲食・サービス業の雇用が拡大しました。雇用の拡大はそのまま転入増につながり、賃貸需要を底支えします。このように、都市機能と住宅需要がバランスよく成長している点が、府中を収益物件の候補地として際立たせているのです。
収益物件のタイプと収支シミュレーション
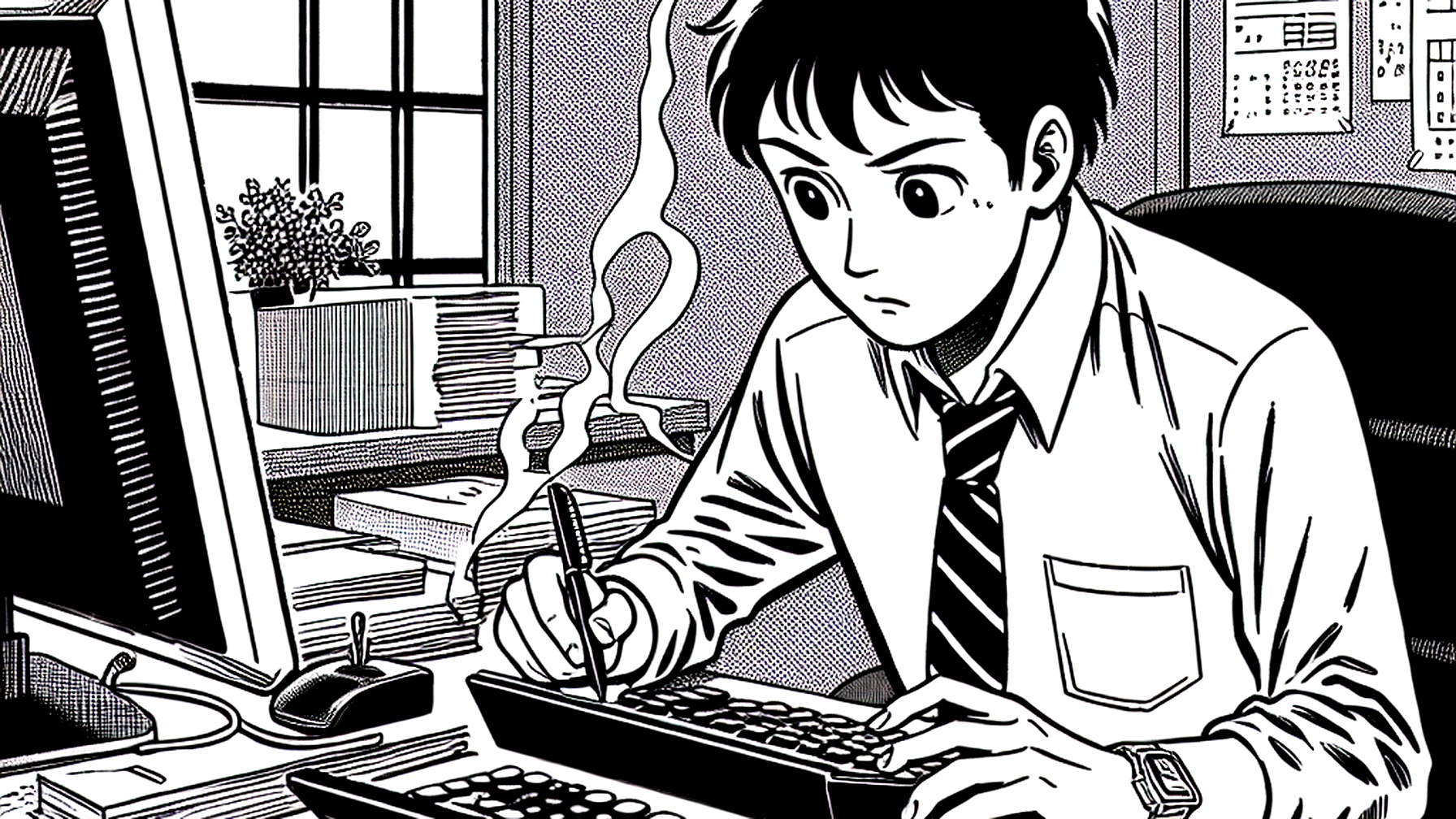
まず押さえておきたいのは、物件タイプごとの収支構造です。ワンルームマンションは初期投資を抑えやすい反面、空室が出ると収入がゼロになるため、複数戸の購入でリスク分散する戦略が主流です。ファミリー向けアパートは一戸当たり家賃が高く、長期入居が期待できるものの、修繕費が嵩みやすい点に注意が必要です。
収支シミュレーションでは、家賃下落率1%/年、空室率8%、修繕積立1,200円/㎡・年という保守的な前提を必ず組み込みましょう。東京都住宅政策本部の家賃指標によれば、府中市の平均家賃下落は過去10年間で年0.6%にとどまっています。つまり年1%を見込んでおけば、多少の景気後退でも耐えられる計算になります。
たとえば築10年、20㎡ワンルームを1,300万円で購入し、家賃7万円、管理費8千円、修繕積立2千円の場合、実質利回りは約5.2%です。ここにローン金利1.7%、返済比率60%を当て込むと、月々のキャッシュフローは1万2千円前後に落ち着きます。この数字がプラス圏で維持できるかが、購入可否の最低ラインです。
さらに、出口戦略として10年後の売却価格を築20年平均の1,000万円と仮定し、内部収益率(IRR)を計算してみると約7%となります。IRRが5%を切るケースでは、より賃料が高い物件か、自己資金比率を上げる対策が求められます。数字で裏づけることが、感覚に頼らない投資判断につながるのです。
エリア分析で差をつける具体的な視点
ポイントは、同じ府中でも駅徒歩分数と標高差による賃料格差を見逃さないことです。京王線は各駅停車が多いため、快速停車駅の府中・中河原・分倍河原に需要が集中します。特に府中駅北口は再開発が一巡し、地価がこの3年で13%上昇しました。一方で、徒歩15分圏まで対象を広げると価格が2割下がることもあり、利回りを高められる余地が残っています。
また、多摩川に近い地域は水害リスクを懸念する入居者もいるため、ハザードマップのチェックは必須です。国土交通省の重ねるハザードマップでは、南町や是政で洪水浸水深2〜3mの想定が示されています。低リスクエリアと比べると賃料が月3千円程度安くなる傾向があり、保険料も高くなる点を加味すべきです。
加えて、大学キャンパスへのアクセスも単身需要を左右します。東京農工大学府中キャンパスへは分倍河原駅からバス7分ですが、2025年度に駅東口からのコミュニティサイクルが導入予定となり、利便性はさらに向上します。このような小さなインフラ改善が将来の賃料アップにつながる場面が多く、行政計画のチェックは欠かせません。
実は、小学校区もファミリー層の入居継続を決める大きな要因です。府中第五小学校区は児童数が増え続けており、PTA活動が活発なことで知られます。こうした学区プレミアムは平均家賃を月5千円押し上げるケースもあり、長期入居率を高める手助けになります。数字だけでなく、生活目線でのリサーチが高稼働につながるのです。
2025年度の融資環境と活用できる制度
実は、金融機関の融資姿勢は2023年を底に改善し、2025年度はフルローンが再び視野に入ってきました。日本銀行の「貸出動向アンケート」では、2025年4月時点で地方銀行の55%が「不動産投資向け貸出をやや拡大」と回答しています。特に自己居住用を兼ねる「オーナーチェンジ型住宅ローン」は金利1.2%台が登場し、返済負担を抑えやすい選択肢となっています。
一方で、投資専用ローンは自己資金10〜20%を求められるケースが主流になりつつあります。返済期間を35年に設定すると総返済額が膨らむため、繰上返済シミュレーションを事前に行い、金利上昇リスクに備えることが重要です。固定金利期間10年タイプを選び、11年目以降は3%まで上昇する保守シナリオで試算すると、利幅の薄い物件は赤字転落する可能性が浮き彫りになります。
制度面では、2025年度も「長期優良住宅化リフォーム推進事業」が継続され、賃貸アパートの大規模修繕に対し最大250万円の補助が受けられます。適用要件は耐震性と断熱性能を高める改修を行うことですが、補助額相当を差し引けば利回りが0.4ポイント向上する例もあります。補助対象工事は着工前に申請が必要なので、購入後すぐに工事計画を立てるとスムーズです。
さらに、東京都独自の「住宅太陽光サポート事業」は2025年度も継続予定です。10kW未満の太陽光パネル設置で1kWあたり10万円の補助が出るため、屋根付きアパートではランニングコストの削減につながります。売電収入よりも入居者向けに電力を供給し、光熱費を抑えるサービスを提供することで差別化を図る投資家も増えています。
成功事例から学ぶリスク管理のコツ
ポイントは、リスクを細分化して数値管理することです。筆者がサポートした30代会社員Aさんは、府中駅徒歩12分の木造アパート4戸を自己資金400万円で購入しました。毎月のキャッシュフローは当初1万5千円程度でしたが、購入直後に屋根防水工事を実施し、雨漏りリスクを事前に排除しました。その結果、追加費用はかかったものの、長期入居率が高まり12カ月連続満室を維持しています。
また、Bさんは分倍河原駅近くの区分マンションを2戸同時に取得し、家賃設定を周辺相場より1割高めに設定しました。高賃料でも埋まった理由は、無料Wi-FiやIoT鍵を導入して若年層のニーズを満たしたからです。導入費用は1戸当たり15万円でしたが、月々の家賃増加で1年半で回収できました。付加価値投資がリスクヘッジと収益アップを両立させた好例です。
一方で、失敗事例もあります。府中本町駅徒歩20分の築40年アパートをフルローンで購入したCさんは、購入後に給排水管の大規模修繕が必要となり、急遽300万円を負担する羽目になりました。建物診断を怠ったことが主因で、キャッシュフローは3年間マイナスが続いています。このケースから学べるのは、物件価格の安さだけで飛びつかず、事前のインスペクションと長期修繕計画を徹底する重要性です。
結論として、リスク管理の本質は「見える化」と「迅速な対策」です。空室率、修繕費、金利上昇などの主要リスクごとに年間上限額を設定し、四半期ごとに実績を比較する仕組みを作れば、不測の事態にも冷静に対応できます。逆に言えば、このプロセスを省くと、どんな好立地の収益物件でも失敗する可能性が高まります。
まとめ
本稿では、府中で収益物件を選ぶ際の市場動向、物件タイプごとの収支、エリア分析、融資環境、制度活用、そして成功事例までを網羅的に解説しました。府中は人口と賃貸需要が安定し、駅前再開発でさらなる成長が期待できるエリアです。ただし、立地の細かな差異や修繕リスクを見逃さない姿勢が不可欠になります。まずは自分の資金力とリスク許容度を明確にし、保守的なシミュレーションを作成してください。そのうえで、現地調査と制度活用を組み合わせれば、長期にわたり堅実なキャッシュフローを確保できるでしょう。
参考文献・出典
- 東京都都市整備局「東京都長期人口推計(2024年版)」 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「日管協短観2024年度」 – https://www.jpm.jp
- 東京都住宅政策本部「民間住宅賃料指標2024」 – https://www.metro.tokyo.lg.jp
- 日本銀行「貸出動向アンケート調査2025年4月」 – https://www.boj.or.jp
- 国土交通省「重ねるハザードマップ」 – https://disaportal.gsi.go.jp

