都会の築浅マンションに興味はあるものの、「本当に利益が出るのか」「表面利回りと実質利回りの差が分からない」と悩む人は多いものです。実際、毎月のローン返済や管理費を差し引くと、思ったより手残りが少ないという声もよく聞きます。本記事では、築浅物件の特徴とともに、投資判断の核心である実質利回りを丁寧に解説します。最後まで読むことで、初心者でも数字と物件の見方が身につき、将来の空室リスクを抑えながら安定収益を狙う方法が分かるはずです。
実質利回りとは何か
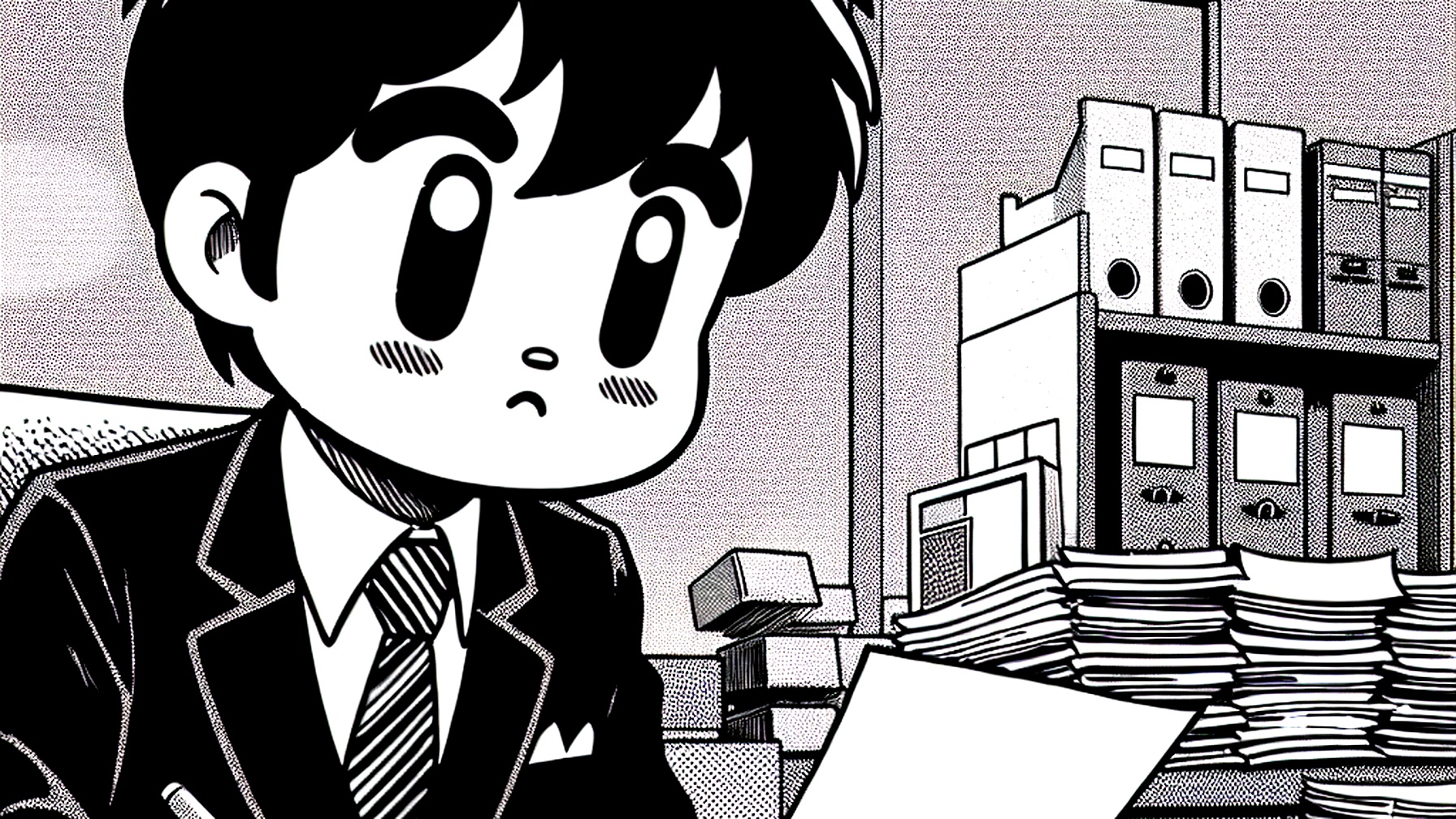
重要なのは、表面利回りと実質利回りを混同しないことです。表面利回りは年間家賃収入を物件価格で割った単純な指標にすぎません。一方で実質利回りは、管理費や修繕積立金、固定資産税、ローン金利など運用コストを控除した後の手取り収入をベースに計算します。つまり実際のキャッシュフローを示すため、投資の良し悪しを判断するにはこちらが不可欠です。
日本不動産研究所によると、2025年10月時点の東京23区ワンルームの平均表面利回りは4.2%です。しかし管理費や税金を差し引くと、実質では1.5〜2.5%に落ち込むケースも珍しくありません。数字の差が大きいほど、運用コストの重さを物語ります。したがって購入前には、必ず実質利回りでシミュレーションする習慣を付けましょう。
築浅マンションのメリットと落とし穴
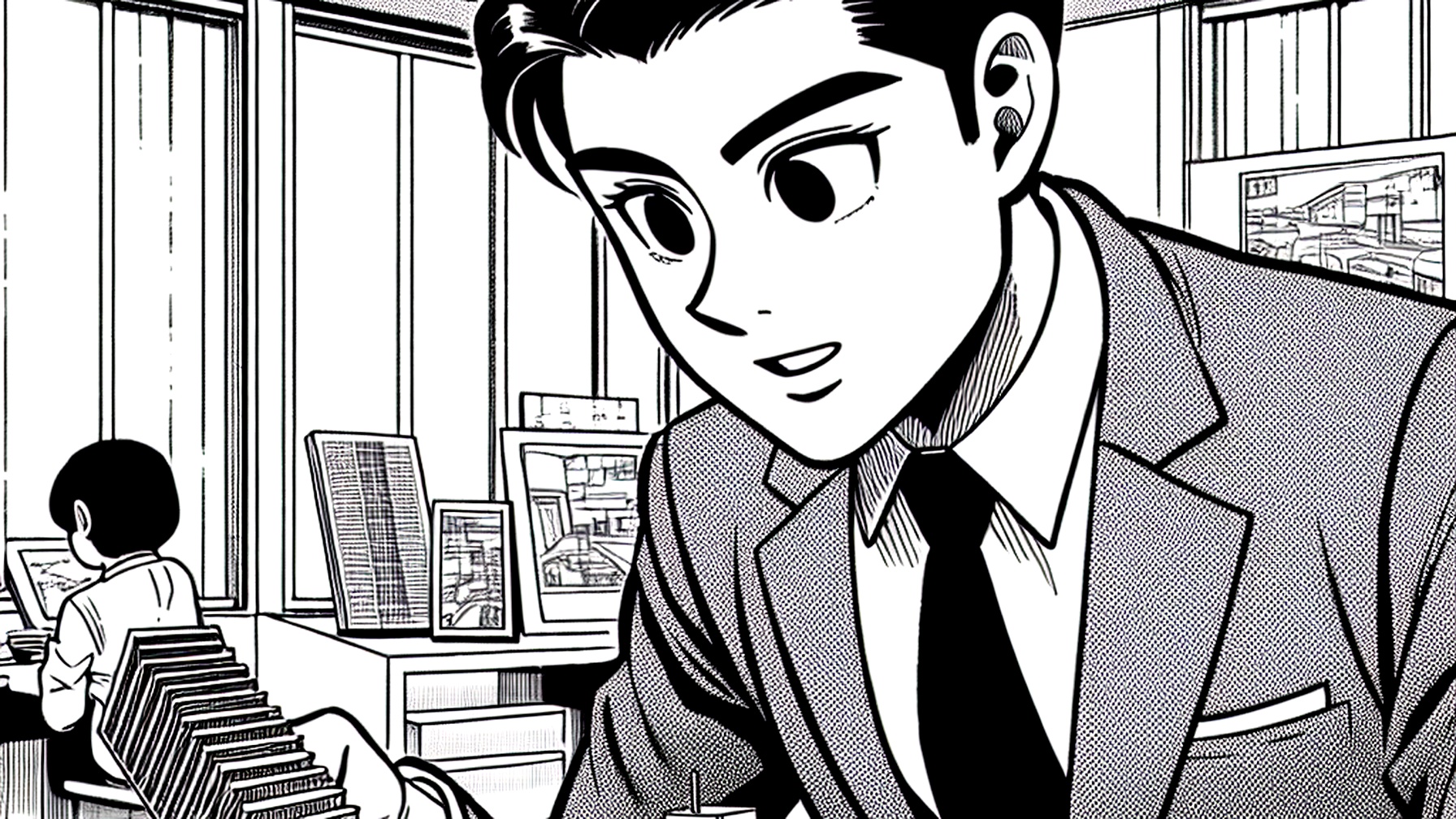
まず押さえておきたいのは、築浅マンションが設備トラブルの少なさという強力な武器を持つ点です。築5年以内なら給排水管や外壁はまだ健全で、突発的な修繕費が発生しにくくなります。また最新の耐震基準や断熱性能が評価され、入居者募集でも優位に立てることが多いです。結果として、空室期間を短縮できる確率が高まります。
一方で、購入価格が高いという弱点は見逃せません。不動産経済研究所のデータでは、2025年10月の東京23区新築マンション平均価格は7,580万円で前年比3.2%上昇しました。価格が高いほど、同じ家賃でも表面利回りは低下し、返済比率は上がります。また築浅物件でも、修繕積立金は年数とともに増額されるのが一般的です。将来的なコスト上昇を織り込み、長期シミュレーションを行う姿勢が欠かせません。
実質利回りを高める購入前のチェックポイント
ポイントは、購入時点で削れるコストを見抜くことにあります。まず金融機関選びで金利を0.3%下げると、3,000万円借入・35年返済の場合、総支払額は200万円以上縮まる試算になります。また仲介手数料や登記費用などの諸経費は総額で物件価格の6〜8%に達するため、交渉やキャンペーンを利用して1%でも減らすだけで、実質利回りが上向きます。
次に、家賃設定の妥当性を確認しましょう。周辺成約事例と比較し、500円でも高く設定すると長期空室につながる恐れがあります。逆に適正水準を守れば、入居付けにかかる広告費の増加や家賃交渉を避けられ、運用コストを抑制できます。さらに管理会社と契約する際は、サブリース(家賃保証)の手数料や更新料の有無を細かくチェックし、手取りを最大化できるプランを選ぶことが大切です。
運用中に実質利回りを守る管理術
実は、購入後の運用次第で実質利回りは大きく変動します。入居者募集を管理会社任せにせず、定期的に家賃相場を確認して適切なリフォームタイミングを判断する姿勢が必要です。築浅マンションでも、居室のクロスや水回りのコーキングに小さな劣化が出れば、入居者はシビアに見ています。早期に手を打つことで、家賃下落を防げるでしょう。
一方で、設備投資は費用対効果を吟味してください。たとえばインターネット無料化は月額1,500円程度で導入でき、家賃を2,000円上げられる事例もあります。年間では家賃アップ分がコストを上回り、実質利回りが向上します。こうした小さな改善を積み重ねることで、築年数による家賃低下を緩和し、長期的な収益安定につなげられるのです。
2025年度の税制と資金計画の基礎
基本的に、2025年度も不動産取得税や固定資産税の優遇措置は新築・築浅物件で続きます。新築から3年間は固定資産税が1/2になるため、初期のキャッシュフローを強化できます。ただし適用期限は取得後3年度分で終了するため、4年目以降の増税を資金計画に組み込むことが欠かせません。また住宅ローン控除は自己居住用が対象で、投資用ローンには適用されない点にも注意が必要です。
資金計画を立てる際は、家賃下落率1%・空室率10%・金利上昇1%という厳しめの前提でシミュレーションすることを勧めます。この条件でキャッシュフローが黒字なら、市場変動があっても破綻リスクは低いといえます。加えて、突発的な修繕費や再販コストに備え、年間家賃収入の10%を内部留保として積み立てる仕組みを作ると安心です。
まとめ
ここまで見てきたように、マンション投資で鍵を握るのは購入価格と運用コストを加味した実質利回りです。築浅物件は設備の新しさと空室リスクの低さが魅力ですが、価格の高さと将来の修繕積立金増額を忘れてはいけません。購入前に金利や諸経費を徹底的に抑え、運用中は小まめなリフォームと相場チェックで家賃を維持することが成功への近道です。今日紹介したシミュレーション手法と管理術を実践し、数字で判断する習慣を身につければ、市場環境が揺れても安定収益を確保できるでしょう。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 住宅局 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
- 東京都都市整備局 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 総務省 統計局 – https://www.stat.go.jp

