不動産投資を始めると、「築古アパートを建て替えるべきか」「REITに乗り換えるべきか」という悩みに必ず直面します。老朽化した物件を持ち続けるデメリットは理解しつつも、多額の建て替え費用や空室リスクを考えると決断が難しいものです。本記事では、現物不動産とREIT(不動産投資信託)の仕組みを比較しながら、建て替えに踏み切るタイミングや資金計画の立て方を解説します。初心者でも分かりやすい言葉でまとめていますので、今後の投資方針を整理する手掛かりにしてください。
REITとは何か、なぜ個人投資家に人気か
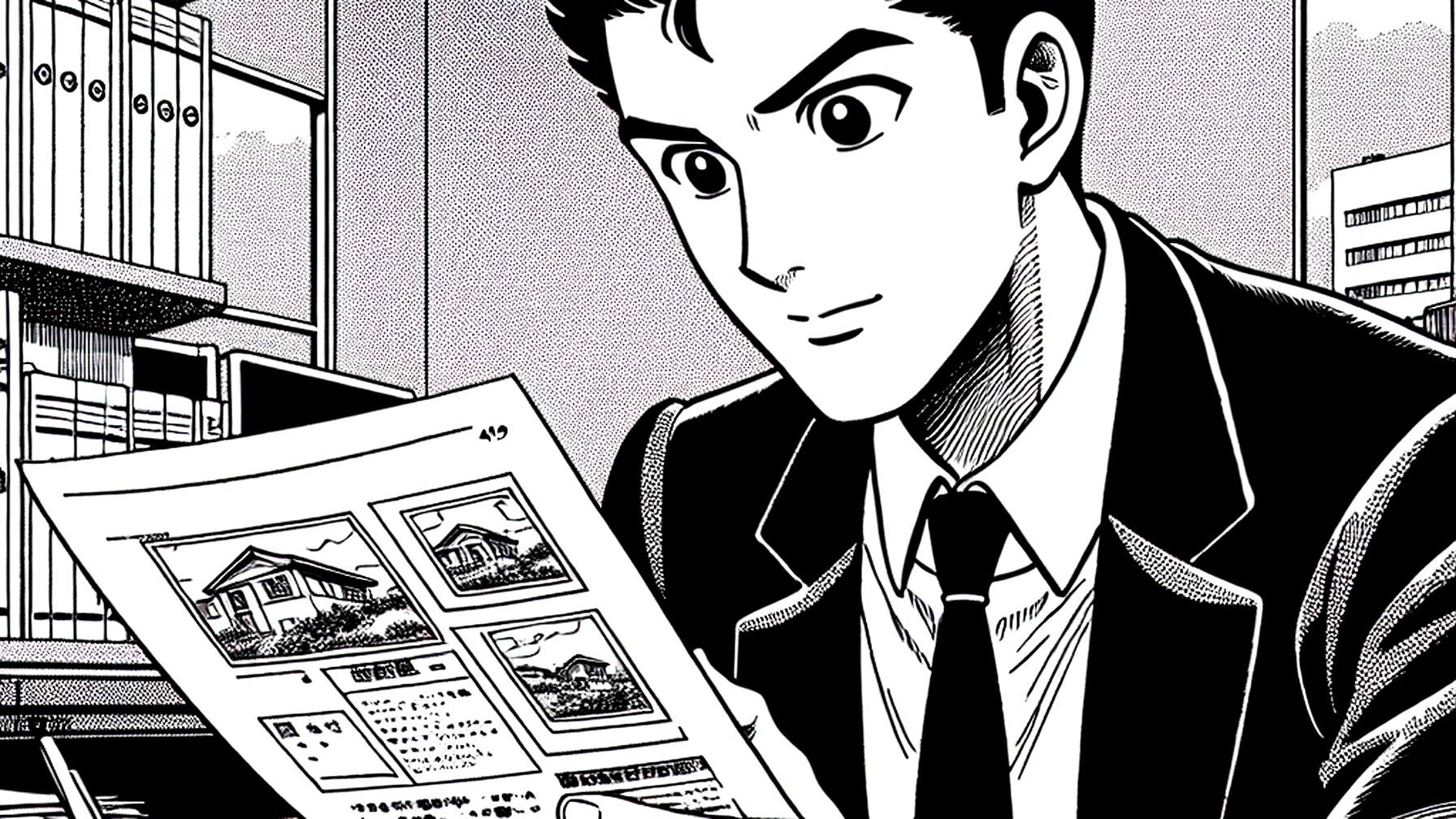
まず押さえておきたいのは、REITが不動産を小口化し、株式のように売買できる金融商品だという点です。東京証券取引所に上場しているため、1口数万円から投資可能で、分散効果を得やすい仕組みになっています。2025年10月時点で日本の上場REIT時価総額は約19兆円と、日本銀行の統計でも成長が続いていることが示されています。
REITの最大の魅力は、専門家チームが運用することで管理の手間がかからない点です。建物の修繕計画やテナント募集はアセットマネージャーが担い、投資家は配当として分配金を受け取ります。また流動性が高く、売りたいときに市場価格で換金できるため、現物不動産に比べて資金拘束が小さいのも特徴です。
一方、デメリットとして価格変動リスクは避けられません。株式市場と同じく需給で価格が動くため、経済不安時には含み損が出る可能性があります。また配当利回りは4〜5%が平均的で、レバレッジを効かせた現物投資よりもリターンが低く感じる場面もあります。つまり手間を取るか、利回りの高さを取るかが判断ポイントになるのです。
建物の老朽化と建て替えのリアルコスト
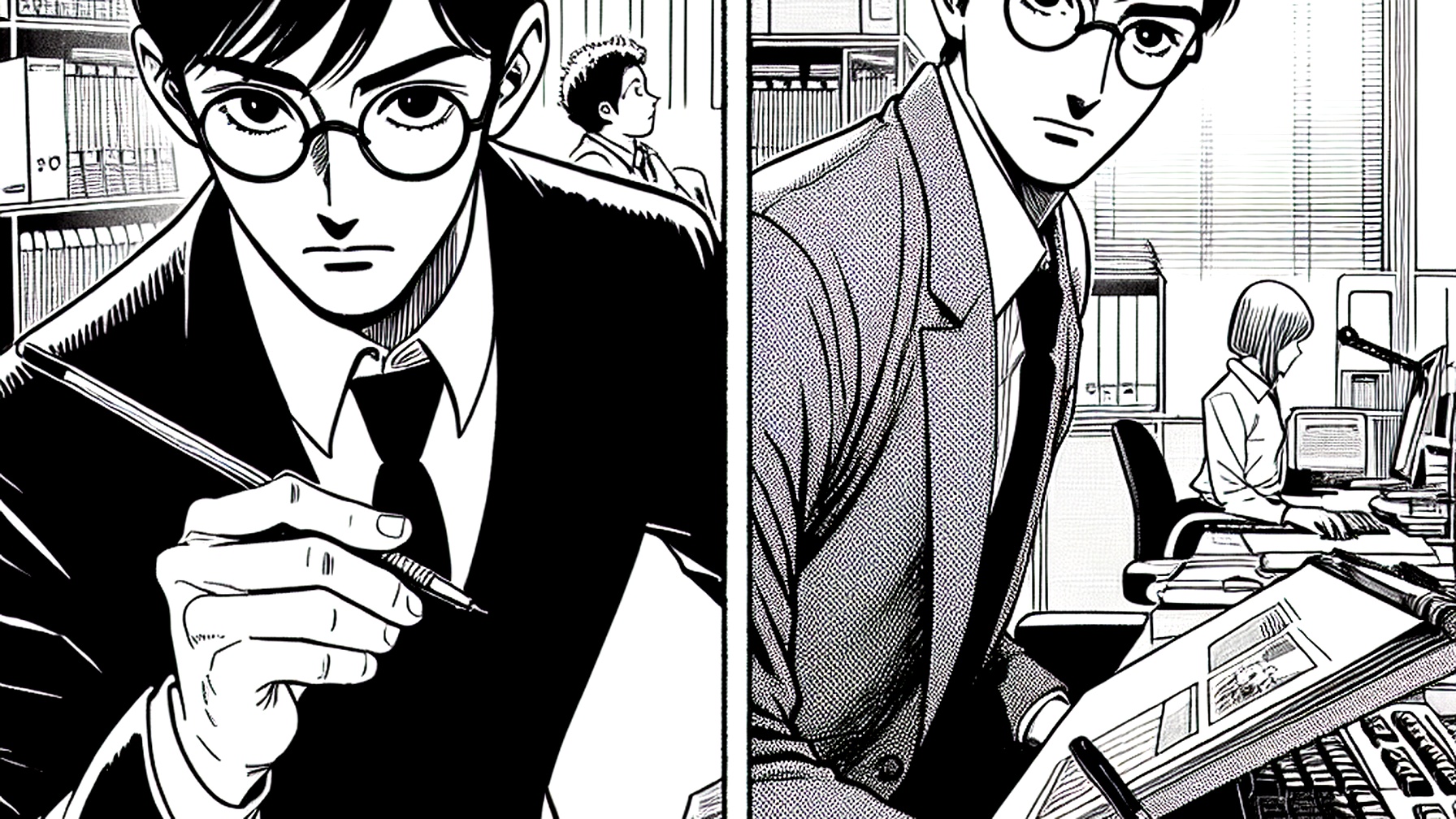
重要なのは、築30年以上の木造アパートを保持し続ける場合の維持費を正確に見積もることです。国土交通省の「建築物ストック統計」によると、築40年超の賃貸住宅は全体の22%を超え、修繕費は築20年時点の約1.5倍に達します。外壁塗装や屋根防水だけでも300万〜500万円、給排水管の更新を含めると総額は軽く1,000万円を超えるケースも珍しくありません。
建て替えとなれば、さらに大きな資金が必要です。延床面積200㎡、木造2階建てアパートを想定すると、2025年度の坪単価は約70万円が一般的で、建築費だけで4,000万円前後になります。解体費や仮住まいの保証料、設計費を合算すると総事業費は6,000万円規模になることもあります。金融機関の融資が付いたとしても、自己資金1〜2割は確保しなければなりません。
さらに工期中は家賃収入がゼロになります。6カ月の工期で月額家賃40万円の物件なら、機会損失は240万円です。こうした隠れコストを含めて初めて、建て替えが妥当かどうかの判断が可能になります。言い換えると、単に古くなったから建て替えるのではなく、総投資額と将来収益のバランスを冷静に比較する必要があるのです。
REITと直接保有物件、デメリットの比較
実は、REITと現物不動産ではデメリットの質が大きく異なります。現物の場合、空室リスクや突発的な修繕費がキャッシュフローを圧迫します。支出タイミングをコントロールしづらく、流動性も低いため、売却までに時間がかかる点も見逃せません。
一方でREITは管理の手間がなく、税務処理も年間取引報告書に従って確定申告するだけで完結します。しかし市場価格が下落すると、短期で含み損を抱えることがあります。さらに分配金は内部留保の影響で減配リスクがあり、長期的に見て安定配当が続くとは限りません。
ここでポイントになるのがレバレッジの違いです。現物投資は融資を活用することで自己資金以上のリターンを狙えますが、金利上昇局面では返済負担が重くなります。REITは基本的に無担保で購入できる反面、レバレッジ効果を得にくいのが特徴です。つまり、投資家自身のリスク許容度と目的に応じてメリットとデメリットを天秤にかける作業が欠かせません。
建て替えを選ぶべきタイミングと判断軸
まず押さえておきたいのは、建て替え判断に「絶対的な築年数」は存在しないという事実です。賃料水準、地域の人口動態、土地の形状など複数の要素を組み合わせて検討する必要があります。東京都の住宅着工統計によれば、駅徒歩10分圏内で築40年超の木造アパートでも高稼働率を保つ事例がありますが、地方では築25年で空室率が40%に達するケースもあります。
キャッシュフローの観点では、修繕費が年間家賃収入の15%を超えるようになった時点が一つの目安です。さらに金融機関が提示する融資条件が「返済比率50%以内、金利1.5%前後」であれば、建て替え後の負担も許容範囲に収まる可能性が高まります。また建て替え後に住宅性能評価やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を取得すれば、2025年度も継続見込みの固定資産税軽減措置を受けられる点も検討に値します。
しかし、土地の流動性が高いエリアでは売却してREITに資金を振り向ける選択肢も有効です。特に相続が近い場合、現物不動産よりも分割しやすいREITを保有することで、家族間トラブルを回避できるメリットがあります。つまり、建て替えか売却かの分岐点は、税金・家族構成・地域性を総合判断することで見えてきます。
税務とキャッシュフローから見る最終判断
重要なのは、手残りキャッシュフローと税務負担を同時にシミュレーションすることです。建て替え後の減価償却費は木造なら22年で償却しますが、RC造(鉄筋コンクリート)なら47年です。耐用年数が伸びる分、毎年の経費計上額は小さくなり、課税所得が増える可能性があります。
一方、REITの分配金は20.315%の源泉徴収で完結し、給与所得と分離して扱える点がシンプルです。ただし雑所得として申告分離課税を選択すると、配当控除が適用されないため納税額が増えるケースもあります。投資額が大きくなるほど、税理士にシミュレーションを依頼して最適解を探る価値が高まります。
結論として、長期的な資産形成を目指すなら、「建て替えで資産価値を高めつつインカムゲインを追う」か「REITで流動性と分散効果を取る」かの二択ではなく、両者を組み合わせるポートフォリオ発想が有効です。例えば建て替え後の新築アパートを根幹資産とし、余剰資金をREITで運用すれば、相互にリスクをヘッジしながら収益源を多様化できます。
まとめ
本記事では、老朽化物件を抱えるオーナーが直面する「建て替え」か「REIT」かという選択について、コスト構造とリスクの違いを整理しました。建て替えは高額な初期投資と空室期間の機会損失がある一方、長期的な家賃アップと資産価値向上が期待できます。対してREITは手間と時間を節約でき、流動性にも優れますが、市場変動と減配リスクを受け入れる必要があります。まずは自身のリスク許容度と投資目的を明確にし、キャッシュフローと税務をシミュレーションしたうえで、両方を組み合わせる戦略を検討してください。将来の選択肢を増やすことこそが、不動産投資を長く安定して続けるコツです。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅着工統計 – https://www.mlit.go.jp/toukei
- 日本銀行 金融システムレポート – https://www.boj.or.jp/statistics
- 東証REIT指数 月次レポート – https://www.jpx.co.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 不動産証券化協会 J-REITデータ – https://www.ares.or.jp
