年収が700万円前後になると、手取りは増えても将来への不安は消えません。銀行預金の利息はほとんど付かず、株式市場は値動きが読みにくい。そこで注目されるのが、毎月の家賃収入で現金を積み上げられる収益物件投資です。本記事では、年収700万の会社員が無理なく始めるための資金計画、物件選び、管理会社の選定方法を最新データとともに解説します。読み終えたとき、投資プロセスの全体像が見え、次の一歩を具体的に踏み出せるはずです。
年収700万から始める資金計画の基礎
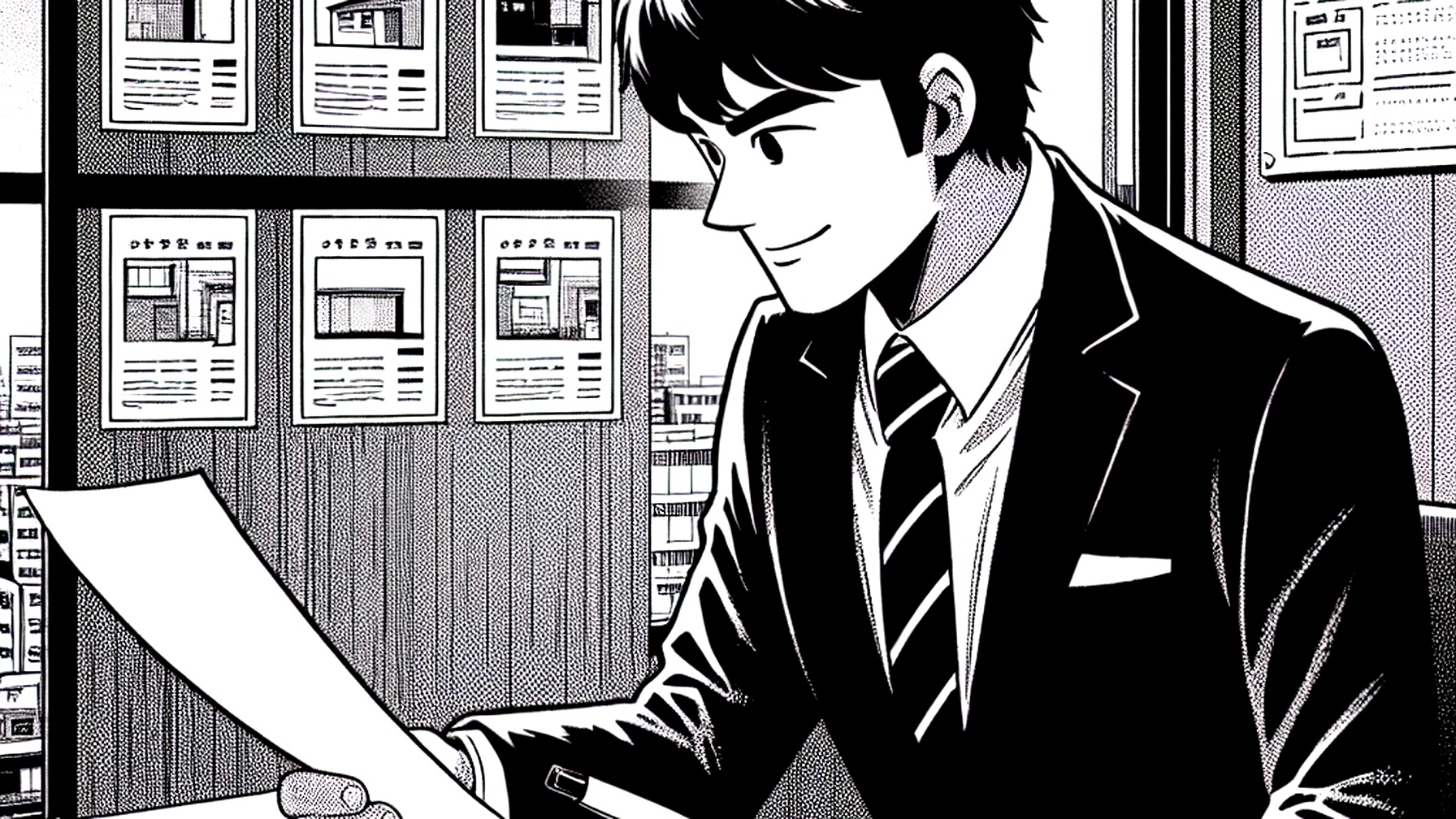
まず押さえておきたいのは、自己資金と融資のバランスです。国土交通省の不動産価格指数を見ると、2025年は都心部の中古マンションが前年比3%上昇し、依然として資金手当ての重要度が高まっています。年収700万の場合、金融機関が見込む年間返済限度額は年収の35%前後が一般的です。つまり、年間245万円、月額では約20万円程度までが安全圏となります。
この枠内でローンを組むには、物件価格の20〜30%を自己資金で賄うと返済負担が適正に収まります。たとえば3,000万円のワンルームを想定すると、自己資金600万円、ローン2,400万円が目安です。日本政策金融公庫の2025年度データによると、自己資金が2割を下回ると融資審査通過率が約15%低下するため、頭金の準備は成功率を大きく左右します。
なお、固定資産税や火災保険、突発的な修繕に備える運転資金として、物件価格の5%前後を別途確保すると安心です。2025年度の修繕積立金ガイドラインでは、築15年以降に外壁改修や給排水工事が集中しやすいと指摘されています。これらの費用をあらかじめ見込むことで、キャッシュフローが予想外に圧迫されるリスクを抑えられます。
収益物件の選定で失敗しない視点
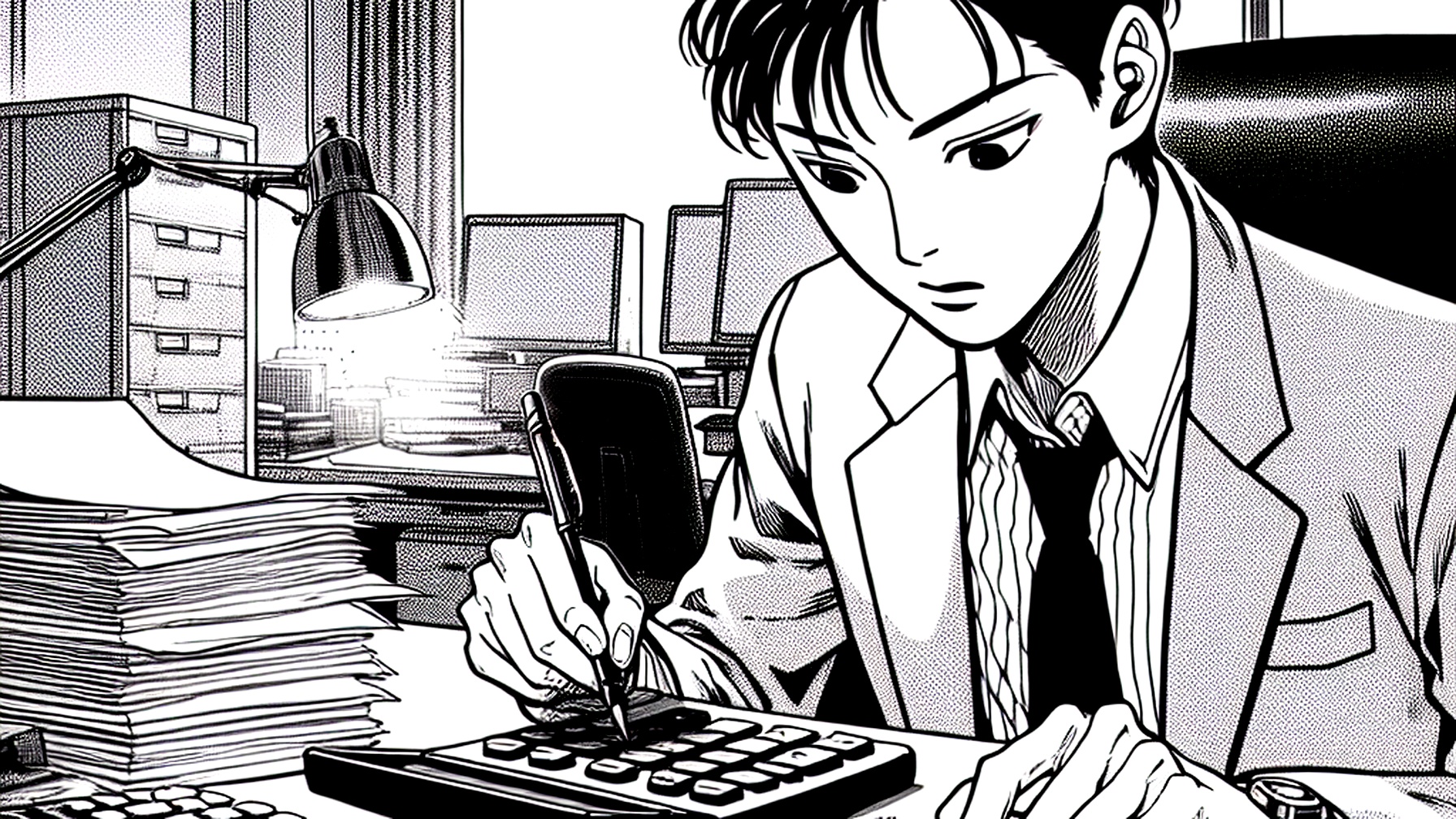
重要なのは、表面利回りだけで判断しないことです。不動産研究所の調査では、都心区分マンションの平均表面利回りが4.5%、地方中古アパートが9.0%ですが、空室率と維持コストを差し引いた実質利回りでは、両者の差が2%未満に縮まることが示されています。
そこで立地、需要、供給の三つの軸で評価しましょう。立地では最寄り駅から徒歩10分以内が空室リスクを約40%下げると国交省が報告しています。需要については、総務省の将来人口推計で2030年まで人口横ばいが見込まれるエリアを選ぶと、長期保有時の賃料下落が緩やかになります。供給面では、新築ラッシュが続く地域を避け、築浅中古が流通量の主流であるエリアを選ぶと競合が限定されます。
結論として、年収700万の投資家は、利回りと空室リスクのバランスが取れた都心近郊の築10年以内区分マンションをまず1戸保有し、実績を蓄積してからアパート一棟へステップアップする戦略が堅実です。
キャッシュフローを安定させる管理会社活用術
ポイントは、管理会社の選定が長期収益を左右するという事実です。賃貸管理は募集、入居審査、家賃集金、トラブル対応、退去精算と多岐にわたります。オーナーが片手間で行うと、不払い対応や修繕交渉で時間を奪われ、本業の収入源に影響しかねません。
全国賃貸管理ビジネス協会の2025年調査では、管理委託率が95%のオーナーが自己管理と比べて平均空室日数を20日短縮しています。家賃6万円の物件なら年間約4万円の機会損失を削減できる計算です。また、サブリース(一括借上げ)契約の平均手数料は家賃の10%前後ですが、完全空室保証が付くわけではなく、3年ごとに賃料改定がある点に留意しましょう。
【管理会社選びの比較ポイント】
- 管理戸数:2,000戸以上でシステム化が進み、対応が早い
- 退去立会い代行費:家賃1ヶ月分以内が適正
- 原状回復の発注方式:見積もりを2社提示できる会社はコスト透明性が高い
実は、複数社へ募集を依頼する「客付け専門会社併用型」を選ぶと平均成約期間が15%短縮します。管理はA社、募集はB社にも開放する形で、家賃3%の管理手数料を維持しつつ空室対策を強化できるため、キャッシュフローの安定に直結します。
2025年度の税制・融資環境を味方にする
まず押さえておきたいのは、2025年度も続く住宅ローン減税と不動産取得税の軽減措置です。住宅ローン減税は自宅用ですが、一棟アパートを取得して自宅と一部併用する「居住割合要件」を満たすと適用対象となります。具体的には、延床面積の2分の1以上を自身が居住する場合で、所得合計3,000万円以下の年収700万オーナーも可能です。期限は2025年12月31日取得分までとなっています。
一方、投資用ローンは金利上昇局面に入りましたが、政策公庫の「不動産担保融資」では、2025年10月時点で固定1.55%が上限金利として据え置かれています。民間銀行の平均固定金利が1.90%に達しているため、創業計画書を活用して政策公庫を併用するスキームは依然有効です。
固定資産税については、新築住宅の減額措置が2026年度まで延長されましたが、築13年超の中古物件では恩恵がありません。そのため、中古区分マンションを購入する場合は、取得当初から標準税率1.4%相当の負担を見込み、利回り計算に折り込みましょう。税務戦略では、減価償却費による所得圧縮が鍵となります。鉄骨造アパートの法定耐用年数34年に対し、築20年の物件を購入すると残存14年で償却でき、年間200万円超の経費計上が可能となるケースもあります。
シミュレーション事例で学ぶ成功パターン
実は、数字を具体化するとリスクとリターンの輪郭が鮮明になります。ここでは、都内駅徒歩7分の築8年区分マンション(30㎡、価格3,000万円、家賃105,000円)を事例にシミュレーションします。
ローンは頭金600万円、金利1.6%、期間30年で毎月の返済額は約103,000円。管理費・修繕積立金が12,000円、管理会社手数料が3,500円、固定資産税が月あたり5,000円とすると、支出合計は123,500円に達します。家賃との差額は18,500円のマイナスですが、年間減価償却費が70万円見込めるため、課税所得は大きく圧縮されます。これにより、所得税と住民税で年間15万円程度の還付が期待でき、キャッシュフローは実質プラスに転じます。
空室率10%、家賃下落率年1%の厳しめシナリオを追加すると、5年後の実質利回りは3.9%に落ち着きます。それでも、頭金を多めに入れたことでローン残高は2,200万円まで減少しており、売却時に含み益が狙えます。つまり、年収700万の投資家が安全余裕を持たせた資金計画を実行すれば、中長期で資産拡大が可能になるわけです。
一方、地方木造アパート(価格5,000万円、利回り9%)を想定すると、銀行金利は2.0%、頭金1,000万円で毎月の返済は約184,000円。家賃収入375,000円から運営費120,000円を差し引くと、手残りは71,000円です。木造は耐用年数が22年と短いため、築浅を選ぶと減価償却メリットが限定されます。物件価格が低くても、減価償却が終わったタイミングでキャッシュフローが急減する点に注意が必要です。
まとめ
この記事では、年収700万の会社員が収益物件投資で安定収入を得るための全プロセスを整理しました。資金計画では自己資金2割と予備費の確保が最優先となり、物件選びでは立地・需要・供給の3軸分析が欠かせません。さらに、管理会社を戦略的に活用すれば、空室期間を短縮しキャッシュフローを最大化できます。最後に、2025年度の税制優遇と低金利融資を併用し、シミュレーションを通じてリスク耐性を確認することが成功への近道です。今日できる行動として、金融機関3社へ事前審査を申し込み、気になる物件で試算表を作ってみてください。数字が見えると、最初の一歩がぐっと軽くなるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫「融資制度概要」 – https://www.jfc.go.jp
- 不動産研究所「全国賃貸市場動向2025」 – https://www.reinet.or.jp
- 総務省「将来人口推計2025」 – https://www.stat.go.jp
- 全国賃貸管理ビジネス協会「管理戸数調査2025」 – https://www.jpm.jp

