親族から不動産を受け継ぐと、嬉しさと同時に「本当に所有し続けて良いのか」「売却か運用か」など多くの迷いが生まれます。特に初めて相続を経験する方は、評価方法や税金、リフォーム費用など分からないことばかりでしょう。本記事では、2025年10月時点で有効な制度と市場データをもとに、初心者でも実践しやすい相続物件の選び方を解説します。読了後には、自分に合った「おすすめ 相続物件」を判断する基準が明確になり、次の一手を自信を持って選べるはずです。
相続物件の価値を決める三つの基本要素
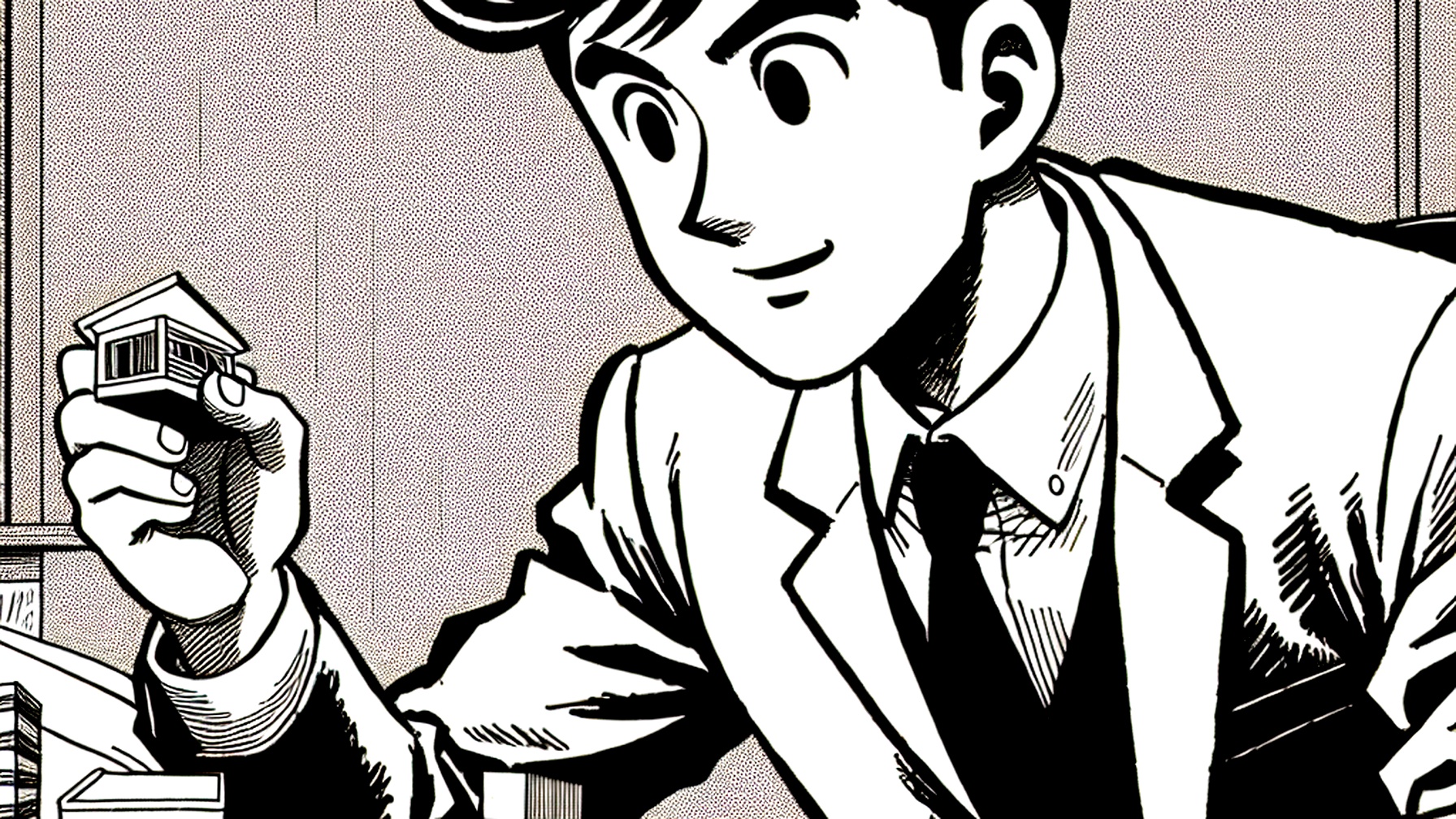
重要なのは、相続物件の評価を「立地・建物・法規」の三方向から俯瞰することです。これらをバランスよく検証すれば、感情に流されず合理的な結論にたどり着けます。
まず立地について考えます。国土交通省の地価調査(2025年)では、全国平均の地価は横ばいですが、地方中核都市の駅徒歩10分圏は前年比3.2%上昇しました。つまり「駅近・再開発エリア」は依然として強い需要があり、長期保有でも値下がりリスクが小さいと言えます。
次に建物の状況です。築25年を超える木造アパートは減価償却のメリットが薄れ、修繕費が増える傾向があります。一方、築20年以内のRC(鉄筋コンクリート)マンションは耐用年数が47年と長く、金融機関の評価も得やすい点が魅力です。
最後に法規制の確認です。都市計画区域内では建ぺい率・容積率の制限が資産価値を左右します。加えて、2025年4月に改正された「相続登記の義務化」により、取得を知った日から3年以内の登記が必須となりました。未登記のまま放置すると10万円以下の過料が課されるため、法的リスクにも目を向けましょう。
立地価値を数字で読み解く方法
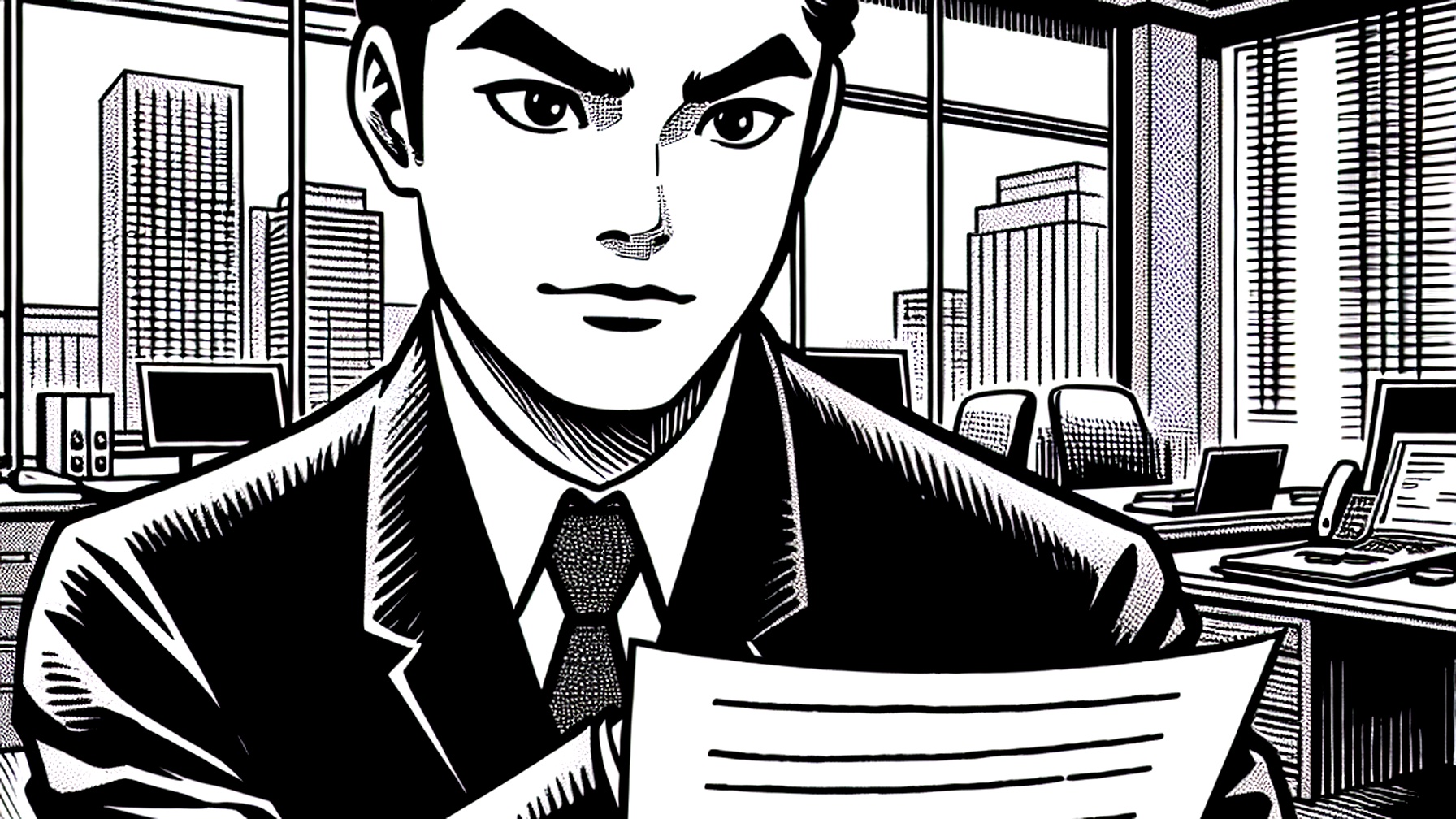
ポイントは、人口動態・賃料相場・公共投資という三つの数字を組み合わせて判断することです。これらが揃えば、表面的な地価だけでは見えない将来性が浮かび上がります。
総務省統計局の住民基本台帳によると、2020〜2025年の5年間で地方郊外の人口は平均1.8%減少しましたが、同期間で政令指定都市の中心区は1.4%増加しています。人口増加エリアは、実需が下支えするため空室リスクが低いと考えられます。
次に、公益社団法人全国賃貸住宅経営協会の2025年調査では、都心区の平均家賃は前年比1.5%上昇した一方、郊外の古い団地型は0.8%下落しました。つまり賃料トレンドを確認することで、キャッシュフローの安定度を測れます。
さらに自治体の公共投資計画をチェックします。たとえば札幌市は2030年の冬季五輪招致を見据え、地下鉄延伸と駅前再整備に合計3,000億円超を投じる方針です。このような大型インフラ計画は資産価値の底上げ要因になるため、資料を図書館や自治体サイトで確認しておくと良いでしょう。
築年数と構造が将来の収益を左右する
実は、建物の「表面利回り」よりも「修繕コストの時間軸」を意識したほうが、長期的な手取りは多くなります。
木造アパートは築15年で屋根・外壁の大規模修繕が必要になり、おおむね250万〜350万円かかります。これを家賃収入で賄うと、年間キャッシュフローが急減する可能性があります。一方で、RC造は修繕周期が12年〜15年、費用は400万〜600万円と高めですが、耐用年数が長く金融機関からの融資期間も延ばしやすい利点があります。
日本不動産研究所の「収益不動産調査2025」では、RCワンルームマンションの実質利回りが4.3%、木造アパートが6.0%でした。しかし、30年間の累積修繕費を考慮すると、最終的な手取り差は1%未満に縮小するという試算もあります。つまり目先の利回りだけで判断すると、後悔するリスクが高いのです。
税制優遇を活用して手取りを最大化する
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続している「小規模宅地等の特例」です。被相続人の自宅を相続人が引き続き居住する場合、敷地330㎡までの評価額を80%減額できます。この制度を活用すれば、財産評価が大幅に下がり、相続税の圧縮効果が高まります。
さらに令和5年改正で創設された「暦年贈与の控除枠見直し」は2025年も有効です。相続開始前7年以内の贈与が加算対象になりますが、毎年110万円の基礎控除は維持されています。相続開始を見据えて早めに贈与を組み合わせれば、評価額の高い都市部マンションでも負担を抑えやすくなります。
一方、不動産所得による節税も見逃せません。減価償却費を最大限に計上できる築古RCマンションを活用すれば、給与所得と損益通算し税負担を軽減できます。ただし2025年の税制改正で赤字の損益通算額に上限(年間300万円)が導入されたため、償却期間と金額を慎重にシミュレーションする必要があります。
運用戦略別に見るおすすめ 相続物件
ポイントは、目的と期間を明確にすると「おすすめ 相続物件」が自然に絞り込めることです。以下では代表的な三つの戦略を示します。
● 安定運用型 地方中核都市の築20年以内RC区分マンションは、空室率が低く管理も委託しやすいです。銀行評価が高く金利1%台のローンが利用できるため、月々のキャッシュフローが読みやすい点が魅力です。
● キャピタルゲイン型 再開発が進む駅前の古家付き土地は、解体後に戸建分譲や共同住宅の建築を検討できます。建物解体と測量に約500万円かかっても、再販益で1,000万円以上を見込める事例が福岡市で増えています。
● 節税特化型 築古の木造アパートを法人名義で取得し、短期で償却を進めて所得圧縮を狙う手法です。前述の損益通算上限に注意しつつ、法人化による税率差を活用すれば、実効税率を20%前後まで下げられます。
いずれの戦略でも、金融機関の融資姿勢と地域需要をセットで分析すると、失敗リスクを大きく減らせます。
まとめ
ここまで、相続物件を選ぶ際の視点として「立地・建物・法規」「人口動態と賃料の数字」「修繕コスト」「税制優遇」「目的別戦略」の五つを紹介しました。これらを総合的に判断すれば、感情や思い出に左右されず、収益とリスクのバランスが取れた物件を選べます。まずは自治体の都市計画図や法務局の登記簿を取り寄せ、簡易なキャッシュフロー表を作ることから始めてみてください。行動を起こすことで、相続物件は負担ではなく将来の資産に変わるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 土地・建設産業局 地価調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省統計局 住民基本台帳人口移動報告2025 – https://www.stat.go.jp/
- 日本不動産研究所 収益不動産調査2025 – https://www.reinet.or.jp/
- 公益社団法人全国賃貸住宅経営協会 家賃動向調査2025 – https://www.zenchin.or.jp/
- 住宅金融支援機構 フラット35利用実態調査2025 – https://www.jhf.go.jp/

