不動産投資を始めようとすると、「収益物件 収支計算 違い」が分からず手が止まる人が少なくありません。物件広告には高い表面利回りが並びますが、その数字だけでは本当の手取り額は見えてきません。本記事では、収益物件とはそもそも何か、収支計算はどのような手順で行うのか、そして両者が投資判断にどう影響するかを順序立てて説明します。読み終えた頃には、自分でキャッシュフローを試算し、物件ごとのリスクとリターンを比較できるようになります。
収益物件とは投資用不動産の総称

まず押さえておきたいのは、収益物件が「家賃収入などを目的に保有する不動産」を指す点です。区分マンションから一棟アパート、さらには商業施設まで幅が広く、収入形態も物件ごとに異なります。つまり物件タイプを理解することが、正確な収支計算への第一歩となります。
実は、同じ家賃10万円の部屋でも区分マンションと一棟アパートでは経費構造が違います。区分の場合、管理組合への修繕積立金が必須ですが、外壁塗装などの大規模修繕は組合が行います。一方、一棟を所有する場合は大規模修繕費をオーナーが全額負担するため、長期的な資金計画が欠かせません。このように、物件形態が異なれば必要経費も変わるため、収益物件の種類を把握することは極めて重要です。
また、2025年10月時点で金融機関は木造アパートに対し最長35年、RC造に対し最長45年の融資期間を提示する傾向があります。融資期間が長いほど月々の返済額は抑えられ、表面上のキャッシュフローは良く見えます。しかし、期間が長いほど総返済額は増えるため、単純比較は禁物です。ここでも収益物件の構造的な違いが収支計算に直結します。
さらに、投資指標として「グロス利回り(表面利回り)」と「ネット利回り(実質利回り)」があります。前者は家賃収入を物件価格で割っただけの単純指標で、経費を考慮しません。後者は経費や空室損を差し引いた指標で、手取りイメージに近い数値です。この利回りの使い分けこそが、収益物件を正しく評価する土台となります。
収支計算の基本構造は四つのステップ
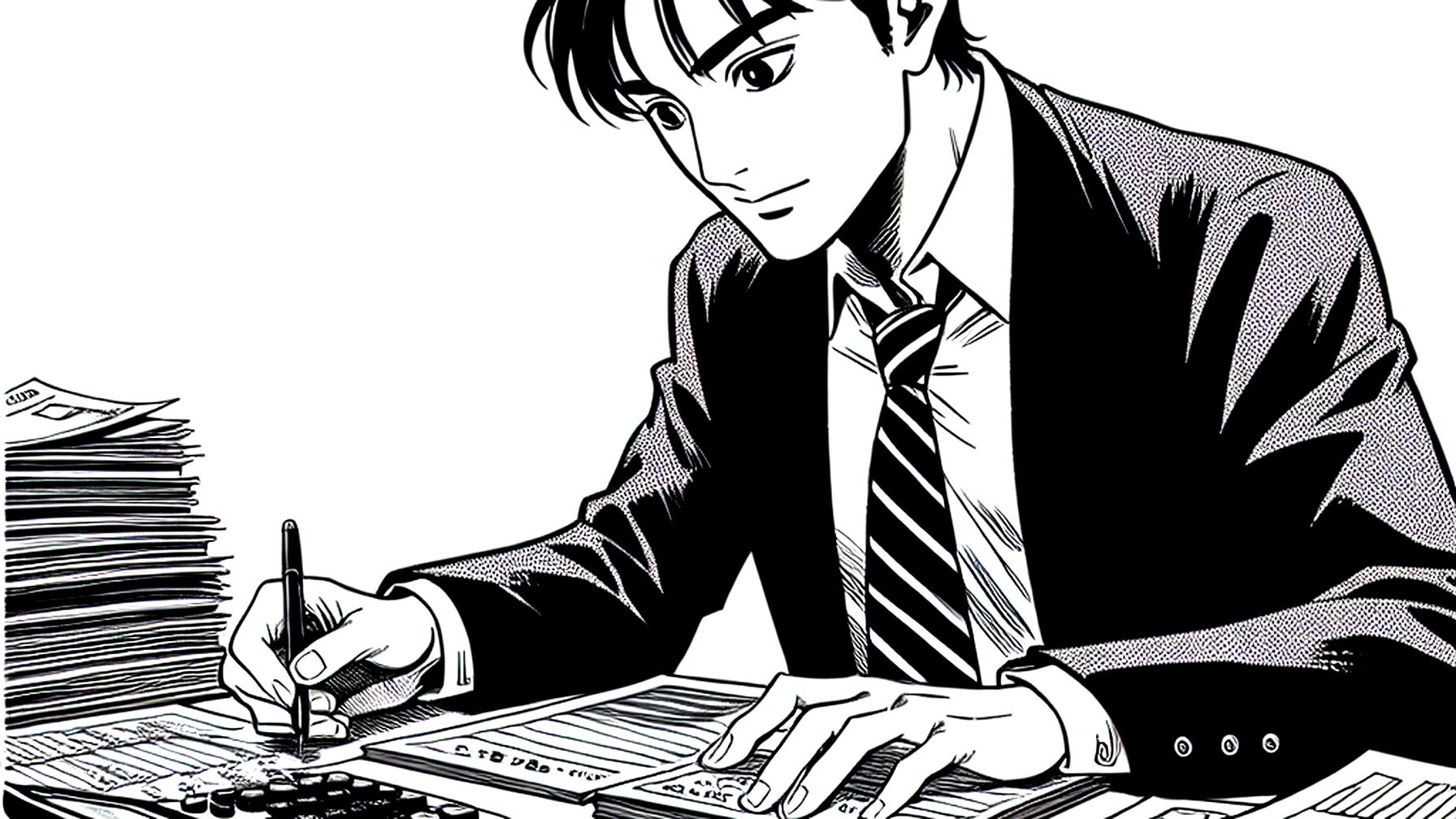
ポイントは、家賃収入から税引き後キャッシュフローまでを階段状に落とし込むことです。具体的には「総収入」「運営費」「借入返済」「税金」の順で計算します。
最初の段階である総収入には家賃だけでなく、駐車場代や自販機設置料なども含めます。国土交通省の2024年賃貸住宅市場調査によると、都市部のワンルーム物件では家賃外収入が平均収入の5%を占めています。こうした副収入を漏れなく計上することで、より正確なシミュレーションが可能になります。
次に運営費を差し引きます。ここには管理委託手数料、修繕費、火災保険料、固定資産税が含まれます。国税庁の令和6年固定資産税評価替えでは、標準的な区分マンションの税額は年間家賃収入の8〜10%が目安と示されています。修繕費は建物構造ごとに大きく異なり、木造で年間家賃収入の7%、RC造で4%程度が一般的と言われます。
運営費を引いた後、借入返済額を差し引くと税引き前キャッシュフローが算出されます。2025年現在、地銀の投資用ローン金利は変動型で年1.8〜2.5%が主流です。金利が0.5%上がると、35年ローン3,000万円の場合で月々約7,000円返済額が増える計算になります。つまり金利シナリオの違いを盛り込むことが欠かせません。
最後に所得税・住民税を計算します。所得税は累進課税で、個人投資家の場合は総合課税です。経費計上によって赤字が出れば給与所得と損益通算が可能ですが、その効果は年収や他の控除額によって変わります。また、2025年度税制では損益通算の上限額が設けられていないため、赤字全額を控除可能です。この税引き後キャッシュフローこそ、最終的に手元に残る現金となります。
利回りとキャッシュフローの違いを押さえる
重要なのは、利回りがあくまで瞬間的な収益性を示す指標であり、キャッシュフローは実際の資金繰りを示す指標だという点です。両者を混同すると、想定外の支出で資金ショートを起こすリスクが高まります。
言い換えると、利回りは走行距離あたりの燃費、キャッシュフローはガソリン代を払った後の財布の中身に近い感覚です。どちらも大切ですが、日々の運転が滞れば投資は続けられません。不動産投資で失敗する典型例は、利回りだけを見て物件を選び、キャッシュフローが赤字になるケースです。
たとえば、表面利回り10%の築古アパートと表面利回り6%の築浅マンションを比較してみましょう。築古アパートは修繕費が高く、運営費率が30%に達することも珍しくありません。一方、築浅マンションは運営費率が15%前後に収まるため、実質利回りで見ると差が縮まります。さらに、融資条件も築年数によって変わるので、キャッシュフローでは逆転する可能性があります。
日本銀行の資金循環統計によると、家計部門の不動産投資向けローン残高は2025年3月末時点で28兆円を超え、過去最高を更新しました。融資の門戸が広い分、不動産投資の裾野は広がりましたが、表面利回りだけに飛びつく投資家も増えています。だからこそ、利回りとキャッシュフローの違いを正しく理解することが、生き残るための必須条件となります。
見落としがちな経費が収支を左右する
ポイントは、広告には載らない細かな費用こそがキャッシュフローを圧迫するという事実です。具体的には原状回復費、更新料返還分、入居者募集費用などが代表例です。
原状回復費は退去時に発生し、敷金で賄いきれない部分はオーナー負担となります。東京都住宅確保条例のガイドラインによると、ワンルームの平均原状回復費は一件あたり7万円ですが、築20年を超えると10万円を超えるケースもあります。これを空室発生率と組み合わせると、年間の平均負担額が見えてきます。
次に、入居者募集費用として仲介会社に支払う広告料(AD)が挙げられます。最近では競争激化により、家賃の1か月分以上を支払うエリアも増えています。ADが高止まりすると、満室を維持するためのコストが年単位でかさみ、表面利回りとの乖離が広がります。
また、2025年度から義務化された省エネ性能表示制度により、新築・大規模改修時にはBELS評価の取得費用が発生します。評価費用は戸建てで5〜10万円、共同住宅で30万円前後が目安です。この制度は長期空室抑止には有効ですが、初期費用に計上し忘れると計算が狂います。
最後に忘れがちなのが水漏れや設備故障などの突発修繕です。国土交通省「民間住宅ローン実態調査」では、突発修繕費は年間家賃収入の2%が平均と報告されています。これを見込まずに運用すると、いざという時に自己資金を取り崩すことになり、再投資の機会を逃す原因になります。
シミュレーションは複数シナリオで比べる
まず大切なのは、楽観・標準・悲観の三つのシナリオを作り、各シナリオでキャッシュフローがどう変化するかを比較することです。これによってストレス耐性のある物件かどうかを判断できます。
楽観シナリオでは空室率5%、金利現状維持、家賃下落なしを設定します。標準シナリオでは空室率10%、家賃年1%減、金利0.3%上昇を組み込みます。悲観シナリオでは空室率20%、家賃年2%減、金利1%上昇という厳しい条件を置きます。金融庁の2025年「金融システムレポート」によれば、地方銀行の投資用ローン金利は景気後退局面で平均0.7%上昇した実績があるため、悲観シナリオも現実味があります。
シナリオごとのキャッシュフローをエクセルやクラウド型シミュレーターで計算し、税引き後でプラスが維持できるかを確認します。もし悲観シナリオでマイナスに転じるなら、自己資金を増やすか、別の物件を検討するべきです。このプロセスにより、単なる数字合わせではなく、将来の不確実性まで織り込んだ投資判断が可能になります。
さらに、物件を複数保有する将来を見据え、ポートフォリオ全体の資金繰り表を作成すると安全度が増します。日本取引所グループのJ-REIT分配金データによると、複数物件への分散が分配金の安定化に寄与しています。個人投資家であっても、物件タイプとエリアを分けて購入することで、収益の振れ幅を抑えられる点は共通しています。
こうしたシナリオ比較を行えば、銀行面談でも説得力のある事業計画書を提示でき、好条件の融資を引き出せる確率が高まります。つまり、シミュレーションは物件選定だけでなく、融資交渉の場面でも威力を発揮するのです。
まとめ
ここまで、収益物件の種類、収支計算の手順、利回りとキャッシュフローの違い、見落としがちな経費、さらにはシミュレーションの作り方まで解説しました。結論として、数字は一つひとつの前提条件で大きく変わるため、表面利回りだけで判断するのは危険です。まずは自分で収支表を作成し、空室率や金利上昇に備えた複数シナリオを試算してください。そのうえで、将来の資金繰りに耐えられる物件を選べば、不動産投資は強力な資産形成ツールになります。
参考文献・出典
- 国土交通省 賃貸住宅市場統計 – https://www.mlit.go.jp/
- 国税庁 所得税基本通達 – https://www.nta.go.jp/
- 日本銀行 資金循環統計 – https://www.boj.or.jp/
- 東京都住宅確保条例 ガイドライン – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/
- 日本取引所グループ J-REIT統計 – https://www.jpx.co.jp/
