アパート経営に興味はあるものの、実際の手間やリスクを想像すると一歩を踏み出せない人は多いでしょう。特に相続対策として有効なのか、あるいは短期投資として利益が出るのかは悩みの種です。本記事では十五年以上の投資現場で得た知見をもとに、現実的なアパート経営の進め方を解説します。読み終えたとき、相続と短期投資を両立させる具体的な手順がイメージできるはずです。
アパート経営が相続対策に向く理由
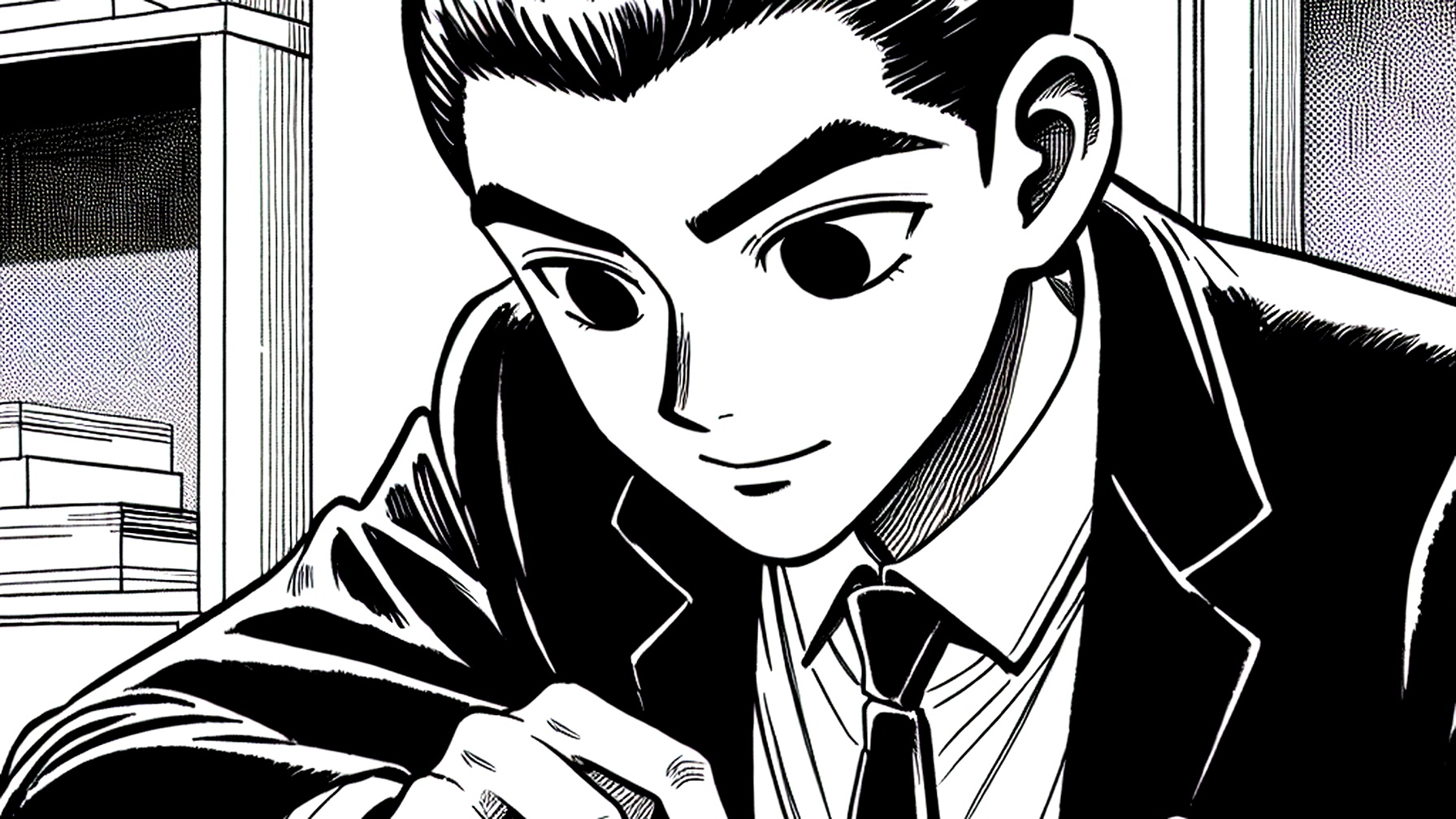
まず押さえておきたいのは、アパートという不動産が相続財産の評価額を圧縮しやすい点です。ここでは税務上の仕組みと家族の資産承継にどのように作用するかを整理します。
相続税では土地の評価を路線価、建物を固定資産税評価額で計算します。どちらも実勢価格より二〜三割低く出る傾向があり、相続人が負担する税額を抑えられます。さらに貸家建付地の評価減を使うと、貸家がついた土地はおおむね二割評価が下がります。つまり現金で持つよりアパートに置き換えたほうが課税対象が小さくなるというわけです。
評価を下げるだけではなく、家賃収入で納税資金を作れる点も見逃せません。相続発生後に預金が不足すると不動産の売却を急がざるを得ず、安値で手放すケースが目立ちます。毎月の家賃があれば物件を守りながら税金を分割で納められるため、遺族の心理的負担も軽減されます。また長期保有を前提にすれば、節税と資産形成を同時にかなえられます。
2025年度も小規模宅地等の特例は継続しており、一定要件を満たす賃貸住宅の敷地は330平方メートルまで評価が五割減となります。金融庁のデータによると、この特例を利用した場合としない場合では、相続税負担が平均で三割近く差が出ています。制度は毎年見直されるため、着工前に税理士とシミュレーションを行うことが肝心です。
短期投資として成立させるための時間軸
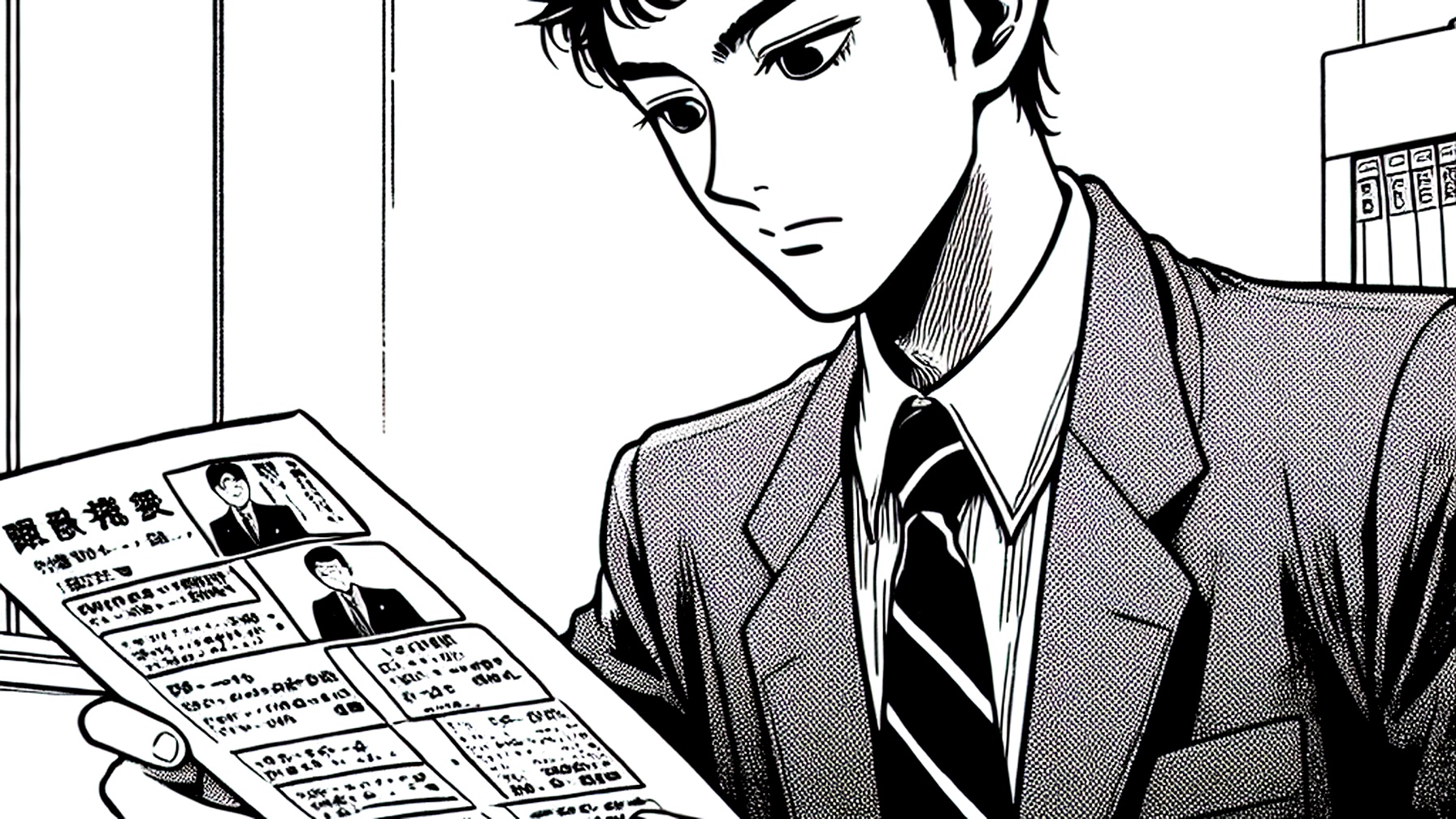
次に、アパートを短期投資として捉える場合のタイムラインを確認しましょう。重要なのは建築から売却までの出口を最初に描くことです。
新築木造アパートは法定耐用年数が22年ですが、最初の四年間は加速度的に減価償却費を計上できるため、所得税を圧縮しやすいです。手残りが大きいこの期間にキャッシュを積み上げ、五〜七年で売却するモデルが一般的な短期戦略とされています。国土交通省住宅統計によれば築五年時点の都心部木造アパートの平均流通価格は新築比約九割で推移しており、価格下落は比較的緩やかです。
短期投資ではローン期間を長めに設定し、売却時に元本が多く残ることを想定します。表面利回り八%、融資金利1.9%、期間30年のケースでは、五年後に残債が購入価額の約八一%まで減少します。この差額がキャピタルゲインの源泉となり、家賃収入と合わせた総合利回りは年換算で十二%前後に達することも珍しくありません。また法人を使えば、売却益に対する税率をコントロールしやすくなります。
しかし、短期での売却益は需給に大きく左右されます。2025年8月の全国アパート空室率は21.2%と高止まりしていますが、前年より0.3ポイント改善しており、都心と地方で動きが分かれています。売却を判断する際は自物件のエリア空室率と家賃相場の推移を毎月チェックし、利回りが低下し始めたタイミングで早めに動くことが重要です。
現実的なキャッシュフローの組み立て方
ポイントは、過度に楽観的な収支計画を避け、手元資金の厚みを確保することにあります。
家賃収入だけを見て黒字でも、管理費や修繕積立を加えると赤字になるケースは珍しくありません。一般社団法人日本賃貸住宅管理協会の調査では、築五年以内でも年間家賃収入の約七%が維持費として消えると報告されています。さらに地方銀行のアパートローンでは、金利上昇リスクへの備えが不可欠です。変動金利が1%上がると月々の返済は約1.1倍になるため、ストレスシナリオを想定しておきましょう。
私は最低でも家賃収入の三か月分を予備費として法人口座に残すよう推奨しています。この金額があれば、エアコンの大量故障や入居者退去が重なったときに慌てず対応できます。実際、2019年の大型台風では共用部の破損修理に平均80万円かかったというデータがありますが、備えがあった物件は家賃下落を回避できました。また予備費は金融機関への信頼度を高め、追加融資交渉を有利に進める効果もあります。
建物の減価償却は経営初期のキャッシュフローを押し上げる強力な武器です。木造なら定額法で年間建物価格の4.6%前後を経費化できますが、築年数や設備仕様により上下します。2025年度から適用されている中小企業経営強化税制を活用すれば、一定の省エネ設備は即時償却も可能です。もっとも、この制度は2027年3月までの時限措置なので、導入計画を早めに立てることが得策です。
リスク管理と出口戦略
実は、リスクを限定しながら出口を複数準備しておくことで、アパート経営はぐっと安定します。
同一エリアに物件を集中させると、地域要因で収益が大きく揺らぎます。そこで私は駅徒歩圏と郊外戸建て需要の高い地区を組み合わせるポートフォリオを推奨しています。これにより家賃動向の相関が下がり、空室率ショックを緩和できます。東京都区部と北関東の二物件を保有したクライアントは、コロナ禍でも総収入の減少を三%に抑えられました。
火災保険や地震保険の補償内容もこまめに見直しましょう。2025年1月の料率改定で木造アパートの地震保険料は平均5.1%値上げされましたが、免責金額を調整すれば保険料を抑えつつ補償を確保できます。さらに家賃保証特約を付けておくと、災害後の空室期間も家賃を確保できるため、短期投資の収支ブレを減らせます。
出口は売却だけではありません。相続が近い場合には、アパートを法人に移して株式で承継する方法も有効です。この手法なら登録免許税や不動産取得税がかからず、評価も純資産を基準に決まるため、相続税額を圧縮できます。また金融機関が後継者の経営継続を評価し、低金利で融資を継続する場合が多い点もメリットです。
2025年度の税制と金融環境を読む
さらに、制度と金利動向を理解しておくと、戦略の精度が高まります。特に2025年度は金融・税制の小さな変更が多いため注意が必要です。
日銀は2025年4月にマイナス金利を解除しましたが、長期金利は依然として1%台にとどまっています。都市銀行の投資用ローン固定金利は平均2.4%と、2023年比で0.3ポイント上昇にとどまっています。つまり金利は上げ基調ながら緩やかで、借り換えの余地がまだ残っている状態です。繰り上げ返済より借り換えを優先するほうが、キャッシュを温存できるケースが多いでしょう。
税制面では、2025年度税制改正で顧問税理士の間接費として認められる要件が緩和され、不動産所得との損益通算がしやすくなりました。また、登録免許税の軽減措置は2027年3月まで延長されることが決まっており、建築後の法人移転を計画している人には追い風となります。一方、過大な広告費を使った節税スキームへの調査が強化されているため、過度な経費計上は避けましょう。
2025年度に新設された「既存賃貸住宅省エネ改修補助金」は、外壁断熱や高効率給湯器を導入する場合に工事費の三分の一(上限120万円)が補助されます。制度の対象は2027年2月着工分までと期限があるため、短期投資で売却価値を高めたい人は早めに申請すると効果的です。省エネ改修は家賃を平均5.5%引き上げたという実績があり、空室率改善にも貢献します。
まとめ
アパート経営は相続税評価を圧縮し、家賃収入で納税資金を生み出す点で相続対策に向いています。一方、減価償却と市場動向を利用すれば短期投資としても十分に成立します。ただし楽観的な収支計画は禁物で、金利上昇や空室率の変動を織り込んだ備えが欠かせません。制度と金融環境を随時チェックし、自分に合った出口戦略を複数持つことが成功への近道です。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅局 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 相続税評価基準 – https://www.nta.go.jp
- 一般社団法人 日本賃貸住宅管理協会 – https://www.jpm.jp
- 日本銀行 統計データ – https://www.boj.or.jp
- 金融庁 2025年度税制改正概要 – https://www.fsa.go.jp
- 環境省 既存賃貸住宅省エネ改修補助金要綱 – https://www.env.go.jp

