不動産投資に興味はあるものの、都心の新築マンションは高すぎて手が出ない――そんな悩みを抱える方は多いでしょう。築古のアパートや戸建てなら購入価格を抑えられますが、古さゆえのリスクも気になります。そこで本記事では、収益物件として築古物件を選ぶ際に「何を」「どこまで」現実的な目線で確認すべきかを詳しく解説します。読み終えれば、物件選びのチェックポイントから資金計画、2025年度に利用できる補助制度まで、初心者でも自信を持って次の一歩を踏み出せるはずです。
収益物件として築古を狙うメリットと前提条件
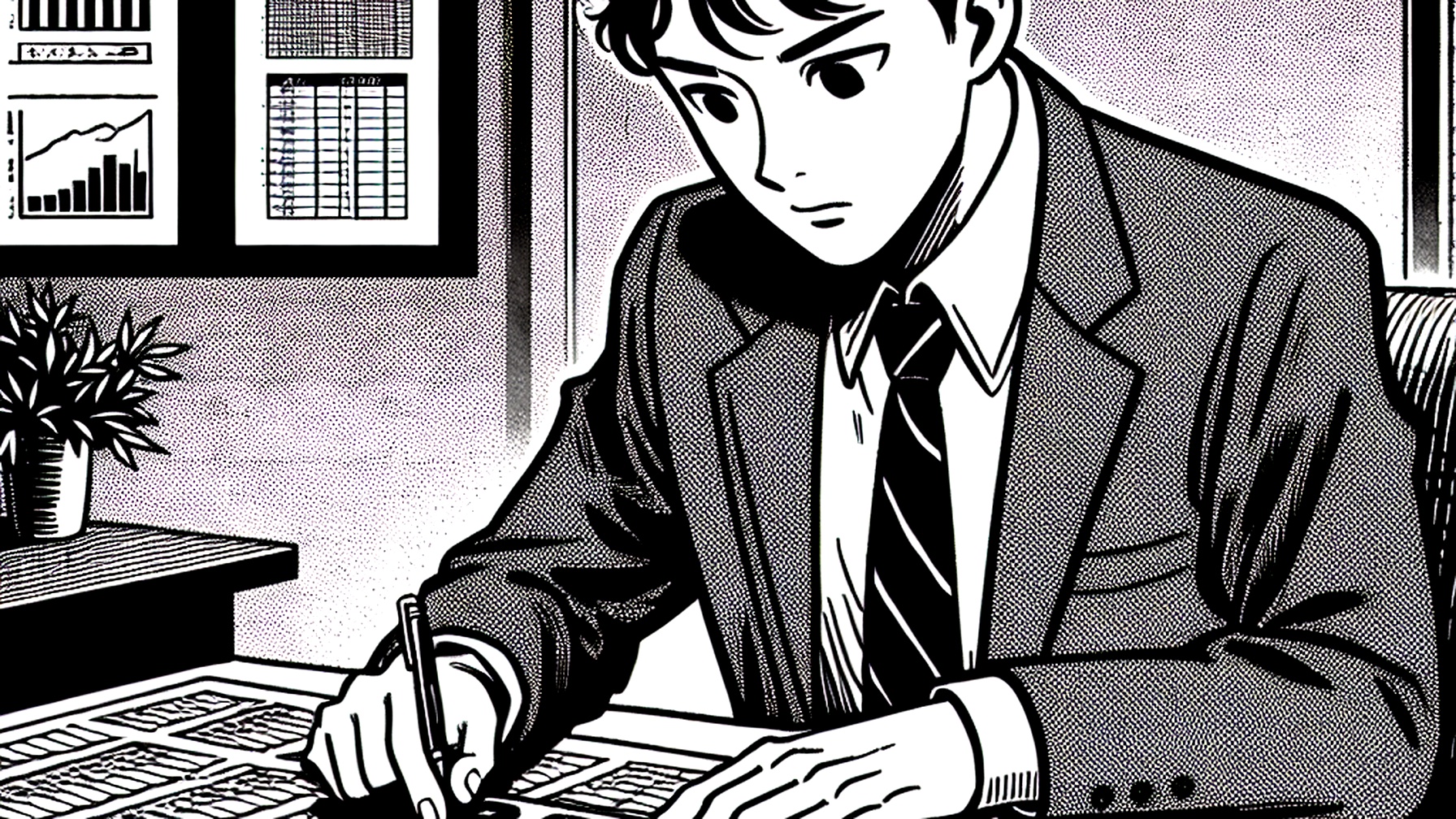
ポイントは、低い購入価格がもたらす利回り改善効果を正しく理解することです。新築に比べて築古の価格は大幅に下がるため、同じ家賃でも表面利回りが高くなりやすいのが最大の魅力です。
まず都心近郊の木造アパートを例に取ると、築30年超で価格が土地値に近づいているケースが少なくありません。土地値割れを起こしにくい水準で買えれば、売却損のリスクを抑えつつインカムゲイン(家賃収入)を狙えます。また、減価償却費を大きく取れるため、課税所得の圧縮が可能になる点も税務上の利点です。
一方で、設備の老朽化による修繕コストが無視できないことを忘れてはいけません。購入直後に屋根や配管をまとめて交換するケースもあり、初期投資が想定より膨らむことがあります。つまり、築年数だけでなく、実際の状態をプロに調査してもらい、修繕計画と見積もりをセットで把握する姿勢が欠かせません。
現実的なキャッシュフロー計算の手順
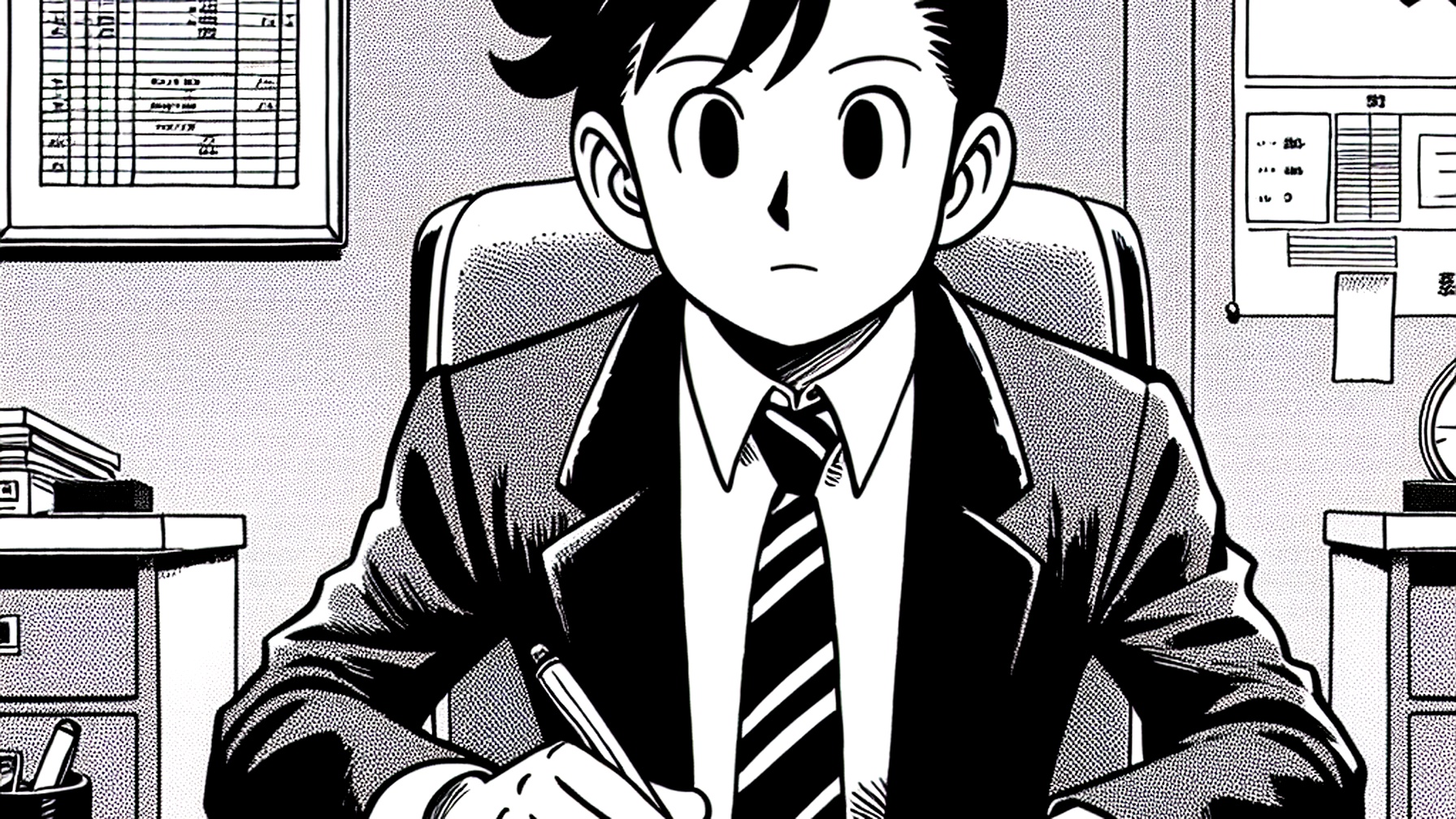
重要なのは、家賃収入からすぐに返済額を引くだけでは不足するという点です。空室期間や維持費を織り込むことで、手残りを実態に近づけられます。
家賃収入には平均7〜10%の空室率を見込み、さらに管理手数料5%、固定資産税1〜2%、火災保険0.3%程度を差し引きます。総収入に対するランニングコストが20%を超えるかどうかで、投資の安全度が大きく変わります。国土交通省「賃貸住宅市場概況調査」(2024年版)によると、築30年超の木造アパートの平均空室率は13%前後です。やや厳しめの数字を使い、最悪でも月々のキャッシュフローが赤字にならないラインを確認しておきましょう。
融資条件については、地方銀行や信用金庫が築年数に応じて「耐用年数−築年数+10年」程度の返済期間を提示する場合が多いです。返済を短めに設定されると毎月の負担が増えるため、金利だけでなく期間も総合的に交渉することが肝要です。
物件調査で必ず見るべき法的・物理的チェック
まず押さえておきたいのは「建築基準法違反」の有無です。再建築不可物件や接道義務を満たさない土地は、出口戦略が制限されます。固定資産税評価額が安くても、買い手が付かず将来売却できないリスクが高まるからです。
次に物理的側面として、給排水管・屋根・外壁の劣化状況を把握しましょう。国交省の長寿命化ガイドラインでは、築30年を超えると配管や屋根の全面更新が推奨されています。調査報告書で交換実績が確認できない場合、購入後2〜3年以内に100万〜300万円規模の出費が発生する可能性があります。現地調査に同行するインスペクション(建物検査)専門家の費用は10万円前後ですが、潜在的な不具合を把握するためには不可欠な投資と言えます。
また、都市計画法上の用途地域を確認し、将来の土地活用の自由度をチェックすることも忘れないでください。例えば第一種低層住居専用地域では建ぺい率・容積率に制限が厳しく、増改築の幅が狭まります。将来的に再開発やアパート建て替えを検討するなら、より緩やかな用途地域の土地を選ぶと選択肢が広がります。
2025年度に活用可能な補助・減税制度
実は、築古物件でも一定の省エネ改修を行えば、国の補助金を受けられる場合があります。2025年度の「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は、窓や外壁の断熱改修を実施する際、費用の最大1/3(上限120万円)が補助対象です。適用には事前の事業者登録と工事完了報告が必須で、申請枠が上限に達すると終了しますので早めの計画が求められます。
さらに固定資産税の軽減措置も検討に値します。築20年以上の木造住宅であっても、耐震補強工事を実施し自治体の認定を得れば、翌年度分の固定資産税が1/2になる制度が2025年度も継続予定です。期限は各自治体により異なりますが、「工事完了から3カ月以内に申告」が共通の条件なので注意してください。
加えて、個人投資家が受けられる代表的な減価償却メリットは2025年も変わりません。木造は法定耐用年数22年を超えると、残存年数でなく4年で償却可能です。これにより初年度から大きな経費計上ができるため、所得税や住民税を圧縮し、キャッシュフローを実質的に改善できます。
現実的な出口戦略と将来価値の読み方
基本的に、築古物件の出口は「建物価値ゼロで土地のみ売却」と考えると安全です。土地値が下支えしていれば、家賃が下がり続けても最終的な損失を限定できます。国税庁の路線価は毎年7月に更新されますが、直近5年のデータを並べ、下げ幅が小さい地域を選ぶと将来の値下がりリスクを抑えられます。
一方で、リノベーションによる価値向上を狙う戦略もあります。築30年超のファミリー向けマンションを1室あたり200万円でフルリフォームし、家賃を月2万円上げられれば、年間24万円の増収です。利回り換算で12%になるため、投資額の回収に約8年しかかかりません。こうした計算を複数パターン行い、「投資回収期間10年以内」を一つの目安にすると、無理のない計画を立てやすくなります。
出口までの期間を想定し、ローン返済完了時点での残債と土地価格を比べるシミュレーションも必須です。万一の金利上昇や空室悪化を考慮したシビアな数字を使い、それでも最終的に黒字になるか確認しておくことで、精神的なゆとりを保ちやすくなります。
まとめ
築古物件を収益物件として選ぶ際は、低価格ゆえの高利回りに目を奪われがちですが、現実的なキャッシュフローと修繕費を綿密に計算する姿勢が欠かせません。法的リスク、物理的劣化、融資条件をトータルで点検し、2025年度の補助金や減税策を活用すれば、投資効率をさらに高められます。まずは信頼できる専門家とともに現地調査を行い、修繕計画と出口戦略を数値で検証することから始めてみてください。堅実な準備が、長期にわたり安定した家賃収入を生む最大の近道となるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 賃貸住宅市場概況調査(2024年版) – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 既存住宅における断熱リフォーム支援事業概要(2025年度) – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 路線価図・評価倍率表(2020〜2025年) – https://www.rosenka.nta.go.jp
- 総務省 固定資産税の住宅耐震改修促進措置ガイド – https://www.soumu.go.jp
- 日本インスペクション協会 建物検査費用統計レポート2025 – https://www.jshi.or.jp
