不動産投資に興味はあるけれど、一棟購入は資金も知識もハードルが高い──そんな悩みを持つ方が急増しています。実は、近年伸びている「不動産クラウドファンディング」を使えば、少額から物件オーナーの一員になれます。とはいえ、案件をどう比較し、どこまで堅実性を担保できるのかは初心者の大きな疑問です。本記事では、築古物件を中心としたクラウドファンディングの特徴を解説し、2025年時点の市場データを踏まえて選び方を具体的に示します。読み終えたころには、リスクを抑えて着実に資産形成を進めるための視点が身につくでしょう。
不動産クラウドファンディングの仕組みと魅力
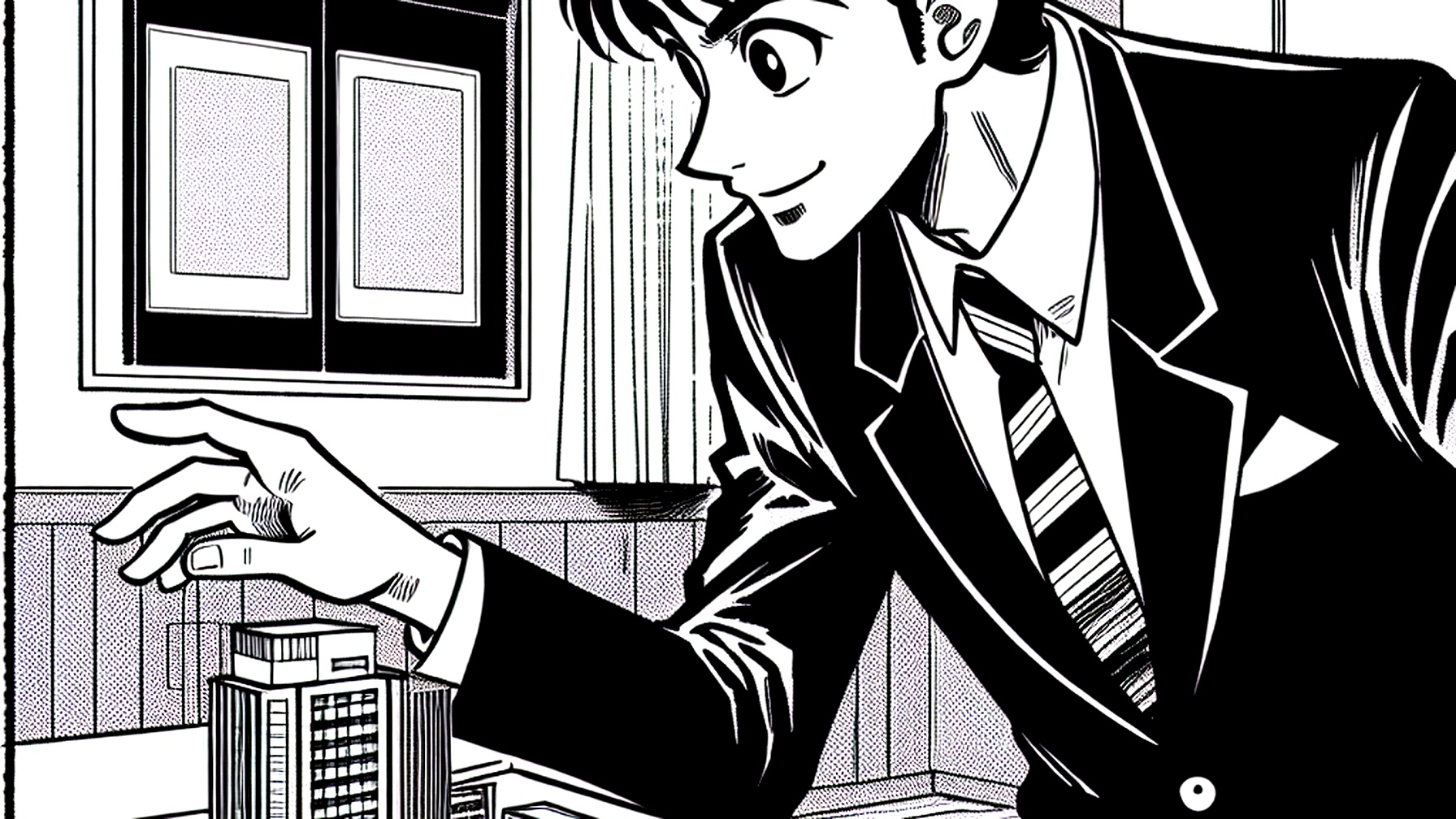
まず押さえておきたいのは、クラウドファンディングが小口化とプロ運営を組み合わせた新しい不動産投資だという点です。事業者は数千万円から数億円規模の物件を取得し、出資単位を1口1万円前後に細分化して投資家を募ります。運用期間が1〜3年と比較的短く、分配金は半年ごとに支払われる案件が多いので、キャッシュフローを確認しやすいのが特徴です。
次に魅力となるのが、プロによるアセットマネジメントです。物件の取得、工事、賃貸管理、売却までを一括で行う事業者が大半を占め、投資家は運営の手間を負いません。つまり、実物不動産の利点を維持しながら、REIT(上場不動産投資信託)よりも物件を選べる自由度を確保できるわけです。
さらに、2024年の改正不動産特定共同事業法でオンライン完結型ファンドの規制が整理され、2025年10月時点では全ての主要事業者が電子取引業務の認可を取得しています。金融庁のモニタリング報告によると、2025年度上期のクラウドファンディング累計調達額は前年同期比34%増となり、市場の裾野は確実に広がっています。
築古物件に投資するメリットとリスク
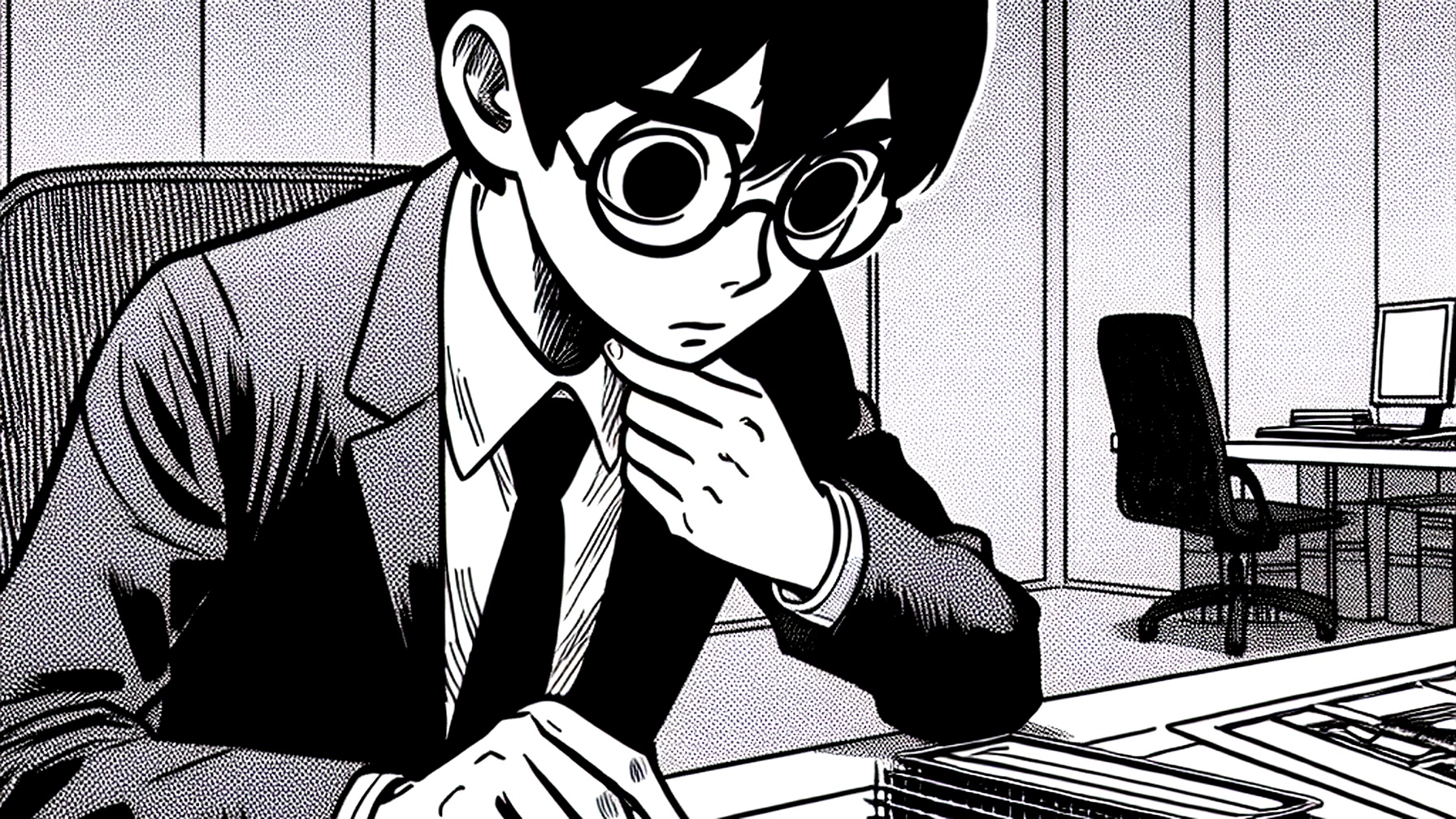
重要なのは、築年数が古い物件だからこそ得られる収益源泉があるという事実です。築古は取得価格が安いため、賃料に対する投資額の比率(利回り)が高くなります。国土交通省の不動産価格指数(2025年7月公表)では、築30年以上の区分マンション価格は築浅物件の約6割にとどまりましたが、平均賃料は8割を維持していました。つまり、家賃が下がりにくい一方で購入価格が抑えられる構造が利回りを押し上げます。
一方で避けられないリスクが修繕費です。築古は給排水管や屋上防水の工事が必要になるケースが多く、ファンド期間中に突発的な出費が発生する可能性があります。また耐震性も懸念材料ですが、2025年時点で主要事業者は耐震基準適合証明を取得した物件に限定する動きが広がっており、募集要項で確認できるようになりました。
加えて、出口戦略にも工夫が求められます。築古は値上がり益を狙うより、運用期間中のインカムゲイン(賃料収入)を重視する設計が多いです。そのため、売却益より分配金依存度が高くなる点を理解し、ファンドの収支シミュレーションが保守的かどうかを確認することが堅実性を高める鍵となります。
堅実派が押さえるべき比較ポイント
ポイントは、利回りだけでなく「劣後出資比率」「空室損設定」「運営者の実績」を総合評価することです。劣後出資とは、損失が出た際に事業者が先に負担する自己資金の割合で、10〜30%が一般的ですが、築古ファンドでは20%以上あると安心感が高まります。また、空室損を賃料収入の10%前後で見込むのが保守的とされ、募集ページに明示されているか必ず確認しましょう。
次に比較したいのが、運営者の過去償還実績です。2023年以降に10本以上のファンドを満期償還し、元本割れゼロを維持している事業者は、金融庁公表データで全体の4割にとどまります。実は、案件単位で見ると築古ファンドの方が延滞リスクは高めなので、事業者の経験値が大きくものを言います。
さらに、情報開示のレベルも重要です。物件所在地が「東京都○○区」まで開示されているか、工事費用・管理費の内訳が開示されているかで、透明性に差が出ます。総務省「住宅・土地統計調査」を参照し、人口動態が安定しているエリアかどうかを自分でも調べることで、受け身の投資から一歩抜け出せます。
2025年時点の市場動向と成長シナリオ
実は、空室率の改善と金利情勢が築古クラウドファンドの追い風になっています。日本不動産研究所のレポートによると、2025年4月時点の東京23区ワンルーム空室率は3.9%と過去10年で最低水準に下がりました。背景にはテレワーク浸透後のオフィス回帰と、単身転入の再加速があります。
金利面では、日銀が長短金利操作(YCC)を段階的に修正しつつも、住宅ローン変動金利の平均は1%未満を維持しています。事業者が調達するシニアローンも低水準にとどまり、利回りの源泉を確保しやすい状況です。つまり、築古でもキャッシュフローが出やすい環境が続いているわけです。
ただし、2026年以降は人口減少エリアで賃料下落が予想されるため、物件所在地の将来人口をチェックする視点が欠かせません。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計でも、郊外の一部で20代転入超過が反転する見通しが示されています。投資判断の際は、賃料下落シナリオが組み込まれているかを確認すると、リスク管理が一段と強固になります。
賢いポートフォリオ構築法
まず、築古クラウドファンドを資産全体の20〜30%にとどめ、残りは上場REITや投資信託で分散することで、流動性リスクを抑えられます。クラウドファンドは途中解約ができない案件が多いので、満期まで使わない余裕資金を投じるのが基本です。
次に、案件をローリングで組み合わせると安定したキャッシュフローが生まれます。たとえば、3年満期、2年満期、1年満期を同時に仕込めば、毎年いずれかが償還し、再投資資金が確保できます。これにより、景気変動を受けるタイミングを分散できるわけです。
最後に、所得税の損益通算を意識しましょう。クラウドファンドの分配金は雑所得として総合課税されますが、他の不動産所得や青色申告特別控除と相殺できません。課税所得が高い方は、iDeCoや新NISAなどの非課税枠と併用し、税負担を最小化する戦略を取ると、手取り利回りが向上します。
まとめ
築古物件を対象とした不動産クラウドファンディングは、低価格で高利回りを狙える一方、修繕費や空室リスクといった固有の課題が存在します。劣後出資比率や運営者の実績、空室損の設定などを丁寧に比較すれば、堅実性を高めながら市場成長の果実を享受できます。まずは少額から複数案件へ分散投資し、データを読み解く習慣を身につけてください。それが、2025年以降も続く人口・金利動向の変化に柔軟に対応できる投資家への近道となります。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp/
- 金融庁 モニタリングレポート2025 – https://www.fsa.go.jp/
- 日本不動産研究所 市場動向レポート2025 – https://www.reinet.or.jp/
- 総務省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp/
- 一般社団法人 不動産証券化協会(ARES)データライブラリ – https://www.ares.or.jp/

