不動産価格は上がる一方、年金だけでは老後資金が足りるのか不安――そんな声を毎日のように耳にします。都内でマンションを買うには数千万円が必要ですが、手元資金が限られていると二の足を踏んでしまうでしょう。そこで注目されるのが少額から始められるREIT(リート)です。実は、荒川区のように生活コストを抑えやすいエリアに住みつつ、REITで全国の優良物件に投資すれば、利回りを確保しながら老後資金を効率よく積み上げられます。本記事では、初心者でも分かるようREITの基礎、荒川区の不動産事情、2025年度の税制優遇まで丁寧に解説します。
預金だけでは賄えない老後資金ギャップ
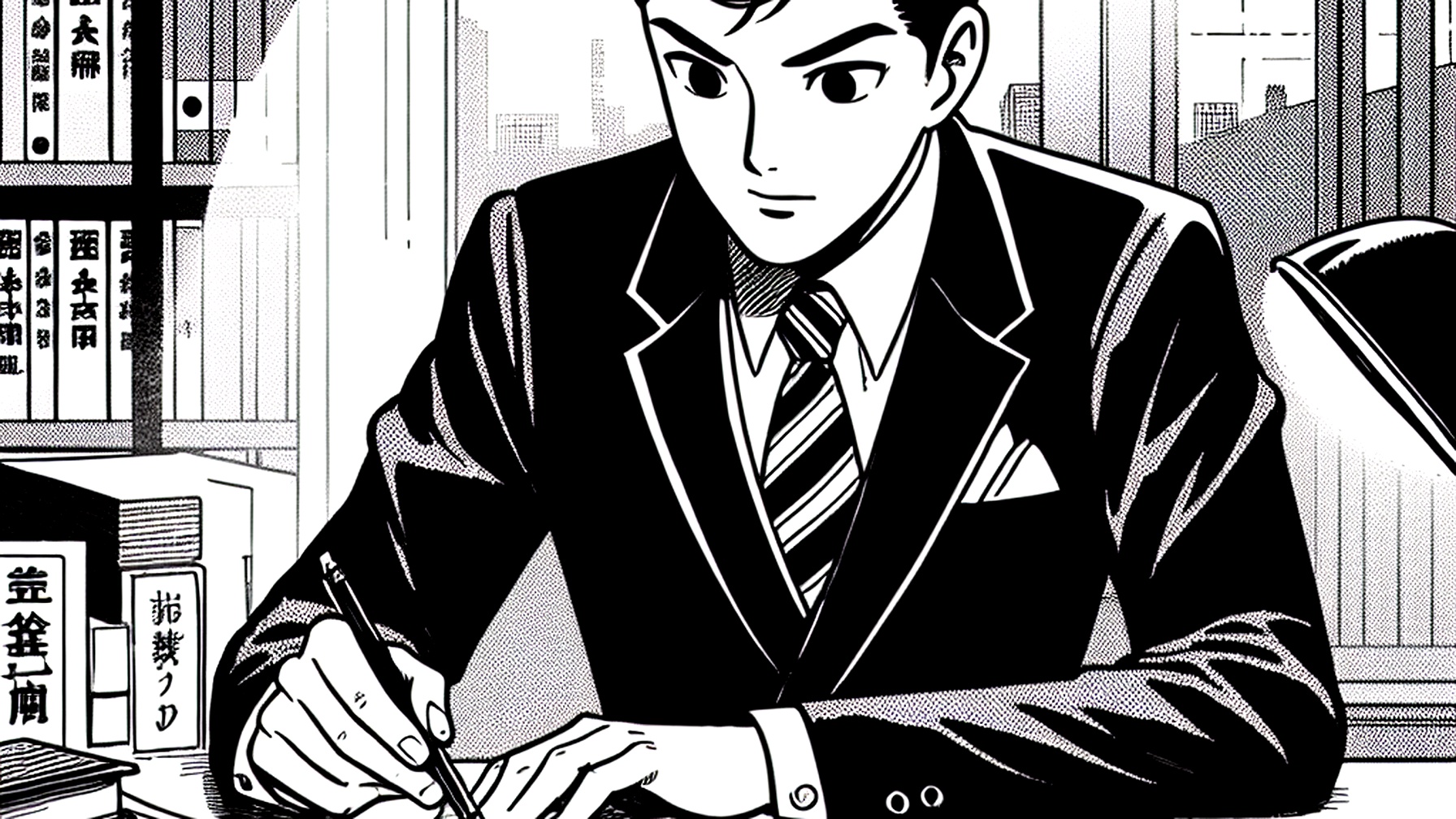
まず押さえておきたいのは、平均寿命の延伸によって老後生活が長期化している点です。厚生労働省の最新統計では、65歳時点での平均余命は男性が約20年、女性は約25年に達しました。総務省の家計調査によると、夫婦2人の最低日常生活費は月平均約24万円ですが、年金受給額の平均は約19万円にとどまります。つまり単純計算で月5万円の不足が生じ、30年間で1,800万円の資金ギャップが発生するのです。定期預金の金利が年0.2%前後にとどまる中、この差を埋めるには利回りの高い投資先が不可欠になります。
では、株式や投資信託だけで良いのかと言えば、価格変動が大きくリタイア後の生活費を取り崩す局面では心理的負担も小さくありません。そこで家賃という安定収入を背景に配当を受け取れるREITが注目されるわけです。荒川区民の平均可処分所得は23区内でも中位に位置し、生活コストは比較的抑えられます。ゆえに、余裕資金をREITへ回し老後資金を補填する戦略が現実味を帯びてきます。
REITと利回りの基本構造を理解する
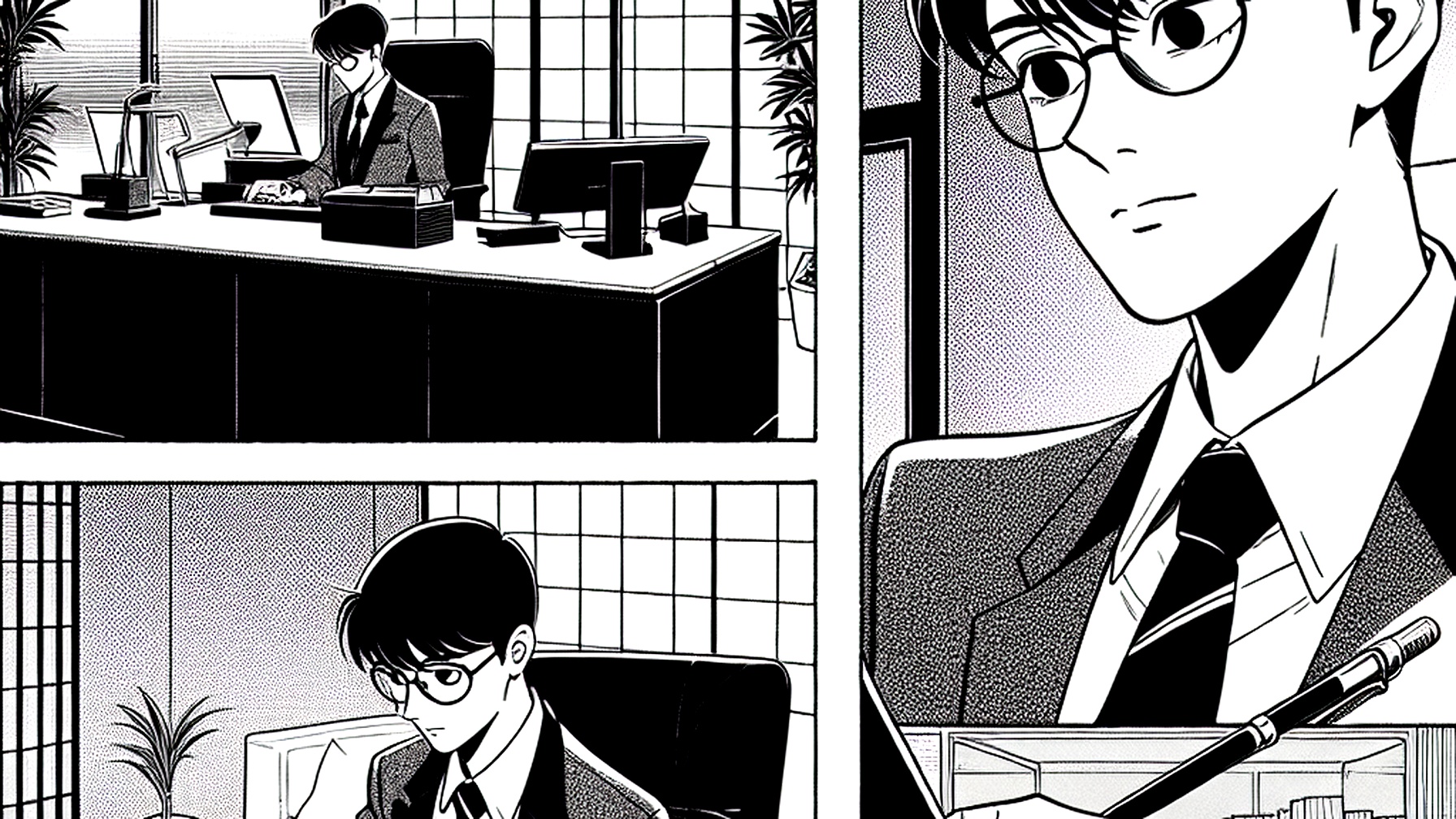
重要なのは、REITが投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設、住宅など複数の不動産を保有し、その賃料収入や物件売却益を分配する仕組みだという点です。法律上、利益の90%以上を分配すれば法人税が実質免除されるため、分配金利回り(配当利回り)が相対的に高くなります。2025年10月時点で東証REIT指数の平均分配金利回りは約4.1%で、同時期の長期国債利回り(約1.1%)を大きく上回っています。
利回りは「予想年間分配金÷投資額」で算出されますが、銘柄によって賃料の安定性や修繕コストが異なるため、数字だけで判断するのは危険です。例えば都心オフィス主体のREITは景気変動の影響を受けやすい一方、住宅特化型はリーマンショック時でも分配金の落ち込みが小さかった実績があります。つまり、自身のリスク許容度に合わせて複数のREITを組み合わせ、ポートフォリオ全体で利回りと安定性をバランスさせることが欠かせません。
加えて、REITは株式と同様に証券取引所で売買されるため価格が日々動きます。分配金利回りを高めたいあまり下落相場で飛びつくと、含み損に耐えきれず売却してしまうケースも散見されます。荒川区から都心への通勤時間が短い利点を活かし、仕事帰りにマーケット情報をこまめにチェックしておくと、冷静な投資判断が下しやすくなるでしょう。
荒川区の不動産事情とREIT投資の相性
実は、荒川区は再開発の波が緩やかな分、地価上昇が落ち着いているため居住コストを抑えやすいエリアです。国土交通省「地価公示」によると、2025年の住宅地平均単価は23区平均の6割弱に過ぎません。一方、JR山手線沿線に近く、都心へのアクセスは良好なので賃貸需要は安定しています。この住環境を活かし、住宅ローンや家賃を抑制したぶんをREITへ回すことで、複利効果を最大化できる点が大きなメリットと言えます。
2025年の日本不動産研究所のデータでは、東京23区のワンルームマンション平均表面利回りが4.2%と報告されています。荒川区の区分マンション利回りはそれを上回る4.5%前後の事例もありますが、自己資金や融資条件によっては物件購入よりREITへ分散投資した方が手取り利回りは高くなる場合があります。理由は、取得時の仲介手数料や固定資産税、修繕積立金などのコストをREITがスケールメリットで吸収しているためです。
さらに、荒川区の人口は微増傾向ながら高齢化率が上昇しています。将来、自宅を売却して介護施設費用に充てる選択肢を持つなら、流動性の高いREITで資産運用しておくと現金化が容易です。このように、自分が暮らすエリアの特徴とREITの機動力を組み合わせることで、老後資金戦略の柔軟性が高まります。
ポートフォリオ作りとリスク管理の具体策
まず意識したいのは、分配金利回りだけでなく「LTV(負債比率)」や「稼働率」といった財務指標を確認することです。LTVが50%台に収まっていれば財務健全性は概ね良好とされ、賃料収入が一時的に減っても減配リスクは限定的です。また、稼働率が継続的に95%を超えている住宅系REITは賃料下落局面でも耐性があります。
分散投資の目安として、オフィス系40%、住宅系30%、商業・物流系30%程度から始めるとバランスが取りやすいでしょう。ただし、荒川区で自宅を持つ場合、住環境として都心アクセスのメリットを既に享受しているため、REITでは地方物流施設やデータセンターを多く組み込むと地域リスクの分散効果が高まります。つまり、自分の生活圏と投資対象を意図的にズラすことがカギです。
価格変動リスクに備えるには、毎月一定額を購入する積立投資が有効です。積立なら高値掴みを避けられ、平均取得単価を平準化できます。なお、騰落率が大きい局面では配当性向が維持されているか確認しましょう。もし大幅な減配予告が出た場合は、含み損益にかかわらず資金を別銘柄へシフトする柔軟さも必要です。
2025年度の税制優遇と実践ステップ
ポイントは、REIT投資を非課税枠と組み合わせることで手取り利回りを高めることです。2024年に刷新された新しいNISAは2025年度も継続しており、年間360万円の成長投資枠を利用してREITを購入すれば、分配金と譲渡益にかかる20.315%の税金が最長無期限で非課税になります。また、iDeCo(個人型確定拠出年金)は掛金が全額所得控除となり、運用益も非課税のまま60歳以降まで繰り延べ可能です。荒川区に在住する会社員であれば、月2.3万円の掛金上限を活用し、REIT型投資信託を組み入れることで税負担を抑えつつ老後資金を積み立てられます。
実際の手順はシンプルです。まず証券会社で一般口座とNISA口座を同時開設し、毎月の予算を決めます。次に、東証REIT指数連動型ETFをベースに、個別REITを1〜2銘柄追加してコア・サテライト戦略を構築します。荒川区内の金融機関窓口も便利ですが、ネット証券の方が売買手数料が低く、積立設定も柔軟です。最後に、年1回はポートフォリオを見直し、分配金の再投資や銘柄入れ替えで利回りを底上げしてください。こうした手間を惜しまなければ、10年後の資産規模に大きな差が生まれます。
まとめ
本記事では、年金だけでは不足する老後資金を補う手段としてREITを活用する方法を解説しました。荒川区は住居費を抑えやすく、余剰資金を投資に振り向けるには好適なエリアです。REITは少額から高利回りを狙える一方、銘柄選びと分散投資が欠かせません。NISAやiDeCoの非課税メリットを重ねれば、手取り利回りは預金の数十倍に達します。今日からできるのは、証券口座を開設し、毎月の積立額を決めること。将来の自分への仕送りを着実に増やし、安心してセカンドライフを迎えましょう。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 国土交通省 地価公示 – https://www.mlit.go.jp
- 厚生労働省 令和6年簡易生命表 – https://www.mhlw.go.jp
- 総務省 家計調査報告 2024年 – https://www.stat.go.jp
- 東京証券取引所 REIT情報 – https://www.jpx.co.jp

