不動産投資に興味はあるけれど高額な自己資金や融資のハードルが心配――そんな悩みを抱える方が近年急増しています。実は、少額から物件オーナーと同じ利益構造を得られる方法として「不動産クラウドファンディング」が注目を集めています。しかし、相続物件を絡めた投資となると、税務や法律の問題が複雑に感じられるかもしれません。本記事では、不動産クラウドファンディングの基本から具体的な始め方、相続物件を活用する際のチェックポイントまでを整理し、2025年10月時点で有効な制度や最新データを交えて解説します。読み終えるころには、自分に合った投資戦略と注意点がクリアになるはずです。
不動産クラウドファンディングとは何か
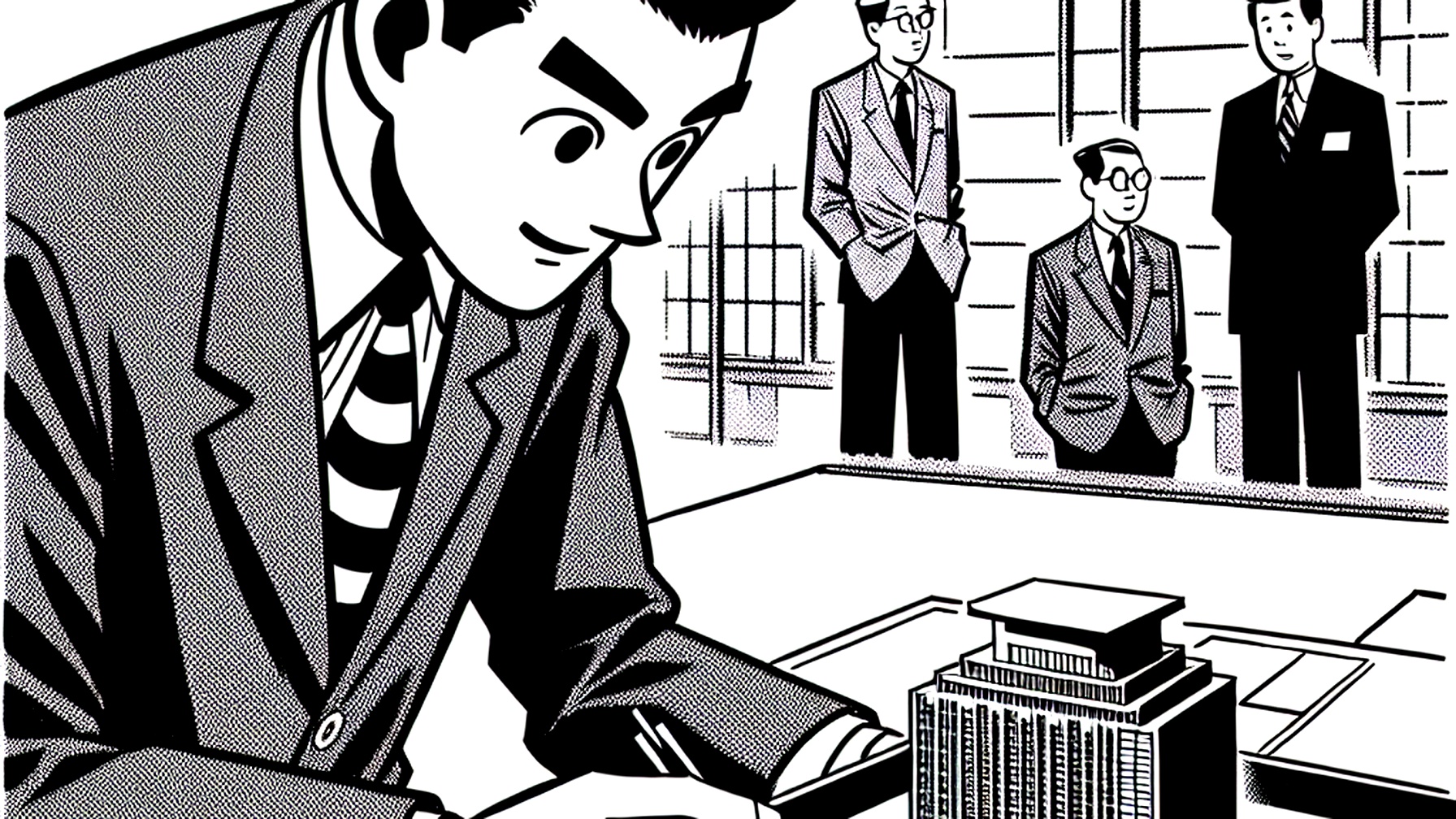
まず押さえておきたいのは、不動産クラウドファンディングが「不動産特定共同事業法」に基づく仕組みだという点です。この制度では事業者が小口出資を集め、取得・運用した不動産の賃料や売却益を出資者に分配します。金融庁の2025年6月レポートによると、同年3月末時点で累計調達額は3,400億円を超え、前年同期比で28%伸びました。
こうした成長の背景には、最低1万円程度から参加できる手軽さと、オンラインで契約完結できるスピード感があります。言い換えると「物件を直接所有せず、分配金だけ受け取る」という新しい投資体験が支持を集めているのです。一方で、出資対象ファンドのリスクや運営会社の信用力を自分で見極める必要がある点は忘れられません。
また、実際の不動産を保有しないため、固定資産税や管理費はファンド側で処理されます。この点は忙しい会社員にとって大きなメリットですが、裏を返せば物件を自分の裁量でリフォームしたり、賃料設定を変えたりできないデメリットでもあります。つまり、クラウドファンディングは「運営会社に運用を委ねる仕組み」と理解したうえで、リスクとリターンのバランスを判断することが大切です。
始め方の具体的ステップ
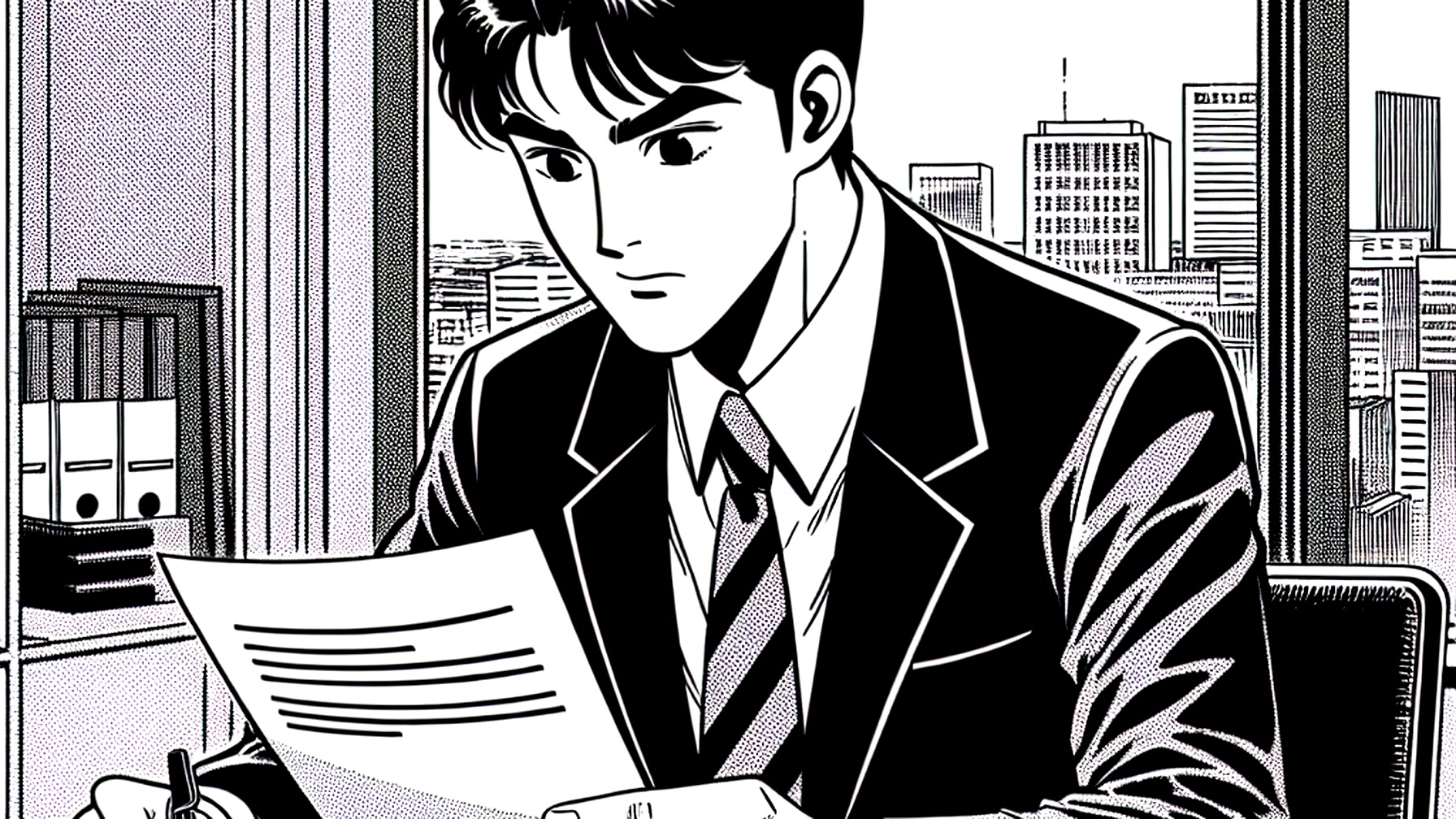
ポイントは「登録→審査→ファンド選択→入金→運用」の五段階を順番にこなすことです。まず、希望する事業者のサイトで投資家登録を行い、本人確認書類をアップロードします。マイナンバーカードと運転免許証があれば、最短当日に取引開始できるケースもあります。
次に行うのがオンライン適合性審査です。これは金融商品取引法に基づき、年収や投資経験を確認するプロセスで、リスク許容度に合わない商品への出資を防ぐ目的があります。審査に通過すると、公開中のファンドに申し込める状態になりますが、人気案件は募集開始数分で満額になることも珍しくありません。そのため、事前に通知メールを設定し、募集開始のアラートを受け取る準備が有効です。
入金は投資家専用口座に振り込む形が一般的で、2025年現在は銀行振込手数料を事業者が負担するサービスも増えています。入金確認後、正式に出資が成立し、運用がスタートします。運用期間中はマイページで賃料収入や工事進捗を確認でき、途中解約は原則不可ですが、セカンダリ市場を開放する事業者も一部出てきました。こうした柔軟性の有無は、始める前に必ずチェックしておきましょう。
相続物件を活用する際の基礎知識
実は、相続した空き家や区分マンションをファンドに組み入れることで、維持コストを削減しつつ収益化を図る動きが広がっています。国土交通省の2025年版「空き家実態調査」では、所有者が管理できないまま放置される物件が約358万戸と推計され、社会問題化しています。
相続物件をクラウドファンディングに提供する場合、まず不動産を信託会社に移転し、受益権をファンド参加者に分配する形が一般的です。この方法なら、相続人自身は追加資金を出さずにリフォーム費用をまかなえ、投資家は賃料収入の一部を受け取る仕組みが成立します。ただし、信託契約の設定費用や登録免許税が発生するため、物件評価額が1,000万円未満だと費用対効果が合わない場合があります。
さらに、2025年度の税制では、相続空き家の譲渡所得3,000万円特別控除が引き続き適用されています。ただし、適用期限が2026年12月31日までと定められているため、クラウドファンディングに組み込む前に売却するか、長期運用するかの判断が重要になります。税理士と相談し、どのタイミングでどの制度を使うか戦略的に決めましょう。
覚えておきたいリスクと注意点
重要なのは「元本保証ではない」という事実を常に認識することです。不動産市場が下落し、売却益が想定を下回る場合、分配金が減少したり、元本割れが起こるリスクがあります。加えて、賃料遅延や災害による修繕費増大も分配金に影響します。
また、運営会社の財務体質に問題が生じれば、ファンド自体の継続性が揺らぎます。金融庁登録番号を確認することは最低条件ですが、直近の貸借対照表や運用実績、匿名組合か任意組合かといった契約形態も必ず確認してください。匿名組合契約の場合、投資家は出資額を超える損失を負わない一方、意思決定への関与も制限されます。
さらに、相続物件を使う場合は共有者間の合意形成が不可欠です。共有持分のまま信託契約を結ぶと、分配比率や売却時期でトラブルになりやすく、実務では事前に持分を一本化しておくケースが多く見られます。こうした法的リスクを軽減するため、司法書士や弁護士を交えたスキーム設計が推奨されます。
2025年度の関連制度と最新動向
まず、2025年4月に施行された相続登記の義務化に伴い、登録免許税の軽減措置(固定資産評価額の0.1%)が2027年3月まで継続されます。空き家を含む相続物件を早期に登記すればコストを抑えられるため、クラウドファンディング活用前に済ませておくと有利です。
一方で、不動産特定共同事業法の改正により、オンライン完結型の事業者は自己資本規制比率を20%から16%へ引き下げる猶予措置が2025年度末で終了します。これにより、財務体質が弱い事業者は統合や撤退を迫られる可能性があります。投資家としては、事業者の増資や業務提携の動向を注視し、長期的に安心して預けられる先を選ぶことがポイントです。
さらに、環境価値を高めた「ZEB賃貸マンション」への出資では、国土交通省の2025年度サステナブル建築補助金が適用されます。ファンドを通じて投資した場合でも、事業者が補助を受ければ、運用コストが下がり分配金が安定する効果が期待できます。公式サイトや事業者の説明資料で、補助金申請の有無を必ず確認しましょう。
まとめ
本記事では、不動産クラウドファンディングの仕組み、始め方、相続物件の活用法、主要リスク、そして2025年度の最新制度までを網羅しました。少額からスタートできる魅力は大きいものの、事業者選びと契約内容の理解が成功のカギを握ります。相続物件を組み込む場合は、税制優遇の期限と共有者の合意形成を早めに進めることで、コストとトラブルを最小限に抑えられます。まずは信頼できる事業者を比較し、シミュレーションを作成して、自分の資金計画に無理がないかを確認してみてください。不動産クラウドファンディングは、準備と情報収集を怠らなければ、資産形成と空き家問題解決の両立を実現できる手段となるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省「空き家実態調査2025」 – https://www.mlit.go.jp/
- 金融庁「クラウドファンディング業界動向(2025年6月)」 – https://www.fsa.go.jp/
- 総務省統計局「住宅・土地統計調査2024」 – https://www.stat.go.jp/
- 法務省「相続登記の義務化に関する手引き」 – https://www.moj.go.jp/
- 国土交通省「サステナブル建築物等先導事業(2025年度)」 – https://www.mlit.go.jp/

