不動産投資に興味はあるものの、REITや民泊という言葉を聞くたび「難しそう」「リスクが高そう」と感じていませんか。特に最近はSNSで成功談ばかりが拡散され、逆に失敗の情報が見えにくくなっています。本記事では、2025年10月時点の制度と市場データを踏まえ、REITと民泊それぞれのデメリットを包み隠さず解説します。仕組みや費用構造を理解すれば、過度な心配をせずに自分に合う投資スタイルを選べるようになります。
REITとは何かを正しく知る
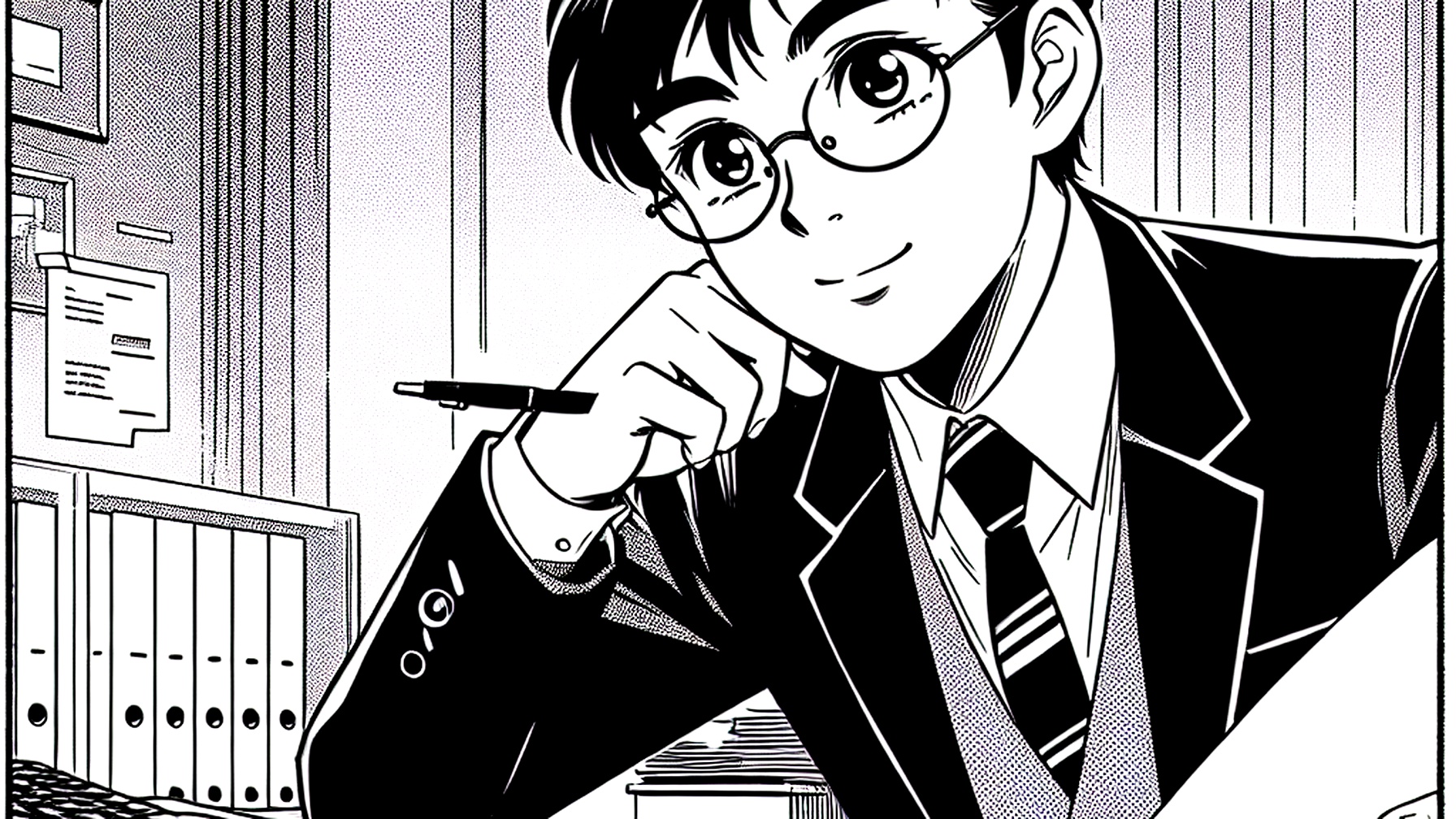
重要なのは、REITの仕組みを理解したうえで利回りの源泉を見極めることです。REIT(不動産投資信託)は、多数の投資家から集めた資金で複数の収益不動産を保有し、賃料や売却益を分配する金融商品です。
まず、証券取引所に上場しているため売買が容易です。四半期ごとの決算情報が開示され、運用状況を比較的簡単に把握できます。一方で、価格は日々変動し、株式市場の影響を受けやすい点が特徴です。つまり実物不動産より流動性は高いものの、市場センチメントに左右されやすい側面があります。
次に、投資対象の物件はオフィスや住宅、物流施設などに分かれます。国土交通省の2025年度統計によると、オフィス系REITの平均分配利回りは3.8%前後で推移しています。分散投資効果は高いものの、分配金は空室率やテナント賃料の改定で変動します。入居契約が長い物流施設型は安定しやすい一方、ホテル系は景気の波を受けやすい点に注意が必要です。
加えて、REITは不動産取得額の50%前後を借入金で賄う「レバレッジ」をかけています。金利が上昇すると分配金が圧迫される仕組みです。金融庁のモニタリングでは、平均LTV(総資産に占める借入比率)が2025年6月時点で46%と報告されています。金利上昇局面では、保守的なLTVの銘柄を選ぶことがリスク軽減につながります。
REIT投資の主なデメリットと対策
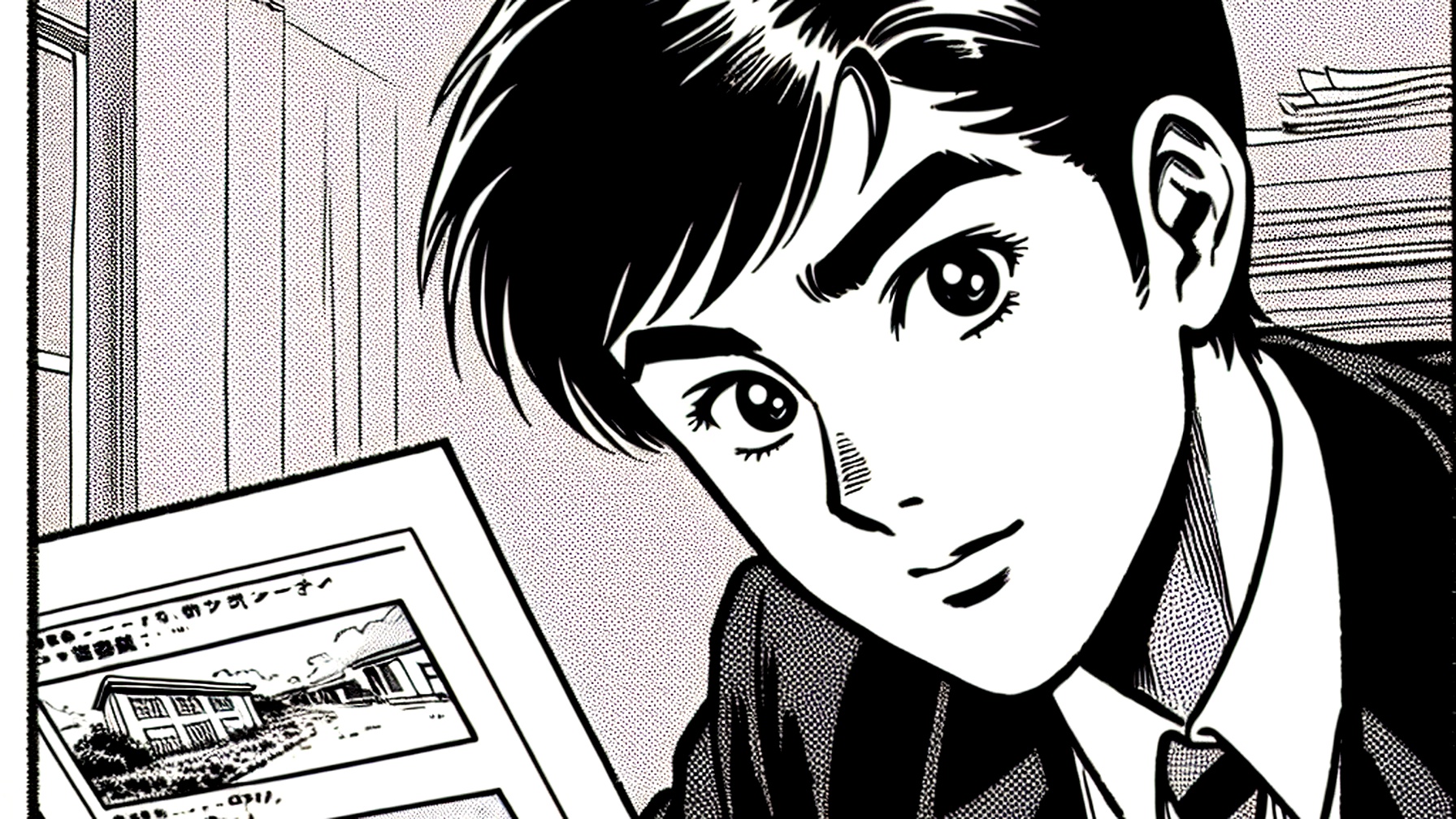
ポイントは、価格変動リスクと追加コストを具体的に把握し、過度な期待を避けることです。
最初に挙げられるのが、株価並みのボラティリティです。東証REIT指数は2024年末から2025年夏にかけて約12%の値幅を記録しました。実際の賃料は急に下がらないものの、市場心理が悪化すると価格は短期で下落します。長期目線での保有が基本とはいえ、含み損を抱えやすい点は覚悟が必要です。
次に、信託報酬や物件の運用手数料がかかります。投資法人が支払う報酬は年間総資産の0.3〜0.5%が一般的で、個人投資家が直接負担する管理費に相当します。表面利回りが高く見えても、手数料や金利負担を差し引くと実質利回りは1%台に低下するケースもあります。運用報告書で費用比率を確認する習慣が重要です。
さらに、空室リスクや賃料下落リスクは間接的に分配金へ影響します。特に複合型REITでホテル比率が高い場合、インバウンド需要が減ると収益が不安定になりがちです。日本政府観光局のデータでは、訪日外国人は2025年上期にコロナ前の96%まで回復したものの、地域による差が大きいことが分かっています。セクター分散が進んでいる銘柄を選び、分配金の安定性を確認することがリスク低減につながります。
最後に、REITは減価償却を考慮した利益の90%以上を分配する代わりに、内部留保が限られます。大規模修繕や物件リニューアルの資金を自己調達しにくいため、追加の公募増資で1口当たり分配金が希薄化するリスクがあります。増資予定の有無をIR資料でチェックし、配当性向の推移を追うことが大切です。
民泊投資の仕組みと広がり
まず押さえておきたいのは、民泊が「住宅宿泊事業法」(いわゆる民泊新法)に基づくビジネスであり、営業日数上限と自治体独自の規制を受ける点です。
住宅宿泊事業法では、年間営業日数が180日に制限されています。観光庁の2025年度レポートによると、全国の民泊届出件数は約7万5千件で、2023年比20%増となりました。インバウンド需要が戻り、地方都市でも民泊開設が進んでいますが、営業日数の制約が利益を左右します。つまり、稼働率が高くても上限に達すれば稼げる日数は頭打ちになるわけです。
また、賃貸物件を転貸する「サブリース型民泊」は、オーナーの承諾と用途変更手続きが必須です。無断転貸が発覚すると、旅館業法違反や契約解除のリスクが生じます。国土交通省のガイドラインでも、賃貸借契約に特約を明記するよう求められており、法令遵守が前提となります。
さらに、運営はゲスト対応や清掃の外注費が想定以上にかかります。東京都の平均清掃費は1回5千〜8千円で、1泊あたりの単価が引き下がると利益が圧縮されます。加えて、宿泊者とのトラブル対応や近隣クレームへの対応も不可欠です。実物不動産を長期賃貸に出すより運営の手間が大きく、システム利用料やOTA(宿泊予約サイト)手数料も発生します。
最後に、資金調達のハードルです。住宅ローンを使った民泊運営は原則認められず、投資用ローンや事業性ローンが必要です。金融機関は事業計画を厳格に審査するため、自己資金を3割以上求めるケースが多いです。金利もアパートローンより0.3〜0.5%高い水準で、初期コストがかさむ点は覚えておく必要があります。
民泊投資のデメリットとリスク管理
実は、民泊の最大のデメリットは稼働率と単価がともに下振れしたときの収益急減です。匿名性が高い宿泊者相手のビジネスだからこそ、レビュー評価とリピーターが利益を支えます。
第一に、季節変動リスクがあります。観光庁統計では、2025年8月と2月の宿泊者数を比較すると、地方都市では平均で3割以上の差が出ています。オフシーズンに料金をどの程度下げても稼働率が上がらない場合、固定費が重荷になります。繁忙期の売上だけに依存しない価格戦略が欠かせません。
第二に、感染症や災害による需要蒸発です。コロナ禍で需要が消滅した経験は記憶に新しいですが、地震や台風でも似た事態が起こりえます。宿泊予約サイトは規約により、非常事態時のキャンセル料を請求できないケースも多く、売上の急減に備えた運転資金が必要です。資金繰り計画においては、3か月以上の固定費をカバーするキャッシュを確保することが推奨されます。
第三に、地域コミュニティとの摩擦です。夜間の騒音やゴミ出し問題で苦情が寄せられると、自治体から改善命令が出る可能性があります。大阪市の行政指導件数は2024年度に前年度比15%増加しており、運営体制の整備がより厳しく問われています。英語対応スタッフの確保やハウスルールの多言語掲示が必須となり、運営コストは想像以上に膨らみます。
最後に、物件価値の下落リスクです。民泊用途で改装した物件は、通常の賃貸に戻す際に追加工事が発生します。水回りの増設や家具備え付けが資産価値を下げる場合もあり、出口戦略を考えた計画が重要です。売却時に「民泊用途だった」という情報がマイナス評価につながる地域もあるため、取得前に不動産会社へ査定影響を確認しておくと安心です。
REITと民泊、目的別の選択基準
ポイントは、投資目的と手間の許容度を明確にし、両者を比較することです。安定配当を重視するか、高い粗利を狙うかで最適な手法は変わります。
まず、手間の観点ではREITが優勢です。購入後は価格をウォッチするだけで、運営や修繕の実務は不要です。分配利回りは3〜4%が目安で、大きく儲かるわけではありませんが、サラリーマンが副業として保有しやすい点が魅力です。ただし株式市場の急変動で資産評価が変わるため、長期保有を前提に精神的余裕が必要です。
一方で、民泊は実務の負担が大きいものの、稼働率次第で想定利回り10%超も現実的です。自己裁量で価格設定やマーケティングを行えるため、ビジネスオーナー感覚で取り組めます。時間と労力をかけられる人ほど収益が伸びる構造ですが、参入障壁は年々高くなっています。2025年度は規制強化により、消防法対応や騒音計測装置の設置が求められる自治体が増え、初期費用は従来より10〜15%高くなる傾向です。
両者を組み合わせる戦略もあります。たとえば資産全体の7割をREITで安定運用し、3割を民泊事業に充てることで、リスク分散と成長性を同時に追求できます。金融庁のポートフォリオ例では、リスク資産を分散すると最大ドローダウンが平均15%低下すると報告されています。自分のリスク許容度とライフスタイルを踏まえて比率を調整することが、長期的な資産形成を実現するカギとなります。
まとめ
REITと民泊は同じ不動産投資でも、リスクと手間の質が大きく異なります。REITは市場変動と手数料による利回り低下に注意し、民泊は営業日数制限と運営コストが収益を左右します。どちらが優れるかではなく、自分が確保できる時間と資金、そしてリスク許容度を基準に選択することが重要です。まずは小口でREITを購入し、市場感覚を養いながら、余裕があれば民泊の事業計画を精密に組み立てるステップが現実的と言えます。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産証券化協会統計 – https://www.mlit.go.jp/
- 金融庁 REITモニタリングレポート2025年6月 – https://www.fsa.go.jp/
- 観光庁 住宅宿泊事業法に関する統計2025年度 – https://www.mlit.go.jp/kankocho/
- 日本政府観光局 訪日外国人統計2025年上期 – https://www.jnto.go.jp/
- 大阪市 民泊指導状況報告書2024年度 – https://www.city.osaka.lg.jp/

