30代でアパート経営を検討しつつ、将来の相続対策も同時に進めたいと考える人が増えています。住宅価格の上昇や給与だけでは不安な老後資金、そして相続税の負担を意識すると、早めの行動が有利に働くからです。本記事では、アパート経営を「資産形成」と「相続対策」の両面から捉え、誰が名義人になるべきか、30代が押さえるべき資金計画や税制まで丁寧に解説します。初めての方でも理解できるよう、制度の概要からリスク管理まで順を追って説明しますので、読み終えたときには具体的な第一歩を踏み出せるはずです。
30代でアパート経営を始めるメリットとリスク
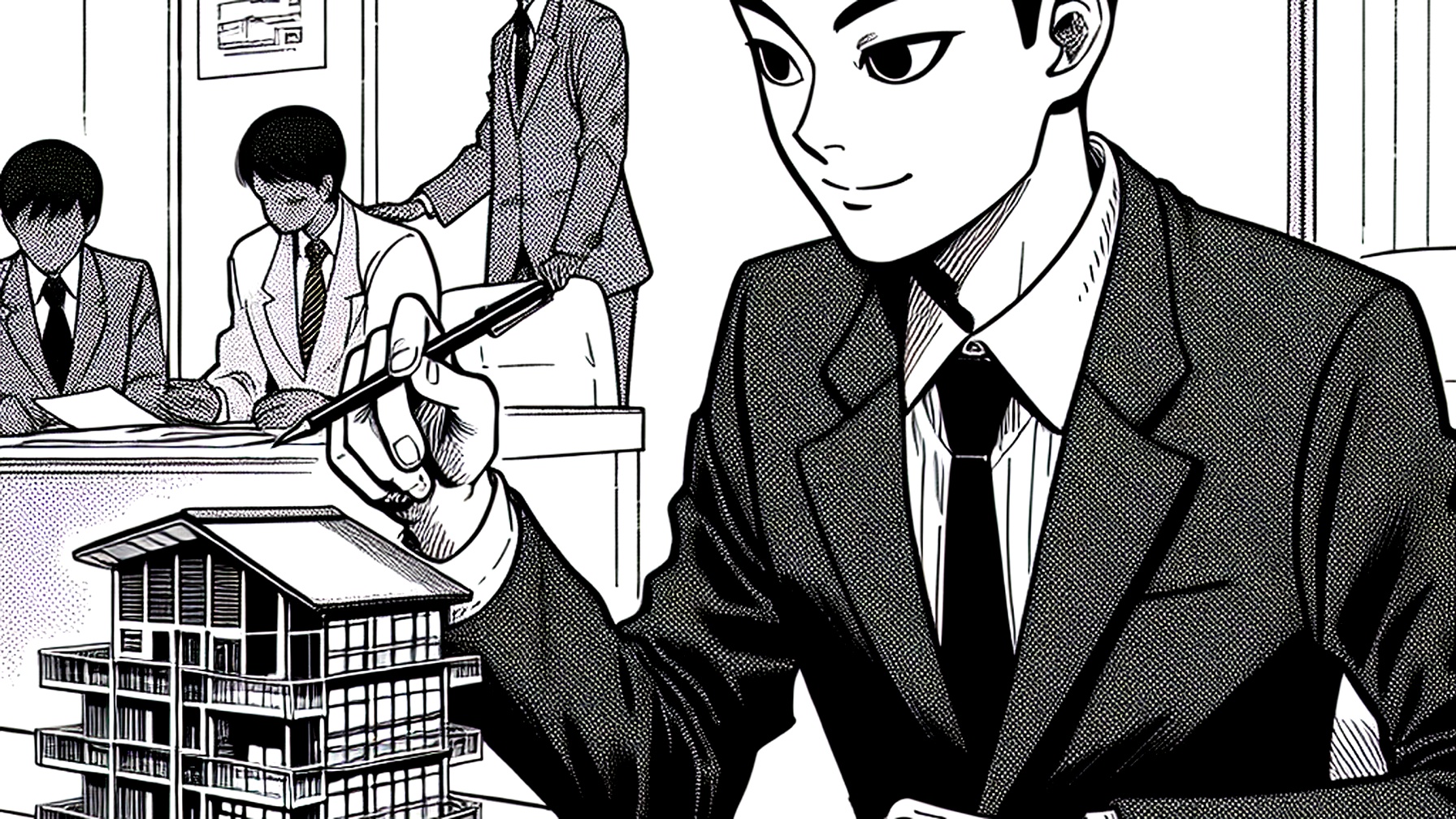
まず押さえておきたいのは、30代でアパート経営を始めることによる時間的優位です。若いうちにローンを組めば返済期間を長く設定でき、毎月のキャッシュフローに余裕が生まれます。また、空室リスクを抑える長期的なリノベ計画も立てやすく、物件価値を維持しやすい点も見逃せません。
一方で、若さゆえの経験不足が大きなリスクになることは否定できません。入居者対応や修繕計画を甘く見積もると、想定外の支出が積み重なります。国土交通省の住宅統計によれば、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%ですが、地域別にみると30%を超えるエリアも存在します。エリア調査を怠れば、長期的な空室に苦しむ可能性が高まります。
さらに、金利変動も無視できません。日本銀行は低金利政策を続けていますが、長期固定ローンで年1%台後半の水準が提示される事例も出ています。仮に金利が1%上昇すると、借入額5000万円・残期間25年で総返済額は約700万円増加します。資金計画には十分なシミュレーションが必要です。
重要なのは、メリットとリスクを天秤にかけ、現実的な投資プランを構築することです。特に30代はライフイベントが多く、教育資金や住宅購入とのバランスが求められます。余裕資金を確保したうえでアパート経営に取り組むことで、失敗リスクを大幅に低減できます。
相続対策としてのアパート経営の基本
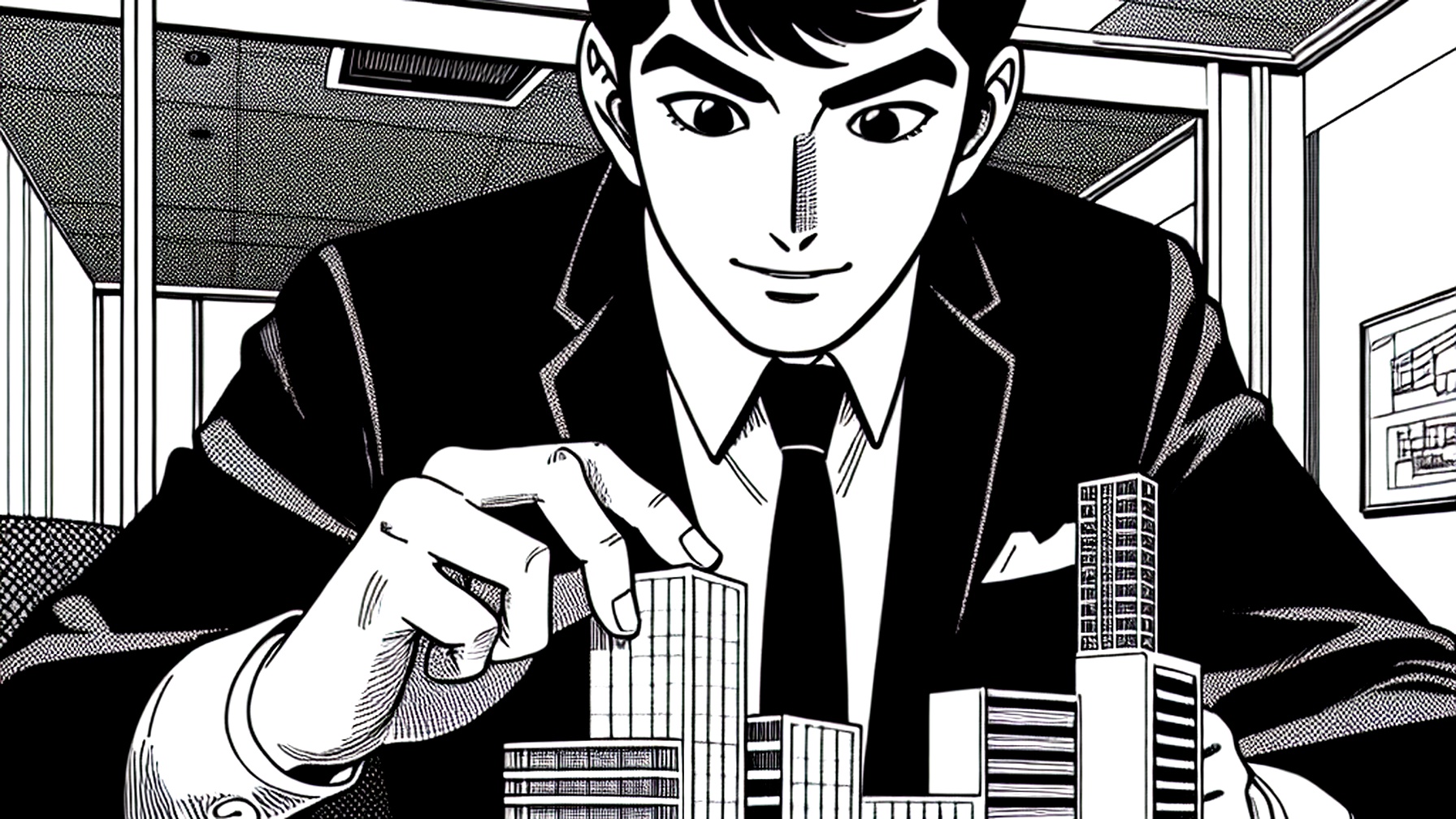
ポイントは、アパート経営が相続税評価額を下げる効果を持つ点です。土地は「貸家建付地」として評価額が20%程度下がり、建物は固定資産税評価額で算定されるため、市場価格より低く評価されます。つまり、同じ3000万円の現金で取得した場合より、相続税の課税対象額を抑えられるのです。
2025年度の相続税基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人」のまま据え置かれています。控除額に収まらない資産を持つ家庭では、現金からアパートに資産を組み替えるだけで課税対象額が圧縮されるケースが多々あります。特に都市部の更地を所有している場合、賃貸物件を建築して貸家建付地に変更する効果は大きいと言えます。
ただし、相続開始前3年以内に取得した賃貸物件は「駆け込み対策」とみなされる可能性があります。国税庁の通達では、過度な節税スキームを排除する姿勢が強まっており、30代のうちに計画的に始めておくことが安全策です。この時間的余裕こそが、若い世代がアパート経営を選ぶ大きな理由になります。
また、小規模宅地等の特例も2025年度に存続しており、330㎡までの住宅用地で最大80%の評価減が可能です。ただし、要件を満たさなければ適用されません。具体的には「被相続人と同居」「相続開始後に継続して賃貸経営を行う」などの条件があるため、事前に専門家へ相談しながらプランを練ることが欠かせません。
誰がオーナーになるべきか家族ごとの最適解
実は、アパートを誰の名義で取得するかによって、相続対策の効果は大きく変わります。夫妻と子ども二人の四人家族を例にすると、夫名義で取得した場合、将来の相続で妻と子に法定相続分が生じます。一方、妻の名義に分散しておけば、将来夫が相続する際に一次相続の課税額を抑えやすくなることがあります。
配偶者控除が使える一次相続では、配偶者が取得した遺産のうち1億6000万円までは非課税となります。そこで、経営能力がある配偶者がオーナーになり、ローンを返済しながら収益を得る方法が現実的です。30代夫婦であれば住宅ローン控除を利用しつつ、アパートローンを組み合わせる資金戦略も考えられます。
子どもが20代前半であれば、教育費を考慮しつつ贈与税の年110万円非課税枠を活用して、出資額の一部を計画的に移転する方法も有効です。ただし、2024年導入の「贈与加算期間延長」により、相続開始前7年間の贈与が加算対象になりました。30代の早い段階から少額贈与をコツコツ行うことで、後年の相続税負担を軽減できます。
家族全体のキャッシュフローを可視化し、誰がローンを負担し、誰が賃料を受け取るかを設計することが欠かせません。公正証書による「家族間賃貸契約」や「管理委託契約」を整えておけば、税務調査が入った際にも正当性を説明しやすくなります。
30代が押さえるべきファイナンスと税制
重要なのは、自己資金と融資のバランスです。2025年度の銀行融資は、自己資金10〜20%を求める金融機関が主流ですが、日本政策金融公庫の創業融資では自己資金ゼロでも審査が通る例があります。とはいえ、自己資金を3割程度入れたほうが金利優遇を受けやすく、総返済額を抑えられます。
固定金利と変動金利の選択では、返済期間が20年以上の長期ローンであれば固定金利の安心感が高まります。2025年10月時点で長期固定2.1%、変動0.9%前後の水準ですが、変動金利は景気回復局面で上昇余地が大きい点に注意が必要です。金利1%差で月々の返済が約2万円変わるケースもあり、堅実な資金計画が欠かせません。
税制面では、所得税の損益通算が注目されます。給与所得が高い30代ほど、不動産所得の赤字による所得税軽減効果が見込めます。ただし、赤字が継続すると税務署から「事業性の有無」を指摘される可能性があるため、黒字化を目標に計画的に進めましょう。
減価償却は節税の大きな味方ですが、過度に期間を短くする「耐用年数短縮」は税務上リスクが高いです。建築確認済証に記載された構造と用途から法定耐用年数を正しく算定し、適切な会計処理を行うことが将来の税務リスクを抑えます。税理士と定期的に打ち合わせ、月次の試算表で利益と現金収支をチェックする習慣を身につけると安心です。
実践ステップと成功事例に学ぶ
まず、物件購入までの流れを押さえましょう。エリア調査、収支計算、金融機関の事前審査、売買契約、引き渡しという一般的な手順ですが、各段階でプロに相談することで失敗確率は大きく下がります。特に収支計算では、空室率15%と固定資産税、修繕費を組み込んだ保守的シミュレーションが必須です。
成功例として、30代後半の会社員Aさんは、都内駅徒歩10分の木造アパート(築15年)を自己資金1500万円、ローン5500万円で購入しました。フルリフォームを実施し、家賃を7000円引き上げることで入居率を98%まで回復させ、年間キャッシュフローは180万円を確保しています。将来は賃料収入を使って繰上返済し、60代でローン完済を目指す計画です。
一方、郊外に新築アパートを建築したBさんは、完成後の入居付けが想定より3カ月遅れました。仲介手数料や広告費が膨らみ、当初計画より年間収支が50万円悪化しましたが、家族名義で土地を共有していたため相続税評価は大幅に下がりました。資金繰りには苦労したものの、相続対策としては一定の成果を上げた好例と言えます。
30代で「アパート経営 相続対策 誰が 30代」というキーワードを意識するなら、成功事例と失敗事例の双方から学び、自分に合った投資スタイルを確立することが肝要です。相続だけを目的にすると運営が疎かになり、運営だけを追うと節税効果が薄れるため、両者のバランスを意識し続ける姿勢が求められます。
まとめ
この記事では、30代がアパート経営を通じて資産形成と相続対策を同時に進める方法を解説しました。若いうちから始めることで時間を味方にでき、相続税評価額の圧縮も狙えます。しかし、空室リスクや金利変動といった課題を甘く見ると、家計を圧迫する可能性があります。家族構成に応じた名義選択と、堅実な資金計画を両立させることが成功の鍵です。今日できる第一歩として、信頼できる不動産会社や税理士に相談し、具体的な数字をもとに自分の投資シナリオを描いてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年8月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 相続税のあらまし 2025年度版 – https://www.nta.go.jp
- 総務省 統計局 人口推計 2025年4月確定値 – https://www.stat.go.jp
- 日本政策金融公庫 2025年度融資案内 – https://www.jfc.go.jp
- 不動産流通推進センター 不動産投資レポート2025 – https://www.retpc.jp
