都市部でも地方でも、相続した土地の活用や老後資金づくりを考えながら「アパート経営に挑戦したい」と悩む方が増えています。しかし一方で、ローン返済が滞り競売にかけられるケースも耳にします。この記事では、アパート経営で相続対策を図りつつ競売を避けるための基本と実務を、最新の税制や市場データをもとに分かりやすく解説します。読み終える頃には、リスクを抑えながら安定収益をめざす具体的な手順が見えてくるはずです。
アパート経営が相続対策になる理由
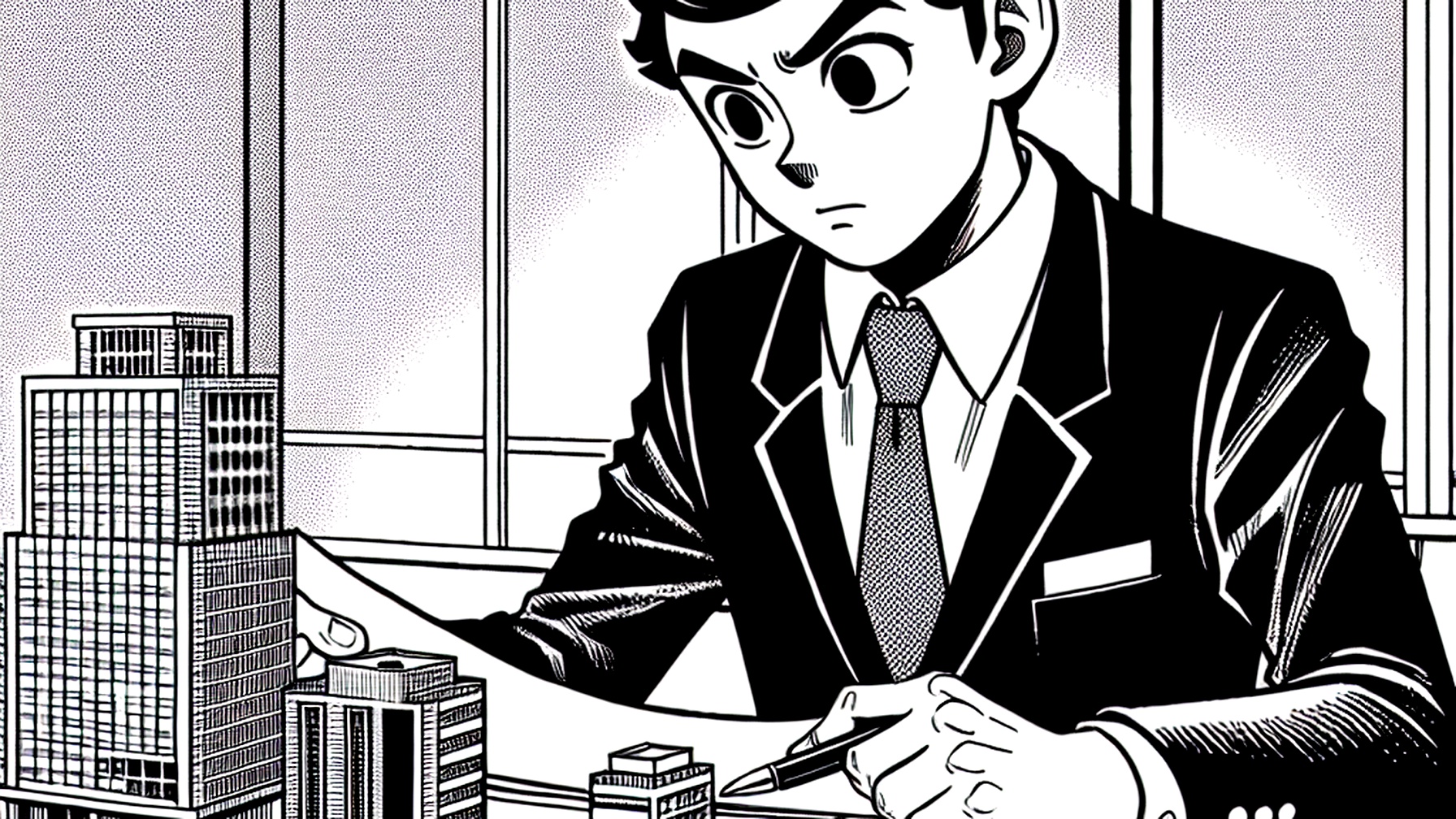
ポイントは、アパートの建物部分が相続評価を下げ、現金よりも課税額を抑えられる仕組みにあります。これにより、相続税の納税資金を物件からの家賃で賄える可能性が高まります。
まず、土地をそのまま保有すると、その評価額は路線価にほぼ連動します。一方、土地の上に賃貸住宅を建てると、「貸家建付地」として評価が約20%下がり、さらに建物自体も「貸家」とみなされて評価額が7割程度になります。つまり、現金をただ残すよりも、資産をアパートに組み替えるだけで評価圧縮が見込めるわけです。
また、2025年度も小規模宅地等の特例が継続しており、330平方メートルまでの賃貸事業用宅地は最大50%の評価減を受けられます。適用条件として「相続開始前3年以内の新規賃貸は除外される」など細かい点があるため、早めの建築計画が欠かせません。
さらに、家賃収入を相続人が得る構図を作ると、所得分散による節税効果も期待できます。高い税率の被相続人から、比較的低い税率の相続人へ所得が移るため、現金配当よりも手取りが増える場合が多いのです。
重要なのは、相続対策として始めても「経営」である以上、空室率や修繕費を正しく見積もり、単独ではなく家族全体のライフプランに合った計画を立てることです。
競売リスクを生む三つの落とし穴
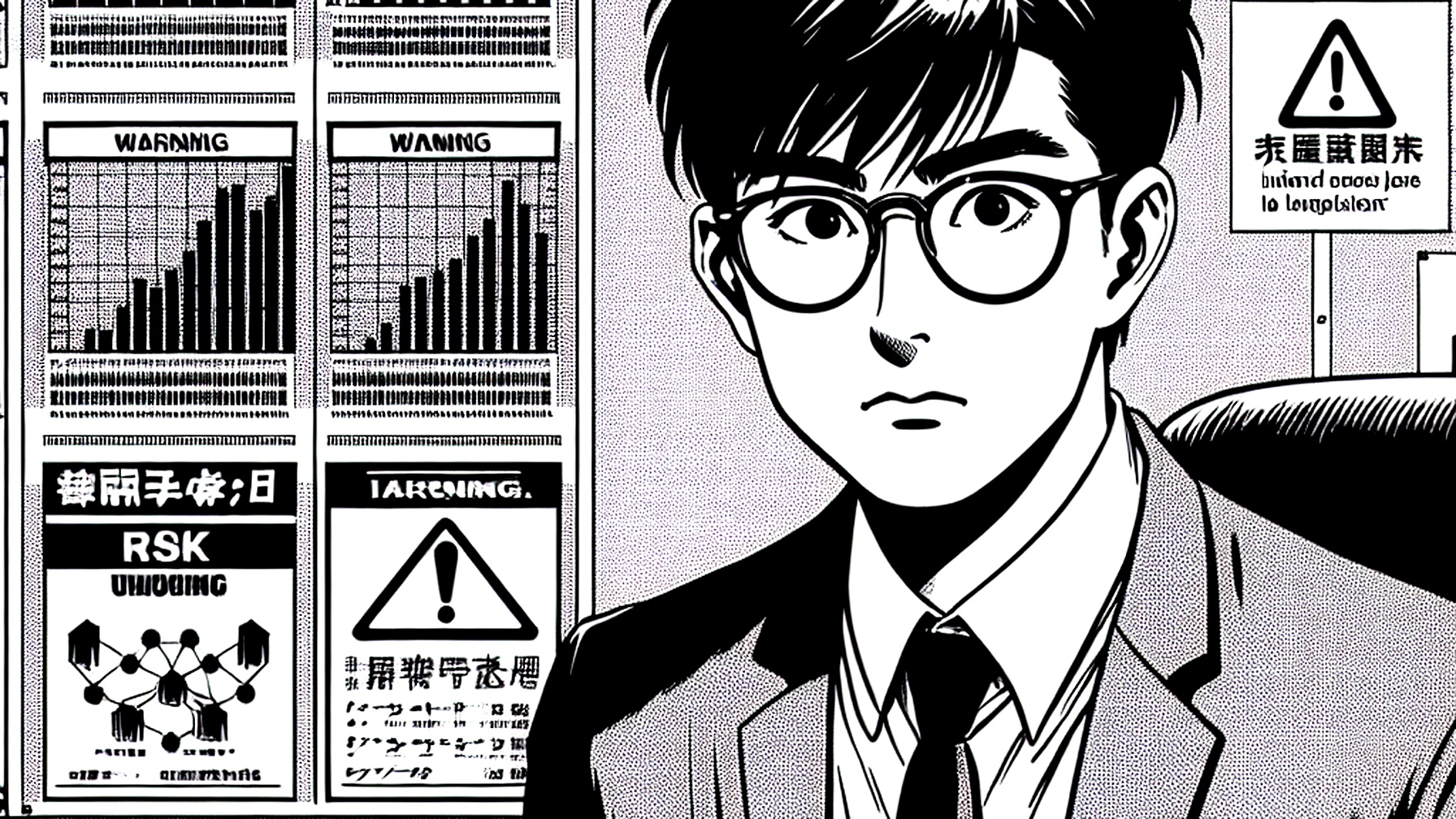
まず押さえておきたいのは、競売に至る物件には共通点があるという事実です。家賃収入の過大見積もり、修繕費の計上不足、そして金利上昇への備えが薄いことが典型です。
国土交通省住宅統計によれば、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント改善したものの、地方中核都市では30%近いエリアも残ります。実際の家賃を調べず机上の想定で計算すると、返済比率が急に上がり競売の引き金になります。
次に、10年目以降の大規模修繕費を「将来の家賃で払えばよい」と先送りする点です。外壁や屋根、防水工事だけで1戸あたり30万円以上かかるケースも珍しくありません。修繕積立を毎月2,000円/戸でも実施していれば、資金ショートの危険は大幅に下がります。
最後に、変動金利一本で長期ローンを組むと金利上昇局面で収支が急変します。日本政策金融公庫によると、2025年7月の長期金利は1.2%前後ですが、2013年の同水準から見れば倍近い水準です。「1%上昇すると年間返済額がいくら増えるか」を必ず試算し、固定金利への借り換えや繰上げ返済の余力を確保しておくことが、競売回避の最短ルートとなります。
安定経営のための資金計画と融資戦略
実は、資金計画を精緻に組んでいる投資家ほど、相続対策としても成功しやすい傾向があります。金融機関は、自己資金の割合と賃料下落への耐性を重視して審査するからです。
自己資金は物件価格の25%を目安に用意すると、返済比率(年間返済額÷年間家賃)が60%以下に収まりやすく、空室や金利上昇に耐えられる体制になります。また、余剰資金として家賃の6か月分を別口座にプールしておくと、突発修繕にも慌てず対応できます。
融資先は、地元地銀、信用金庫、政策金融公庫、信託銀行と特性が異なります。低金利を優先するか、長期固定・団体信用生命保険(団信)の充実度を重視するかで選択肢が変わります。たとえば、団信付き固定2%でも団信なし1.3%の変動よりリスクが低い場合があるため、総返済額と保障のバランスを比較しましょう。
さらに、2025年度の住宅ローン控除は賃貸住宅には適用されませんが、建物取得費の減価償却が最大4%(定額法・鉄骨造の場合)で経費算入できるため、税後キャッシュフローの改善に寄与します。適切な税理士と連携し、「見かけの赤字」をうまく活用することも資金戦略の一部です。
相続発生時の手続きと評価見直し
重要なのは、相続が発生してから慌てない体制づくりです。遺言書、管理会社との契約、融資契約の連帯保証人など、書類の整備次第で手続きの時間とコストは大きく変わります。
相続開示前に遺言書がないと、法定相続人全員で遺産分割協議書を作る必要があります。アパートは分割が難しいため、共有とすると将来の修繕や売却で意見が割れ、経営判断が遅れがちです。したがって、生前に「一括相続+代償分割」などで調整することで、競売に至るリスクを軽減できます。
相続税の申告期限は10か月以内です。この間に不動産の評価を精査し、減額要因(私道負担、セットバック、賃借人の権利など)を洗い出すと課税額が大幅に下がる場合があります。税務署は市場価格ではなく路線価評価を基準にするため、専門家の意見書を添えて根拠を示すと認められやすくなります。
一方で、納税資金が不足すると物件を慌てて処分しがちですが、相続税の物納や延納制度を検討する選択肢も残されています。2025年度の改正で物納の審査期間が最長2年から1年に短縮され、早期の経営安定が図りやすくなりました。制度の要件を満たすには、申告時から物納を視野に入れた書類準備が欠かせません。
2025年度の税制優遇と実務ポイント
まず、2025年度の固定資産税軽減措置は新築賃貸住宅に対して3年間1/2の減額が継続しています。床面積要件(40~280平方メートル)を満たすアパートなら、建築後3年は年間コストが抑えられ、キャッシュフローが改善します。
また、賃貸住宅省エネ改修促進税制も2025年度末まで延長され、断熱材追加や高性能サッシへの改修費の10%(上限250万円)が所得税額から控除可能です。省エネ化は入居促進だけでなく、長期的な維持費削減につながるため、空室リスク対策としても有効です。
さらに、相続発生後に賃貸経営を継続する場合、登録免許税の軽減措置が使えます。2025年度は所有権移転登記の税率が2%から1.5%に軽減される特例が継続しており、相続登記義務化(2024年施行)への対応が容易になっています。
とはいえ、制度は適用条件を満たさなければ意味がありません。補助金や減税は自治体で独自上乗せがある場合もあるため、着工前に市区町村の窓口で確認することが大切です。制度を逃さず活用することで、同じ規模の投資でも手取りは大きく変わります。
結論として、制度を知り、計画的に組み合わせることで、アパート経営の収益力と相続対策の効果を同時に高める道が開けます。
まとめ
アパート経営を用いた相続対策は、評価圧縮と家賃収入で税負担を抑えられる一方、空室や金利上昇を軽視すると競売に直結します。自己資金比率、長期修繕計画、金利変動シミュレーションを整え、制度優遇をきめ細かく活用することが成功の鍵です。まずは家族で情報を共有し、専門家と試算を重ねながら、一歩ずつ確実に準備を進めていきましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査(2025年8月版) – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 相続税法令解釈通達(2025年度版) – https://www.nta.go.jp
- 日本政策金融公庫 金融情報2025年7月号 – https://www.jfc.go.jp
- 総務省 固定資産税関係法令集(2025年度) – https://www.soumu.go.jp
- 環境省 省エネ改修促進税制の手引き2025 – https://www.env.go.jp

