始める前に、多くの読者が抱く悩みを整理しましょう。堅牢で長寿命といわれるRC造(鉄筋コンクリート造)の物件は、本当に投資先として有利なのか。さらに、手軽に不動産収益を得られるREITの分配金とどちらが効率的なのか。実は、この二つを単純に比較するだけでは、見落としてしまうポイントがいくつもあります。本記事では「RC造 比較 REIT 分配金」をキーワードに、構造ごとの収益性やリスク、そして2025年10月時点の市場動向を踏まえた投資判断のコツを丁寧に解説します。
RC造の耐久性と長期収益のポテンシャル
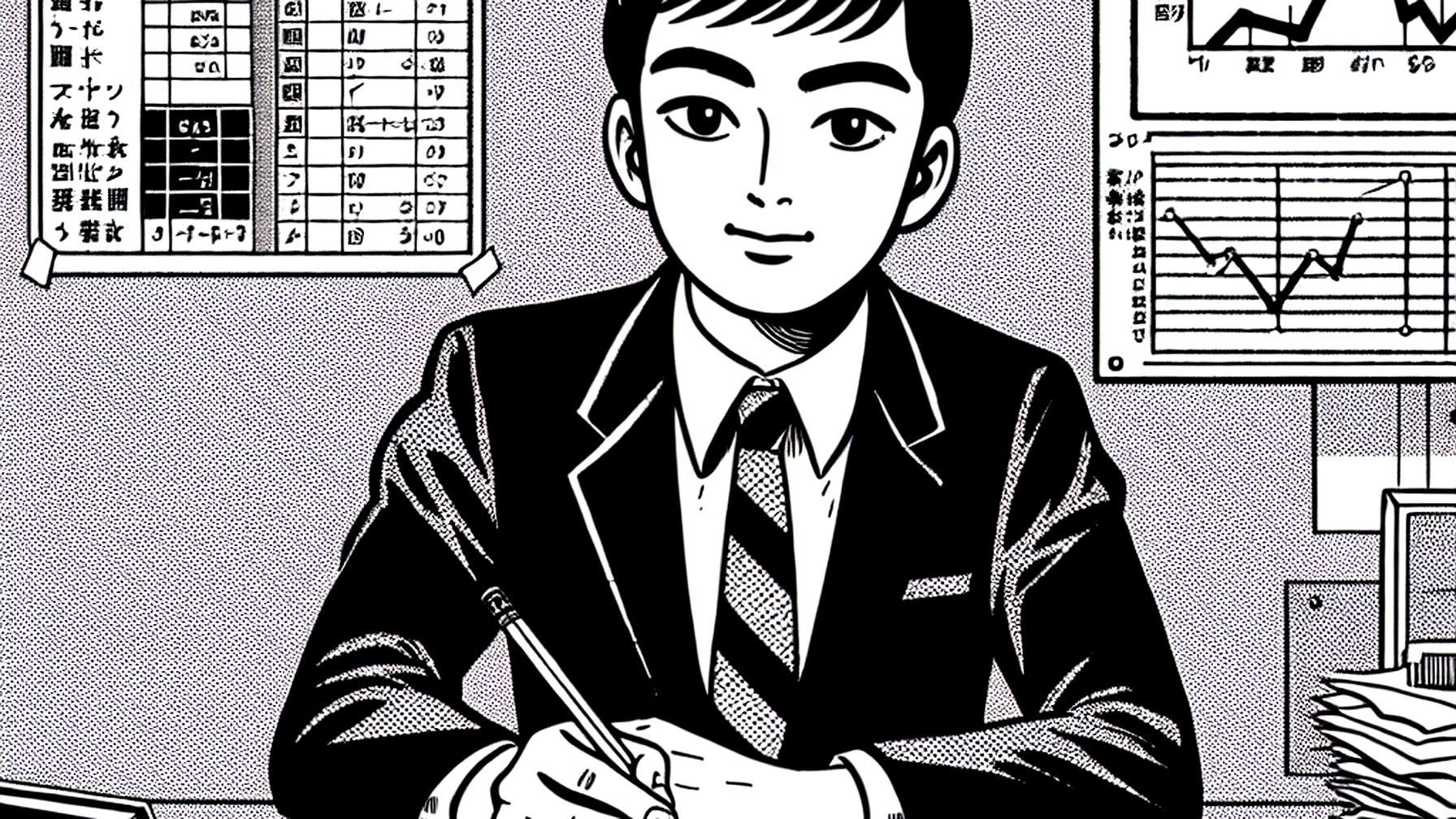
まず押さえておきたいのは、RC造がもつ物理的な強さと長い法定耐用年数です。国土交通省の基準では、RC造の法定耐用年数は47年に設定されており、木造(22年)やS造=鉄骨造(34年)より明らかに長いとされています。この数字は減価償却や融資期間に直結し、長期運用の計画を立てやすいことがメリットです。
一方で、建設コストは木造の1.5倍前後になるのが一般的です。つまり、初期投資が膨らむ分だけキャッシュフローが圧迫される可能性があります。しかし、RC造は空室期間が短い傾向にあると指摘されています。関東圏の管理会社データでは、同等立地での平均空室期間はRC造が1.9カ月、木造が2.7カ月でした。ここから分かるのは、耐火性への安心感が入居率を支えている点です。
耐久性は修繕計画にも影響します。外壁補修の周期が12〜15年程度と長く、大規模修繕のコスト総額は木造より若干高いものの、年平均に均すとむしろ低くなるケースが珍しくありません。重要なのは、長期視点でのトータルコストを把握し、利回りを算出することです。
木造・S造との比較が示す投資効率
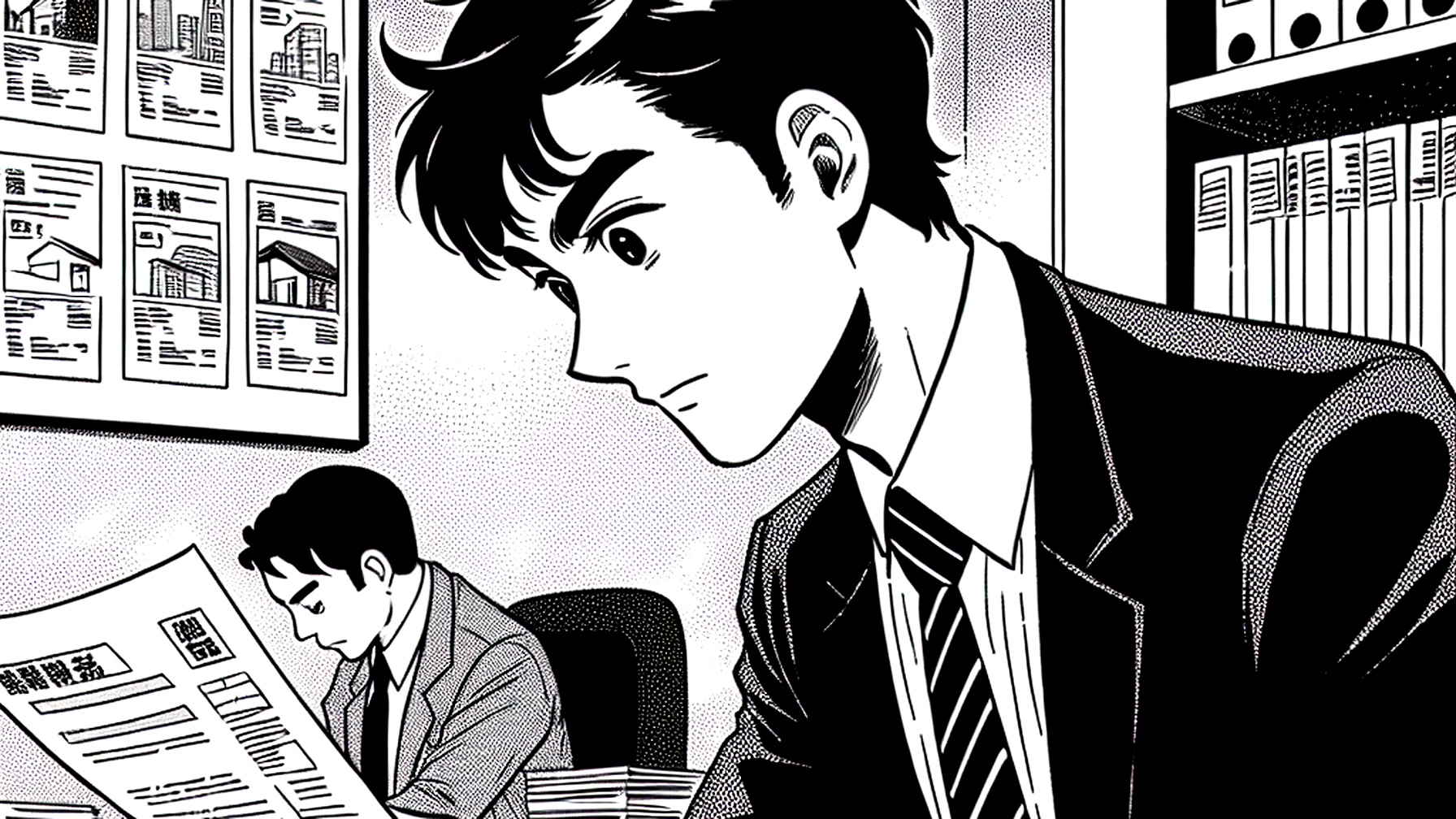
ポイントは、構造別の収益性を数字で理解することです。東京都心で築浅の賃貸物件を想定し、実質利回りをシミュレーションするとRC造が4.1%、木造が4.6%、S造が4.3%となる例が多いです。木造の利回りが高く見えるのは建築費が低いからですが、築20年時点の資産価値を考慮すると、RC造の下落率は木造より10ポイント程度小さい傾向があります。
また、金融機関の融資姿勢にも差が見られます。2025年度の主要都市銀行では、RC造への最長融資期間は35年、木造は25年が上限というケースが一般的です。返済期間が長いほど月々の返済負担は抑えられ、キャッシュフローの安定に寄与します。つまり、利回りだけでなく融資条件まで含めた総合判断が不可欠です。
さらに、入居者層の安定性にも注目しましょう。賃料帯が同等でも、RC造は防音性が高いためファミリー層やテレワーカーに選ばれやすく、賃料下落リスクが比較的低いとされています。言い換えると、将来の賃料下落を織り込んだ実質利回りで考えると、RC造の数字は見かけ以上に良好になる可能性があります。
REITの仕組みと分配金の安定性
重要なのは、REIT(不動産投資信託)が持つ分配金の源泉を理解することです。REITは複数の物件をファンド化し、賃料収入や売却益を投資家に分配します。法律上、その90%以上を分配金として還元することで法人税が軽減される仕組みがあり、結果として利回りが高く見えやすいのです。
東京証券取引所REIT指数のデータでは、2024年度の平均分配金利回りは3.7%でした。2025年9月末時点では4.0%前後に上昇し、金利上昇局面でも一定のパフォーマンスを保っています。分散効果が高いため、個別物件特有のリスクを抑えられる点が特徴です。
ただし、分配金は安定している反面、基準価格(株価に相当)が市場要因で変動します。たとえば金利が0.25%上がるとREIT指数が3%前後下落する相関が観測されます。つまり、キャピタルロスのリスクを無視すると実際のリターンを見誤ります。個別RC造物件が持つ現物資産の安定感と、REITが持つ流動性と分散性をどうバランスさせるかが鍵です。
RC造物件とREITを組み合わせるハイブリッド運用
実は、現物のRC造物件とREITへの投資を組み合わせることで、収益の安定度を高める戦略が可能です。現物物件では家賃収入が相対的に景気変動の影響を受けにくく、中長期でのキャッシュフローを確保できます。一方、REITは少額から購入できるため、余剰資金を機動的に運用しやすいのが利点です。
たとえば自己資金3000万円を想定し、2000万円をRC造区分マンションの頭金、残り1000万円をREITに振り向けるとします。RC造区分の年間手取りが約90万円、REIT分配金が40万円とすると、合計利回りは4.3%程度になります。ここで注目したいのは、REIT側の分配金は四半期で支払われるため、突発的な空室でRC造の家賃が途絶えてもキャッシュフローを補完できる点です。
さらに、2025年度の税制では、REIT分配金は20.315%の源泉分離課税となり、損益通算はできません。一方、現物不動産は減価償却による損益通算が可能です。両者を組み合わせることで、税引き後キャッシュフローの最適化を図れる点も見逃せません。
2025年度の融資環境とリスク管理
ポイントは、金融環境と規制の変化を踏まえたリスク管理です。日本銀行は2025年7月の金融政策決定会合で長期金利の誘導目標を0.5%から0.75%に引き上げ、市場金利が緩やかに上昇しています。この動きはRC造への長期融資金利にも影響し、3大メガバンクの35年固定金利は平均で2.1%へ上昇しました。ただし、木造や築古物件に比べてRC造への与信は依然として手厚く、金利優遇幅が0.2%程度大きい傾向が続いています。
同時に、不動産投資ローンに対する審査は、総収入に占める返済比率35%を上限とする姿勢が強まっています。そのため、RC造物件を購入する際は、家賃収入が10%下落しても返済比率が上限を超えないよう、慎重にシミュレーションを行うことが欠かせません。
REITについては、金利上昇がネガティブ要因となる反面、オフィス系から住宅系への資金シフトが進み、住宅系REITは分配金の成長率が2年連続で3%超となっています。分配金増加が期待できる銘柄を選定することで、金利上昇リスクをある程度相殺できます。つまり、個別物件とREITの両面で金利感応度を把握し、適切にヘッジをかける姿勢が重要です。
まとめ
ここまで見てきたように、RC造は耐久性と長期融資の好条件から安定した家賃収入を期待でき、一方でREITは分散効果と流動性により機動的な運用が可能です。両者を比較すると、単純な利回りでは木造や一部REITが上回るケースもありますが、資産価値の維持や税務効果まで含めると、RC造とREITの組み合わせが最もバランスに優れます。まずは長期視点でキャッシュフローを試算し、金利上昇や空室リスクを織り込んだうえで投資割合を決定しましょう。前向きに分析を重ねることが、2025年以降の変動局面でも安定した資産形成への近道になります。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 東証REIT指数月次レポート – https://www.jpx.co.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 東京都都市整備局 賃貸住宅実態調査 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

