不動産投資に興味はあるものの、「区分と一棟のどちらが自分に合うのか分からない」と迷う声をよく耳にします。私自身も15年前は同じ悩みを抱え、数多くのセミナーや書籍を読み漁りました。この記事では、実際に私が経験した一棟買いの体験談を交えながら、資金計画、物件選定、運営方法まで順を追って解説します。読むことで、一棟マンション投資があなたの目的に合うかどうかを判断し、最初の一歩を安心して踏み出せるようになるはずです。
体験談で知る一棟買いの魅力と現実
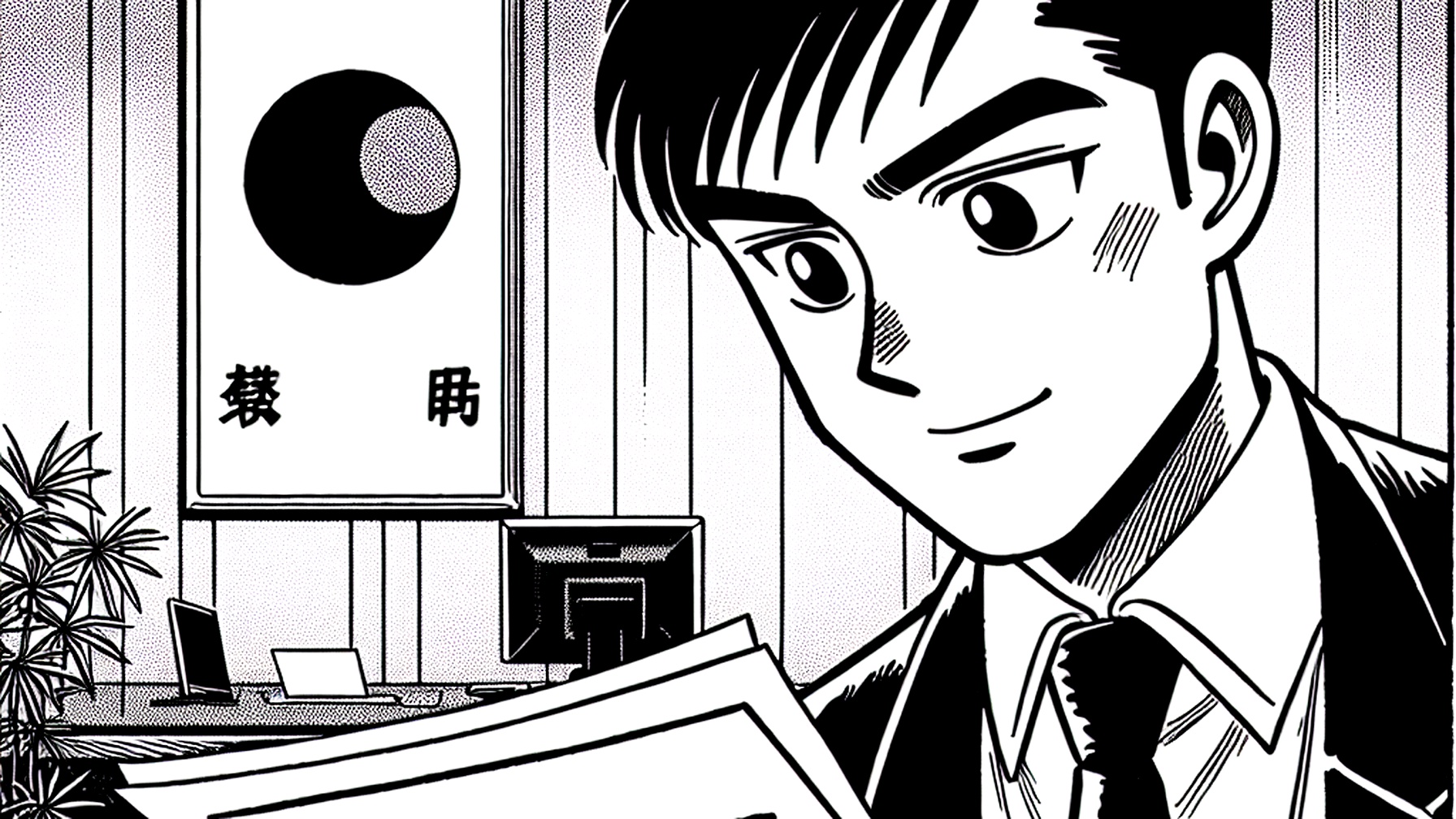
まず押さえておきたいのは、一棟買いが高い収益性と裁量権の広さを両立できる点です。しかし、その裏側には空室リスクや修繕費の重さといった現実が潜んでいます。私は2014年に都内の築25年RC造15戸を購入し、年間表面利回り10.2%を確保しました。一方で、取得から3年目にエレベーターを交換することになり、300万円超の突発支出に悩まされました。
当初は家賃収入が返済額を上回るプラスのキャッシュフローを生み、金融機関からの追加融資も比較的容易でした。また、自分で管理会社を選定し、リノベーション方針を決められる自由度が区分投資より大きいと実感しました。ところが、エレベーター交換や外壁の大規模修繕は区分オーナーと違い私一人で負担します。家賃収入から修繕積立を確保していたため致命傷には至りませんでしたが、利回りは9.1%まで低下しました。
つまり、一棟買いはレバレッジを利かせて高収益を狙える反面、突発支出への備えがなければ一気に資金繰りが苦しくなる投資手法です。体験談として強調したいのは、収益とリスクを同じテーブルで冷静に比較し、長期目線で判断する姿勢が不可欠だという点に尽きます。
初心者が押さえたい資金計画と融資戦略
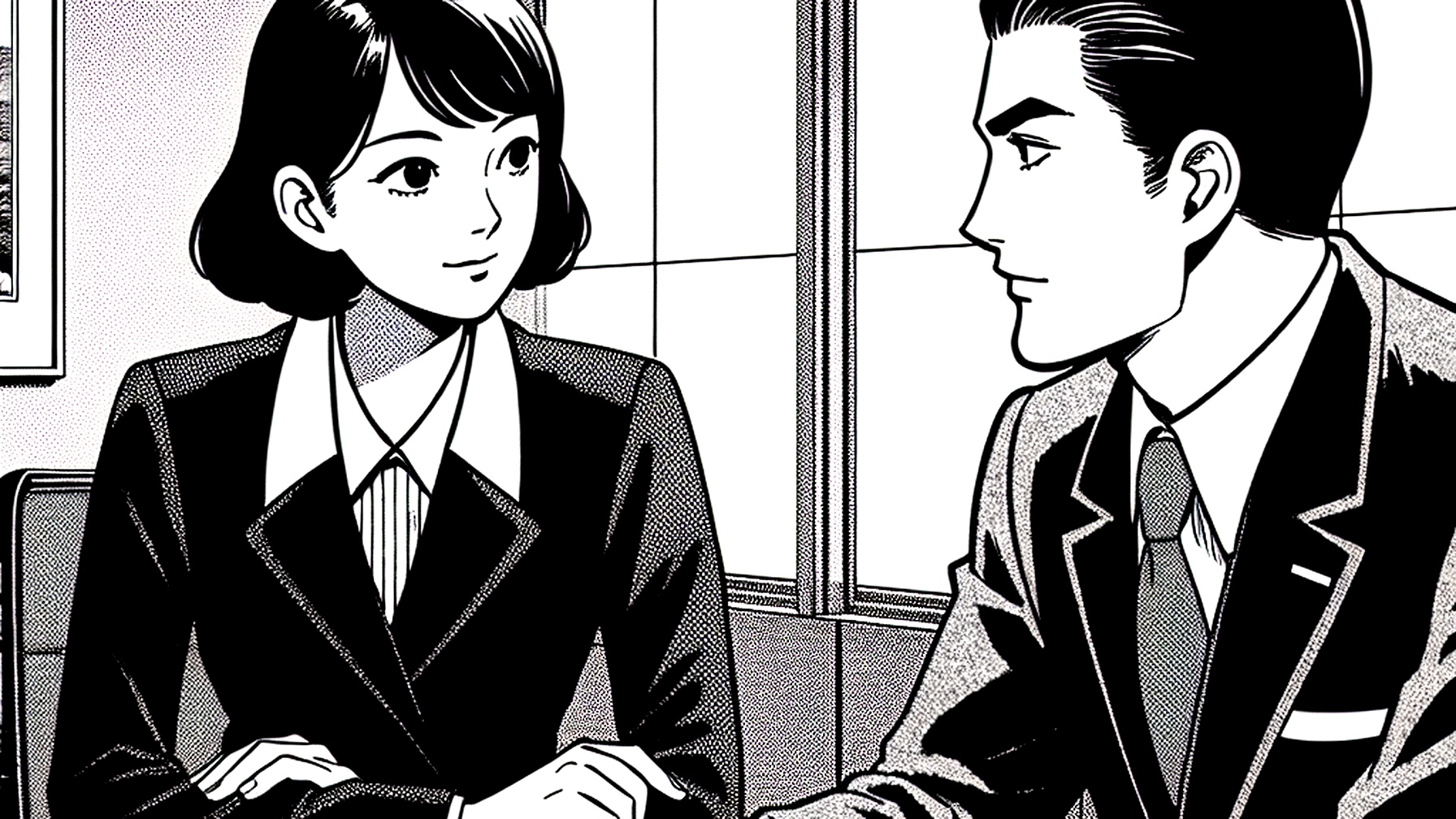
重要なのは、物件価格だけでなく維持費や金利上昇を織り込んだ資金計画を立てることです。2025年度の住宅ローン減税は自宅用に限られるため、投資用物件には適用されません。したがって、税効果よりキャッシュフローと金利条件に焦点を当てる必要があります。私は自己資金2割を用意し、残りを地方銀行の変動金利1.8%で調達しましたが、今なら固定1.9〜2.3%で安定させる戦略も検討に値します。
日本銀行のマイナス金利政策が縮小局面に入った2024年以降、長期金利は徐々に上昇傾向です。不動産経済研究所のデータによれば、東京都23区の新築マンション平均価格は2025年10月時点で7,580万円と前年より3.2%上昇しました。価格高騰が続く環境下では、融資条件の差が総収支に直結します。シミュレーションでは、金利が1%高くなるだけで30年総返済額が約2,000万円増えるケースも珍しくありません。
資金計画を作る際は、空室率20%と修繕積立年間50万円を含めた保守的な試算を行いましょう。そのうえで、自己資金の範囲で元本返済を早められるか、繰上げ返済の余力を確認します。私は月々のCFを10万円残す想定で計画し、実際は平均13万円を確保できました。余剰分を毎年50万円繰上げ返済に充てた結果、元本70万円分を短縮でき、利息負担の軽減につながりました。
物件選定で失敗しないためのチェックポイント
ポイントは、利回りだけでなくエリアの需給バランスと建物コンディションを多角的に検証することです。具体的には、最寄り駅から徒歩10分以内、築30年以下、RC造であれば耐久性に優れ修繕計画も立てやすいと言えます。私が購入した物件は駅徒歩7分の準工業地域に立地し、周辺人口は都の統計で今後10年間横ばいと予測されていました。
内覧時は、空室の状態を確認しながら間取りの競争力をチェックしました。単身用18㎡の部屋は需要が安定しているものの、風呂トイレ同室タイプは成約スピードが鈍ります。そのため、空室3戸のうち2戸をリフォームし、バストイレ別へ変更しました。工事費は1戸あたり60万円でしたが、家賃を月1.5万円上げても3か月で入居が決まり、投資回収期間は約3年に短縮できました。
建物調査報告書(インスペクション)も欠かせません。配管の劣化や屋上防水の状態は外観から判断できないため、専門会社に依頼し、修繕時期と概算費用を把握します。報告書で「5年以内に屋上防水要更新、費用350万円」と判明したことで、取得後のキャッシュフロー計算に盛り込み、慌てず対応できました。
運営フェーズで利益を伸ばす管理と出口戦略
実は、収益性の差は購入後の運営で大きく開きます。入居者募集はエリア内で実績のある管理会社を選び、賃料査定を任せるのが基本です。しかし、広告料の設定や写真のクオリティはオーナーがチェックできます。私は360度カメラで室内を撮影し、ウェブ掲載写真を更新しただけで、空室期間が平均45日から27日に短縮しました。
修繕では、国土交通省の「長期修繕計画ガイドライン」に沿って10年先までの予定表を作成し、家賃収入の8〜10%を毎月積立口座に回しています。また、2025年度も継続する「省エネ改修支援事業(中小ビル向け)」は賃貸マンションにも適用可能です。一定の断熱性能を満たす窓改修に対しては補助率1/3、上限200万円が設定されているので、対象範囲かを確認すると良いでしょう。
出口戦略として、物件価値を高めてから5〜7年目に売却する方法と、長期保有で家賃収入を積み上げる方法があります。私はキャッシュフローが安定している間に担保評価が上がったため、別の一棟を追加取得し、ポートフォリオを拡大しました。売却しない選択肢を取ったことで、デフレ脱却局面における家賃上昇を取り込めています。
まとめ
ここまで、体験談 マンション投資 一棟買いの実例を通じて、資金計画、物件選定、運営、出口戦略の流れを解説しました。キーワードは「保守的なシミュレーション」と「計画的な修繕積立」です。今後も金利や人口動態は変化しますが、基本を押さえていれば環境の逆風にも対応できます。まずは自己資金割合と長期修繕計画を見える化し、信頼できる管理会社を探す行動から始めてみてください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp/
- 国土交通省 長期修繕計画ガイドライン – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp/
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp/
- 東京都都市整備局 住宅・土地統計 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/

