多くの投資家が「インフレに強い商品を持ちたい」と考えていますが、いざ調べると専門用語ばかりで挫折してしまう人も少なくありません。REIT(不動産投資信託)は手軽に不動産に分散投資できる半面、価格変動や手数料などのデメリットも存在します。本記事では、初心者の疑問に寄り添いながら、REITの仕組みと弱点、そしてインフレ対策としてどう位置づけるかを丁寧に解説します。読み終えるころには、リスクを踏まえた上での活用方法が見え、次の行動を具体的にイメージできるはずです。
REITとは何かを改めて整理する
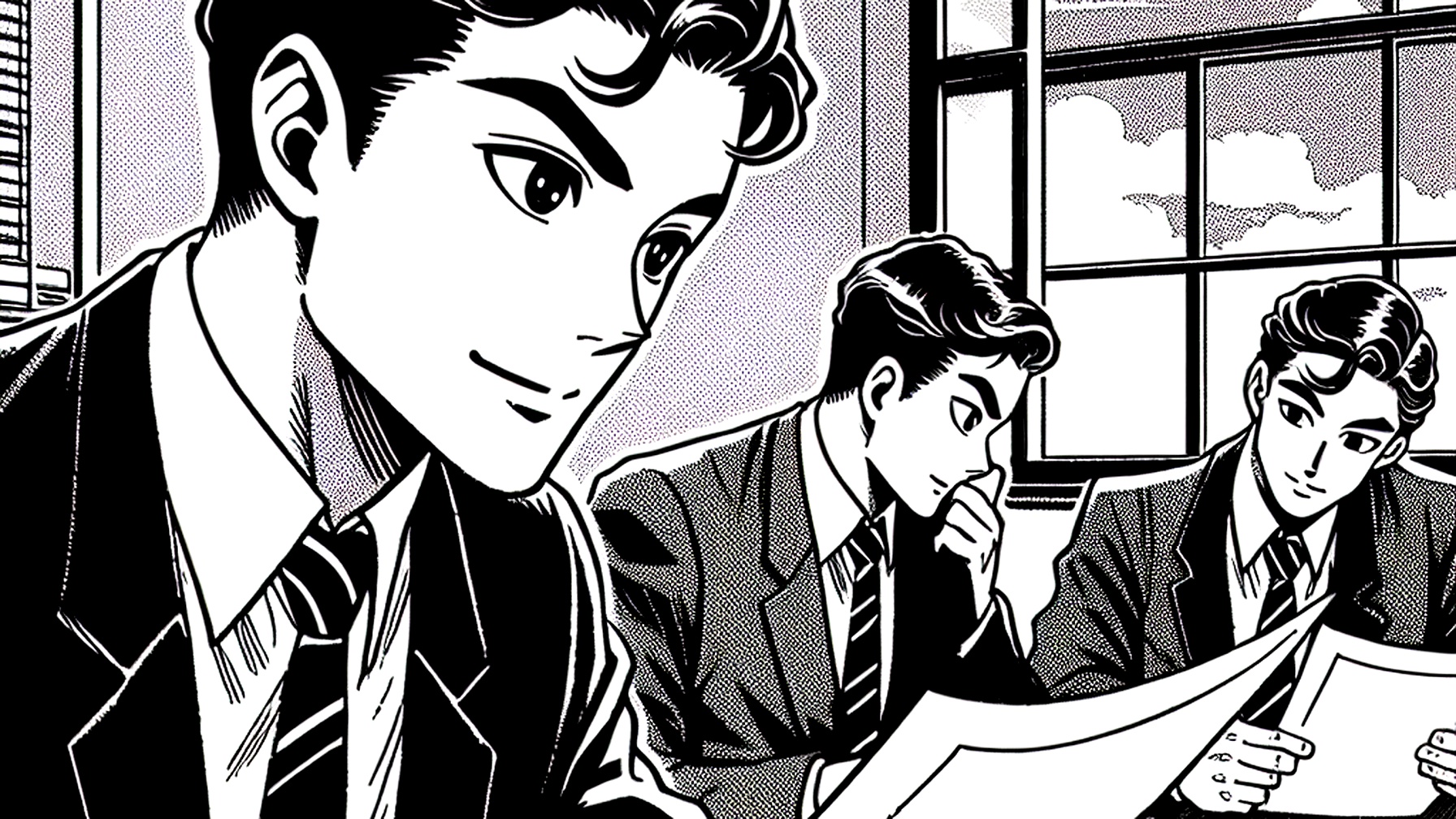
まず押さえておきたいのは、REITが「投資家から集めた資金で複数の不動産を購入し、賃料や売却益を分配する金融商品」だという点です。証券取引所で株式のように売買でき、少額から始められるため、個人投資家の裾野が広がっています。一方で、価格は市場の需給や金利動向によって日々変動し、元本保証はありません。つまり、不動産の安定性と株式の値動きが混在する独特のリスクを抱えているのです。
次に仕組み面を見てみましょう。運用会社は物件の取得からテナント管理、資金調達までを担い、投資家はその成果を「分配金」という形で受け取ります。国土交通省の2025年4月の統計によると、東証に上場する国内REITの平均分配利回りは3.8%前後で推移しています。これは長期国債利回りの約2倍に当たり、インカムゲイン(保有中の収入)を重視する投資家にとって魅力的な水準です。
ただし、分配金が高いからといって安泰ではありません。物件の稼働率が下がれば賃料収入が減り、分配金も減少します。また、建物の修繕や設備更新に伴うコスト負担は運用会社が計上するため、内部留保が薄いREITほど影響が顕著です。したがって、投資前にポートフォリオの築年数やテナント構成を確認する姿勢が求められます。
代表的なデメリットを深掘りする
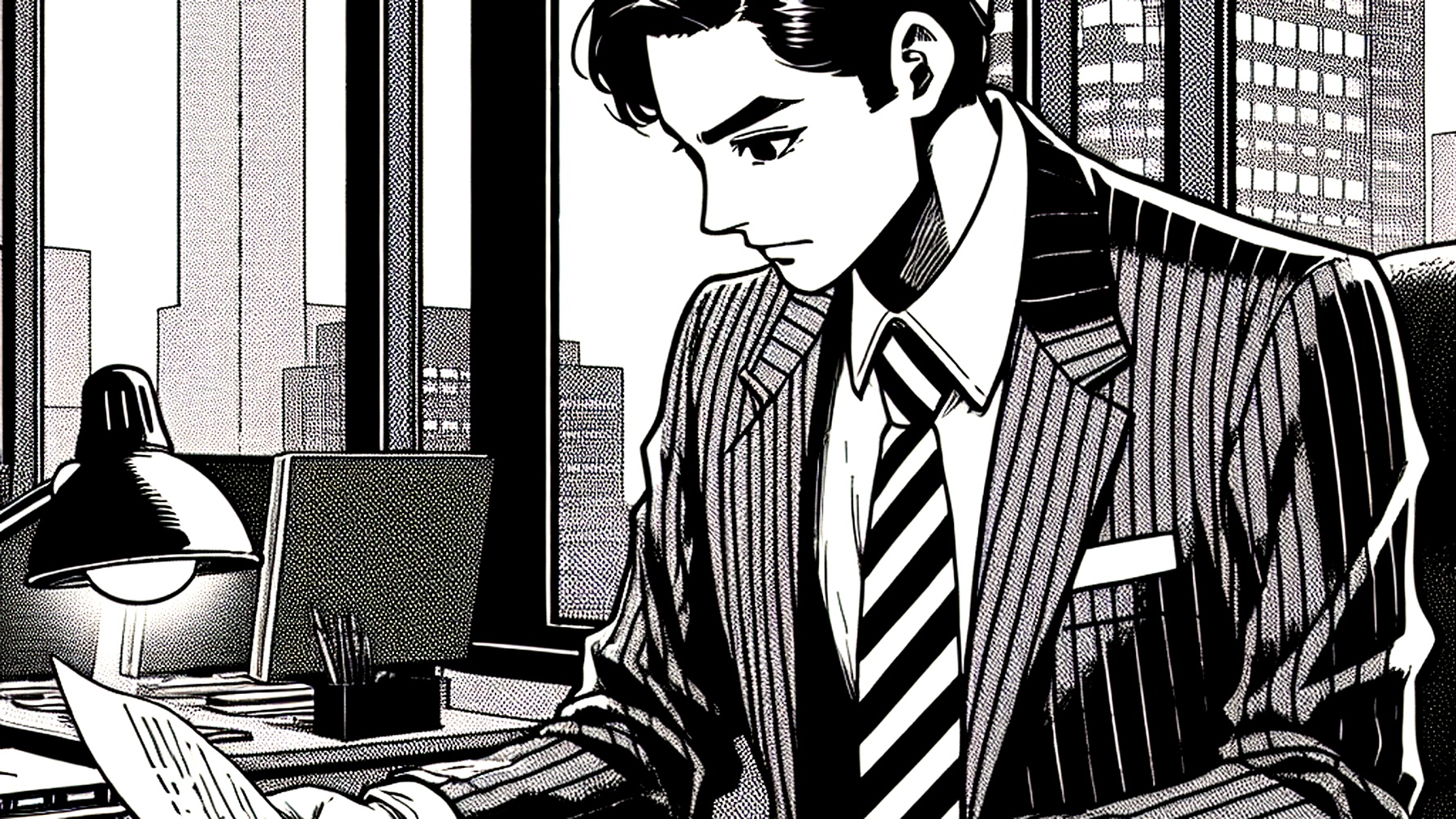
重要なのは、リターンと表裏一体のリスクを正しく理解することです。REITのデメリットは大きく分けて「価格変動リスク」「金利上昇リスク」「追加費用の発生」の三つに集約できます。ここではそれぞれの背景と影響を具体的に見ていきます。
まず価格変動リスクです。REITは株式市場で取引されるため、景気悪化や不動産市況の悪化が織り込まれると、実際の賃料収入が安定していても価格が下落する場合があります。例えば2023年の金融引き締め局面では、日銀短観で不動産業の業況判断が小幅悪化しただけで、J-REIT指数は一時5%下落しました。短期の値動きに過敏な人には精神的負担が大きくなりがちです。
次に金利上昇リスクです。REITは物件取得資金の約40〜50%を借入で賄うのが一般的で、日銀のマイナス金利政策が修正されると、支払利息が増え分配金が圧迫される可能性があります。2024年末に長期金利が1%台へ上昇した際、借入比率の高い銘柄は分配金予想を下方修正しました。つまり、財務体質が強固かどうかを見極めることがインフレ局面での防御策になります。
最後に追加費用の発生です。上場REITには投資口を保有するだけで発生する「資産運用報酬」「物件管理報酬」などの内部コストがあり、さらに証券会社の売買手数料もかかります。野村資本市場研究所の調べでは、年間の実質コストが利回りを0.4%程度押し下げるケースが確認されています。利回りだけを見て判断すると、想定より手取りが減る結果になりかねません。
インフレ耐性を測る三つの視点
ポイントは、上記デメリットを踏まえた上で「REITがインフレ対策になり得る条件」を知ることです。その視点としては「賃料改定力」「物件用途の分散」「内部留保の厚み」が挙げられます。これらの要素が強いほど、インフレ局面で分配金を維持しやすくなります。
賃料改定力とは、テナントとの契約更新時に賃料を引き上げられる交渉余地のことです。オフィス系REITよりも、短期契約が多い商業施設系やホテル系の方が改定サイクルは短く、インフレを価格転嫁しやすい傾向にあります。一方、長期固定賃料の物流施設は値上げが難しいものの、EC需要の拡大で稼働率が高く保たれやすい利点があります。このように、物件用途ごとの特性を把握することで、ポートフォリオ全体の耐性を高められます。
また、用途を分散させることで、個別セクターの不況を緩和できます。総合型REITはオフィス・商業・住宅を組み合わせることで、どれか一つの市況が悪化してもダメージを限定できます。総務省の2025年家計調査によれば、インフレ下でも住居関連支出は伸び率が小さく、住宅系資産が一定の安定装置として機能することが示唆されています。
内部留保の厚みも重要です。分配金支払い後に手元資金を残す「内部留保戦略」を採るREITは、修繕費や金利上昇に備えやすくなります。日本ビルファンド投資法人の2025年上期決算では、分配金性向をあえて90%に落とし、残り10%を内部留保に回すことで財務健全性を確保しました。インフレが急加速して設備更新費が増えても、こうした準備があれば分配金の急減を避けやすくなります。
デメリットを緩和する具体的な投資戦略
実は、REITの弱点を完全に排除するのは不可能ですが、組み合わせ次第で影響を小さくできます。ここでは個人投資家が実践しやすい三つの戦略を紹介します。なお、いずれも短期売買ではなく、中長期での保有を前提としています。
第一に、インデックス型ETFの活用です。東証REIT指数連動型ETFを購入すれば、数千円から市場全体に分散投資できます。銘柄選定の手間を省きつつ、個別REITの価格急落リスクを希薄化できます。投資信託協会の2025年3月統計では、個別REITよりETFの方が1年リターンのブレが約20%低く抑えられています。値動きを穏やかにしたい人に向く方法です。
第二に、ドルコスト平均法で積立購入する方法があります。価格が高いときには少なく、安いときには多く買う仕組みが自動で働き、平均取得単価を平準化できます。楽天証券のシミュレーションでは、2015年から10年間、毎月3万円ずつ積み立てた場合、リターンの標準偏差が一括投資の約半分になりました。精神的ストレスが軽減されやすい点もメリットです。
第三に、REITと現物不動産、さらにはインフレ連動債を組み合わせる方法です。資産クラスの相関を下げることで、インフレや金利変動の影響を部分的に打ち消せます。内閣府の2025年版経済財政白書でも、複数資産への分散が長期リターンを高める有効策と示されています。現物不動産を保有する余力がない場合は、インフラファンドや海外REITで補完する手もあります。
税制と2025年度の公的支援策を確認する
基本的に、REITの分配金は「配当所得」に分類され、課税方法は株式配当と同じ源泉徴収20.315%が適用されます。ただし、2025年度も継続する「NISA新制度」を活用すれば、年間最大240万円までの買付け分について分配金と譲渡益が非課税となります。投資期間が無期限化された成長投資枠を組み合わせることで、長期でのインフレヘッジ効果を高められます。
一方、iDeCo(個人型確定拠出年金)ではREIT投資信託を選択でき、掛金所得控除と運用益非課税の二重メリットがあります。受取時には退職所得控除や公的年金等控除が使えるため、将来のインフレが年金購買力を下げても補完効果が期待できます。国税庁のシミュレーターによると、年収600万円の会社員がiDeCoで月2万円を積み立てれば、年間約3万6千円の所得税・住民税が節税できる試算です。
結論として、税制優遇を最大限活用し、コストを抑えながら長期保有することが、REITのデメリットを補いインフレ対策効果を高める現実的な道筋といえます。制度は毎年見直される可能性があるため、金融庁や証券会社の最新情報を定期的に確認しましょう。
まとめ
REITは少額で複数の不動産に分散投資でき、インカムと値上がり益の両方を狙える便利な商品です。しかし、価格変動や金利上昇、内部コストといったデメリットを理解せずに購入すると、想定外の損失を被る恐れがあります。本記事で触れた「賃料改定力」「用途分散」「内部留保」といった視点で銘柄を選び、ETFや積立投資でリスクを薄める戦略を組み合わせれば、インフレ局面でも安定した資産形成が可能になります。まずは少額から実践し、経験を積みながら自分の投資ルールを磨いてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産・建設経済局 – https://www.mlit.go.jp
- 日本取引所グループ JPXデータクラウド – https://www.jpx.co.jp
- 総務省統計局 家計調査 2025年版 – https://www.stat.go.jp
- 内閣府 経済財政白書 2025 – https://www5.cao.go.jp
- 投資信託協会 統計資料 2025年3月 – https://www.toushin.or.jp
- 野村資本市場研究所 レポート – https://www.nicmr.com
- 国税庁 iDeCo節税シミュレーター – https://www.nta.go.jp
