家賃収入を得ながら効率よく税金を抑えたい――そんな思いで不動産投資を検討している方は多いはずです。実際、利益が出ても税負担が大きくなると手残りが減り、投資の魅力も半減してしまいます。本記事では「不動産投資 おすすめ 節税」という視点から、2025年9月時点で実際に使える制度と実務的なコツを整理しました。初めての方でも理解しやすいように基礎から応用までを段階的に解説するので、読み終わる頃には自分に合った節税戦略が描けるようになります。
不動産所得の仕組みと節税の全体像
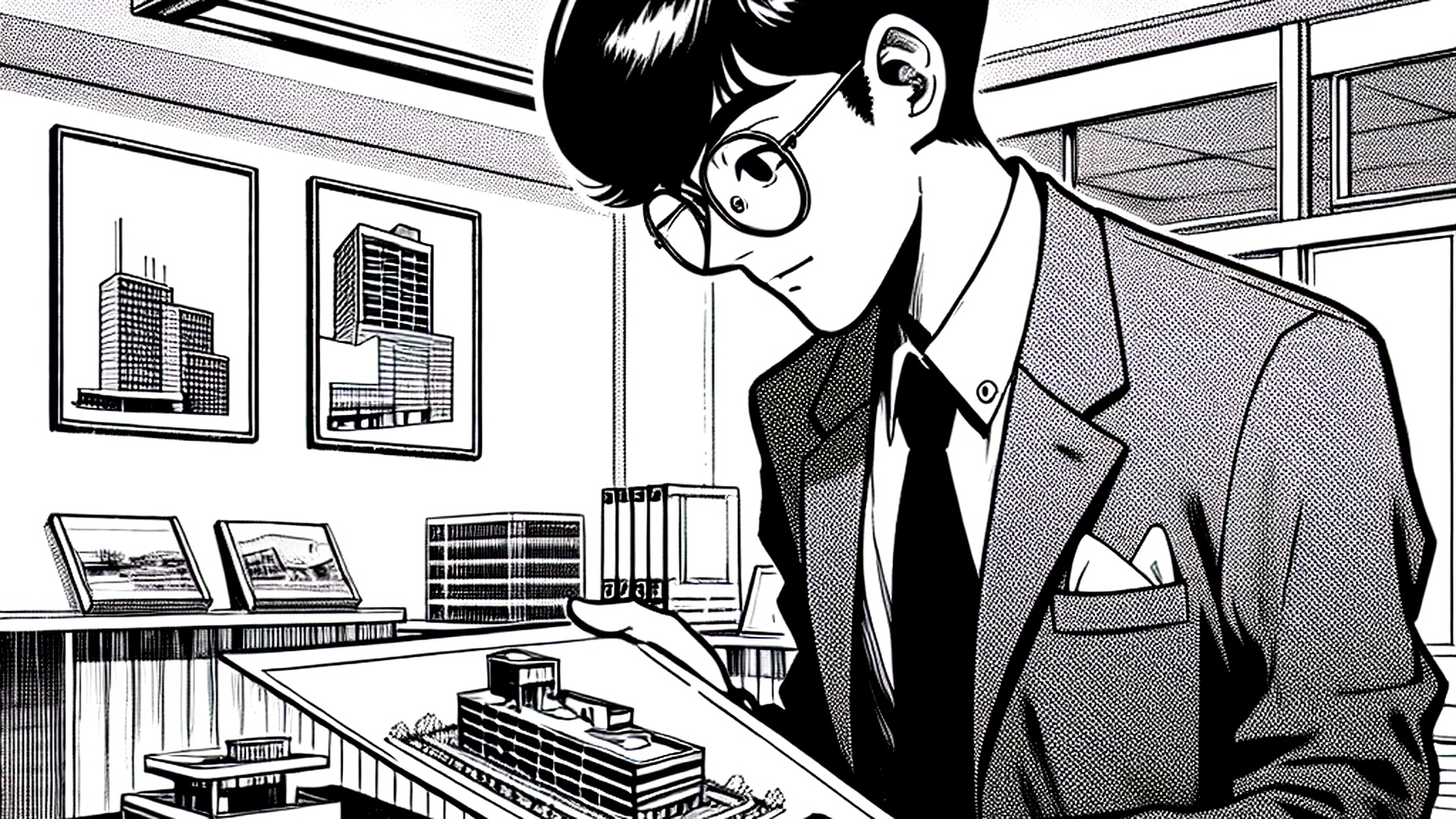
まず押さえておきたいのは、不動産所得の計算構造です。家賃などの総収入から必要経費を差し引き、さらに青色申告特別控除などを適用した残額が課税所得となります。
税務署が公表する「所得税基本通達」によると、必要経費には管理委託費、固定資産税、修繕費のほか、減価償却費が含まれます。減価償却費は実際の支出を伴わない経費として知られ、キャッシュを温存しつつ所得を圧縮できる点が魅力です。また、一定要件を満たせば65万円の青色申告特別控除(2025年度も継続)が使え、さらなる節税が期待できます。
重要なのは、経費と控除を組み合わせることで実効税率を下げるという発想です。例えば年間家賃収入600万円、経費240万円の物件なら、経費率40%です。このケースで減価償却費を80万円、青色申告特別控除を65万円確保できれば、課税対象は215万円にまで減少します。税率20%と住民税10%を合わせた30%で計算すると、税額は約65万円となり、何もしない場合と比べて年間40万円近い差が生まれます。
空室リスクや金利上昇に備えるためにも、まずは所得計算の仕組みを理解し、経費と控除を計画的に活用することが節税の出発点になります。
減価償却を活かしたキャッシュフロー改善

ポイントは、法定耐用年数と残存耐用年数の考え方を把握することです。建物や設備は種類ごとに耐用年数が決められており、購入後に残存耐用年数で償却を行います。
中古木造アパート(法定耐用年数22年)を築15年で購入した場合、残存耐用年数は22年-経過年数15年=7年です。ただし2025年度の所得税法では、残存耐用年数が2年未満になると「耐用年数×0.2」を下限とする特例が認められており、最短4年での償却が可能になります。4年償却を選択すれば年間償却費は大きくなり、課税所得の圧縮効果が高まります。
一方で償却期間を短くすると、将来の償却費が早期に枯渇する点に注意が必要です。計画段階で長期シミュレーションを作り、4年償却と7年償却の双方で手残りを比較すると、適切なバランスが見えてきます。また、耐用年数が47年と長いRC造マンションは、残存年数が長くなる傾向にあり、安定した節税メリットを得やすいのが特徴です。
つまり、減価償却は短期キャッシュ最大化と長期安定のどちらを優先するかで最適解が変わります。投資目的と資金繰りを照らし合わせ、物件構造や築年数を選ぶ段階から節税シナリオを組み込むことが成功への鍵です。
青色申告と法人化、どちらが有利か
実は、個人の青色申告か法人化かで節税効果が大きく異なります。青色申告の主なメリットは65万円控除と赤字の3年繰越、そして家族への給与支払いが経費化できる点です。
家賃収入が年間800万円程度までなら、累進課税の個人所得税でも実効税率が20%前後に収まり、青色申告だけで十分なケースが多いです。しかし、収入が1,000万円を超え、最高税率33%帯に入ると、法人実効税率約30%のほうが有利になる場合が出てきます。さらに法人なら役員報酬と配当を使い分けることで、社会保険料負担もコントロールできます。
2025年度の税制改正では、中小法人の所得800万円以下に対する軽減税率15%が据え置かれました。この優遇を受けると、課税所得800万円の法人税は120万円となり、同所得を個人で受け取る場合より40万円前後低くなります。もっとも、法人設立には登記費用や毎期の決算申告費用が発生するため、初期費用と維持コストを差し引いてメリットが残るかを必ず計算してください。
所得規模が拡大してから慌てて法人化すると、金融機関との取引履歴が浅く融資で不利になることもあります。将来的な事業規模と資金調達計画を見据え、早期に個人か法人かの方針を固めることが、継続的な節税と資産拡大を両立させるポイントになります。
修繕・リフォーム費用を経費にするポイント
基本的に、修繕費は発生年度に全額経費計上できますが、資本的支出に該当すると減価償却の対象になります。国税庁のタックスアンサーでは、20万円未満またはおおむね3年周期で行う修繕は費用計上が妥当と説明されています。
例えば、空室対策としてキッチンを交換し、同等品に取り替える場合は修繕費として処理できる可能性が高いです。一方、キッチンをハイグレード仕様に変更し、価値を大幅に高めた場合は資本的支出となり、耐用年数で償却しなければなりません。費用と資本的支出の線引きは微妙なケースも多いため、見積書や写真で「現状回復」か「価値向上」かを説明できる資料を準備しておくと安心です。
また、2025年度も継続する「省エネ改修促進税制」は、賃貸住宅の断熱改修に対して一定割合の税額控除が受けられる制度です。ただし、国土交通省の認定を受けた工事であること、控除上限が工事費用の10%または250万円のいずれか低い方に制限される点に注意しましょう。適用には事前申請が必要なため、着工前に税理士と施工業者を交えてスケジュールを確認してください。
修繕を計画する際は、空室期間の損失リスクも考慮に入れます。繁忙期直前に完工させると、家賃アップと節税を同時に実現できる可能性が高まります。経費のタイミングを調整することで、所得の平準化とキャッシュフローの安定化が図れる点を意識しましょう。
相続と贈与を踏まえた長期的節税戦略
重要なのは、保有期間中の所得税だけでなく、将来の相続税・贈与税まで視野に入れることです。不動産は評価額が時価より低く算定される傾向があり、現金よりも相続税の圧縮効果が高い資産となります。
国税庁の「財産評価基準書」に基づけば、貸家建付地は自用地評価額に借家権割合(30%)を掛け、さらに借地権割合を考慮して評価します。これにより、時価1億円の賃貸アパートでも相続税評価は概ね7,000万円前後まで下がる例が珍しくありません。加えて建物部分には「貸家評価減」が適用され、課税対象額をさらに引き下げることが可能です。
2025年度の税制では、基礎控除3,000万円+法定相続人600万円×人数の式は維持されています。ただし、2024年から始まった相続登記の義務化に伴い、相続発生後3年以内に登記をしないと過料の対象となるため、節税だけでなくリスク管理の面でも早めの対策が必要です。
生前贈与を活用する場合は、相続時精算課税と暦年贈与を組み合わせる手法が有効です。特に相続時精算課税は2,500万円まで非課税で一括贈与できるため、築浅物件を子ども名義に移し、将来の家賃収入を世代間で分散させることで所得税と相続税の双方を抑えられます。家族構成や資産規模によって最適解が異なるため、遺言書と合わせて専門家のサポートを受けることが欠かせません。
まとめ
本記事では、不動産所得の仕組み、減価償却、青色申告と法人化、修繕費の扱い、さらに相続までを一気に整理しました。ポイントは「経費と控除を戦略的に組み合わせ、長期シミュレーションで判断する」ことです。まずは自身の収入規模と投資目的を明確にし、減価償却や青色申告で手残りを確保しつつ、将来の相続まで見据えた計画を立てましょう。早期に行動を起こし、2025年度の制度を最大限に活用することで、安定したキャッシュフローと資産形成が実現できます。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 財務省「所得税法令集」 – https://www.mof.go.jp
- 国土交通省「省エネ改修促進税制の概要」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局「家計調査」 – https://www.stat.go.jp
- 不動産流通推進センター「不動産取引価格情報」 – https://www.retpc.jp

