古いアパートでも高い利回りが取れると聞いて興味はあるものの、「空室が多いのでは」「修繕費がかさむのでは」と二の足を踏む方は多いはずです。実は、築年数が進んだ物件には価格が抑えられている分、収益面で優位に立てる場面が少なくありません。本記事では利回りの基本から、物件選定、運営改善、2025年度の制度活用までを順序立てて解説します。読み終えたときには、築古アパート 利回りをどう見極め、どう伸ばすかの具体的イメージが描けるようになるでしょう。
築古アパート投資が注目される背景
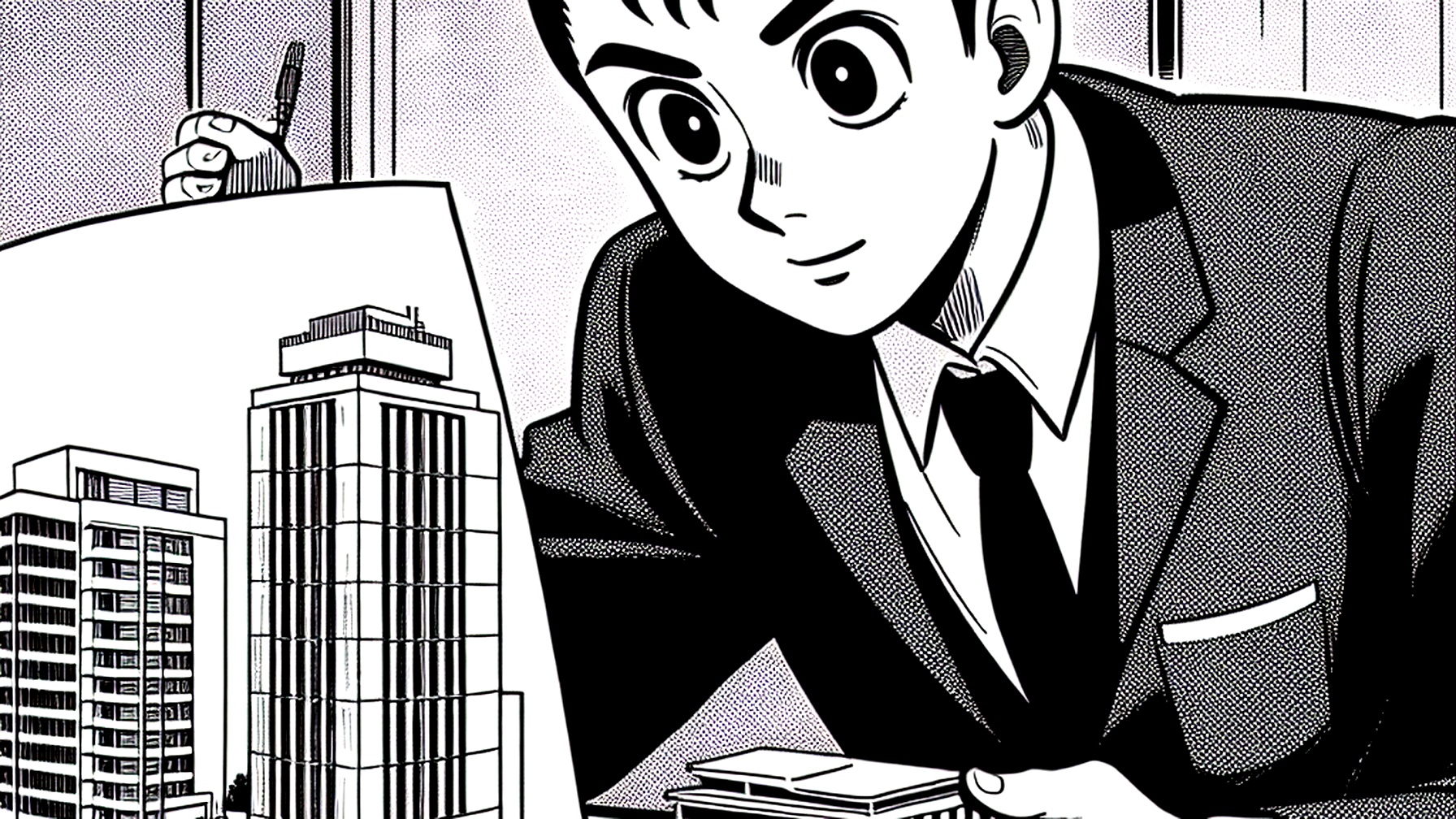
ポイントは、低取得価格と賃料水準のギャップが大きいことです。日本不動産研究所の調査では、2025年10月時点の東京23区アパート平均表面利回りは5.1%ですが、築30年以上の木造に絞ると7%前後まで跳ね上がります。つまり築年数が進むほど、家賃が緩やかに下がる一方で、売買価格は急激に落ち込む傾向があるのです。
一方で全国平均のアパート空室率は21.2%(国土交通省、2025年8月)と依然高い水準にあります。空室をどう埋めるか、修繕コストをどう抑えるかを誤れば利回りは簡単に崩れます。だからこそ事前に需要を把握し、数字だけでなく周辺環境や競合物件の状況を確認する姿勢が求められます。
加えて、コロナ禍以降に続いた物価上昇で新築コストは上がり続けています。建築費の高騰に伴い、築古への資金シフトが進んでいることも流通価格を押し下げ、高利回りを狙える土壌をつくっています。
利回りの基本と築古の特徴
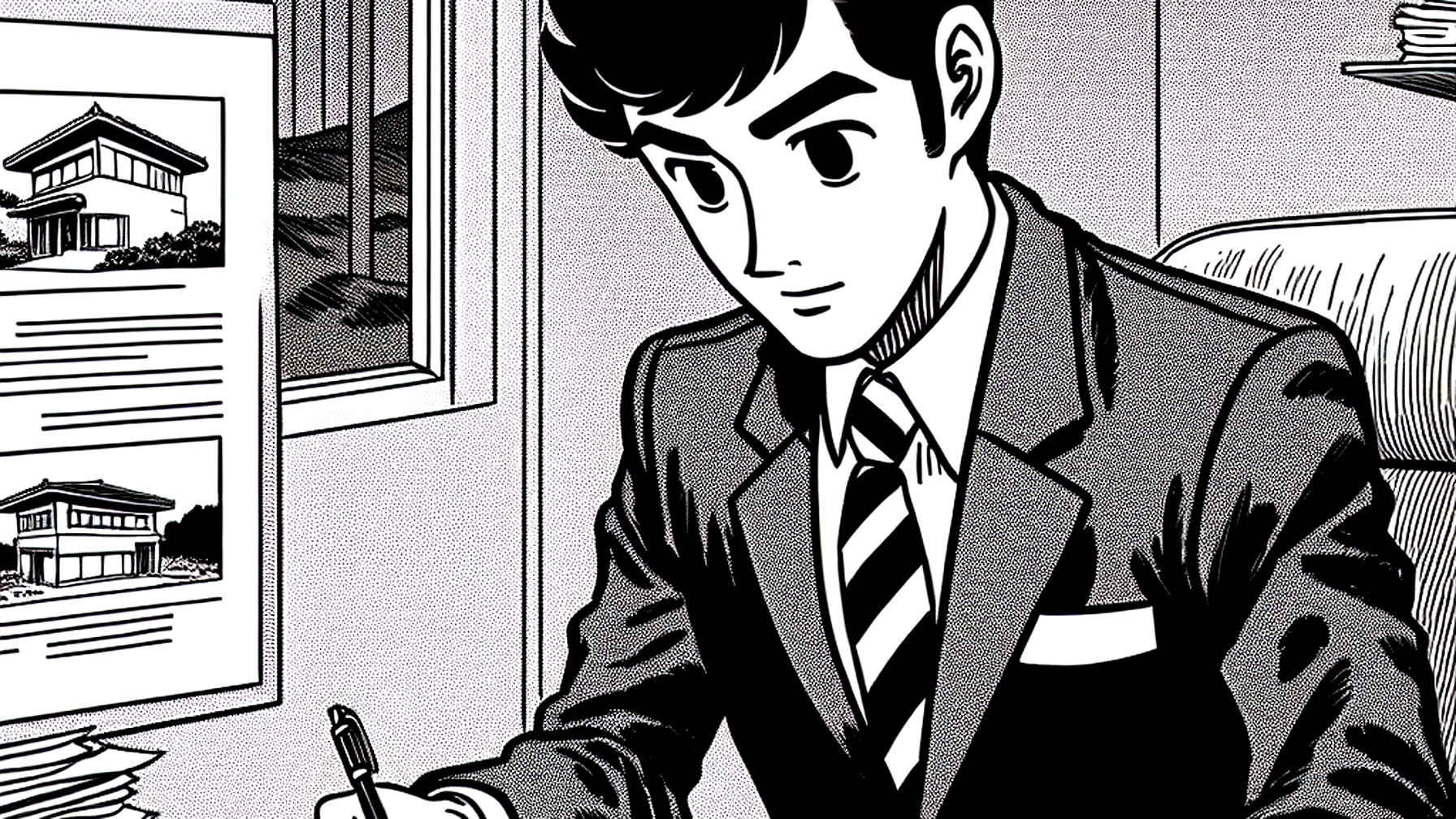
まず押さえておきたいのは、利回りには「表面」と「実質」がある点です。表面利回りは年間家賃収入を物件価格で割った単純な指標で、広告に載るのはこちらがほとんどです。対して実質利回りは諸経費や空室リスクを考慮した後の手取りベースの指標となります。築古では修繕費が増えがちなため、実質利回りで6%以上を保てるかが一つの目安になります。
築年数が20年を超える木造は原価償却が進んでおり、税務上の残存価額が小さい点が特徴です。所得税の圧縮効果が高まるため、高所得者ほど手取り後の利回りが改善しやすい構造になります。また、構造上の耐震基準が1981年を境に変わったことは忘れがちです。旧耐震の場合は金融機関が融資期間を短めに設定するので、キャッシュフローが圧迫されるリスクを織り込む必要があります。
さらに、築古の家賃は下げ止まりやすいという実務的メリットもあります。家賃下落カーブは築15年までが急で、その後は緩やかになります。つまり購入時点で家賃が底打ちしていれば、家賃下落による利回り低下を過度に心配する必要はありません。ただし、リフォームによる競争力強化は不可欠です。
高利回りを実現する物件選定の視点
重要なのは、単に利回りの数字が高い物件を追いかけないことです。まず賃貸需要を見極めるため、駅徒歩10分以内、主要大学や工業団地まで自転車圏内など、ターゲット層が明確なエリアに絞ります。次に競合物件との賃料差を調べ、同等の部屋が満室かどうかを確認すると、空室リスクを推定できます。
建物の状態は外壁、屋根、防水の3点に注目します。築古アパートで想定外に費用が膨らむのは外壁と屋根の大規模修繕です。購入前にドローン調査や赤外線診断を実施し、5年以内に必要となる工事費を見積もると実質利回りの精度が高まります。また、間取りは風呂・トイレ別かどうかが入居率を左右するため、水回りを分離できるスペースがあるか確認することが欠かせません。
利回りを底上げするうえで、土地と建物の割合にも目を向けるべきです。土地比率が高いほど減価償却は取りづらくなりますが、担保評価は安定します。一方、建物比率が高いと節税効果は高いものの、金融機関によっては評価が下がるケースがあります。自分が重視するキャッシュフローと借り入れ条件のバランスを考えながら、シミュレーションを複数パターン作ることが安全策になります。
購入後の運営改善で利回りを守る
実は、購入後の運営次第で利回りは大きく変動します。まず空室対策として、スマートロックや高速インターネットを導入すると、月額賃料を2,000〜3,000円上げても競争力を保てる事例が増えています。初期投資は一戸あたり10万円程度ですが、家賃アップが続けば2〜3年で回収可能です。
次に修繕計画を長期にわたり組むことで、突発的な資金流出を防げます。屋根塗装、外壁補修、給水設備交換などを10年サイクルで平準化し、毎月修繕積立を行えば、実質利回りのブレが小さくなります。ここで重要なのは、見積もりを複数社から取り、相場と比較することです。国土交通省の「建築工事費デフレーター」を参考に、材料費高騰の影響を見込んでおくと予算超過を避けられます。
家賃滞納リスクに備え、2025年10月時点で主流となった家賃保証会社の利用率は90%を超えています。保証料は賃料の4〜5%が相場ですが、実質利回りを守る保険と考えれば有効です。さらにエネルギーコスト削減のために、共用部LED化や太陽光パネル設置を組み合わせると、年間数十万円規模の電気代削減が見込めます。
2025年度の制度と融資環境を活かす
まず、耐震・省エネ改修を行った住宅に対する2025年度固定資産税の軽減措置は築古アパートにも適用されます。工事完了の翌年度に限り、家屋部分の課税標準が最大2分の1になるため、大規模修繕を計画する際は時期を合わせると効果的です。期限は2026年3月31日取得分までとされているので、スケジュール管理が鍵となります。
金融面では、地銀や信用金庫が地域活性化策として築古アパート向けの長期固定金利商品を拡充しています。2025年9月時点の平均金利は1.7%台で、3年前より0.3ポイント下がりました。地方圏でも評価の高い管理計画書を提示すると金利優遇が受けられるケースがあり、実質利回りをさらに押し上げる余地があります。
また、国土交通省が主導する「賃貸住宅エネルギー性能向上事業(2025年度)」では、断熱改修や高効率給湯器の導入に対して補助率3分の1、上限150万円が設定されています。制度は予算消化次第で受付終了となるため、施工業者と連携して早めに申請するとよいでしょう。こうした公的支援を踏まえた長期計画を立てると、築古アパート 利回りを安定的に確保できます。
まとめ
築古アパートは取得価格の安さと税務メリットから高い利回りを実現しやすい一方、空室や修繕といった落とし穴も抱えています。本記事で示したように、需要が読める立地選定、購入前の詳細な調査、購入後の計画的運営、そして2025年度の制度活用を組み合わせることで、実質利回り6%以上を狙う戦略は十分現実的です。まずは候補エリアの賃貸市場を歩いて確かめ、数字と現場感の両面からシミュレーションを重ねてみてください。行動を起こすことで、高利回りという成果は確実に近づきます。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp/
- 国土交通省 住宅統計調査 – https://www.mlit.go.jp/
- 国税庁 資産の償却率表 – https://www.nta.go.jp/
- 総務省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp/
- 金融庁 監督指針 公表資料 – https://www.fsa.go.jp/

