物件を購入して家賃収入が入り始めると、多くの人が「確定申告って難しそう」と感じます。実際には決まった流れと必要書類を押さえれば、税務署に行かなくても自宅で完結できます。この記事では、不動産投資歴15年の筆者が、2025年度の最新ルールに基づきながら、初めてでも迷わない手順と節税のコツを分かりやすく解説します。読み終える頃には「不動産投資 確定申告 やり方」が具体的にイメージでき、翌年の申告に自信を持てるはずです。
確定申告が必要になるラインを知る
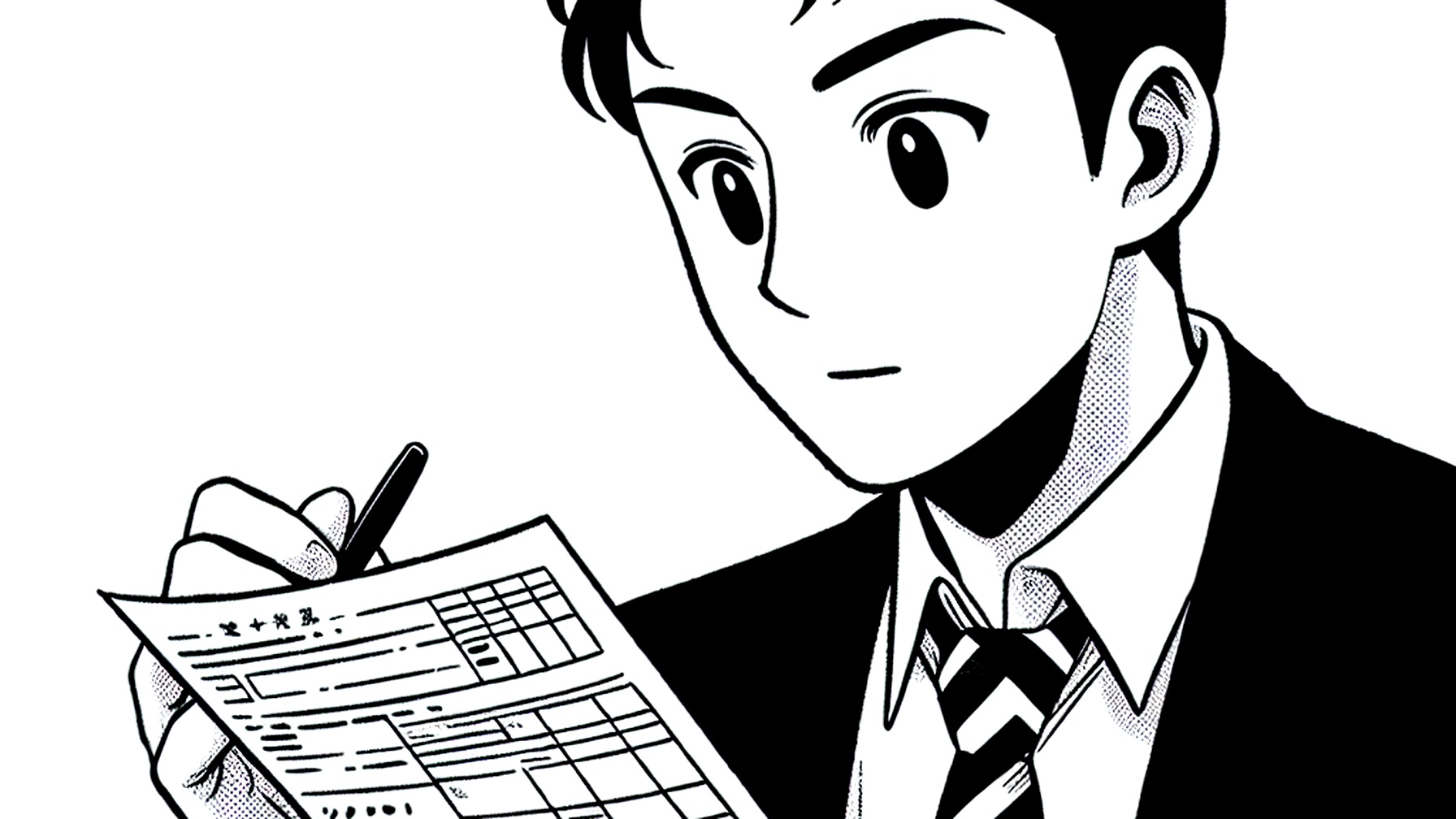
まず押さえておきたいのは、「どのタイミングで申告義務が生じるのか」という基準です。不動産所得が年間20万円を超えると、会社員でも確定申告が必須になります。一方で、家賃収入が20万円以下でも医療費控除やふるさと納税を併せて申告するケースでは、不動産所得の有無にかかわらず手続きが必要です。
加えて、青色申告を選ぶ場合は事前に「青色申告承認申請書」を提出することが条件となります。国税庁の統計によると、青色申告者の約七割が65万円控除を利用し、所得税を平均15%圧縮しています。つまり、所得規模にかかわらず、制度を理解して準備を進めることがトータルの節税に直結するといえます。
必要書類と準備のステップ

ポイントは、1年間の経済活動を「証拠」として残すことにあります。家賃の入金記録、管理会社からの精算書、ローン年末残高証明書、固定資産税の領収書など、収入と支出を裏付ける書類を漏れなく保存しましょう。2024年から義務化された電子帳簿保存法により、紙の領収書をスキャン保存する場合は、受領後おおむね2か月以内にタイムスタンプを付与する必要があります。
次に、会計ソフトへ数字を入力して試算表を作成します。最近のクラウド型は銀行口座やクレジットカードと連携できるため、レシート入力の手間が大幅に減りました。ソフトが自動分類した仕訳を月ごとに点検し、誤りがあれば修正するだけで損益計算書は完成します。最後に、e-Tax用の拡張子(.xtx)でデータを書き出せば準備は完了です。
青色申告と白色申告の違いを理解する
重要なのは、控除額と帳簿の負担をどうバランスさせるかです。青色申告には10万円、55万円、65万円の3パターンの控除があります。65万円控除を受けるには複式簿記と電子申告が必須ですが、帳簿がしっかりしていれば赤字を3年間繰り越せるメリットも付きます。一方、白色申告は帳簿ルールが緩やかで手軽ですが、控除は受けられません。
実は、戸建て1棟だけの投資でも、青色にすることで管理費や減価償却費といった経費を余さず計上でき、税率が15%の人なら年10万円以上の差が出ることもあります。つまり、多少の手間を惜しまなければ青色申告は初心者にも十分にリターンがある制度と言えるでしょう。
経費計上で押さえるべきポイント
まず押さえておきたいのは、「経費は実際に支払った時点で計上する」という現金主義と、「発生した時点で計上する」発生主義の違いです。青色65万円控除を狙うなら発生主義を選びます。例えば12月に修繕を発注し、翌1月に支払う場合でも、発生主義なら前年の費用として計上できます。
減価償却費は建物や設備を年数に分けて費用化する仕組みで、国税庁の「耐用年数表」を参照します。木造アパートなら22年、RC造マンションなら47年です。減価償却の対象にはエアコンや給湯器といった付帯設備も含まれます。高額なリフォームを一括で経費に入れるより、耐用年数に応じて計上したほうが赤字が大きくなりすぎず、金融機関の評価も安定しやすい点を覚えておきましょう。
e-Taxでスムーズに申告するコツ
ポイントは、事前準備と送信テストを早めに済ませることです。マイナンバーカード方式なら、ICカードリーダーまたは2025年版のマイナポータル連携アプリがあればスマホだけで認証できます。国税庁のデータによると、e-Tax利用者は2024年度に3400万人を超え、還付までの平均日数は紙提出より5日短縮されました。
送信画面では「不動産所得の内訳書」を忘れずに添付します。控除証明書や医療費控除のXMLファイルも同時にアップロードできるため、添付漏れのリスクが減ります。最後に受信通知メールが届けば手続きは完了し、マイページから還付状況を確認できます。これらを踏まえると、紙の申告書に印刷して郵送するよりも、時間とコストを大幅に節約できることがわかります。
まとめ
ここまで、不動産投資家として確定申告を行うための流れとポイントを解説しました。義務が発生するラインを知り、1年間の書類を早めに整理し、青色申告で控除を最大化することが大切です。さらに、経費の考え方やe-Taxの活用を理解すれば、手続きは難しくありません。まずは領収書を日付順に整理し、会計ソフトで月次チェックを始めてみてください。行動を早めるほど、来年の申告はスムーズになり、投資のキャッシュフロー改善にもつながります。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp
- デジタル庁(マイナンバーカード関連) – https://www.digital.go.jp
- 中小企業庁(電子帳簿保存法解説) – https://www.chusho.meti.go.jp
- 全国銀行協会(住宅ローン統計) – https://www.zenginkyo.or.jp

