RC造(鉄筋コンクリート造)マンションに興味はあるものの、「実際の利回りはどうなのか」「木造や軽量鉄骨と比べて本当に有利なのか」と迷う方は多いものです。投資額が大きいだけに、判断を誤れば数百万円単位で損失が出る可能性もあります。本記事では、2025年10月時点の最新データを基に、RC造マンション 利回りの基本から収益を高める具体策までを丁寧に解説します。読み終える頃には、ご自身の投資戦略を一段深く考え直すヒントが得られるはずです。
RC造マンションが選ばれる理由
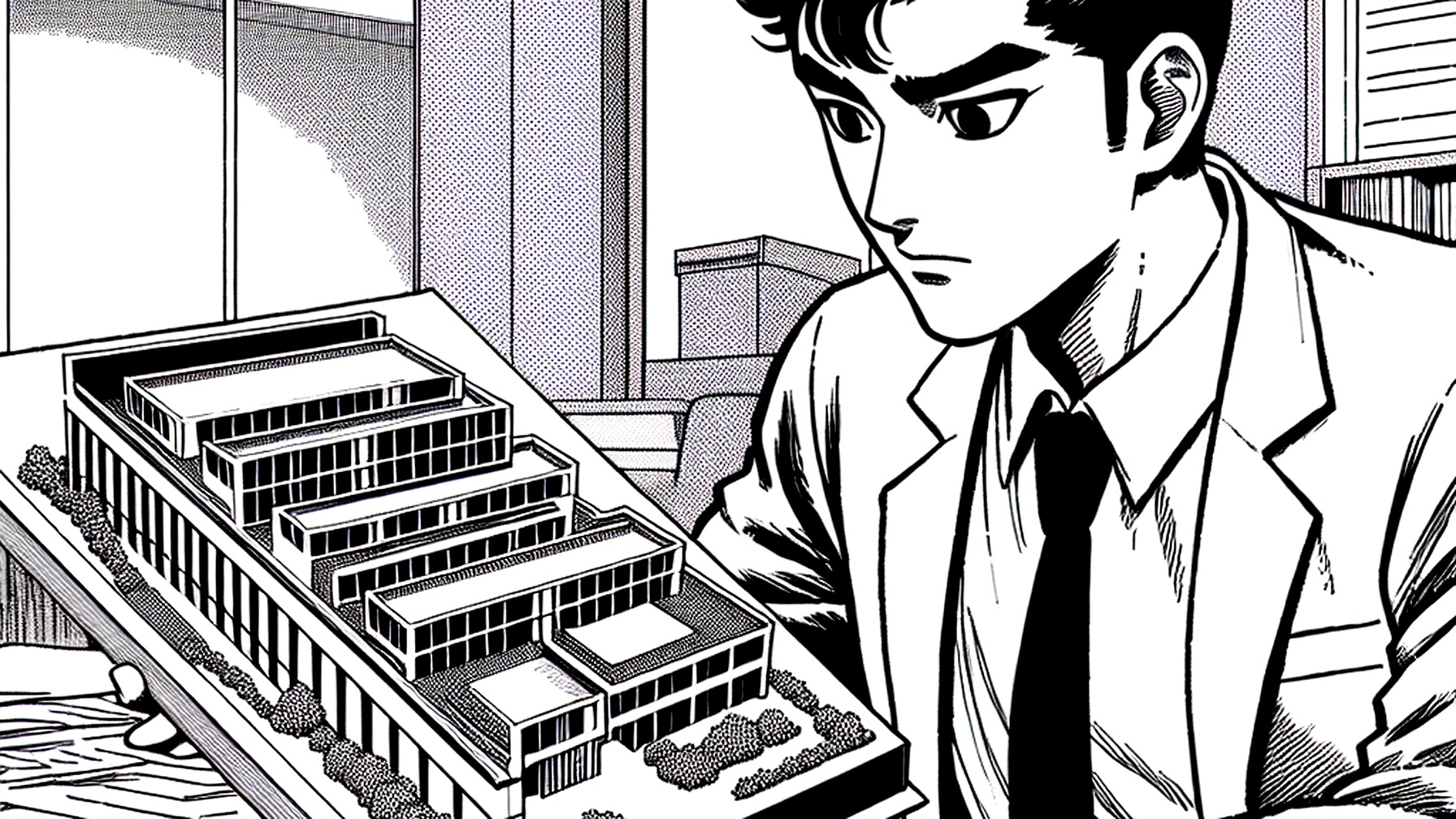
まず押さえておきたいのは、RC造マンションが他の構造よりも耐久性と資産価値の維持に優れている点です。鉄筋コンクリートは耐用年数が長く、法定耐用年数は47年に設定されています。木造(22年)や軽量鉄骨(27年)よりも長いことから、金融機関の融資期間を長く取りやすく、毎月の返済負担を抑えやすい利点があります。
さらに、遮音性や防火性が高いことから入居者満足度も高く、長期入居につながりやすい傾向があります。日本不動産研究所の2025年10月レポートによれば、東京23区におけるRC造ワンルームの平均入居年数は8.4年と、木造アパートの6.1年を大きく上回ります。長期入居は空室期間の短縮につながり、ひいては安定したキャッシュフローを生み出します。
加えて、RC造は大規模修繕のサイクルが長いため、長期的に見ると修繕コストが平準化される特徴があります。つまり人気と耐久性の両方を兼ね備えるRC造は、投資家にとって収益とリスクのバランスが取りやすい選択肢といえるのです。
利回りの基本を押さえる
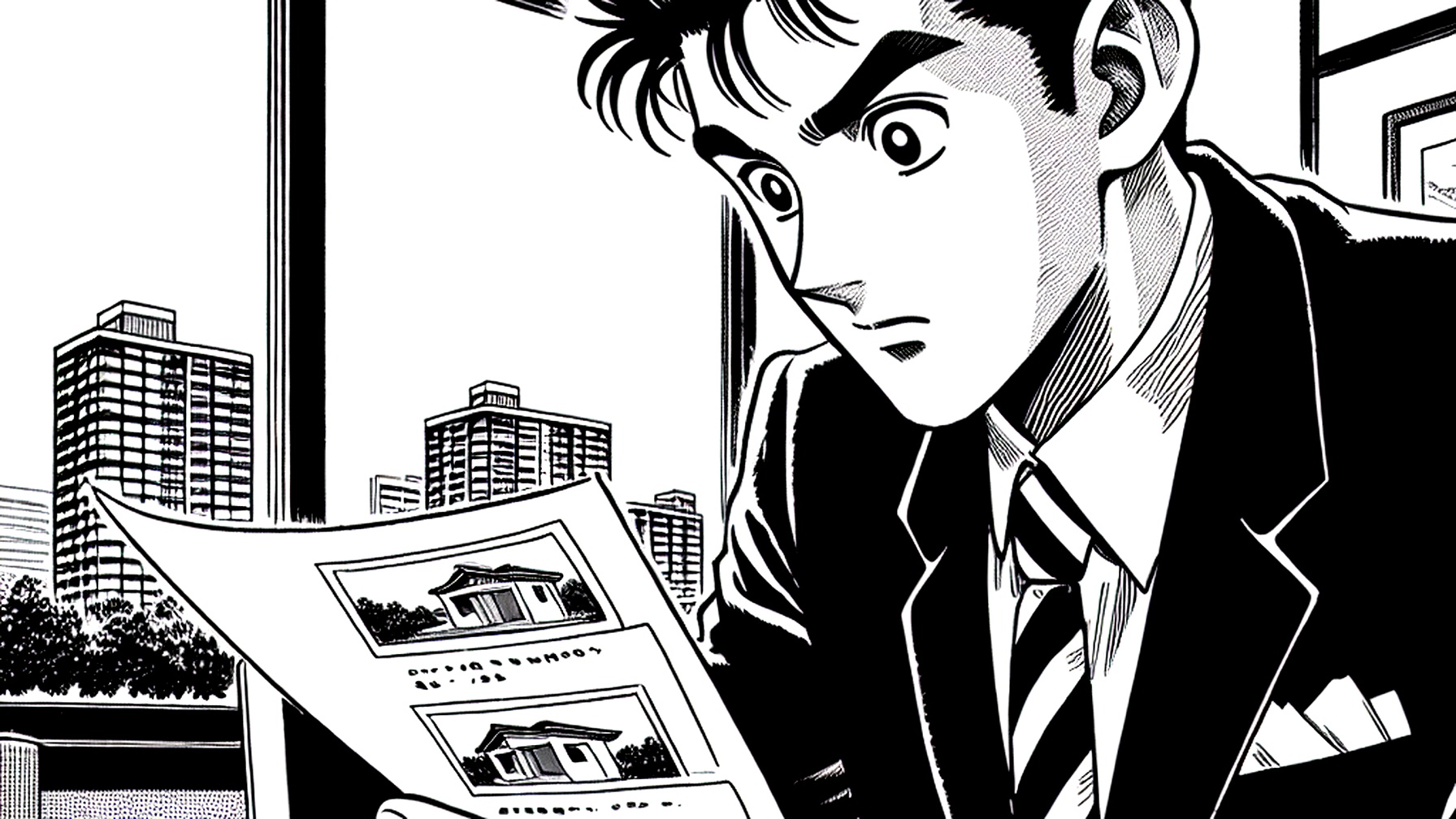
重要なのは、利回りには「表面利回り」と「実質利回り」の二つがある点を正確に理解することです。表面利回りは年間家賃収入を物件価格で割った単純な指標で、東京23区RC造ワンルームの平均は4.2%(日本不動産研究所、2025年10月)です。しかし諸費用を考慮しないため、投資判断には不十分です。
実質利回りは管理費・修繕積立金・固定資産税・損害保険料などのコストを差し引いて算出します。都心RC造の場合、年間家賃収入の15〜20%が運営コストとして消えるのが一般的です。たとえば表面利回り4.2%の物件でも、実質利回りは3.3〜3.6%程度に下がる計算になります。
一方で、金融機関からの借入金利や自己資金割合も実質的な投資効率に大きく影響します。金利1.5%で80%融資を受ける場合、キャッシュフローは表面利回り以上に圧縮されます。したがって投資判断では、家賃収入と運営コストに加え、融資条件を組み込んだ総合シミュレーションが欠かせません。
RC造と他構造の収益性比較
ポイントは、構造ごとの初期投資と運営コストを並べて見ることです。RC造マンションの新築平均価格は東京23区で7,580万円(不動産経済研究所、2025年10月)と、木造アパートより約30%高い傾向があります。初期投資が膨らむ一方で、RC造の空室率は都心で平均5.2%、木造アパートは8.7%となっており、稼働率の面ではRC造が有利です。
耐用年数が長いため、減価償却費を長期にわたり計上できる点も見逃せません。法人であれば節税効果を長く享受でき、キャッシュフローの安定に寄与します。たとえば耐用年数47年を定額法で償却すると、年2.13%程度を経費化できますが、木造の場合は年4.5%以上と高いため、早期に節税効果が薄れるデメリットがあります。
一方で利回りだけを追うなら、地方の木造アパートで表面利回り8%超の案件も存在します。ただし人口減少リスクや建物老朽化リスクが高く、短期的な高利回りと長期的な資産保全のどちらを重視するかで評価は分かれます。つまりRC造は「低めの利回りでも長期安定を図る戦略」に適していると言えます。
利回りを上げる具体策
実はRC造マンションでも工夫次第で利回りを底上げできます。第一に、購入時の価格交渉が最も即効性の高い手段です。売主が法人や相続案件の場合、早期売却を優先するケースがあり、相場より2〜3%下げられることも珍しくありません。価格を抑えられれば、そのまま表面利回りは向上します。
次に、家賃設定の適正化が重要です。東京都住宅供給公社の家賃データによると、築10年RC造ワンルームの中央値は8.3万円ですが、設備を高機能シャワートイレや宅配ボックスに更新するだけで、0.5〜0.8万円の上乗せが可能との調査があります。設備改善に100万円投じても、年間家賃で6〜10万円増収できれば投資回収期間は10〜17年と十分現実的です。
最後に管理の質を高めることが長期的な利回り向上に直結します。自主管理でコストを抑える手もありますが、空室対策や賃料交渉の専門知識がない場合リスクが高まります。賃貸管理業法に基づく登録事業者へ委託すると、月額家賃の3〜5%を手数料として支払うものの、平均入居期間が1.2倍になるとの業界統計もあります。長期で考えれば、適切な委託は結果的に利回りを押し上げる効果が期待できます。
2025年度の制度と金融環境
まず押さえておきたいのは、2025年度も不動産投資ローンの金利は低位で推移している点です。日本銀行は2025年7月の金融政策決定会合でマイナス金利を0.1%から0.0%に引き上げたものの、市場金利は想定より穏やかな上昇にとどまり、都市銀行の投資用ローン固定金利は平均1.38%(2025年10月、国土交通省調査)となっています。低金利は借入コストを抑え、実質利回りの悪化を防ぎます。
税制面では、RC造マンションに関して特別な新制度は設けられていませんが、従来からの減価償却と損益通算が2025年度も有効です。また、環境性能を高める改修を行う際に利用できる「既存賃貸住宅省エネ改修補助事業」(国交省・2025年度)の公募が継続しています。要件を満たせば1戸あたり最大60万円、1棟あたり最大500万円まで補助を受けられ、断熱改修や高効率給湯器の導入費用を圧縮できます。補助は予算上限に達し次第終了するため、申請タイミングがカギです。
一方で、金融機関は収益物件の融資審査において実質利回り3%以上を一つの目安にしています。そのため、利回りを高める工夫だけでなく、長期修繕計画や入居需要の裏付けを示す資料を充実させることが、融資承認への近道になります。
まとめ
RC造マンション 利回りを理解するうえで大切なのは、表面利回りの数字だけにとらわれず、空室率や運営コスト、融資条件まで視野を広げることです。RC造は耐用年数が長く、空室リスクも低いため、安定収益を狙う投資家に適しています。購入時の価格交渉、設備投資による家賃アップ、適切な管理会社選びを組み合わせれば、実質利回り3%台後半も十分に実現可能です。これから物件を探す方は、長期シミュレーションと制度活用の両面を確認し、自分のリスク許容度に合った最適な一棟を見極めてください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 住宅局 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 東京都住宅供給公社 家賃統計 – https://www.to-kousya.or.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp

