家賃が下がり続けるのではないか、修繕費が膨らんで赤字になるのではないか──築古アパート 運用に挑戦したい人の多くは、こうした不安を抱えています。しかし、適切な物件選びと計画的な運用を行えば、比較的少ない自己資金で安定したキャッシュフローを得ることも可能です。本記事では、初めての方でも理解できるよう、築古アパートの魅力と注意点、そして2025年10月時点で活用できる具体的な戦略を、最新データを交えて解説します。
築古アパートが選ばれる理由
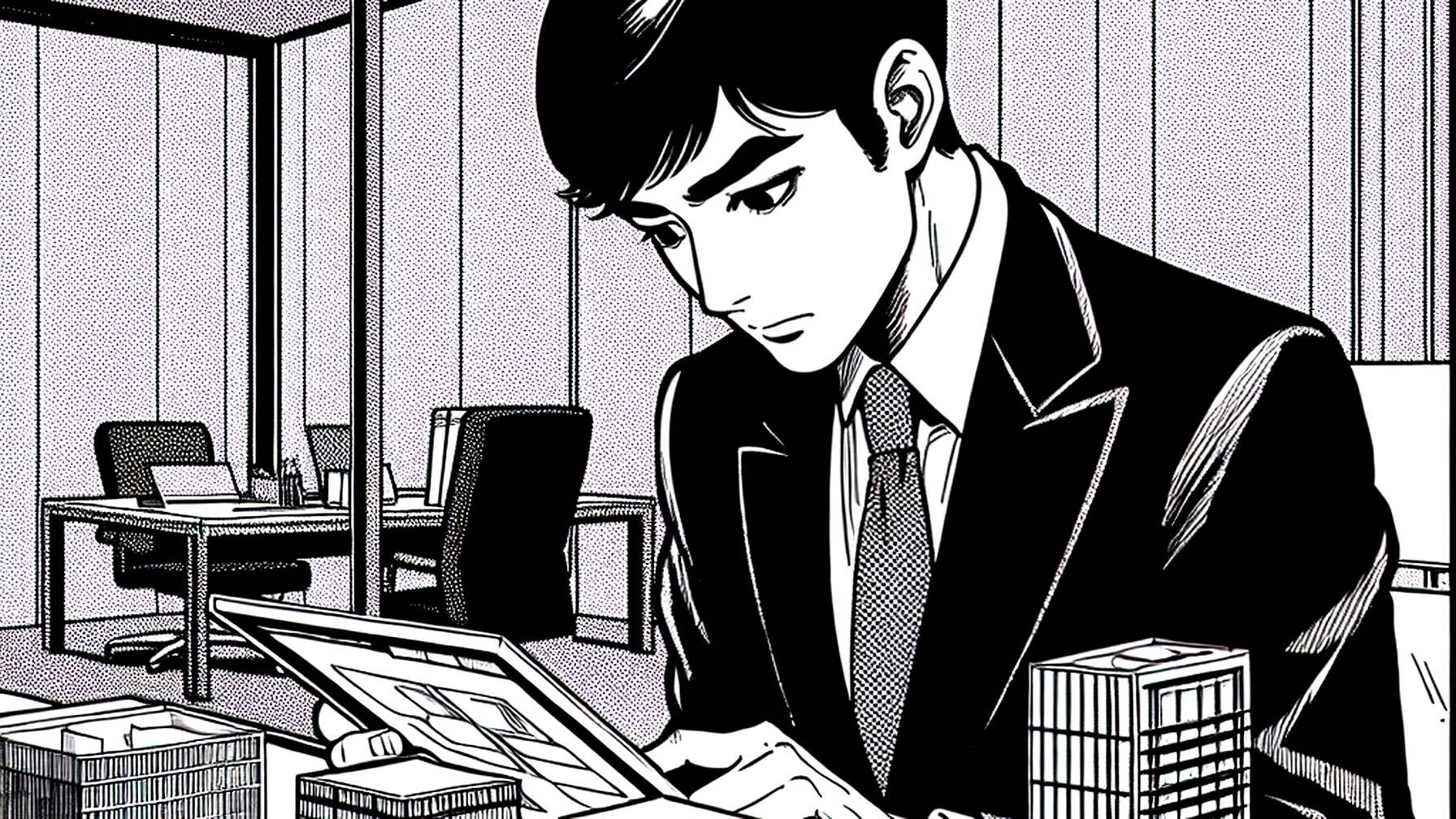
重要なのは、築古アパートならではの利点を正しく認識することです。新築に比べ物件価格が大幅に抑えられるため、投資利回りが高くなりやすい点は大きな魅力と言えます。
まず売買価格を例に取ると、都心近郊の木造アパートは築30年でも表面利回り10%前後で流通しています。自己資金を抑えつつ規模を拡大しやすいので、複数棟を組み合わせたポートフォリオ構築も視野に入ります。また、建物の簿価が低いため、2025年度税制でも認められている「建物部分の短期減価償却」を活用すると、早期に経費計上できるメリットがあります。
一方で、空室リスクや修繕コストの高さは避けて通れません。国土交通省住宅統計によると2025年8月時点の全国アパート空室率は21.2%ですが、築25年以上に限ると約30%に達します。つまり、利回りの高さはリスクと裏表であることを理解し、後述する収支シミュレーションやリフォーム計画を綿密に立てる必要があります。
収支シミュレーションの作り方
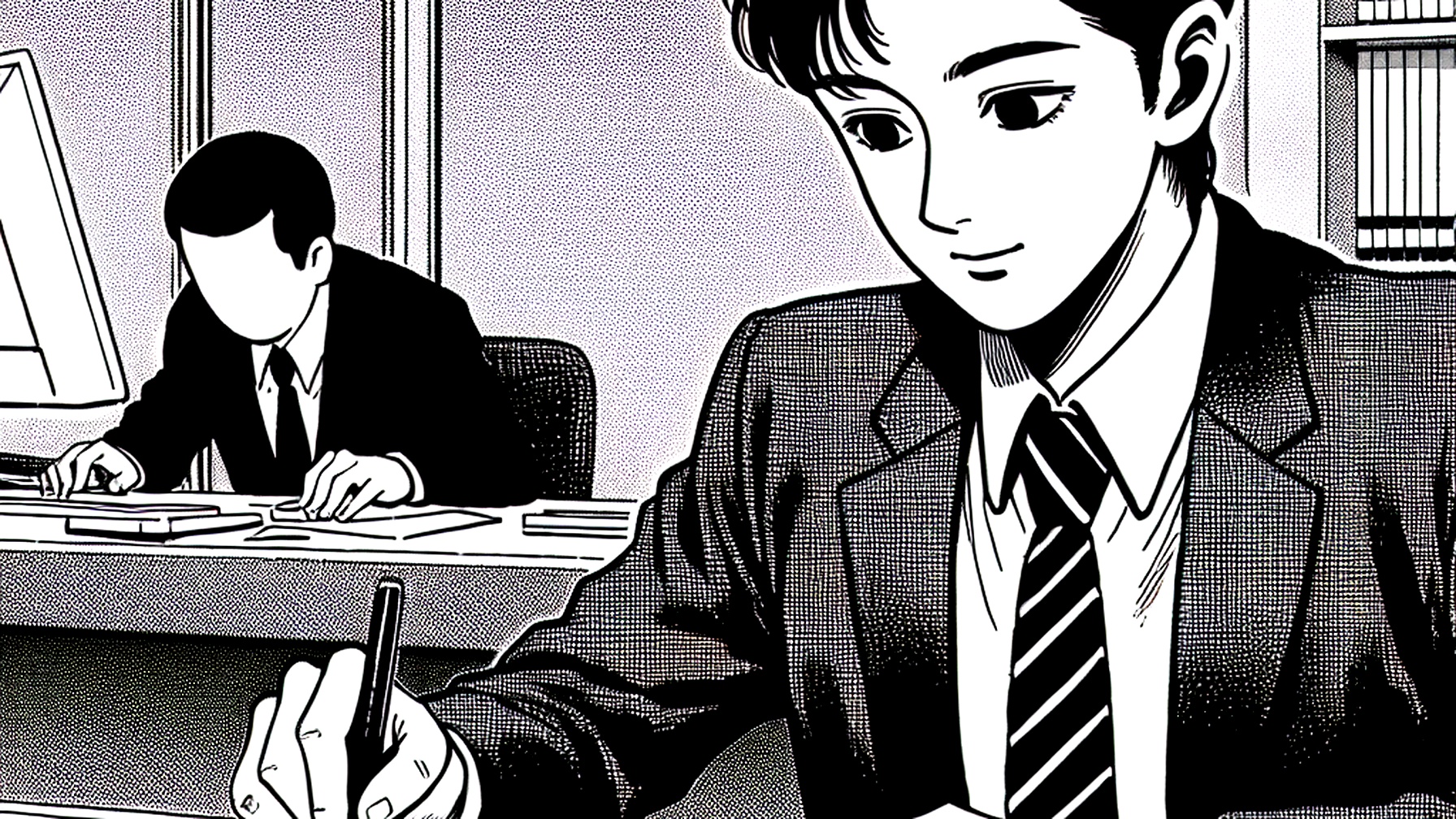
ポイントは、最初に「悲観シナリオ」を組み込むことです。購入価格や家賃だけでなく、空室率25%、金利上昇1.5%、修繕費年間家賃収入の15%といった厳しめの前提条件で計算しましょう。
具体的には、年間家賃収入から空室損失と運営費を差し引き、さらに想定修繕費を上乗せしてネットキャッシュフローを算出します。ここでプラスが確保できれば、現実的な運用でも十分に耐えられます。逆に赤字となる場合は、利回りを引き上げる交渉か購入見送りを検討することが賢明です。
実は、金融機関の審査でも同様の保守的な計算を行います。自己資金を2割以上投入すると金利優遇を受けやすくなるため、利息負担をさらに軽減できます。楽観的な試算だけに頼らず、厳しい数字でも黒字を確保できるモデルを作ることが、築古アパート 運用の成否を左右します。
運用で差がつくリフォーム戦略
まず押さえておきたいのは、リフォーム費を家賃アップで回収できるかどうかです。最近人気のインターネット無料設備やIoT鍵などは、1室あたり10万円前後の投資で家賃を月2000円上げられるケースがあります。単純計算で5年未満に投資を回収できるため、空室率の高い築古物件では効果的です。
一方で、フルリノベーションに300万円以上かけても、エリアの賃料相場が上がらなければ回収は難しくなります。東京都心と違い、地方都市では家賃上限が明確なので、設備投資額と賃料上振れ幅を冷静に比較する姿勢が重要です。
さらに、2025年度の「住宅省エネ改修補助金」は、一定の断熱性能を確保した窓交換などに対して一戸あたり最大45万円が支給されます。期限は2026年3月交付申請分までですが、採択状況によっては早期終了の可能性もあるため、早めの申請が望まれます。補助金を活用すれば、初期費用を抑えつつ競争力の高い物件へと再生できます。
資金調達と減価償却のポイント
実は、築古アパート 運用では「金融機関選び」が収支を大きく左右します。地方銀行や信用金庫は物件の耐用年数を重視しますが、建物評価よりも実質収益力を優先するノンバンクや投資専門の銀行も存在します。複数行を比較し、融資期間と金利を総合的に判断すると良いでしょう。
減価償却では、法定耐用年数を過ぎた木造アパートなら、取得価額を4年間で均等償却できる特例があります。この仕組みを利用すると、初年度から大きな経費を計上できるため、手残りキャッシュを増やしやすいのが特徴です。ただし、償却期間終了後に課税所得が増える点を見越し、繰り延べ効果と納税資金を確保しておく必要があります。
さらに、2025年度税制改正で創設された「賃貸住宅耐震改修促進税制」は、耐震基準を満たす改修工事費用の10%を税額控除できる仕組みです。控除上限は1棟当たり150万円、適用期限は2027年3月31日取得分までと定められています。老朽化が進む物件を安全かつ有利に運用するうえで、見逃せない制度と言えるでしょう。
空室対策と長期運用のコツ
ポイントは、ターゲットを明確にし、募集戦略を変化させ続けることです。例えば、駅から遠い築古アパートでも、駐車場完備かつファミリー向けに間取りを再構成すれば、車移動が主体の郊外エリアで需要を取り込めます。また、ペット共生型やDIY可能物件など、差別化を図る手法も有効です。
国土交通省の調査では、入居者が物件を選ぶ際の決定要因の上位に「インターネット環境」と「防犯性」が含まれます。Wi-Fi無料化に加え、共用部への防犯カメラ設置は、家賃に反映しやすい改善策です。小さな投資で大きな効果が期待できるため、優先度は高いと言えます。
結論として、築古アパート 運用で長期的な収益を確保するには、購入後も継続的に物件価値を高める姿勢が欠かせません。市場ニーズを捉えた施策を機敏に打ち出し、資金計画と税務戦略をアップデートし続けることが、安定した資産形成につながります。
まとめ
築古アパートは価格が低い分、利回りが高く見えますが、空室や修繕のリスクも大きい投資対象です。本記事で紹介したように、厳しめの収支シミュレーションを徹底し、補助金や税制優遇を活用したリフォームで価値を向上させれば、堅実なキャッシュフローを生み出せます。物件取得から運用までの各段階でデータと制度を確認し、専門家の助言も取り入れながら計画を実行することが、成功への近道です。まずは気になる物件の収支表を作成し、現実的に耐えうるかを検証する一歩から始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅局「住宅統計調査」2025年8月速報値 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁「令和7年度(2025年度)法人税法等の一部改正について」 – https://www.nta.go.jp
- 環境省「2025年度 住宅省エネ改修補助金制度の概要」 – https://www.env.go.jp
- 国土交通省「賃貸住宅耐震改修促進税制の手引き(2025年版)」 – https://www.mlit.go.jp/toshi
- 日本政策金融公庫「不動産投資向け融資ガイドライン2025」 – https://www.jfc.go.jp

