投資用のマンションやアパートに興味はあるものの、空室リスクやローン返済が不安で一歩踏み出せない――そんな悩みを抱える方は多いはずです。特に「不動産投資 デメリット 違い」を正しく理解しないまま参入すると、想定外の出費や時間的負担に振り回されるおそれがあります。本記事では、2025年9月時点で有効な制度や最新データをもとに、不動産投資の弱点と他の金融商品との相違点を分かりやすく解説します。最後まで読めば、自分に合った投資スタイルを見極める材料が得られ、リスクを抑えた一歩を踏み出せるでしょう。
不動産投資で避けて通れない固有リスクとは
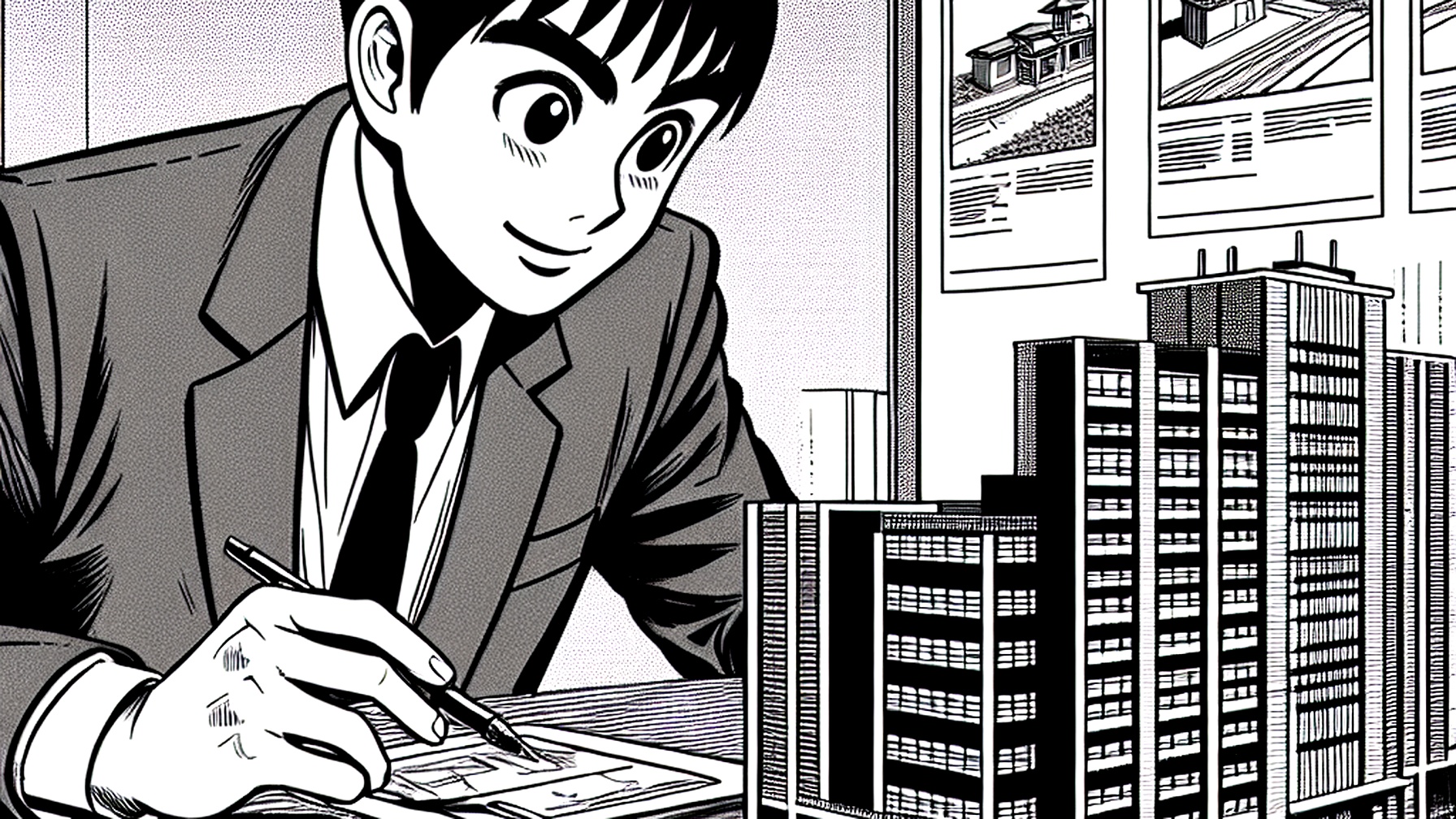
まず押さえておきたいのは、不動産投資が現物資産ゆえに抱える特有のリスクです。金融商品と比較する前に、根本的な弱点を理解しておく必要があります。
国土交通省の「住宅市場動向調査 2024」によると、全国の賃貸住宅空室率は平均12.1%です。空室が続けば家賃収入が途絶え、ローン返済が自己資金に依存します。また建物は経年劣化を避けられず、10年以内に給湯器、15年を過ぎると外壁や屋上の大規模修繕が必要になるケースが多いです。修繕積立を怠れば、突発的に百万円単位の出費が生じる点が悩ましいところです。
さらに流動性の低さも無視できません。株式ならクリック一つで売却できますが、物件処分には買い手探しと引き渡し手続きで最低でも3か月、長ければ1年以上かかります。その間に市場価格が下落する可能性があるため、時間的リスクを抱えやすいのです。
最後に金利変動です。日本銀行が2024年にマイナス金利政策を解除し、2025年時点の変動金利は平均1.5%前後で推移しています。今後さらに上昇すれば、返済額が増える恐れがあります。つまり、不動産投資はレバレッジをかけられる反面、借入コスト上昇の影響を直接受ける点に注意が必要です。
株式・投資信託と比べたときに浮かび上がる違い
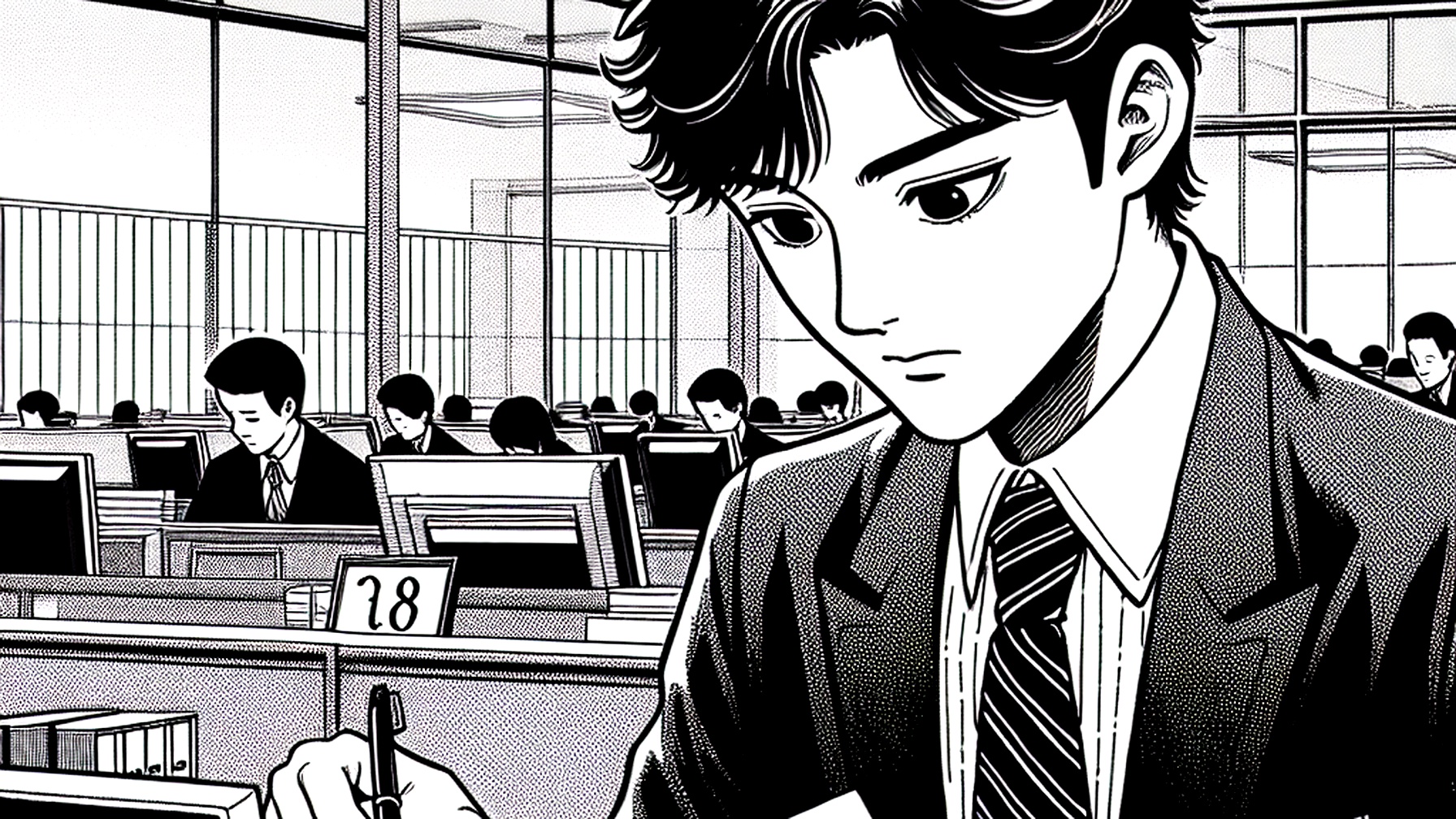
ポイントは、同じ「資産運用」でも運用主体の関与度と収益構造が大きく異なることです。ここでは代表的な金融商品と比較しながら、不動産投資ならではの特徴を整理します。
まず運用の手間です。上場株や投資信託は購入後の管理を運用会社に任せられますが、不動産は賃貸管理、設備修理、入居者対応など決断の連続です。管理会社に委託すれば手間は減りますが、月額家賃の3%前後の手数料が発生します。
次に収益源の性質です。株式は配当と値上がり益の二本柱ですが、市況の影響を受けやすく価格変動が大きいです。不動産の家賃収入は相対的に安定しますが、空室や賃料下落のリスクが常に伴います。値上がり益についても、立地や開発計画など外部要因が複雑に絡むため、読み違えると売却損につながります。
レバレッジの度合いも異なります。証券口座での信用取引は3倍程度が上限ですが、不動産ローンは自己資金の2割前後で物件を取得できる場合が多く、実質5倍以上のレバレッジがかかります。ただし高いレバレッジは返済不能リスクを増幅させる点を忘れてはいけません。
最後に税制面の違いです。株式配当や売却益は一律20.315%の分離課税ですが、不動産所得は総合課税です。給与所得と合算されるため所得税率が上がる場合もあれば、減価償却で赤字計上し節税効果が得られるケースもあります。このように、税負担が柔軟な一方で複雑さも伴う点が大きな違いです。
2025年度の税制優遇と負担のバランス
重要なのは、2025年度の制度を活用しつつ、同時に発生する固定費を見落とさないことです。ここでは代表的な税金と補助制度を整理します。
まず減価償却です。木造住宅は法定耐用年数22年、鉄筋コンクリート造は47年で、取得価格を年数で割り費用計上できます。築古木造を購入すれば償却スピードが速く、所得税の節税につながる場合があります。ただし節税効果が切れた後のキャッシュフロー悪化を見越したプランが不可欠です。
次に固定資産税と都市計画税です。総務省の「固定資産税課税台帳統計 2024」によると、全国平均の戸建住宅評価額は約1,460万円で、年額税負担は約15万円です。小規模住宅用地の特例で200平方メートル以下の住宅地は課税標準が6分の1に軽減されますが、賃貸アパート用地は戸数によって判定されるため、想定より負担が増える例があります。
2025年度も「住宅ローン控除」は自己居住用のみで、不動産投資には適用されません。一方、長期譲渡所得の軽減税率(所有期間5年超で約20%)は投資物件でも利用可能ですが、短期売却では約39%の税率が適用されます。つまり短期転売を狙う場合は、手残りが大幅に減る点を必ず考慮しましょう。
最後に補助金について触れますと、賃貸住宅に対する国の直接的な補助制度は2025年度時点で限定的です。省エネ性能を高めるリフォームには「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」が利用できますが、申請主体はオーナー自身で、補助率は工事費の3分の1以内、上限120万円です。期限や要件が変更される可能性があるため、申請前に最新情報を確認してください。
物件タイプごとに異なるデメリットの現れ方
実は、同じ不動産投資でも物件タイプによって弱点の色合いが変わります。ここでは代表的なタイプ別に注意点を整理します。
ワンルームマンションは流動性が高く入居付けしやすい反面、家賃水準が低く、管理費や修繕積立金の割合が大きくなる傾向があります。築20年を超えると大規模修繕の費用負担が一気に増え、家賃下落とダブルパンチになることが多いです。
一棟アパートは土地付きで資産価値が残りやすく、家賃収入の柱が複数ある点が魅力です。しかし空室が続くと収支への影響が大きく、特に地方都市では人口減少に連動して稼働率が下がるリスクがあります。日本政策投資銀行の「地方人口動態レポート 2025」によれば、20〜39歳人口は2015年比で14%減少しており、若年単身需要が縮小している地域も少なくありません。
商業ビル・テナント物件は賃料単価が高い一方、景気の影響を強く受けます。2023〜2024年にかけてオフィスビル空室率が東京で6%台まで上昇した例から分かるように、契約解除が集中するとキャッシュフローが急減する点に要注意です。
新築と中古の違いにも触れておきます。新築は設備トラブルが少なく入居募集もしやすいですが、購入価格にプレミアムが上乗せされているため利回りは低めです。中古は表面利回りが高く見えますが、修繕履歴が曖昧な場合は追加費用のリスクが潜在します。これらの特徴を把握し、自身の資金力とリスク許容度に合わせた選択が不可欠です。
デメリットを抑えるための実践的チェックポイント
基本的に、リスクを完全に排除することはできませんが、事前の調査と計画で影響を最小化できます。ここでは実践的な視点を紹介します。
まず現地調査です。昼と夜、平日と休日で周辺環境を観察し、交通騒音や治安、店の営業時間を確認します。国勢調査の人口推移を見て、将来的な賃貸需要が減少傾向にないかを把握しましょう。
次に資金計画です。ローン返済比率は家賃収入の50%以内に抑えると、空室や金利上昇が起きても耐えやすくなります。また修繕積立として年間家賃収入の10%を別口座にプールしておくと、急な故障にも対応しやすいです。
管理会社の選定も大切です。手数料率だけでなく、入居者募集力、クレーム対応の迅速さ、修繕の見積もり透明性を比較してください。可能であれば、担当者と面談し、退去立ち会いの様子など具体的な業務フローを確認すると安心です。
最後に出口戦略です。購入時点で「10年後の市場価格が何%下落しても売却益が残るか」をシミュレーションし、保有期間中も定期的に価格動向をチェックします。東京都23区の中古マンション価格指数は2021年比で2025年上期に約12%上昇していますが、地方では横ばいないし微減が続いています。地域差を踏まえた上で、売却タイミングを見極めることが欠かせません。
まとめ
以上、不動産投資の主なデメリットと他資産との違いを見てきました。空室・修繕・流動性・金利という四つの固有リスクを理解し、株式などと比較して運用の手間や税制のクセを把握することが重要です。自分の資金力やライフプランに照らし、物件タイプやエリアを慎重に選べば、弱点を受け止めつつ安定した収益を目指せます。まずは本記事のチェックポイントを使い、購入候補を数字で検証するところから始めてみましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査 2024年版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 固定資産税課税台帳統計 2024 – https://www.soumu.go.jp
- 日本銀行 金融経済統計月報 2025年7月号 – https://www.boj.or.jp
- 日本政策投資銀行 地方人口動態レポート 2025 – https://www.dbj.jp
- 不動産経済研究所 首都圏中古マンション価格指数 2025年上期 – https://www.fudousankeizai.co.jp

