鉄筋コンクリート造(RC造)の賃貸物件に興味はあるものの、「木造より高いのでは」「本当に利回りが出るのか」と迷っていませんか。実は、耐久性と資産価値の両面でRC造は長期的なメリットが大きく、適切に運営すればキャッシュフローの安定度も高まります。本記事では、初心者でも理解できるようRC造の特徴、融資や税制の最新情報、物件選びまで網羅し、2025年9月時点で有効な制度に基づいて解説します。読了後には、RC造に投資する具体的な判断軸と行動プランが見えるはずです。
RC造とは何か、そして投資家にとっての魅力
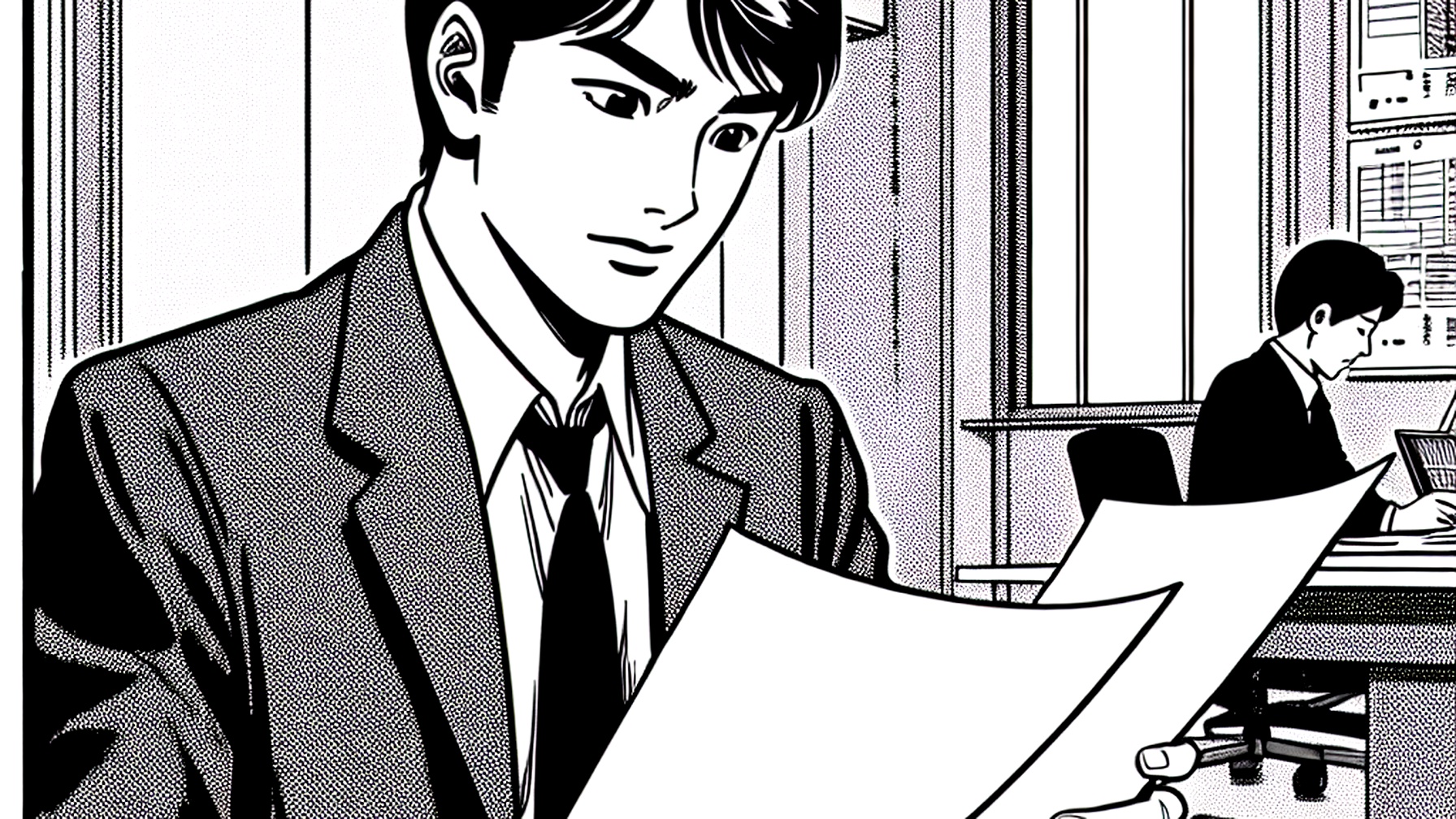
まず押さえておきたいのは、RC造が鉄筋(Reinforced)とコンクリート(Concrete)を組み合わせた構造で、耐震性と耐火性に優れる点です。建築基準法上の耐用年数は47年と木造の22年を大きく上回り、減価償却期間が長い分だけ帳簿上の資産価値が残りやすい特徴があります。
国土交通省「建築着工統計」によると、2024年度のRC造マンションの平均工事費は延べ床1㎡あたり約23万円で、木造の約16万円より高いものの、入居需要が強い都市部では平均家賃が25〜30%高い傾向にあります。つまり、初期投資を回収するスピードは立地次第で十分確保できます。さらに、外壁が厚く遮音性が高いため、住環境を重視する入居者に選ばれやすく、長期入居を期待できる点も魅力です。
一方で、建設コストが高いからこそ、銀行は耐用年数の長さを評価して長期融資に応じやすくなります。みずほ銀行の最新資料でも、RC造の最長融資期間は35年が一般的で、同条件の木造より5〜10年長いケースが多いと公表されています。長い融資期間は月々の返済額を抑え、キャッシュフロー改善に寄与します。加えて、2025年度も継続予定の「住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進制度」に基づく支援対象になりやすく、補助金や税制優遇を受ける余地がある点も見逃せません。
キャッシュフローを高めるRC造の収益構造
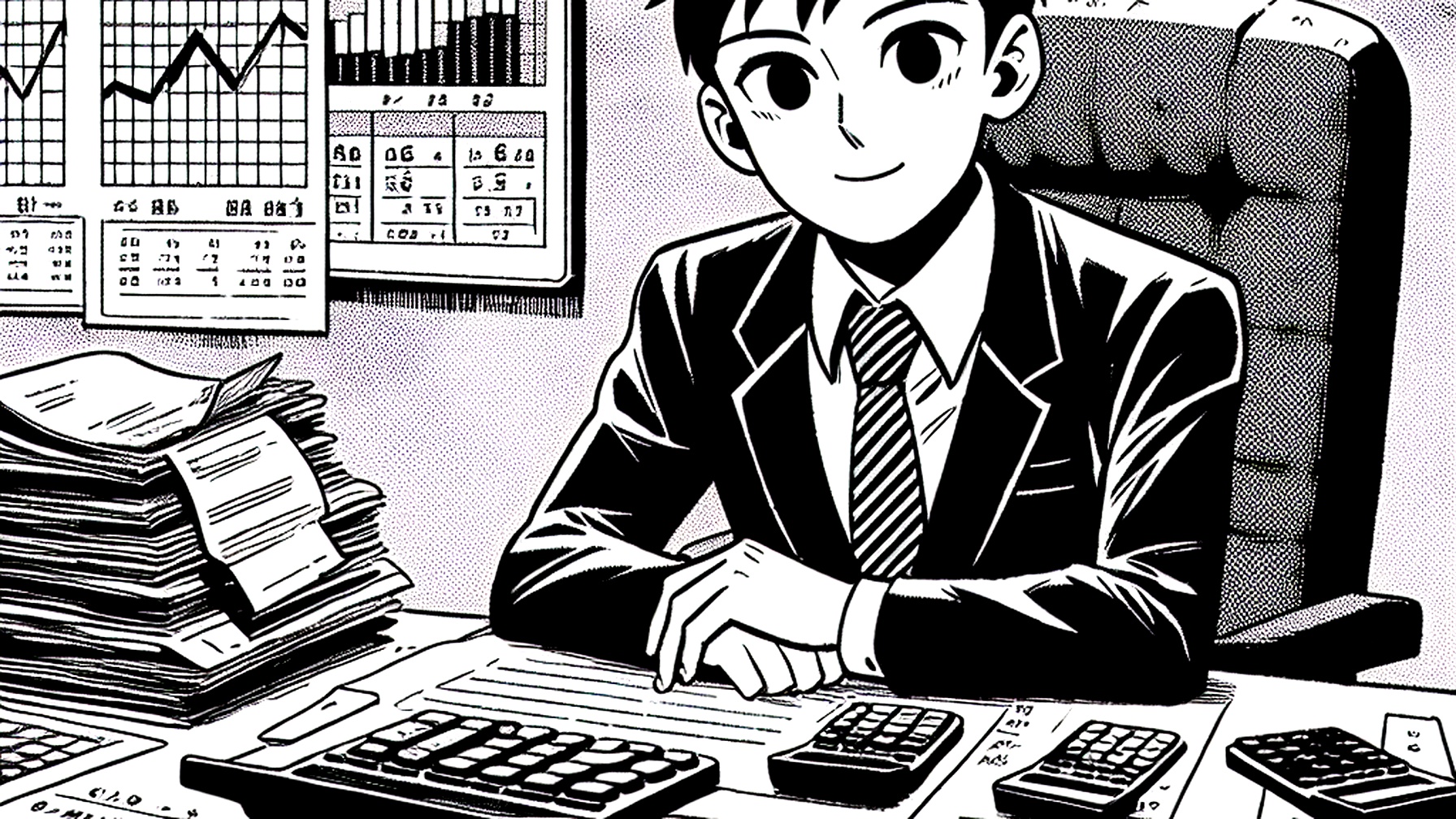
重要なのは、RC造だからといって家賃収入だけでなく費用構造まで把握することです。収入面では高めの家賃設定が可能ですが、固定資産税や修繕積立金は木造よりも大きくなりがちです。例えば、総務省「市町村税課税状況等の調」では、RC造マンションの固定資産税評価額は木造の約1.4倍となっています。それでも、税額は建物評価額が経年で減るにつれて下がるため、築20年を超える頃から実効利回りは改善に転じやすい点が特徴です。
支出を抑えるうえで鍵になるのが長期修繕計画です。国交省が示す指針では、外壁塗装や屋上防水を12〜15年周期で実施するのが望ましいとされています。計画的に積み立てることで、一度の大規模修繕に慌てず対応でき、突発的な資金流出を防げます。修繕積立金を家賃収入の8〜10%に設定する投資家が多いものの、RC造は躯体が強固なぶん設備更新に比重が移る傾向にあります。実際、筆者が運営する都内20戸のRC造マンションでは、年間家賃収入の約6%を積み立てても、10年ごとの大規模修繕に十分対応できています。
融資面では、融資期間が長く設定できるため元利均等返済でも毎月の返済負担率を50%以下に抑えやすくなります。さらに、2025年度の「地域連携型空家活用支援事業」に該当する場合、耐震補強と省エネ改修を同時に行えば補助率が1/3に上がり、自己資金の圧縮が可能です。こうした制度をうまく組み合わせることで、収益性を高めながらリスクを抑えることができます。
RC造物件に特有のリスクとメンテナンスの勘所
ポイントは、RC造が頑丈であってもメンテナンスコストがゼロになるわけではないことです。最大のリスクはコンクリートの中性化による鉄筋腐食で、放置すると耐震性が低下します。日本建築学会の報告によると、海沿いエリアでは中性化速度が内陸部の1.3倍とされ、防水処理の質が資産価値を左右します。
内覧時は、外壁にヘアクラック(細いひび割れ)がないか、屋上の排水溝が詰まっていないかを確認することが肝心です。ヘアクラックは幅0.2mm以下なら構造的問題がない場合も多いのですが、雨水が浸入すると腐食が進みやすくなります。また、コンクリートの打設精度によって躯体強度に差が出るため、建築確認申請図と実際の配筋写真を照合し、施工品質をチェックすることが欠かせません。
さらに、RC造は遮音性が高い半面、気密性が高く結露しやすいという弱点もあります。壁内結露はカビ発生の原因となり入居者満足度を下げるため、24時間換気システムや断熱改修の有無を確認しましょう。省エネ性能の高い設備は、2025年度の「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」の補助対象になっており、1戸あたり最大60万円の補助を受けられます。これにより、リスク対策と収益性向上を同時に実現できます。
融資条件と2025年度税制優遇を活かす実践ポイント
実は、RC造の長期安定収益を支えるのは融資条件の最適化です。日本政策金融公庫の2025年度基準では、RC造賃貸物件への融資上限が3億円、期間40年、金利1.2%からと公表されています。都市銀行より金利は高めですが、自己資金1割でも審査が通りやすい点がメリットです。対して、メガバンクは金利0.9%前後でも自己資金2割を求めるケースが多く、事業計画の堅実さが勝負になります。
固定資産税に関しては、新築RC造マンションが「認定長期優良住宅」の条件を満たすと、2025年度も引き続き5年間の税額1/2減額が適用されます。適用条件として劣化対策や可変性などの基準を満たす必要があり、設計段階から確認すると建築コストを抑えながら制度活用が可能です。また、不動産取得税についても同じく長期優良住宅ならば課税標準から1,300万円が控除され、投資初期の資金負担を軽減できます。
ローン控除は居住用が対象ですが、投資用でも区分所有の場合に限り「一定の省エネ性能を満たす賃貸住宅建設促進税制(2025年度)」の特別償却20%を適用できる可能性があります。税理士と連携し、青色申告特別控除や減価償却の加速度償却を組み合わせることで、税引き後キャッシュフローをさらに改善できるでしょう。
物件選定とエリア戦略で失敗を避ける
まず押さえておきたいのは、RC造の強みを最大化するにはエリア需要の見極めが不可欠だという点です。人口減少が本格化する中でも、総務省「住民基本台帳人口移動報告」では、2024年に転入超過が続いたのは東京23区、大阪市、福岡市、名古屋市などに集中しています。これらエリアはワンルーム規制が厳しく供給が制限される傾向にあり、RC造ファミリータイプの需要が底堅いといえます。
物件選定では、最寄り駅から徒歩10分圏内、築15年以内、総戸数20戸以上を目安にすれば、修繕費の平準化が図りやすくなります。築浅RC造は利回りが低めでも、家賃下落が緩やかで長期運営の安定感があります。一方、築30年超のRC造は取得価格が下がるため表面利回りが高くなりますが、耐震診断と大規模修繕履歴を十分に確認しなければ想定以上の追加投資を迫られるリスクがあります。
つまり、自己資金やリスク許容度に応じて「築浅で安全運転」か「築古で高利回り狙い」かを選ぶ戦略が有効です。なお、将来的な出口戦略として区分売却やリノベ再販を視野に入れるなら、駅前再開発や大学移転計画など自治体の都市計画マスタープランを事前に調べておくことが重要です。行政の長期ビジョンに沿ったエリアは、資産価値が下支えされやすく、売却益も期待できます。
まとめ
最後に、RC造への不動産投資で押さえるべき要点を振り返ります。耐用年数の長さと高い家賃水準により、長期的なキャッシュフローは安定しやすいものの、建設コストと修繕費を的確にコントロールする姿勢が欠かせません。融資期間を最大化し、2025年度の税制優遇や補助金を活用すれば、自己資金を抑えつつ収益性を高められます。また、エリア選定と物件の状態確認を丁寧に行い、長期修繕計画を先手で立てることで、リスクを許容範囲に収められます。行動を起こす際は、信頼できる専門家とも連携し、自分の投資目的に合ったRC造物件を選び、将来の安定収益を実現してください。
参考文献・出典
- 国土交通省 建築着工統計調査報告(https://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/chojou/statistics.html)
- 総務省 市町村税課税状況等の調(https://www.soumu.go.jp/iken/kazei.html)
- 日本政策金融公庫 融資のご案内2025(https://www.jfc.go.jp/)
- みずほ銀行 不動産投資ローン商品概要(https://www.mizuhobank.co.jp/)
- 日本建築学会 コンクリートの中性化に関する調査報告(https://www.aij.or.jp/)
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei-02-m.htm)

