地方でも都心でも、アパート経営に興味を持つ人がここ数年で一気に増えました。しかし実際に物件を買う段階になると「空室が出たらどうしよう」「本当に利益が残るのか」と不安は尽きません。この記事では、筆者自身と顧客の事例を交えながら、最新データに基づくアパート経営 レビューを行います。仕組みからリスク管理、2025年度の制度まで網羅するので、読み終えた頃には自分に合った一歩を具体的に描けるはずです。
なぜ今アパート経営が注目されるのか
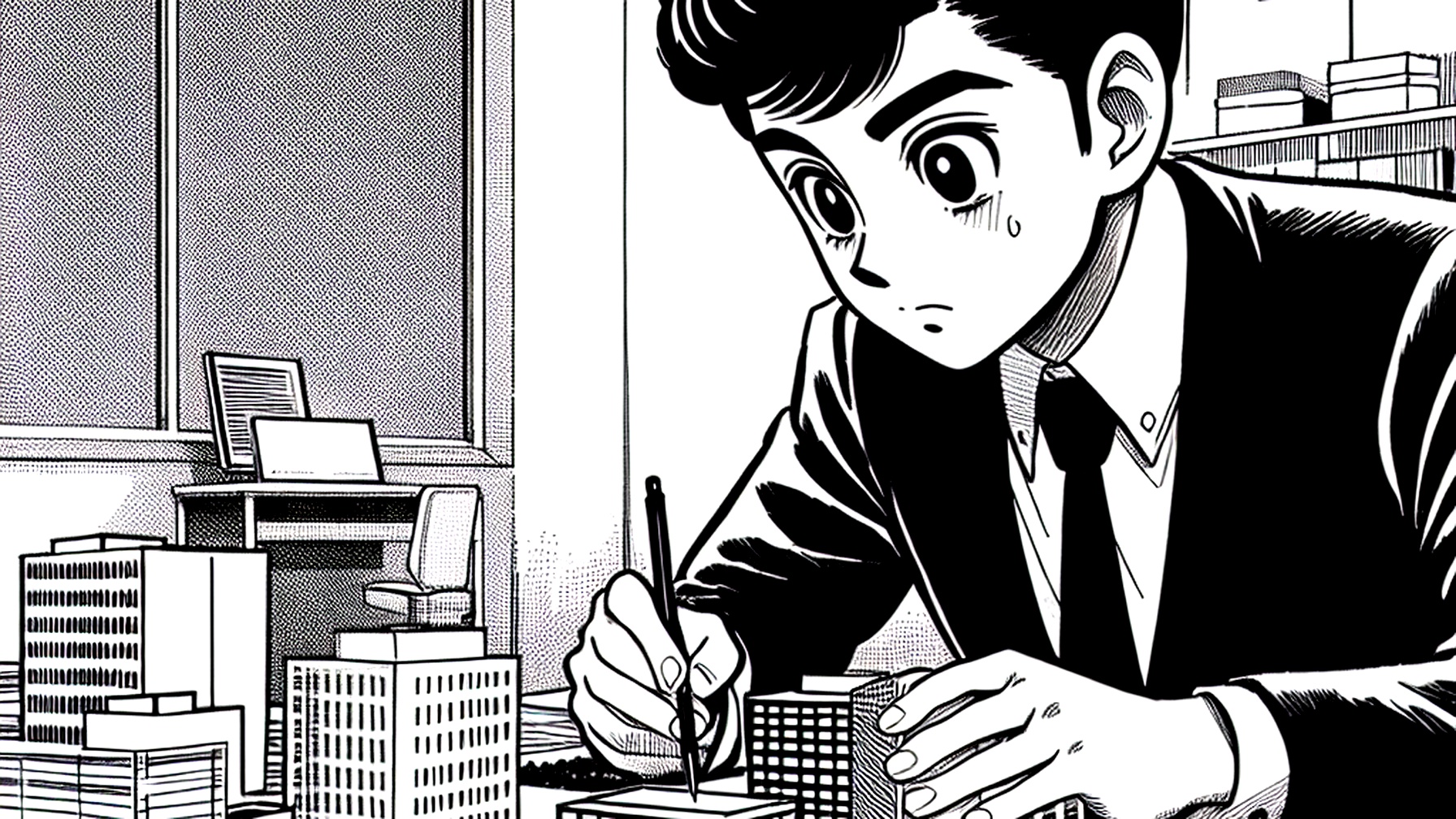
まず押さえておきたいのは、市場環境が「総じて厳しいが読める」段階に入ったことです。国土交通省の住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント下がりました。微減ながら改善が続く背景には、人口が集中するエリアへの供給調整と、リモートワーク定着による住み替え需要があります。
一方で、金利環境も追い風になっています。日本銀行の長期金利誘導目標は依然として1%以下に抑えられ、主要地銀のアパートローン金利は変動で年1.3〜1.8%が中心です。低金利はキャッシュフローを押し上げるため、運営に余裕が生まれやすいのです。
政府の政策も見逃せません。2025年度税制では、住宅取得促進策よりも「既存ストック活用」へ軸足が移りました。結果として、中古アパートの省エネ改修に対する投資促進税制が継続され、工事費の10%を翌期に特別償却できる措置が残っています。こうした支援は利益率に直結するため、今こそ戦略的に参入する価値があります。
キャッシュフローの読み方と実例
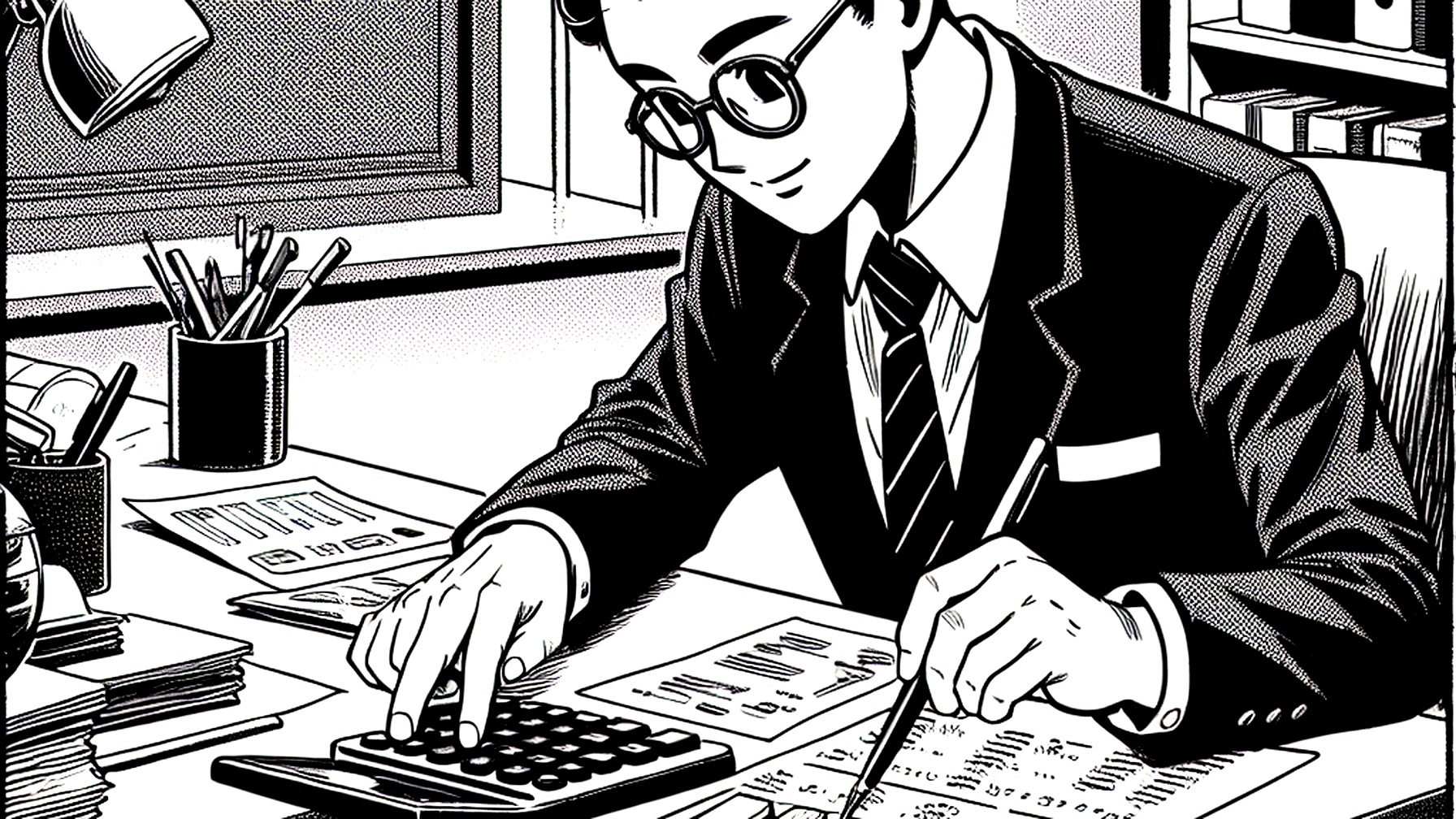
ポイントは、単なる収入と支出の差ではなく「手元に残る現金」を定期的に把握することです。家賃収入から管理費、修繕費、ローン返済、税金を差し引き、さらに将来の大規模修繕に備えた積立を行った後の数字が本当のキャッシュフローになります。
実例として、東京都郊外にある築10年木造アパート(満室時家賃月70万円、総戸数8戸)を見てみましょう。管理費と共用電気代で月7万円、平均空室率5%を考慮すると実質家賃は66.5万円です。ここからローン返済が月40万円、固定資産税などが月換算で2万円、修繕積立を月3万円行うと、手残りは約21.5万円となります。この物件ではローン完済までの年間手残りが約258万円、利回りに直すとおよそ7.2%です。
しかし、空室率が国平均の21.2%に悪化した場合を想定すると、家賃収入は55万円弱まで落ち込みます。積立と税金を据え置けば手残りは月10万円台に半減します。このように、楽観シナリオと悲観シナリオの両方で計算し、自己資金と生活費に対する安全余裕率をチェックすることが不可欠です。
物件選びで押さえるべき三つの視点
重要なのは、立地・建物・収支の三拍子をバランスさせることです。立地では最寄り駅からの距離と生活利便性を軸に、ターゲット層が明確に存在するかを確認します。単身者向けなら都心部への通勤時間、ファミリー向けなら学区や公園などが決定打になります。
建物の構造と築年数も侮れません。木造は減価償却期間が22年と短く、築古でも税務上のメリットを取りやすい反面、修繕周期は早くなりがちです。一方、RC造(鉄筋コンクリート)は耐久性が高く、長期的な入居安定を期待できますが、取得価格は上がります。
収支面では「表面利回りだけでなく実質利回り」を見る癖を付けましょう。例えば都心の築浅物件は表面利回り5%台でも、空室率が低く修繕費も当面少ないため、実質利回りは7%に近づくことがあります。逆に郊外で表面利回り9%でも、入居付けの広告費が年家賃の2か月分かかると、手残りは急減します。数値と現場感覚を往復させながら判断することが成功への近道です。
リスク管理と空室対策のリアル
実は、リスクの八割は購入時点で決まります。それでも運営中の工夫で損失を抑える余地は大きいです。空室対策では、賃料を下げる前に「付加価値」を高める戦略が定番です。例えばネット無料設備の導入は、戸当たり月額千円程度のコストで成約率を高められます。
管理会社との連携も結果を左右します。定期清掃や草刈りの頻度を上げるだけで、内見者の第一印象は大きく変わります。また、入居者アプリを通じてトラブル受付を24時間化するとクレーム減少と口コミ評価向上につながり、退去率の低下に直結します。
資金面のリスクには長期修繕と金利上昇があります。2025年時点で金利は低水準ですが、借入期間が20年を超える場合は3%までの上昇シナリオを織り込んでおくと安心です。大規模修繕は10〜12年ごとに外壁塗装や屋上防水へ500〜700万円かかることが多いため、毎月2万円以上の修繕積立を「経費」として習慣化しましょう。
2025年度の税制と補助制度のポイント
まず知っておきたいのは、賃貸用住宅の固定資産税減額措置です。2025年度も新築貸家は建物部分の固定資産税が3年間1/2に軽減されます(3階建て以上は5年間)。これにより、建築直後のキャッシュフローが安定し、返済余力を持たせやすくなります。
省エネ改修促進税制も継続され、一定の断熱改修や高効率給湯器の導入費の10%を初年度に特別償却できます。古いアパートを購入して価値を高めるリノベーション型投資では積極的に検討したい制度です。
さらに、不動産所得と給与所得の損益通算は2025年度も適用範囲に大きな変更はありません。年間20万円を超える赤字は他の所得と通算できるため、初期の空室期間や修繕費が嵩む年度の税負担を抑えられます。ただし、税制は毎年見直されるため、確定申告前に国税庁の最新情報を確認する姿勢が大切です。
まとめ
ここまで「アパート経営 レビュー」として、市場環境、キャッシュフロー分析、物件選び、リスク管理、そして2025年度の制度まで順に解説しました。重要なのは、楽観と悲観の両面で数字を点検し、立地・建物・収支のバランスを取りつつ、制度を味方に付けることです。まずは自己資金と生活費を照らし合わせ、3年後の手元資金がマイナスにならないシミュレーションを作成してみてください。そのプロセス自体が成功への第一歩となり、安定した家賃収入があなたの将来を支える強固な柱となるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年7月速報値 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 2025年6月 – https://www.boj.or.jp
- 総務省 固定資産税に関するFAQ 2025年度版 – https://www.soumu.go.jp
- 財務省 令和7年度(2025年度)税制改正のポイント – https://www.mof.go.jp
- 国税庁 不動産所得の取扱いQ&A 令和7年版 – https://www.nta.go.jp

