多くのオーナーが最初にぶつかる壁は「家賃をいくらにすればいいのか」という悩みです。高く設定しすぎれば空室が長期化し、安くしすぎれば収益が伸びません。さらに、2025年7月時点で全国のアパート空室率は21.2%と依然高水準で、入居者は物件と家賃を厳しく比較しています。本記事では、家賃設定で陥りやすい落とし穴を整理し、収益を最大化しながら空室リスクを抑える方法を解説します。読み終えるころには、数字と根拠をもとに自信を持って家賃を決める手順が理解できるでしょう。
家賃設定が収益に与えるインパクトを正しく捉える
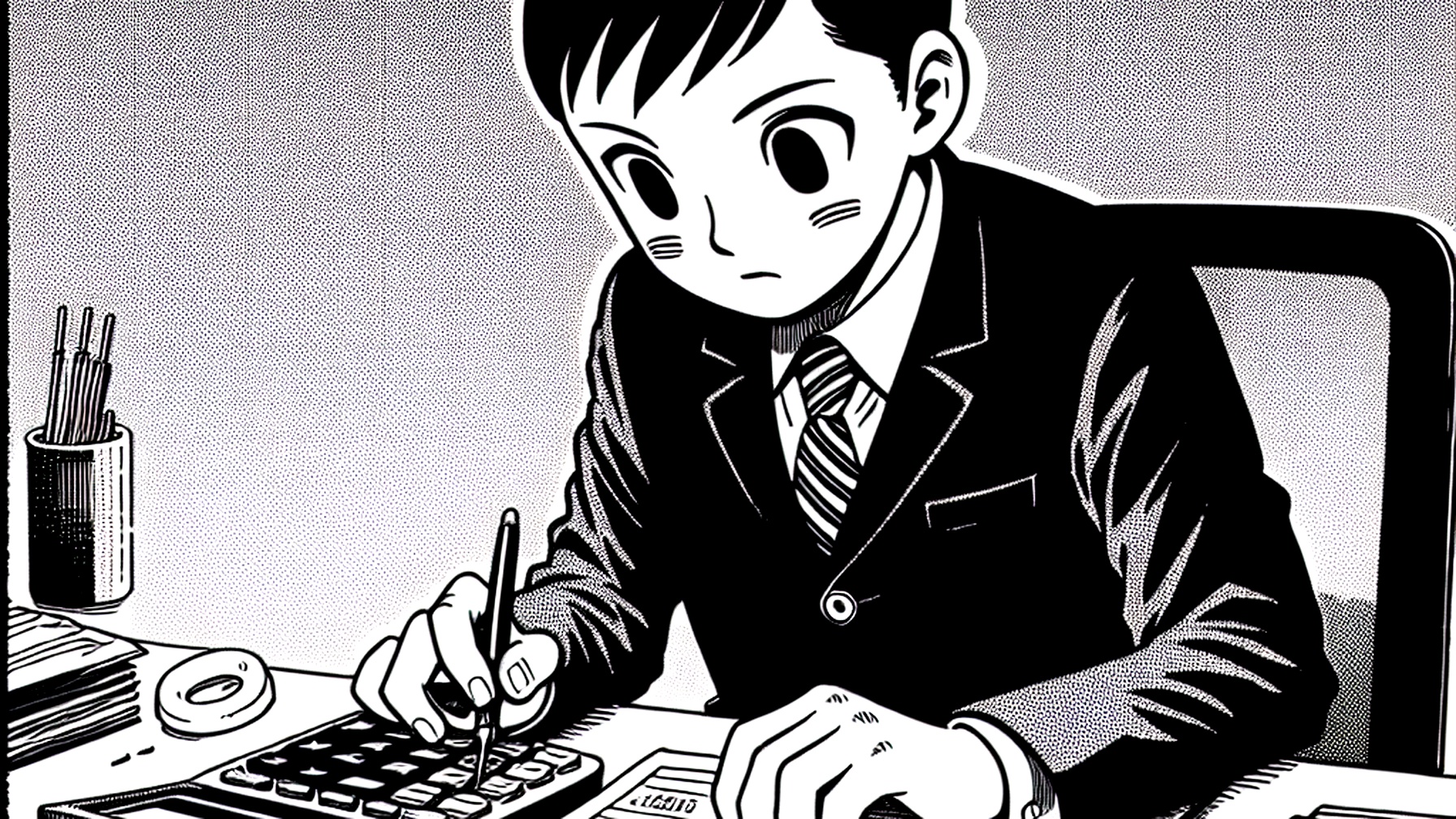
まず押さえておきたいのは、家賃設定のわずかな差が長期的なキャッシュフローを大きく左右する点です。例えば月額家賃を1万円下げると、年間で12万円、10年なら120万円の減収となります。表面利回りで換算すれば、購入時利回りが想定より1%以上下がる場合も珍しくありません。
しかし、家賃を維持した結果として空室期間が延びると、さらに大きな損失が生じます。国土交通省の『令和6年度(2024年度)賃貸住宅市場の実態調査』によると、首都圏の平均空室期間は32日で、1か月の空室があるだけで年間利回りは約0.8ポイント低下します。つまり、収益を守るには「賃料」と「稼働率」を同時に最適化する視点が欠かせません。
家賃を決める際には、長期シミュレーションを作成し、空室率5%刻みで複数のシナリオを確認することが重要です。そのうえで、金利上昇や修繕費といった将来コストも盛り込み、最も保守的な見通しでも黒字を確保できるか検証しましょう。これらの作業を丁寧に行うことで、家賃設定の段階から“持続可能なアパート経営”を実現できます。
市場調査の基本とよくある落とし穴
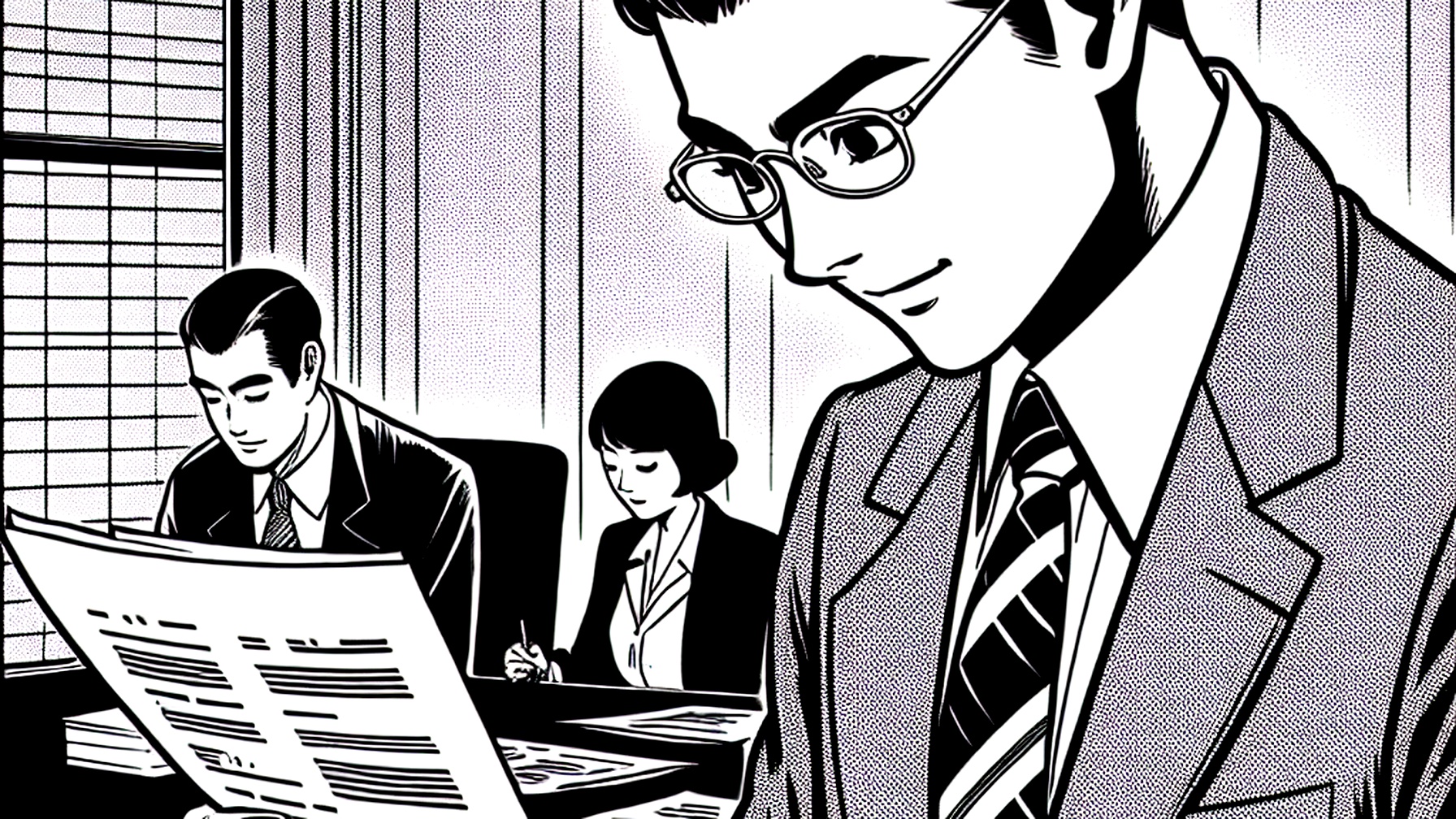
ポイントは「平均値」ではなく「競合物件」の具体的な条件を比較することです。SUUMOやアットホームなどのポータルサイトでは、同じエリア・築年数・設備条件の物件を20件程度ピックアップし、募集家賃と掲載期間を追跡すると傾向が見えてきます。また、地元の管理会社に連絡し、直近3か月で成約した物件の実勢賃料を確認すると、表に出ない値引き幅まで把握できます。
一方で、調査段階で築年数の違いを軽視すると誤差が生じます。築10年と築15年では、東京都内の木造アパートで平均賃料が約8%開くというデータがあります。設備でも、インターネット無料や宅配ボックスの有無が月額2000円前後の差を生むケースが多く、単純な平米単価比較は危険です。
さらに、繁忙期と閑散期で市場が大きく動く点も見落とされがちです。2025年春の転勤・入学シーズンには募集開始から成約までの期間が平均18日短縮されたという自治体レポートも出ています。このような季節変動を考慮せずに家賃を決めると、4月以降に空室が長引く可能性が高まります。調査は必ず複数時点で行い、年間を通じた動きを把握しておきましょう。
適正家賃を導く三つの指標
重要なのは「表面利回り」「実質利回り」「近隣成約賃料」の三つをバランスよく見ることです。表面利回りは購入判断の指標として便利ですが、管理費や修繕積立金を差し引いた実質利回りで再計算すると、手残りが2ポイント前後下がるのが一般的です。この実質利回りが金融機関の返済比率を下回らないか確認しましょう。
次に、近隣成約賃料は現場の需給を反映する“生きた数字”です。日本賃貸住宅管理協会の『賃料動向データ(2025年上期)』によれば、成約賃料は募集賃料より平均3.4%低いという結果が出ています。つまり、想定家賃は近隣の募集賃料から3〜4%低いラインを出発点に設定し、物件固有の強みで上乗せできるか検討する方法が合理的です。
最後に忘れてはならないのが、借主の家計バランスです。総務省「家計調査」では、世帯収入に対する住居費比率が平均24.3%と報告されています。ファミリータイプであれば25%、単身向けであれば30%を超えると入居審査で弾かれる確率が上がるため、入居ターゲットの年収帯も踏まえて家賃を調整しましょう。こうした複合的なチェックを経て導かれた数字こそが“適正家賃”になります。
値上げ・値下げのタイミングと実務手続き
実は、家賃は一度決めたら終わりではなく、運用中の見直しが必須です。空室が続く場合の値下げは「空室期間が3か月を超えたら5%下げる」など、事前にルール化しておくと心理的な迷いが減ります。一方で、値上げの好機は設備投資後とインフレ局面です。省エネ性能の高いエアコンや宅配ボックスを導入した直後に、2,000〜3,000円の上乗せが通った例も増えています。
値上げ交渉には、更新契約の2か月前までに書面通知する必要があります。借地借家法では「相当額」であることが求められ、近隣相場や物件の改良内容を示す資料を添えるとスムーズです。なお、2025年度の住宅セーフティネット制度に登録すると、一定の要件で所得層に応じた家賃補助が適用され、オーナー側は家賃の安定受領が可能です。ただし、登録物件は上限賃料が定められるため、導入前に長期収支を再試算する必要があります。
値下げについても同様に、募集賃料を変更した日付と理由を台帳に残し、金融機関への報告資料に反映させましょう。家賃上下の履歴を透明化しておくと、将来の追加融資や売却時に説明しやすく、結果として物件の評価額維持にも寄与します。
ESG・税制改正と家賃設定の最新動向
まず、2025年度税制改正では、省エネ改修を行った賃貸住宅の固定資産税が最大3年間半額になる措置が継続されました。減税期間中に得られるキャッシュフロー余裕分を入居者サービスに再投入し、プレミアム家賃を設定する戦略が注目されています。東京都ではZEB(ゼロエネルギービル)相当の賃貸住宅が平均4.6%高い実績家賃を確保しており、ESG投資の潮流が地方都市にも波及し始めています。
一方で、2030年に向けた省エネ基準の義務化が示されており、今後は非適合物件が“家賃ディスカウント要因”となる可能性があります。金融機関はすでに、省エネ性能を担保できない築古アパートへの融資金利を0.2〜0.4ポイント上乗せしており、家賃設定だけでなく出口戦略にも影響を及ぼします。
このような制度や市場環境の変化に対応するには、毎年3月に公表される国交省『住宅・土地統計調査』を確認し、エリア別の家賃推移と空室率を把握する習慣が欠かせません。制度の恩恵を取り込むか、規制コストに備えるか。いずれにしても、家賃設定を“静的”ではなく“動的”に捉える姿勢が、中長期で資産価値を守る鍵となります。
まとめ
ここまで、家賃設定がアパート経営の成否を左右するポイントであることを見てきました。収益と稼働率のバランス、市場調査の精度、三つの指標による適正家賃の算定、そして適時の値上げ・値下げ戦略が重要です。さらに、2025年度の税制や省エネ政策を踏まえ、家賃を定期的に見直す姿勢が求められます。読者の皆さまには、本記事で紹介した手順とデータを活用し、自身の物件に最適な家賃を設定していただきたいと思います。行動に移すことで、長期的に安定したキャッシュフローと資産価値向上が期待できるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 – https://www.mlit.go.jp/statistics/details
- 日本賃貸住宅管理協会 賃料動向データ – https://www.jpm.jp
- 総務省統計局 家計調査 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅市場の実態調査 – https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/house
- 東京都環境局 ZEB普及レポート – https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp

