マンション投資に興味はあるものの、表面利回りの数字だけで判断して良いのか不安だ、という声をよく耳にします。確かに利回りは重要な指標ですが、見方を誤れば思わぬ失敗を招きかねません。本記事では、表面利回りの正しい計算方法から実質利回りとの違い、エリア選定の着眼点、融資や税制までを体系的に解説します。読み終えた頃には、「数字の裏にあるリスクとチャンス」を自分で見抜ける視点が身につくはずです。
表面利回りは“スタート地点”にすぎない
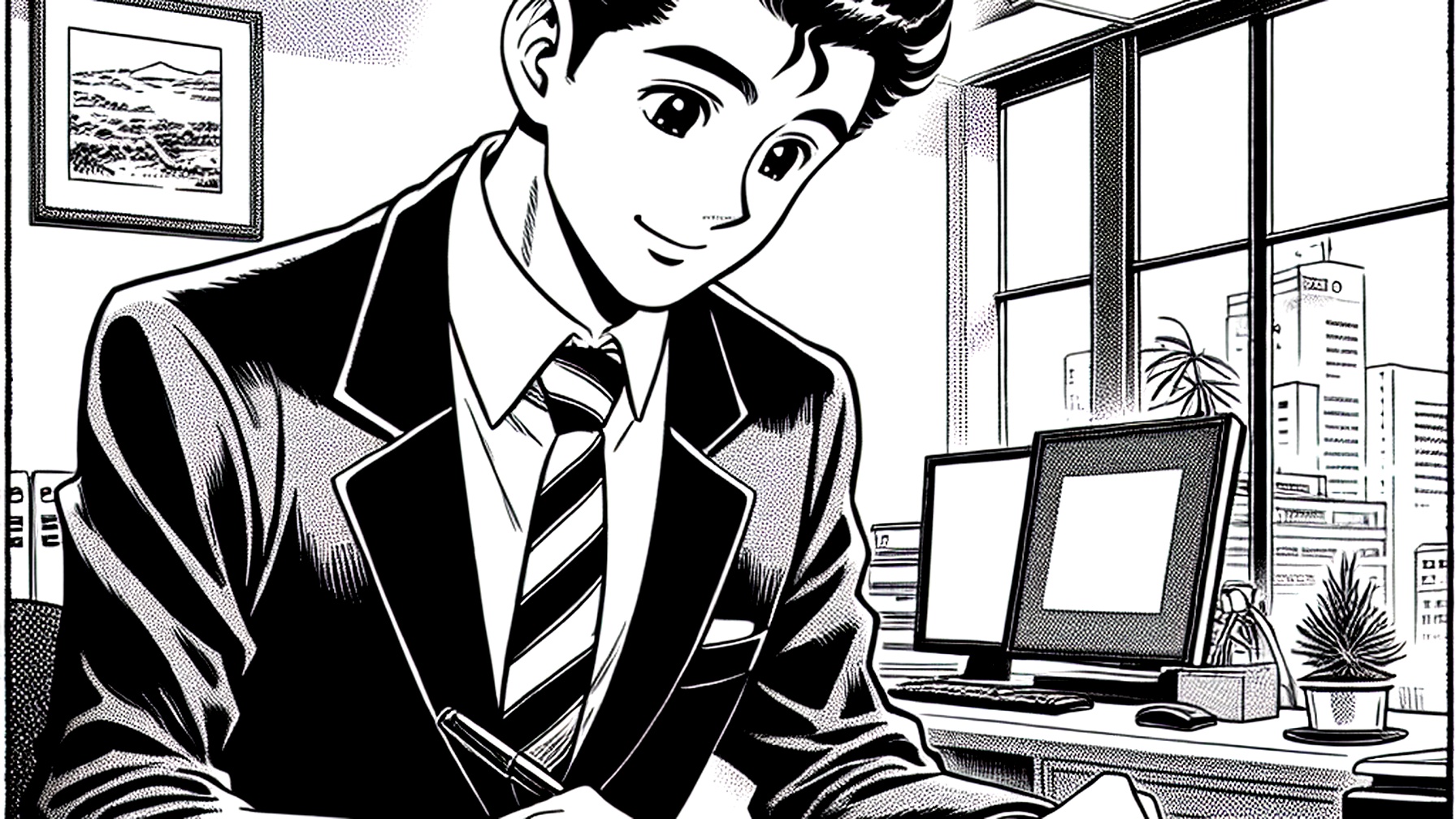
まず押さえておきたいのは、表面利回りが物件価格と年間家賃収入だけで算出される、あくまで概算値だという点です。たとえば購入価格3,000万円、年間家賃収入180万円のワンルームなら表面利回りは6%になります。しかし、この数字には管理費や固定資産税などのランニングコストが含まれていません。また、家賃は常に一定とは限らず、空室や賃料下落が起きると収入は簡単に目減りします。表面利回りを鵜呑みにすると、「実際に手元へ残るお金」と乖離するリスクが高まるのです。
次に、2025年9月時点の平均データを確認しておきましょう。日本不動産研究所によると、東京23区のワンルームマンション平均表面利回りは4.2%です。これは高利回りをうたう中古区分物件の広告より低く感じるかもしれませんが、実態に近い数字と言えます。つまり、市場平均を踏まえずに7〜8%の利回り表示だけを理由に飛びつくと、あとで大きなギャップに気づく可能性があります。表面利回りは比較の“入口”として使い、深掘りして初めて意味を持つ指標だと理解しましょう。
実質利回りを決める三つのコスト
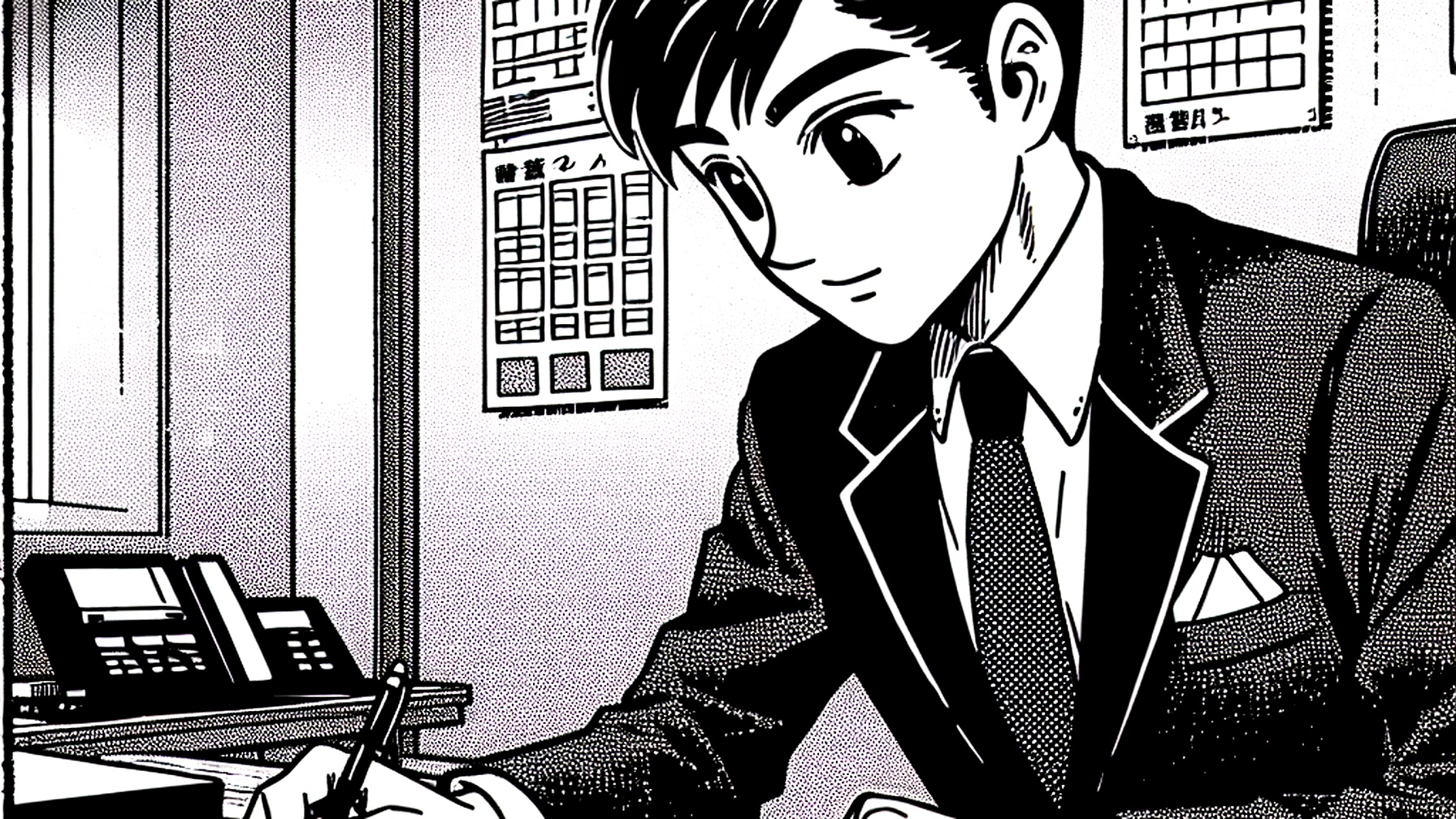
重要なのは、表面利回りから実質利回りへ落とし込む過程です。実質利回りは、年間家賃収入から年間支出を差し引き、購入総額で割ったものです。このとき注目すべきコストは管理費・修繕積立金、税金、空室損失の三つに集約されます。管理費と修繕積立金は新築時ほど安く、築年が進むごとに増える傾向にあります。国土交通省の2024年度マンション総合調査では、築30年超の修繕積立金は築10年未満の約1.6倍という結果が出ています。
税金面では固定資産税と都市計画税が代表的ですが、規模が大きい物件ほど課税額も上がるため、購入前に試算が欠かせません。さらに、空室損失は数値化しにくい隠れコストです。人口統計を見ると、東京23区の単身世帯は2025年も微増傾向にある一方、郊外市部では横ばいから減少へ転じ始めています。単身向けマンションを郊外で購入する場合、空室リスクを5〜10%でシミュレーションすると、実質利回りが1%近く下がることもあります。三つのコストを丁寧に見積もることで、購入後のキャッシュフローが現実に近づきます。
エリア選定で利回りと空室リスクを天秤にかける
実は、表面利回り以上に失敗と成功を分けるのがエリア選定です。都心部は物件価格が高いため表面利回りは低めですが、賃貸需要が底堅く、空室期間が短いというメリットがあります。反対に、郊外や地方都市では購入価格が抑えられる分、利回りは高く見えますが、人口減少や再開発動向の影響を受けやすい点に注意が必要です。
東京都都市整備局の予測では、山手線内側の人口は2035年まで微増が続く一方、多摩地域の一部では緩やかな減少に転じます。つまり、長期保有を前提とするなら、都心で4%台の利回りが「安定収益」という観点で最適解になるケースも多いのです。逆に短期的なキャピタルゲインを狙う場合は、再開発計画が進む駅周辺で、完成前に購入して完成後の値上がりを得る戦略が考えられます。利回りだけでなく、将来の賃貸需要と出口戦略をセットで描くことが、失敗しないための鍵となります。
融資条件と返済計画がキャッシュフローを左右する
ポイントは、同じ物件でも融資条件が異なれば実質利回りが大きく揺れる点です。2025年時点で主要都市銀行の投資用ローン金利は変動1.9〜3.2%が目安ですが、自己資金比率や属性によって上下します。金利が0.5%上がるだけで、3,000万円のローン(期間30年)の総返済額は約280万円増える試算になります。したがって、複数金融機関を比較し、物件価格の20〜30%を自己資金として用意することで、金利面の優遇を受けやすくなります。
また、返済比率の指標として、家賃収入に対する元利返済額が50%以内に収まるかを確認すると安全度が高まります。例えば年間家賃収入180万円に対し、元利返済額が100万円なら返済比率は約56%でやや高めです。管理費や空室を加味すると、キャッシュフローが赤字になる可能性があります。返済比率40%を目標に試算すると、金利上昇局面でも余裕を持って運用を続けられます。
2025年度の税制・減価償却を味方に付ける
まず押さえておきたいのは、2025年度も引き続き不動産所得に対する損益通算が認められている点です。減価償却費を適切に計上することで、家賃収入に生じた黒字を圧縮し、所得税・住民税の負担を軽減できます。特に木造アパートよりもRC造マンションの耐用年数は長く、減価償却費は年ごとに緩やかに減るため、長期的に安定した節税効果が見込めます。
一方、住宅ローン減税は居住用が対象で、投資用物件には原則適用されません。そのため、投資家が利用できる国策としては、地方自治体が設ける空き家再生補助金や、省エネ改修への助成金などが挙げられます。ただし、これらは地域限定の制度が多く、募集期間や条件が頻繁に変わるため、購入エリアの自治体サイトで最新情報を確認することが欠かせません。税理士と連携し、減価償却や修繕費の計上タイミングをコントロールすることで、手取りベースの利回りを引き上げることが可能になります。
まとめ
この記事では、マンション投資で失敗しないために表面利回りをどのように読み解くかを総まとめしました。重要なのは、表面利回りを入り口に、管理費・税金・空室リスクを加えた実質利回りを算出し、エリア選定や融資条件と組み合わせて総合判断する姿勢です。平均利回りや人口動態など客観的データを活用しつつ、自分の資金計画とリスク許容度を明確にすれば、数字に踊らされることなく着実な投資が実現できます。まずはシミュレーション表を作成し、今日紹介した視点で物件を比較してみてください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp/
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp/
- 国土交通省 住宅・土地統計 – https://www.mlit.go.jp/
- 東京都都市整備局 人口予測 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/
- 総務省統計局 国勢調査 – https://www.stat.go.jp/

