退職金や預貯金をどう運用すべきか悩む60代は多いものです。定期預金の金利はほぼ横ばいが続き、株式市場は値動きが激しく、資産を減らす不安が拭えません。その点、マンション投資は家賃収入という安定キャッシュフローを得やすく、年金を補完する手段として注目されています。もっとも「この年齢でローンは組めるのか」「空室が増えたら生活費はどうなるのか」といった疑問が尽きないのも事実です。本記事では、60代がマンション投資で押さえるべき資金計画、物件選び、運用管理、そして2025年度の税制までを順序立てて解説します。読み終えるころには、ご自身にとって現実的な投資プランが描けるようになるでしょう。
60代がマンション投資を検討すべき背景

ポイントは、60代という年齢が持つ資産構成と時間軸の特徴を理解することです。総務省「家計調査2024」によると、60代夫婦世帯の平均的な公的年金受給額は月約22万円ですが、ゆとりある生活費としては月30万円程度が望ましいとされています。言い換えると、毎月8万円前後の不足を補う手段が必要になるわけです。
低金利が続く2025年時点では、定期預金で年率0.1%を得ても1000万円を1年間預けて得られる利息はわずか1万円に届きません。一方でマンション投資は、東京23区の平均家賃を参考にすると、2000万円台のワンルームでも年間家賃収入が120万円前後になるケースがあります。もちろん管理費や修繕積立金、空室リスクを考慮する必要がありますが、利回りという観点では預貯金を大きく上回ります。
ただし60代は投資期間が限られるため、長期的な値上がり期待よりも安定収入に重きを置きます。また年齢が上がるほど金融機関の融資審査は厳しくなり、返済期間も短く設定されがちです。そのため、ローンを組む場合は返済終了年齢とキャッシュフローのバランスを必ず確認する必要があります。
無理のない資金計画とローンのポイント
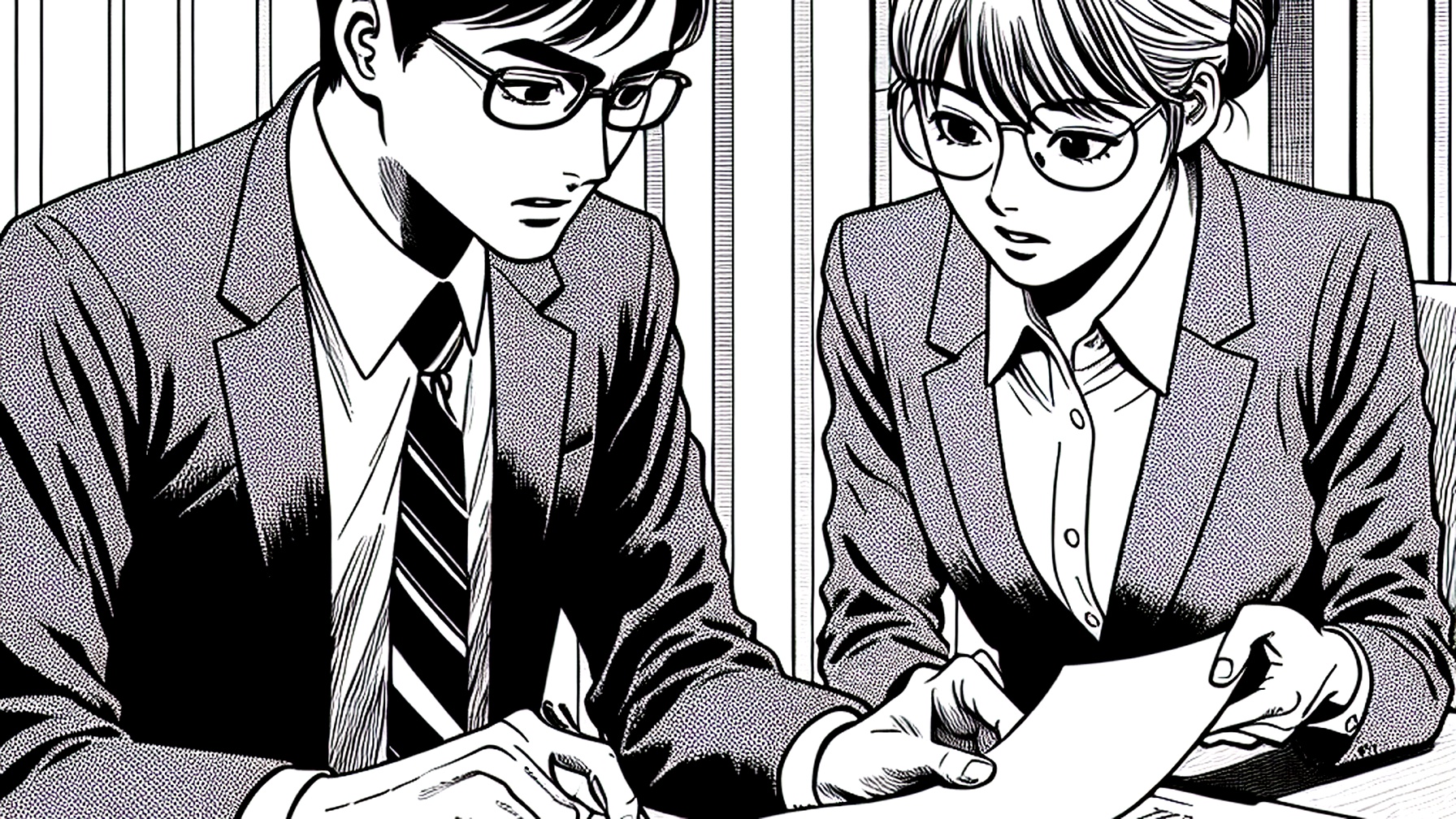
まず押さえておきたいのは、自己資金と融資の比率です。自己資金を多めに投入すれば毎月の返済額は下がりますが、手元の流動性が減り、緊急時の対応力が落ちます。一般的に60代が安心して始めるなら、物件価格の30〜40%を自己資金、残りをローンで調達するケースが多いです。
日本政策金融公庫の「2025年度 高齢者向け不動産投資ローン」では、完済時年齢を75歳以下とし、返済期間は最長15年が目安になっています。例えば65歳で15年ローンを組むと、80歳までに完済する計算です。金利は変動型で年1.9%前後、固定型で年2.4%前後が平均水準と言われます。金利が0.5%違うだけで、2000万円の借入総返済額には約80万円の差が生じるため、複数行の比較は欠かせません。
諸費用を含めた初期費用は物件価格の8〜10%が目安です。具体的には以下のような内訳になります。
- 登記費用・司法書士報酬
- 金融機関事務手数料・保証料
- 火災保険料(5年一括払いが主流)
- 仲介手数料
これらを自己資金で支払うと当初のキャッシュフローが楽になります。さらに、突発的な修繕費に備えて別途100万円程度の予備資金を確保しておきましょう。実はこの余裕資金が、空室や家賃下落時の精神的安全装置として大きな役割を果たします。
失敗しない物件選びと立地戦略
重要なのは、需要が底堅く、出口戦略にも強い立地を選ぶことです。不動産経済研究所のデータによれば、2025年10月時点で東京23区の新築マンション平均価格は7580万円と高止まりしています。60代の投資家にとっては価格帯的にハードルが高いため、築10年前後の中古ワンルームを狙うケースが増えています。中古であれば2500〜3500万円の物件が多く、家賃も表面利回り4〜5%を確保しやすいのが特徴です。
都心部は空室リスクが低い反面、利回りが下がりやすい傾向があります。郊外は購入価格が抑えられるものの、将来的な人口減少リスクが高まります。そのため、駅徒歩5分以内、乗降客数が1日10万人を超える沿線を中心に探し、築年数よりも交通利便性と管理状態を優先しましょう。また、賃貸需要が安定する単身者向けワンルームと、ファミリー向け2LDKではターゲットが異なるため、自身の運用目的を明確にすることが大切です。
実際の購入前には、現地で平日昼夜と休日に周辺環境を確認し、騒音や治安をチェックします。さらに管理組合の議事録を取り寄せ、修繕積立金の滞納率や大規模修繕の実施状況を確認することも欠かせません。修繕計画が破綻している物件は将来的に資産価値が下がりやすく、出口で苦労する可能性が高いからです。
運用開始後に意識したい管理と出口
まず押さえておきたいのは、運用中の時間をどこまで割けるかという点です。自主管理は管理会社への手数料を節約できますが、入居者対応や修繕手配を自分で行う必要があります。60代で趣味や旅行を楽しみたい人は、管理委託料を支払ってでも時間を買う発想が現実的です。
家賃設定は「新築対比▲5%」を初期の目安にすると、競争力を保ちながら空室期間を短縮できます。また家賃保証会社を活用すれば、万一の滞納リスクを抑えられます。ただし保証料が年間家賃の10%前後かかるため、キャッシュフローに与える影響を試算しておきましょう。
出口戦略としては、①保有し続けて家賃収入を受け取る、②相続させる、③売却して現金化する、の三つが考えられます。保有する場合でも、築20年を超えると家賃下落が加速しがちなので、築15年を目安に売却を検討すると資産価値を保ちやすいです。加えて、2025年現在は国内外の投資家による中古区分マンションの需要が高く、早めの売却が成立しやすい市場環境が続いています。
2025年度の税制・支援制度の活用法
実は制度を正しく使うだけで、手取り収益が大きく変わります。2025年度住宅ローン減税は、耐震・省エネ基準を満たす中古マンションであれば、年間最大14万円(控除率0.7%×借入残高2000万円)が控除対象です。60代でも所得がある場合、4年間で最大56万円の税負担を減らせます。
また、2025年度から開始された「相続時精算課税制度の見直し」により、贈与時点での課税対象額がより明確になりました。マンションを子や孫へ生前贈与するときには、2500万円までの非課税枠を活用し、将来の相続税を抑えることも可能です。
高齢者向けには「リバースモーゲージ型ローン」の選択肢も残っていますが、物件評価額の50〜60%が融資上限になりやすく、居住用を担保にする必要があります。投資用マンションの場合は対象外となる金融機関が多いため、事前に利用条件を確認しましょう。
最後に、東京都の「マンション長寿命化推進助成(2025年度)」は、共用部の省エネ改修に対し最大200万円を補助しています。オーナー主導で管理組合と協力し、設備を更新すれば資産価値向上と空室対策の両方につながるので、長期保有を前提とする場合は検討する価値があります。
まとめ
ここまで、60代がマンション投資を始める際に必要な視点を資金計画、物件選び、運用管理、税制の四つに分けて解説しました。最も大切なのは、短めの回収期間でも無理なく返済できる資金計画と、将来の出口を見据えた立地選定です。家賃収入に過度な期待をせず、修繕費や空室を織り込んだシミュレーションを行えば、年金に上乗せできる安定収入を得られる可能性が高まります。行動に移す前に情報を整理し、金融機関や不動産会社へ具体的な数字を持って相談することで、リスクを抑えながら着実にスタートを切れるでしょう。
参考文献・出典
- 総務省統計局「家計調査2024」 – https://www.stat.go.jp
- 不動産経済研究所「首都圏マンション市場動向 2025年10月」 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省「2025年度 住宅ローン減税の概要」 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫「高齢者向け不動産投資ローンの手引き(2025年版)」 – https://www.jfc.go.jp
- 東京都都市整備局「マンション長寿命化推進助成 2025年度」 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

