相続したけれど遠方で管理が難しい物件をどうすればいいか──そんな悩みを抱える人は少なくありません。売却か賃貸かで迷ううちに維持費がかさみ、気付けば負動産へと変わるケースもあります。本記事では、不動産クラウドファンディングを活用して相続物件を収益源に変える方法を解説します。仕組みの基礎から2025年度の最新制度、サービス選びのコツまで網羅するので、忙しい相続人でも実践できる具体策がわかります。
不動産クラウドファンディングとは何か
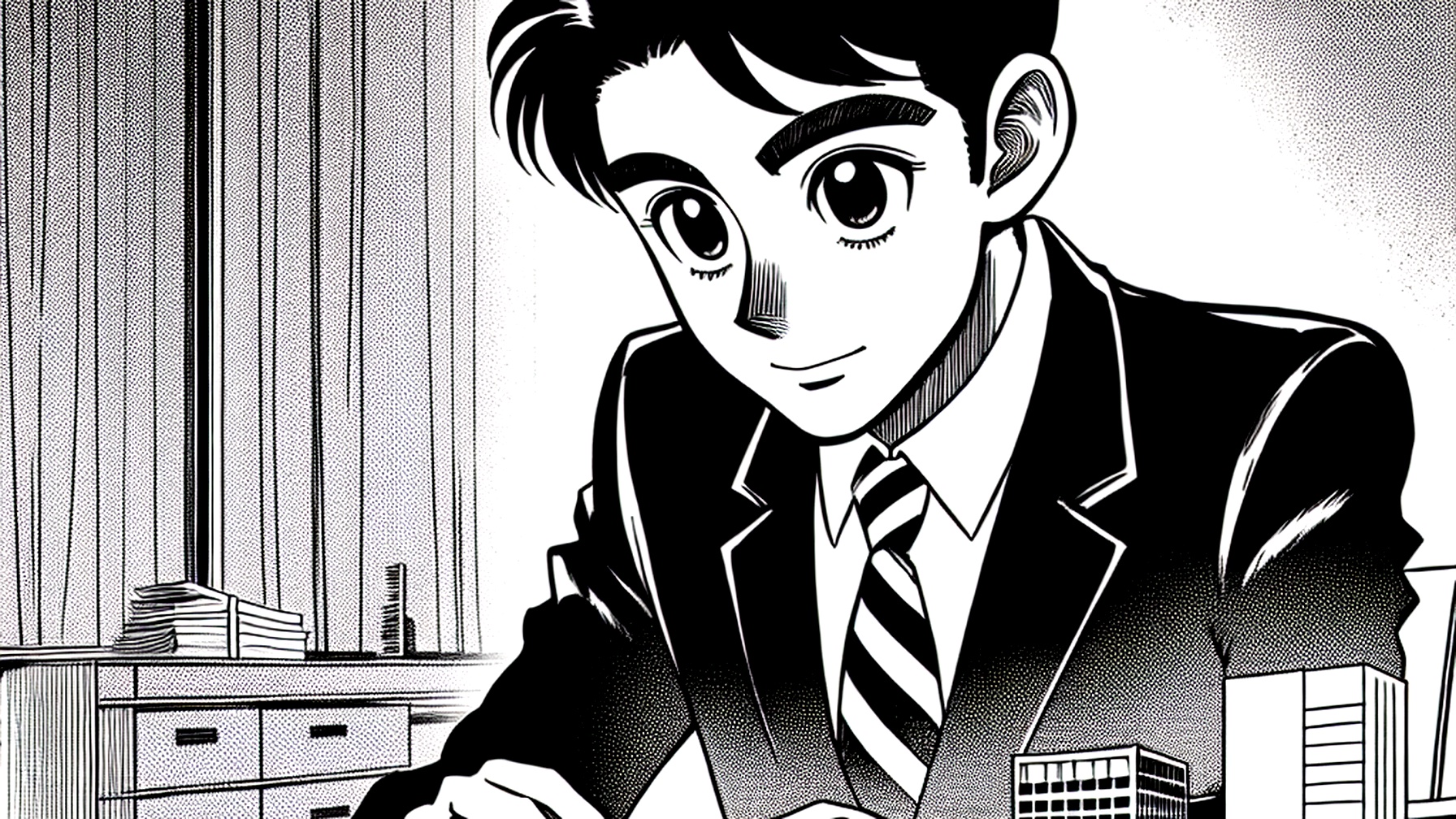
まず押さえておきたいのは、不動産クラウドファンディングの仕組みです。これは不動産特定共同事業法に基づき、小口化された不動産に複数の投資家が出資し、賃料や売却益を分配金として受け取る仕組みを指します。金融庁の2025年6月データによると、国内の累計募集総額は7,000億円を超え、個人投資家のすそ野が急速に広がっています。
一方で従来のREIT(不動産投資信託)と異なり、案件ごとに物件所在地や運用期間、利回りを自分で選べる点が特徴です。つまり相続物件を組み込んだ案件が出た場合、投資家はローカル情報を加味して判断できます。また最低1万円程度から参加できるため、相続税納付後で資金が限られていても参入しやすい点が魅力です。
重要なのは、運用会社が物件管理を担うため、個人での修繕手配や入居者対応が不要になることです。相続後に遠方へ転居した場合でも、オンラインで状況を確認しながら受動的に収益を得る仕組みが整っています。
相続物件を活用した投資のメリット

実は相続物件には、築年や立地が多少不利でもメリットがあります。固定資産税評価額が下がっているため取得コストがゼロに近く、純粋な運用益を取り込みやすいからです。国土交通省の「土地白書2025」によれば、築30年以上の地方物件でも賃料利回りは平均7%を維持しており、保有が収益化につながる可能性があります。
また、2025年度も継続する小規模宅地等の特例により、一定の条件を満たす貸付事業用宅地は評価額が最大50%減額されます。言い換えると、相続時に税負担を抑えたうえで、クラウドファンディングで賃貸運用すれば、税制とキャッシュフローの両面でメリットを享受できるわけです。
一方で空室リスクや修繕リスクを単独で抱えると、せっかくのメリットが吹き飛びます。そこでクラウドファンディングを通じて複数物件に分散投資することで、相続物件単体のリスクを緩和できます。特定の一棟にこだわらず、ポートフォリオ全体で収益を安定させる発想が必要です。
クラウドファンディングで相続物件を選ぶポイント
ポイントは、運用会社の開示情報を精査し、相続物件の再生計画が具体的かを見極めることです。例えばリノベーション費用の内訳、想定家賃、退去後の空室期間をどう想定しているかが明確なら、運用シナリオの信頼度が高まります。
次にチェックしたいのは優先劣後出資比率です。運用会社が劣後出資として10%以上を負担していれば、損失が出た際に投資家より先にリスクを負う仕組みが機能します。金融庁のガイドラインでも、透明性と利益相反対策として劣後出資の明示が推奨されています。
さらに、相続登記の義務化(2024年4月施行、2027年3月罰則開始)に伴い、所有権移転が完了しているかも重要な確認事項です。登記が未了だと売却や賃貸の手続きが停滞し、ファンド全体の運用スケジュールに影響を及ぼします。運用会社の資料で「登記完了済み」と明記されているか必ず確認しましょう。
2025年度に利用できる制度と税メリット
まず注目したいのは、不動産所得に適用される青色申告特別控除です。クラウドファンディングで得た分配金は雑所得として申告できますが、相続物件を賃貸事業として保有し続ける場合、所得区分を事業所得にできれば最大65万円の控除を使えます。
また、2025年度の相続税・贈与税一体化により、生前贈与加算期間が7年に延長されます。相続開始後の税負担を見据え、相続物件を早めにクラウドファンド化して運用益を贈与することで、将来の課税対象を圧縮できます。
さらに、国土交通省が実施する「住宅エコリフォーム推進事業(2025年度)」も見逃せません。一定の省エネ改修を行うと、上限100万円の補助金が物件単位で交付されます。運用会社が補助金申請を代行するケースもあるため、該当する案件かどうか事前に確認すると利回り改善が期待できます。
おすすめのサービスを比較
ここでは公開情報を基に、相続物件を多く取り扱うプラットフォームを三つ比較します。いずれも1万円から出資でき、劣後出資10%以上を掲げています。
・サービスAは地方の築古アパートを再生する案件に強みがあります。平均利回り6.8%で運用期間12カ月と短期型が多く、相続後の現金化を急ぐ人に向きます。
・サービスBは都市部の区分マンションに特化し、空室保証を導入しています。家賃下落リスクを抑えたい相続人に適した設計です。
・サービスCはホテルや商業施設を組み込んだ複合ファンドを提供し、インフレヘッジの観点で人気です。相続物件を投入する際もリノベ予算を補助金と併用する独自モデルを採用しています。
いずれのサービスも、運用報告書を四半期ごとにオンライン開示し、退去率や修繕実績を細かく公開しています。透明性が高いプラットフォームを選ぶことで、遠隔地でも安心して運用を任せられます。
まとめ
相続物件の活用に悩むなら、不動産クラウドファンディングを経由して分散投資を図る方法が有力です。管理の手間を抑えつつ、2025年度の税制優遇や補助金を組み合わせれば、収益性を高めながら資産を守れます。まずは運用会社の開示情報を比較し、登記状況と劣後出資比率をチェックしてください。行動を先延ばしにせず、最初の一口を出資することで、相続物件が負担から収益源へと変わる第一歩が踏み出せます。
参考文献・出典
- 国土交通省 土地白書2025年版 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001_2025whitepaper.html
- 金融庁 不動産クラウドファンディングに関するガイドライン – https://www.fsa.go.jp/policy/realestate_crowdfunding_guide.pdf
- 総務省 住宅・土地統計調査2023 – https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/
- 国税庁 相続税法令等解説(2025年度版) – https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku2025/
- 環境省 住宅エコリフォーム推進事業(2025年度) – https://www.env.go.jp/policy/ecoreform2025/

