家賃収入で将来の資産を築きたいものの、「どこに、どのような物件を買えばいいのか分からない」と悩む方は多いはずです。立地を読み違えると長期空室や家賃下落に直結するため、不動産初心者ほど慎重な判断が求められます。本記事では、最新データを活用した立地分析の手順から、金融機関との交渉術まで体系的に解説します。読み終えた頃には、アパート経営 立地選定 始め方の全体像がつかめ、自分なりの投資戦略を描けるようになるでしょう。
立地が収益を左右する理由
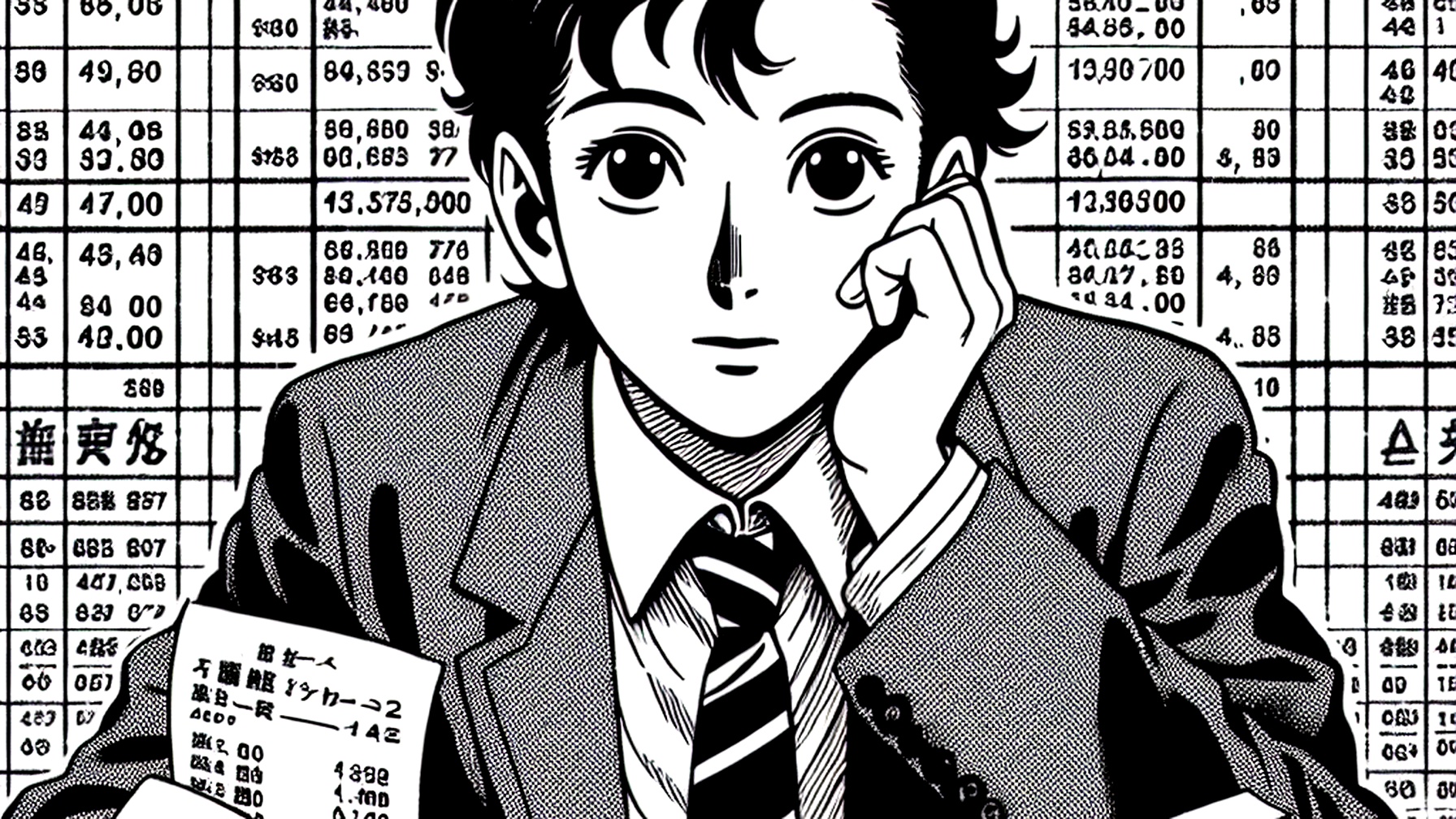
重要なのは、立地がキャッシュフローだけでなく資産価値の変動リスクまで左右する点を理解することです。2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント下がりましたが、低下の主因は人口流入が続く都市圏に限られ、地方では依然として空室率30%超のエリアが散見されます。
まず、家賃は周辺相場の範囲内でしか設定できないため、高い平均所得層が集まる立地ほど家賃の上限が高くなります。一方で、人口減少が目立つ郊外や地方都市では需給バランスが崩れやすく、入居者獲得のために家賃を下げざるを得ません。つまり、同じ利回りで見えても実質的な収益力には大きな差が生じます。
また、売却出口を考えると、将来の購入者も「空室リスクの低いエリア」を求めるため、立地の良し悪しはそのまま売却価格に反映されます。国土交通省の不動産価格指数によれば、東京23区の住宅総合指数は2020年比で2025年に13%上昇した一方、人口減が続く県では横ばいか微減にとどまっています。投資期間中の家賃だけでなく出口戦略まで見据えることで、立地選定の重要性が際立つのです。
初心者でもできるエリア分析の手順
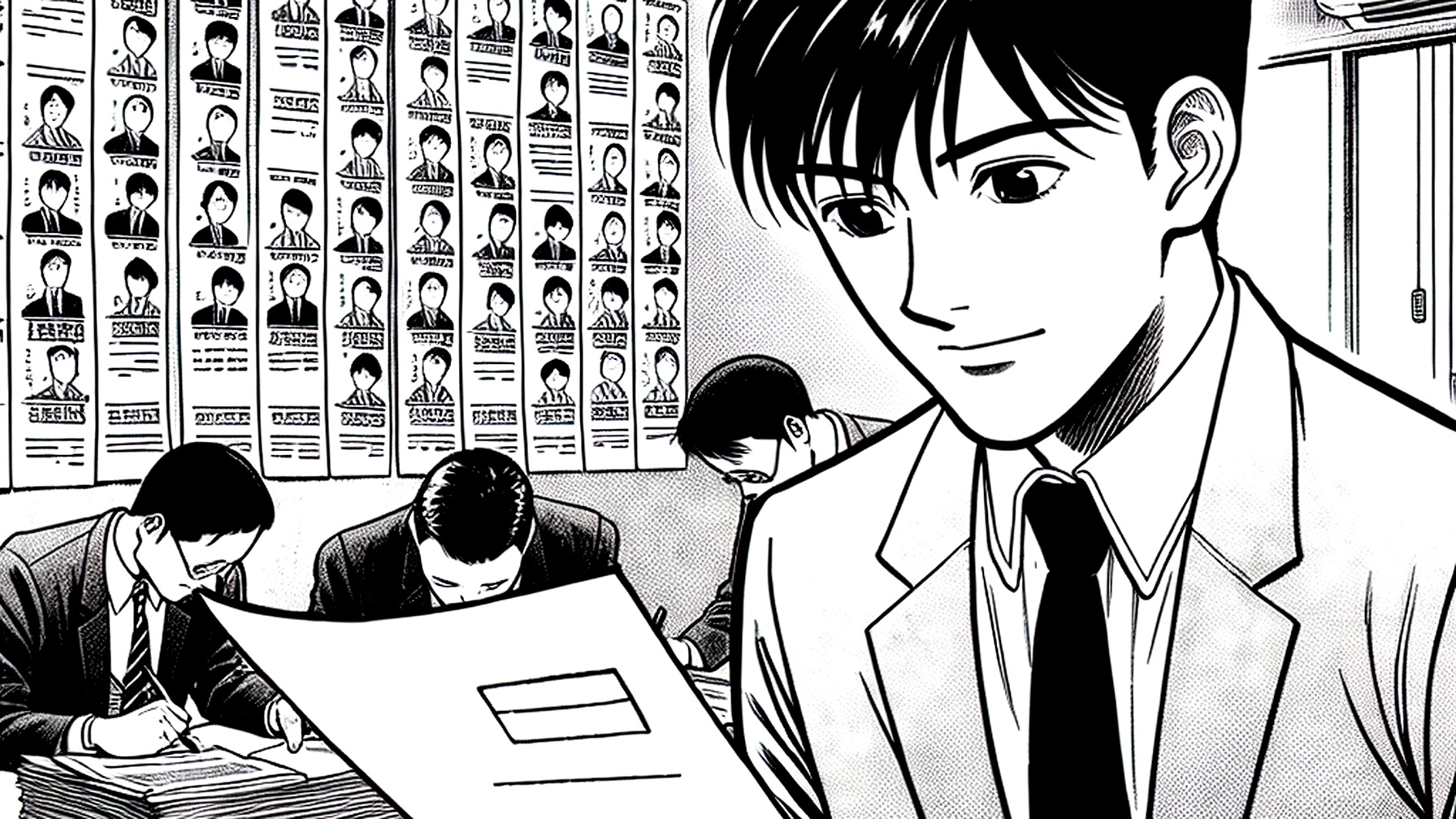
まず押さえておきたいのは、エリア分析を「需要側」「供給側」「規制」の三つに分けるとシンプルになることです。需要側では住民基本台帳や総務省の人口推計を使い、過去5年の人口増減率と年齢構成をチェックします。特に20〜39歳の増減がプラスであれば、賃貸需要が堅調と判断しやすいでしょう。
供給側では、国交省の住宅着工統計からアパート新築戸数の推移を確認します。新築ラッシュが続くエリアは競合が増えるため、利回りが高くても慎重になる必要があります。最後に規制面として用途地域や建ぺい率・容積率を市区町村の都市計画図で確認し、将来的な開発余地や近隣環境の変化を読み取ります。
具体的な手順は次の通りです。
- 市区町村サイトで人口データを入手し、5年間の増減率を算出
- 国交省の住宅着工統計で同エリアの新築アパート戸数を確認
- 地方自治体の都市計画図を閲覧し、用途地域と再開発計画の有無を把握
これらを踏まえ、「人口が微増で供給が限定的、かつ再開発により利便性向上が見込めるエリア」を第一候補に挙げると、初心者でも大きな失敗を避けやすくなります。
需要を見極めるデータの読み方
ポイントは「生の数字を現地の空気感とつなげる」ことです。たとえば総務省の平成27年と令和2年国勢調査を比較すると、福岡市中央区は5年間で人口が4.5%伸びています。しかし現地の不動産会社に聞くと、単身向けワンルームの入居者はIT企業勤務者が多く、休日の天神再開発が追い風になっていると分かります。このように統計データを現地の実感で補完すると、紙面上の数字が生きた情報へと変わります。
さらに、家賃データは民間ポータルサイトだけでなく、不動産適正取引推進機構の「賃料トレンド」を参照すると客観性が高まります。たとえば同じ家賃7万円でも、平均世帯所得が300万円のエリアと500万円のエリアでは負担感が異なるため、入居継続率に差が出ます。言い換えると、家賃は「所得と家賃負担比率」で考えると実態に近づきます。
一方で、データが良好でも実際に歩いてみると夜間の街灯が少ない、スーパーまで遠いといった生活利便性の欠点が見つかることがあります。現地下見を省くと数値だけでは見抜けないリスクを抱え込むので、必ず昼夜2回は足を運び、駅から物件予定地まで歩きながら「荷物を持った入居者目線」で評価しましょう。
物件選びと融資戦略を同時に進める
実は、優良物件は「探してから銀行に行く」のでは遅い場面が増えています。金融機関は物件情報と同じくらい投資家の計画性を重視するため、事前に事業計画書を準備し、借入枠の目安を確認しておくと行動が早まります。日本政策金融公庫のアパートローン金利は2025年9月時点で年2.2〜2.4%ですが、自己資金2割以上を用意し、長期修繕計画を添付すると1.9%台の提示を受けた事例もあります。
物件選定の際は「総事業費で想定利回りを計算する」習慣を付けましょう。購入価格だけでなく、仲介手数料・登記費用・火災保険・リフォーム費を合算し、それに対して年間家賃収入を割り戻します。さらに保守的に空室率15%、運営費25%を見込むと、実力値が把握できます。
一方で、融資期間は物件の耐用年数を上限に設定されるため、木造アパートなら22年が目安です。フルローンを組むと月々の返済負担が重くなるため、自己資金を入れ、返済比率(返済額/家賃収入)を50%以下に抑えると資金繰りが安定します。金融機関と交渉する際は、シミュレーション表を持参し、空室率が上がってもキャッシュフローが耐えうることを示すと信頼が高まります。
2025年度の支援策と注意点
まず、2025年度も継続している「住宅省エネ2025キャンペーン」では、一定の省エネ性能を満たす賃貸住宅の改修費用に対し、最大200万円の補助が受けられます。期間は2026年3月末までの工事完了分が対象で、申請は原則として所有者が行います。
また、東京都では「賃貸住宅耐震化助成(2025年度版)」が存続しており、旧耐震基準の木造アパートを耐震改修する場合、工事費の3分の1(上限150万円)が補助されます。制度を利用すると、耐震補強による家賃アップだけでなく、金融機関の融資条件が改善されるケースもあるため、経済性と安全性を同時に高められます。
ただし、補助金は事前申請が必須で、工事契約後の申請は無効となります。また採択枠に達すると早期終了するため、計画段階で自治体窓口にスケジュールを確認しましょう。補助金目当てで改修規模を拡大しすぎると、キャッシュフローを圧迫するリスクがある点も忘れてはなりません。
まとめ
ここまで、立地が収益と資産価値を左右する理由から、具体的なエリア分析、データの読み方、融資交渉術、2025年度の支援策まで幅広く解説しました。重要なのは、統計データと現地調査を組み合わせ、保守的なシミュレーションで収益性を判断する姿勢です。これらを実践すれば、空室リスクを抑えながら堅実なアパート経営を進められるでしょう。今日紹介した手順を参考に、まずは気になるエリアの人口推移と家賃相場を調べ、最初の一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp/
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省 統計局 人口推計 – https://www.stat.go.jp/
- 日本政策金融公庫 融資情報 2025年9月 – https://www.jfc.go.jp/
- 不動産適正取引推進機構 賃料トレンド – https://www.retio.or.jp/
- 東京都都市整備局 耐震化助成制度 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/
- 住宅省エネ2025キャンペーン 公式サイト – https://jutaku-shoene2025.jp/

