投資用のマンションは欲しいけれど高額だし空室も心配、相続で引き継いだ戸建は管理が面倒、そして銀行預金の金利では資産がほとんど増えない──こんな悩みを抱えていませんか。実は、REIT(不動産投資信託)の「利回り」をヒントにすれば、相続物件を含む現物不動産のポテンシャルを客観的に判断できます。本記事では、REITと現物投資の違い、2025年10月時点の最新利回りデータ、相続物件を収益化する手順、そして税制や支援策まで丁寧に解説します。読み終えたころには、自分に合った戦略を描けるようになるはずです。
REITと現物不動産の違いを理解する

まず押さえておきたいのは、REITと現物不動産では投資の仕組みもリスクも異なる点です。REITは証券取引所に上場しており、株式と同じように売買できる金融商品です。一方で相続物件などの現物不動産は、自分で管理や修繕を行うか管理会社に委託する必要があります。
REITのメリットは、少額から分散投資が可能で流動性が高いことです。例えば東証REIT指数に連動するETFなら、10万円前後で複数の大型オフィスや物流施設に間接保有できます。また、J-REIT全体の平均分配利回りは2025年9月末時点で約4.0%と、普通預金を大きく上回る水準です。
一方で現物不動産はレバレッジを効かせやすい点が魅力です。住宅ローンを活用すれば自己資金を抑えつつ、家賃収入で元本を返済できます。しかし空室や修繕といった運営リスクは自分が負うため、物件選びと管理体制が重要となります。つまり、REITは金融商品としての手軽さが際立ち、現物は運営次第で利回りを高められる余地があるといえます。
利回りの基本と最新相場
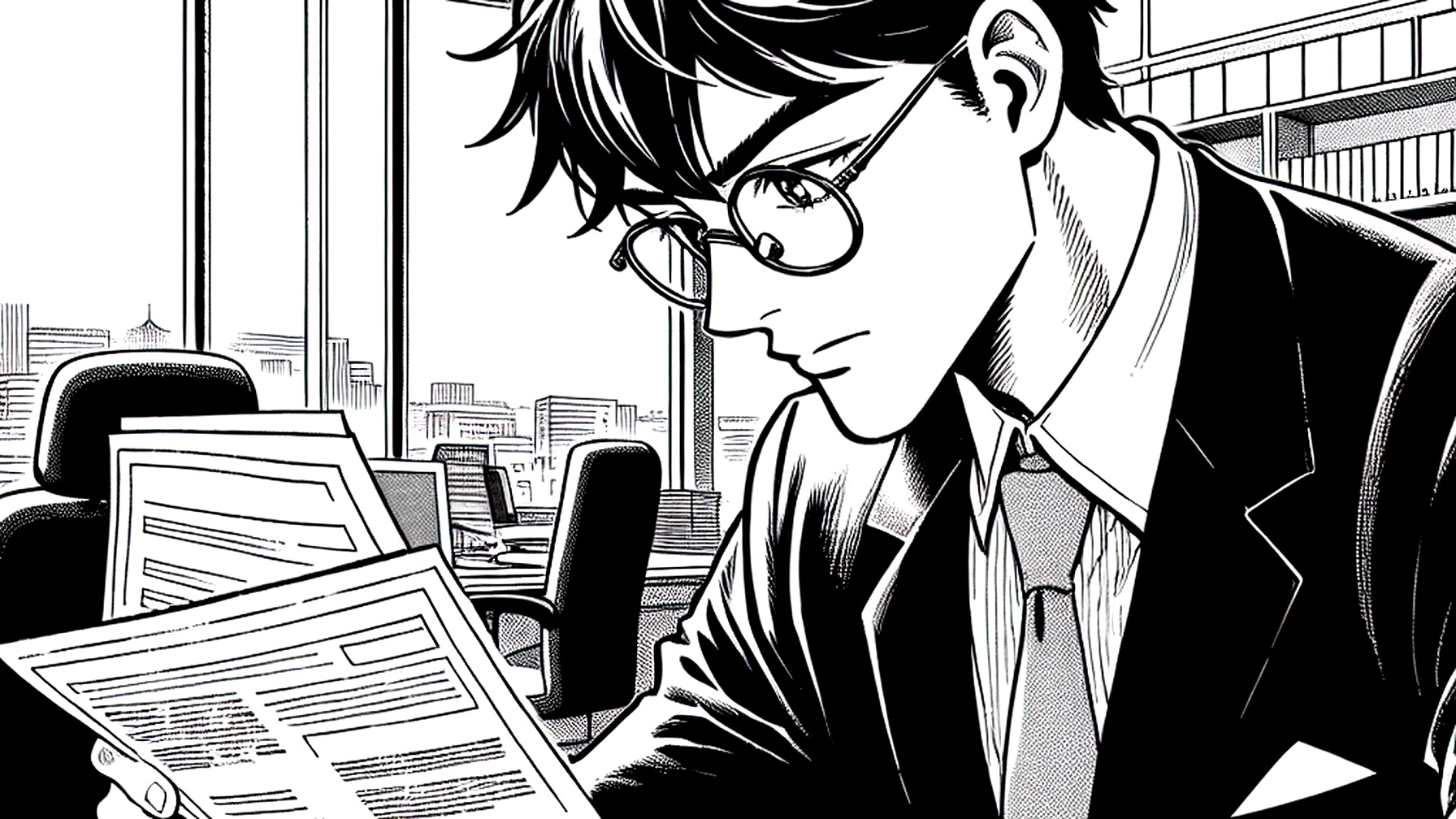
ポイントは、表面利回りと実質利回りの違いを理解することです。表面利回りは年間家賃収入を物件価格で割った数値で、経費や空室の影響を反映しません。対して実質利回りは管理費・修繕費・固定資産税などを差し引き、さらに空室率を考慮して算出します。
日本不動産研究所のデータによれば、2025年10月時点の東京23区平均表面利回りはワンルーム4.2%、ファミリータイプ3.8%、アパート5.1%です。地方都市ではこれに1〜2ポイント上乗せされた水準が一般的ですが、人口動態や入居者属性によってリスクも上がります。
実質利回りを計算する際は、空室率10%、経費率25%程度を見込むと保守的です。例えば表面利回り5%のアパートでも、実質では約3.4%に下がる計算になります。一方、J-REITの分配金利回りは経費控除後の数値が公表されるため、そのまま手取り利回りの目安になります。結論として、同じ「利回り」でも算出方法が異なるため、比較の際には前提条件をそろえることが不可欠です。
相続物件を収益化する3つのステップ
重要なのは、相続物件をそのまま放置せず、収益化または売却の判断を早期に行うことです。相続登記の義務化(2024年4月施行)により、登記を怠れば過料の対象となるため手続きは最優先となります。次に、物件の収益力を客観的に確認するため、REIT利回りをベンチマークにすると比較がしやすくなります。
1. 収支シミュレーションを作成 固定資産税、修繕積立、入居率などを反映し、実質利回りを算出します。もし得られる利回りがJ-REIT平均の4%を大きく下回るなら、保有コストが高すぎる可能性があります。
2. 修繕・用途変更の検討 築古戸建ならフルリフォームに約300万円、アパートなら外壁塗装で100万円程度かかります。これにより家賃が数千円上がる場合、投資回収期間を計算し採算性を判断します。
3. 売却か賃貸かを決定 賃貸運用で実質利回りが4%以上確保できるなら保有も合理的です。一方、利回りが低い場合は早期売却し、売却益をREITに組み替える選択肢も視野に入ります。
この流れを踏むことで、感情ではなく数字に基づいた判断ができ、相続物件のポテンシャルを最大限に引き出せます。
REIT利回りを指標にした投資判断
実は、REIT利回りは金利動向や景気感を映すバロメーターとしても機能します。日本銀行が2025年4月に長期金利誘導目標を0.5%から0.75%へ引き上げた際、J-REIT全体の利回りは4.3%から4.6%へ上昇しました。金利が上がるとREIT価格が下がる傾向があるため、利回りが上昇する仕組みです。
この動きは、現物不動産の評価にも影響します。金融機関は長期金利の上昇を受けて融資金利を0.2〜0.3ポイント引き上げており、借入によるレバレッジ効果はやや縮小しています。したがって、投資判断の際は「融資金利+2%」を最低ラインとし、それを超える実質利回りが確保できるか検証しましょう。
また、REITにはオフィス特化型や物流特化型など複数のタイプがあります。相続物件が住宅系なら、住宅特化型REITの利回りを比較対象にすることで、同一セグメントでの優位性を判断しやすくなります。言い換えると、REIT利回りは現物投資家にとってもシグナルとなる重要なマーケット指標なのです。
税制と2025年度の支援策
まず押さえておきたいのは、2025年度税制改正で相続税の基礎控除や小規模宅地等の特例に大きな変更はない点です。ただし、空き家対策として2025年12月まで延長された「相続空き家売却の3,000万円特別控除」は引き続き利用可能です。これは、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた戸建を、一定の条件で売却した場合に譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。
一方、住宅省エネに関する補助金は新築・大規模リノベーションを対象としたもので、相続賃貸の軽微な修繕では使いにくいケースが多いでしょう。したがって、税制面での最大のポイントは、「取得費加算の特例」や「長期譲渡所得の軽減税率」を上手に活用し、キャッシュフローを圧迫しない売却計画を立てることです。
REITについては、個人投資家がNISA(少額投資非課税制度)の成長投資枠を利用すれば、年間240万円までの分配金が非課税になります。2025年からは売却益も非課税枠に含まれるため、相続物件を売却して得た資金をREITに再投資する場合、この枠を最大限に活用すると税引き後リターンが高まります。
まとめ
相続物件をどうするか迷ったとき、REIT利回りをベンチマークにして実質利回りを計算すると、保有か売却かの判断が明確になります。REITは少額・高流動性という特性があり、分配金利回りは2025年時点で約4%と安定的です。一方で現物不動産はレバレッジや用途変更で利回りを高められる魅力があります。相続登記の義務化や空き家特例など最新の制度を踏まえ、数字に基づいた戦略を立てれば、家計全体のキャッシュフローを着実に改善できるでしょう。まずは保有物件の収支シミュレーションを作成し、次の一歩を具体的に検討してみてください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 国土交通省「J-REIT市場動向」 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 相続税・贈与税のあらまし(令和7年度版) – https://www.nta.go.jp
- 金融庁 NISA制度の概要(2025年改正) – https://www.fsa.go.jp
- 日本取引所グループ 東証REIT指数データ – https://www.jpx.co.jp

