多くの投資家が「区分より一棟のほうが稼げる」と耳にしますが、実際には不安も多いはずです。高額な融資、空室リスク、修繕計画など、乗り越える壁は少なくありません。本記事では、15年以上にわたり一棟物を運用してきた立場から、初心者でも理解できるように基礎から応用までを丁寧に解説します。読み終えたときには、資金計画から物件選び、管理、そして出口戦略まで、一連の流れを具体的にイメージできるようになるでしょう。
一棟マンション運用の魅力とリスク
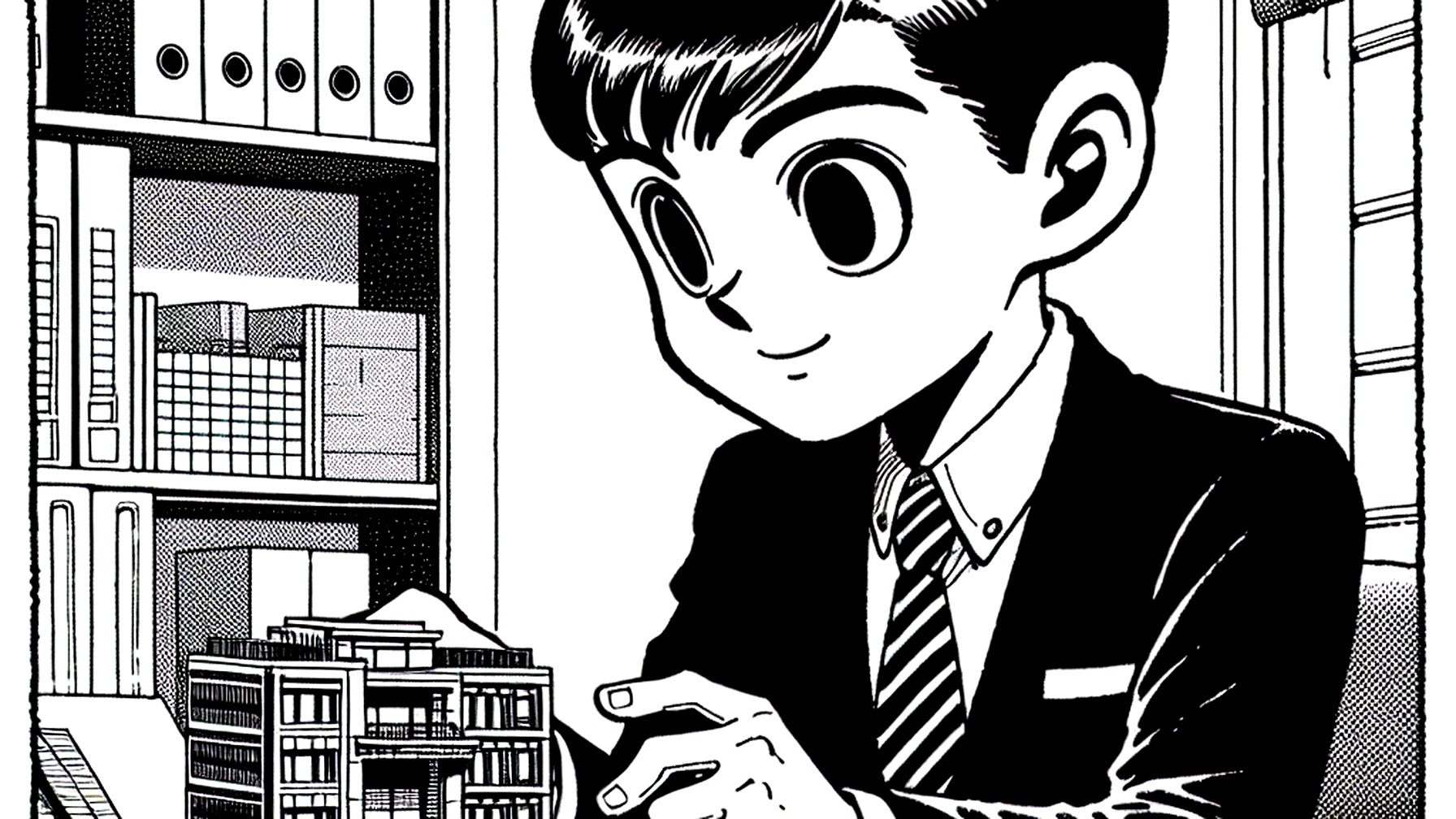
まず押さえておきたいのは、一棟マンション 運用がキャッシュフローを自分でコントロールしやすい点です。家賃設定や修繕計画を一括で行えるため、区分所有では難しい収益最大化が可能になります。一方で、初期投資が大きくなるため、失敗したときの損失も比例して大きくなることを忘れてはいけません。
次に、投資効率という観点で見てみましょう。国土交通省の令和6年度「不動産投資家調査」によると、一棟マンションの平均表面利回りは都心部で4.5%、地方中核都市で6.8%です。数字だけを見ると魅力的ですが、入居率が90%を下回ると途端に手残りが減るケースも多いです。つまり、実質利回りを高めるには稼働率の維持が欠かせません。
さらに、災害リスクと長期修繕リスクも検討が必要です。近年の大雨災害では、地下設備が浸水し多額の修繕費が発生した事例が報告されています。保険と修繕積立のバランスを適切に取ることで、予期せぬ出費を平準化できます。リスクは避けられませんが、事前準備で最小限に抑えられる点を念頭に置きましょう。
収益を左右するキャッシュフローの考え方
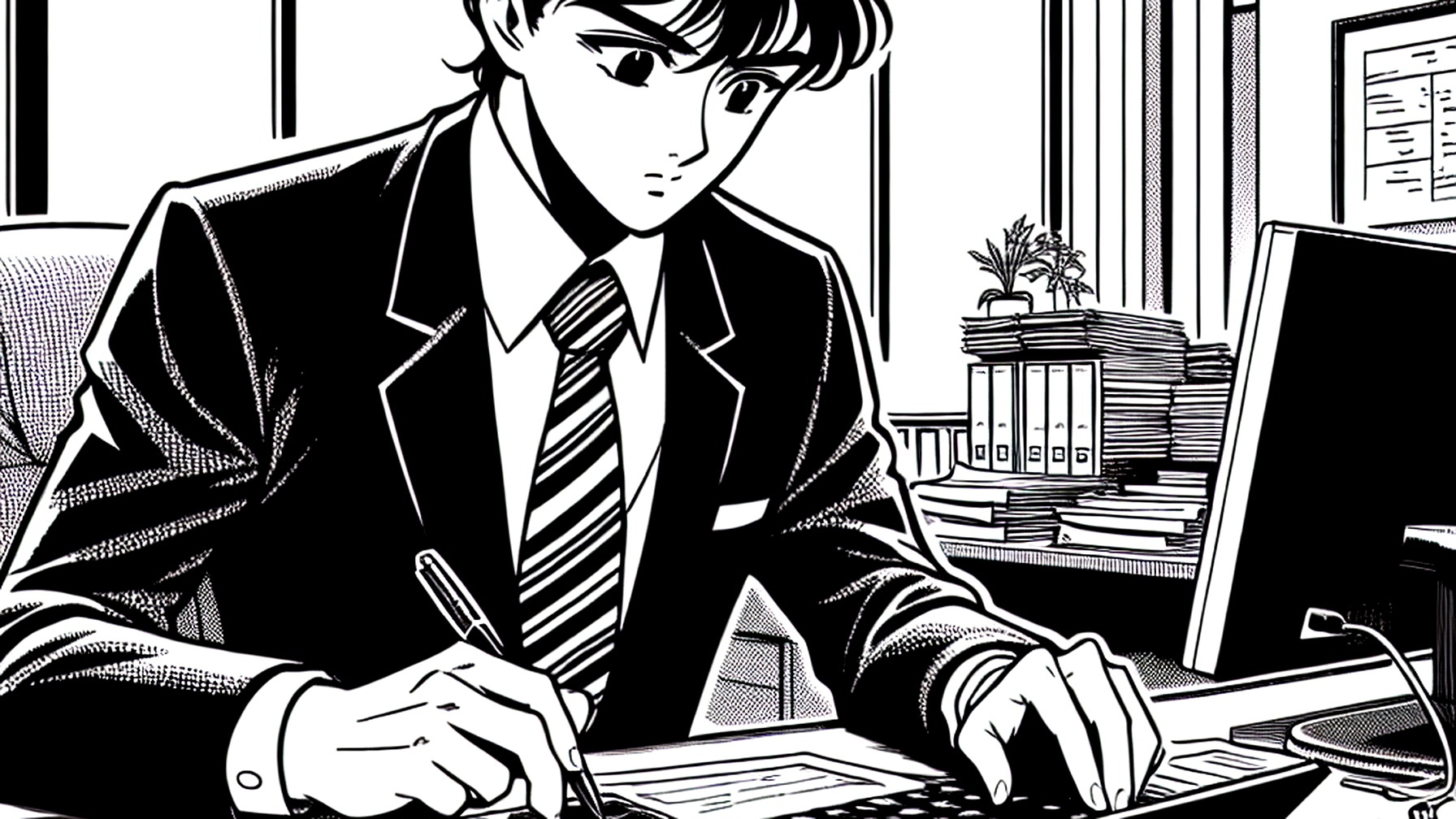
ポイントは、表面利回りではなく「ネットキャッシュフロー」に注目することです。ネットキャッシュフローとは、家賃収入から空室損失・運営費・ローン返済・税金を差し引いた手残り額を指します。ここを正確に把握しなければ、見かけの利回りに惑わされる結果になりかねません。
まず、運営費率の目安を知る必要があります。一般的に鉄筋コンクリート造の一棟マンションでは、固定資産税を含む年間運営費が家賃収入の20〜25%程度に収まると健全といわれます。しかし築年数が20年を超えると、エレベーターや給排水管の大規模修繕が重なり、運営費率が30%を超えるケースもあります。長期シミュレーションには修繕費の山を織り込みましょう。
また、ローン返済にも注意が必要です。金利1%の差は、1億円を35年返済した場合で総返済額が約2,000万円変わります。実は、ネットキャッシュフローを厚くするかどうかは金利交渉にかかっていると言っても過言ではありません。複数行を比較し、物件評価に強い地方銀行や信用金庫を当たり、最適な条件を引き出す工夫が求められます。
成功する物件選びと立地戦略
重要なのは、人口動態と賃貸需要を数値で検証する姿勢です。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2025年以降も都心5区と主要政令市の中心部では単身世帯が増えると見込まれています。単身向けマンションなら、駅徒歩10分以内の物件であれば家賃を維持しやすいのが強みです。
一方で、郊外のファミリー向けマンションは価格が割安なうえ、駐車場収入で利回りを底上げできる利点があります。しかし少子化により、学区や大型商業施設へのアクセスが悪い地域では入居付けが難しくなる可能性があります。つまり、自分の投資目的を明確にし、需要の変化に耐えうる立地を選ぶことが不可欠です。
具体例を挙げると、東京都心で築15年の20戸マンションを購入するケースでは、成約時の入居率が95%を維持できるかが分水嶺になります。反対に、名古屋市郊外で築30年の30戸マンションを買う場合、購入価格が都心の半分でも、空室が3戸出ただけでキャッシュフローが赤字に転落する試算もあります。立地とターゲットを誤れば、価格差以上のリスクを抱える点を強調しておきます。
融資と税制、2025年度のポイント
まず押さえておきたいのは、金融機関の融資姿勢が依然として「事業性重視」であることです。自己資金を物件価格の20%用意し、返済比率を年間家賃収入の50%以内に抑えるプランを提示すれば、地方銀行でも1.2〜1.8%の長期固定金利が狙えます。借入期間は物件の耐用年数と残存年数で決まるため、築浅物件は融資条件が有利になります。
税制面では、2025年度も「不動産所得の損益通算」が継続し、高額所得者が減価償却を活用するメリットは変わりません。また、省エネ性能を満たす新築一棟マンションに対しては、2025年度中に取得すれば固定資産税が3年間半額になる措置が継続予定です(詳細は各自治体で要確認)。制度は期間限定なので、取得タイミングを計画すると節税効果が高まります。
以下の比較は、金利と税制による年間手残り額の違いを示したものです。
- 金利1.3%・固定資産税軽減あり:年間手残り420万円
- 金利1.8%・軽減なし:年間手残り320万円
わずか0.5%の金利差と税制優遇の有無で、年100万円の差が生じます。数字を確認すると、融資と税制の交渉がいかに重要かが分かるはずです。
長期的な管理体制と出口戦略
実は、一棟マンション 運用で最も差がつくのは「購入後の運用力」です。入居率を95%以上で維持できれば、売却時の収益還元価格も高く評価されます。そのため、管理会社の選定は投資判断と同じくらい慎重に行う必要があります。
管理の良し悪しは、入居者アンケートと修繕実績で測れます。たとえば、共用部のLED化や無料Wi-Fi設置は小さな投資で満足度を上げる効果があります。さらに、原状回復工事を内製化しコストを20%削減した事例では、年間運営費を200万円低減し、キャッシュフローが向上しました。数字で成果を管理会社と共有する姿勢が欠かせません。
出口戦略としては、築25年を迎える前に区分売却か一棟売却を検討するのが王道です。金融機関が35年超の融資を組みにくくなる築古物件では、売却価格が下落しやすいためです。言い換えると、修繕計画と売却計画を同時に描くことで、投資全体の利回りを最大化できます。
まとめ
ここまで、一棟マンション 運用の基礎から実践までを見てきました。大きなポイントは、精緻なキャッシュフロー管理と需要を見極めた立地選び、そして融資・税制を味方につける姿勢です。物件取得がゴールではなく、長期運用と出口戦略を同時に設計することで、安定した資産形成が可能になります。まずは自身の資金計画を確認し、信頼できる専門家とともに具体的なプランを作る一歩を踏み出してください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 不動産投資家調査(令和6年度版) – https://www.mlit.go.jp
- 国立社会保障・人口問題研究所 将来人口推計 – https://www.ipss.go.jp
- 総務省 統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 金融庁 地域金融機関の融資動向レポート(2025年度) – https://www.fsa.go.jp

