不動産投資に憧れはあっても、「一棟マンション リスク」と聞くと尻込みしてしまう人は多いものです。高額な融資、長期の運営、突発的な修繕など、想像するだけで不安は尽きません。しかし、リスクを正しく理解し、事前に対応策を講じれば、大きなリターンを得られる投資手法でもあります。本記事では、一棟物件ならではの代表的なリスクと、その実務的な対処方法を基礎から丁寧に解説します。読み終えた頃には、何に注意しどう備えればいいかが具体的にイメージできるはずです。
一棟マンション投資が抱える代表的なリスク
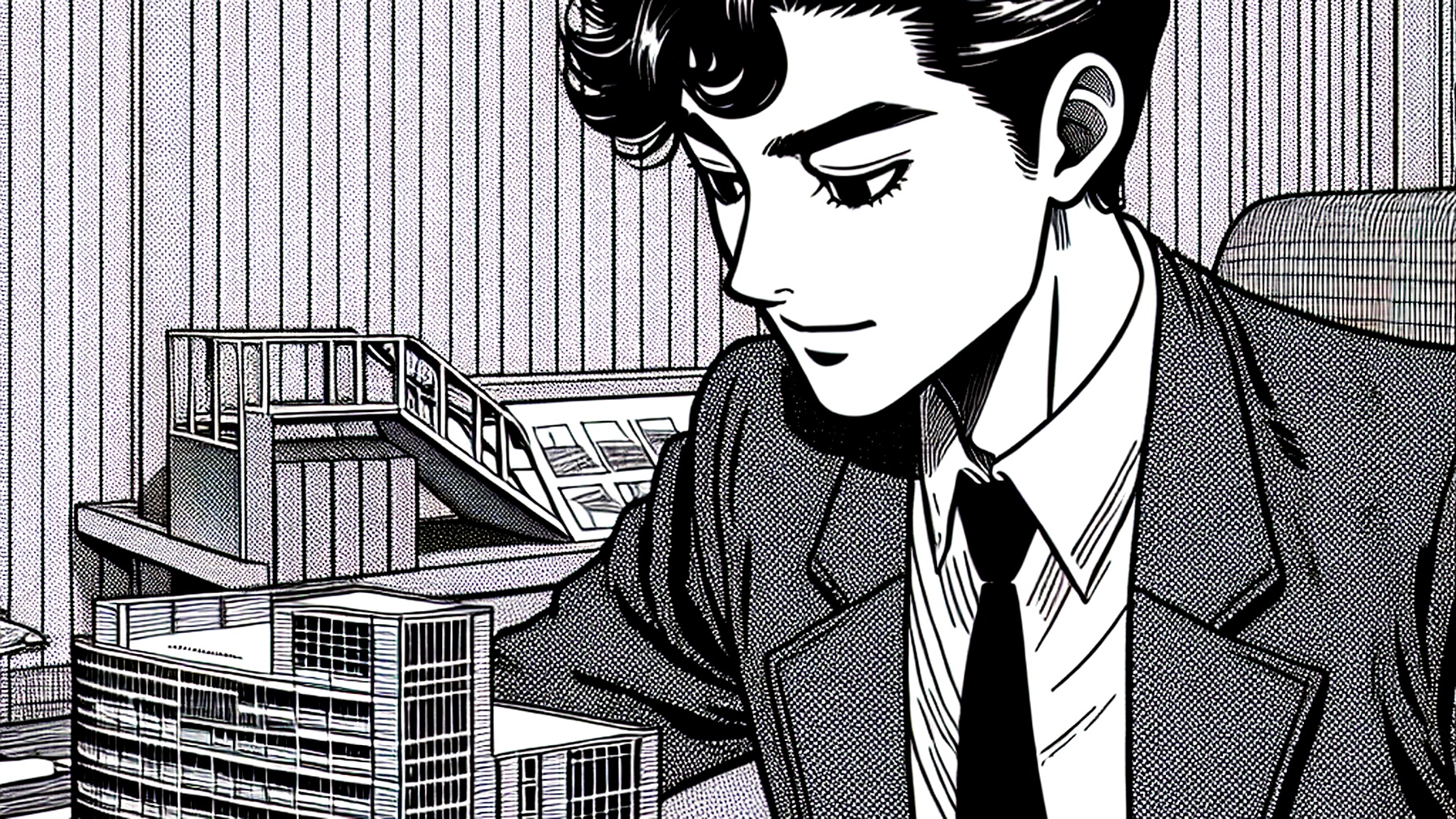
まず押さえておきたいのは、一棟マンション投資のリスクは単一ではなく複合的に絡み合う点です。大きく分類すると「空室・賃料下落」「修繕費用の増大」「金利変動」「資産価値の毀損」「出口戦略の難航」が挙げられます。これらは単体で発生するよりも、連動してキャッシュフローを圧迫することが多いため、総合的な視点が不可欠です。
実は、一棟物件は区分マンションに比べ、空室リスクの平準化が利く一方、建物全体を所有する責任が重くのしかかります。管理や修繕の意思決定権を自分で持てるメリットがある半面、判断を誤ると損失がダイレクトに跳ね返るからです。つまり、リスクを「避ける」のではなく「管理する」姿勢が求められます。
日本政策金融公庫の2025年調査によると、一棟アパート・マンションの収支悪化要因の上位は空室と修繕費で全体の68%を占めています。このデータは、主観的な不安ではなく統計的裏付けがあることを示しています。次章以降で個別のリスクを掘り下げ、対策を具体的に検討していきましょう。
資金繰りを左右する空室・家賃下落

ポイントは、空室率と家賃水準がキャッシュフローに直結するという現実です。ひと部屋あたりの欠損は小さくても、総戸数が多い一棟マンションでは雪だるま式に収益を圧迫します。総務省の住宅・土地統計調査(2023年速報値)でも、地方中規模都市における空室率は20%前後で推移しており、立地選定と賃料設定の精度が生死を分けます。
まず、周辺エリアの賃貸需給を多面的に調べる必要があります。人口動態、大学や企業の動き、再開発計画といったマクロ要因のほか、直近3年の募集賃料と成約賃料の乖離にも注目します。このとき、レインズの成約事例や大手ポータルサイトの掲載期間を参照すると実勢がつかみやすいです。
一方で、空室は完全にゼロにできないと割り切り、損益分岐点をシミュレーションする姿勢も欠かせません。例えば、表面利回り7%の物件でも、空室率10%・家賃下落5%で実質利回りが4%台に落ち込むケースがあります。保守的な想定で収支を確認し、空室対策費や広告料を経費として事前に予算化しておけば、資金繰りに慌てずに済みます。
長期修繕費と建物寿命を読み解く
重要なのは、建物の経年劣化を数字で把握し、計画的に修繕積立を行うことです。区分マンションと異なり、一棟オーナーは修繕積立金を自動的に徴収されません。その結果、「気づいた時には大規模修繕が必要なのに資金が足りない」という事態が起こりがちです。
国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」では、RC造マンションの場合、外壁補修や屋上防水など大規模修繕の周期を12〜15年と示しています。仮に延床1,000㎡の物件で全面改修を行うと、1回あたり1,500万〜2,000万円が相場です。つまり、年間100万円超を積み立てて初めて資金不足に陥らない計算になります。
では、具体的にどう積み立てるか。実務では月々のキャッシュフローから一定額を別口座で封印する方法がシンプルです。また、2025年度の「省エネ改修等促進税制」を利用し、断熱材や高効率給湯器の導入コストを即時償却することで、実質的な負担を軽減するケースも増えています。修繕と同時に設備を高付加価値化すれば、家賃を維持・向上できる可能性も高まるでしょう。
金融情勢と融資条件の変化に備える
まず押さえておきたいのは、金利が1%上がると返済総額が数百万円単位で増えるという事実です。日本銀行は2024年にマイナス金利を解除し、市中金利は緩やかに上昇傾向にあります。2025年10月時点では、主要地銀の不動産投資ローン固定金利が平均2.1%前後となり、1年前より0.3ポイント上がりました。
金利変動リスクを最小化する手段としては、借入期間を短縮し元金を早く減らす、または固定金利期間選択型で最長期間を取るなどが考えられます。さらに、自己資金を2割以上用意すると融資審査が有利になり、金利優遇を得られる確率も高まります。日本政策金融公庫の融資は比較的金利が低い一方、物件エリアや築年数に制約があるため、複数行を比較して総返済額を試算することが肝心です。
一方で、返済比率が高い物件を無理に取得すると、空室や修繕費と重なった途端に返済困難に陥ります。シミュレーションでは、DSCR(債務返済余裕率)を1.3以上確保する保守的な数値を基準にすると、安全余裕が生まれやすいでしょう。
売却出口を計画する重要性
実は、一棟マンション投資の成否は「買うとき」ではなく「売るとき」に確定します。売却益や次の投資への資金回収を考えると、市場が活況な時期に出口を迎える戦略が理想です。不動産経済研究所のデータによれば、2025年10月の東京23区の新築マンション平均価格は7,580万円で前年比3.2%上昇し、都心部の需要は底堅いといえます。
しかし、郊外や人口減少地域では取引件数そのものが減少傾向です。買い手層が限られるエリアでは、売出価格を強気に設定しても成約しづらく、結果として利回りを上げて値下げするしかない場面が増えます。将来売却を見据えるなら、駅徒歩圏内・生活利便性・再開発予定など、需要が持続しやすい属性にこだわるべきです。
出口戦略には二通りあります。ひとつは個人投資家への売却、もうひとつはREITや法人への一括売却です。後者は規模や立地、築浅であるほど売却対象になりやすいという特徴があります。購入前から「誰に」「いつ」「いくらで」売れるのかを逆算し、保有中の賃料改定やリノベーションを計画的に実施することで、最終的なリターンを最大化できます。
まとめ
本記事では、一棟マンション リスクを空室・家賃下落、修繕費、金利変動、資産価値、出口戦略の五つの観点から整理しました。いずれも単独で完結するものではなく、相互に影響し合うため、包括的な対策が不可欠です。実際には、保守的な収支シミュレーションを行い、修繕積立をルール化し、融資は複数行で比較するだけでもリスク耐性は大きく向上します。最後に、常に出口を意識して物件の価値を高める運営を続ければ、変動の激しい市場でも安定した成果が期待できます。今日の学びを踏まえ、まずは気になるエリアの市場調査から一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅局「長期修繕計画作成ガイドライン」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局「住宅・土地統計調査 速報集計」 – https://www.stat.go.jp
- 不動産経済研究所「首都圏マンション市場動向 2025年10月」 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 日本銀行「金融経済月報 2025年9月」 – https://www.boj.or.jp
- 東日本不動産流通機構(レインズ)「マーケットウォッチ」 – https://www.reins.or.jp

