(導入段落) 不動産投資に興味はあるものの、実物を買うには資金も手間もかかる――そんな悩みを解決してくれるのがREITです。しかし銘柄は国内外あわせて数百に及び、利回りや値動きの差も大きいため、何を基準に選べばよいか迷う初心者が多いのも事実です。本記事では2025年9月時点の最新データをもとに、利回り、リスク、分散効果といった観点からREITを比較し、あなたに合った選択肢を見つける手順をわかりやすく解説します。読み終えれば、自信をもって商品を選び、着実に資産形成へ踏み出せるはずです。
REITとは何かを押さえよう
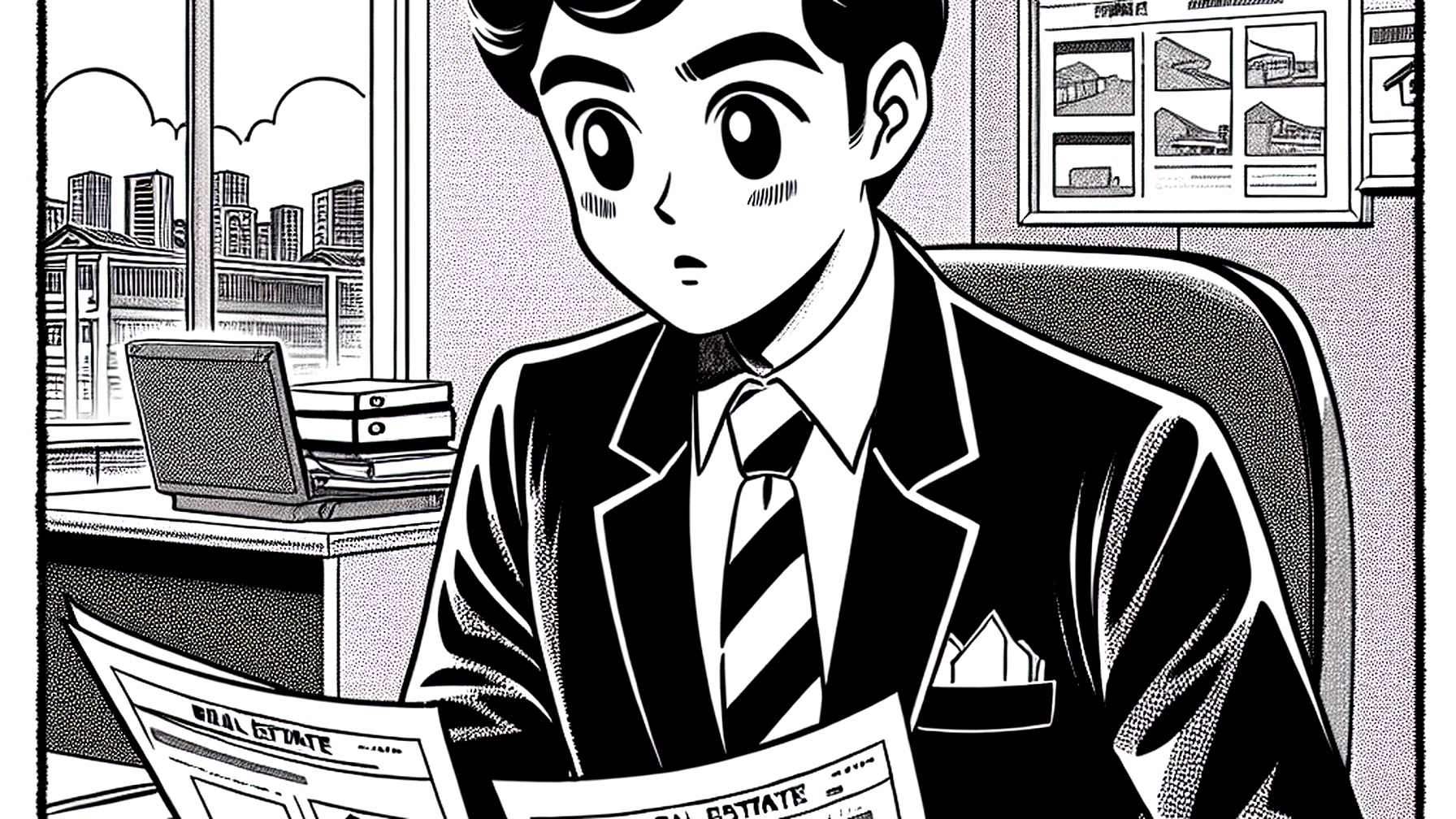
重要なのは、REITが「不動産を小口化して上場した投資信託」である点を理解することです。投資家は一口数万円から参加でき、賃料や売却益が分配金として支払われます。さらに株式市場で売買できるため換金性が高く、個人でも手軽に不動産収益をシェアできる仕組みです。
一方で、REITは株価と同様に市場価格が日々変動します。つまり配当利回りだけでなく、価格変動リスクも考慮する必要があります。2025年9月の東京証券取引所REIT指数は前年比で約6%上昇しましたが、2023年には逆に10%下落した期間もありました。値動きを理解せずに高利回りだけを追うと、短期的な下落に耐えられない可能性があるのです。
日本では上場REIT(J-REIT)が2001年に誕生し、現在は62銘柄が取引されています。オフィス、住宅、物流施設、ホテルといった用途別に分かれ、それぞれ収益構造が異なります。まずは「物件タイプ」「上場市場」「運用方針」という三つの視点で基礎を押さえることが、比較の第一歩となります。
国内REITと海外REITの違い
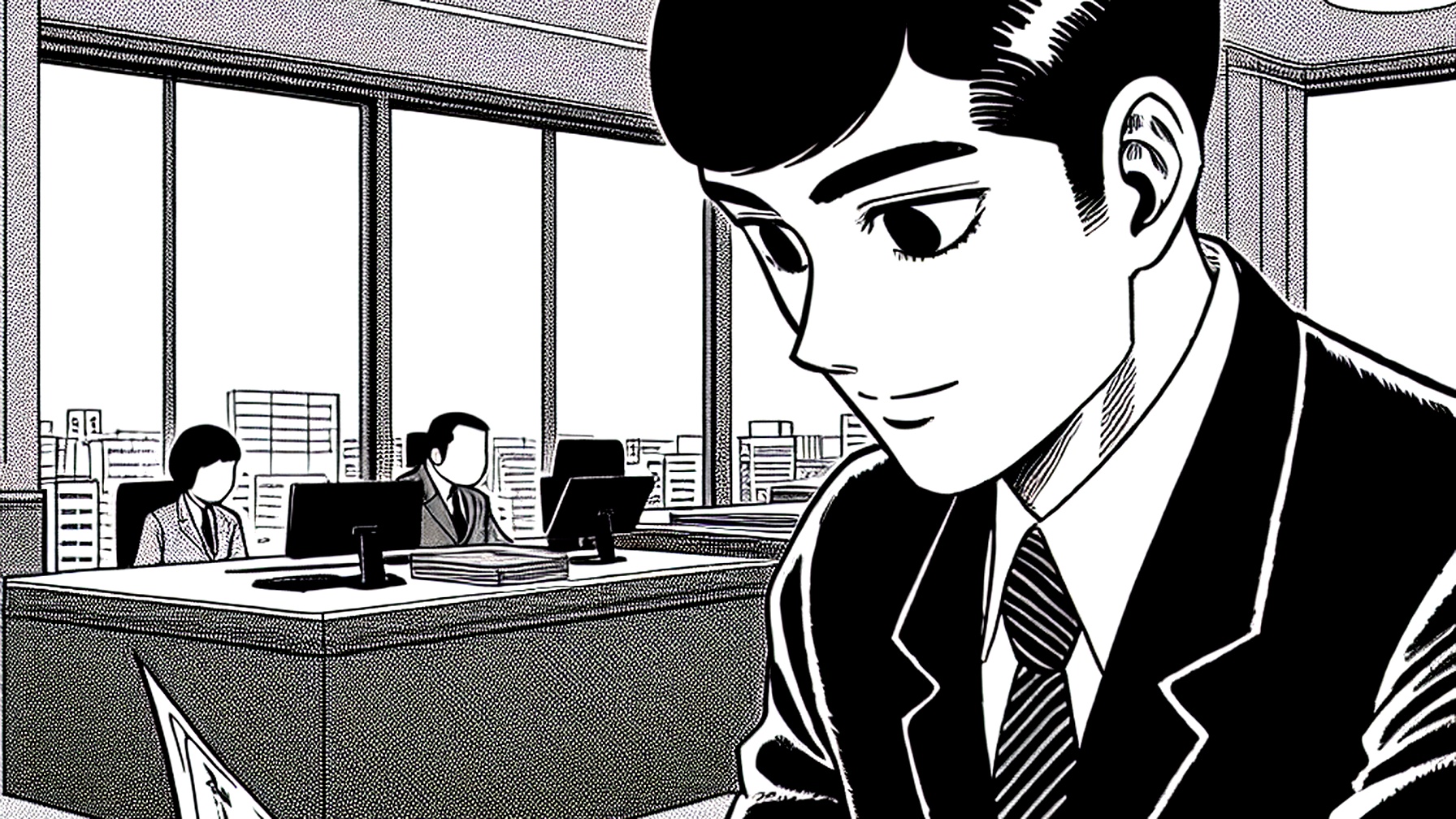
実は、国内REITと海外REITでは収益の源泉もリスク要因も大きく異なります。日本市場は人口減少を背景に安定志向の運用が多く、平均分配利回りは3.7%前後です。対して米国や豪州に上場するグローバルREITは4%超の利回りに加え、成長局面ではキャピタルゲインも狙える一方、為替変動が追加リスクとなります。
たとえば、2025年9月時点のMSCIワールドREIT指数は円建てで前年同月比11%上昇しましたが、その半分はドル高によるものです。言い換えると、円高に振れれば利回りはそのままでもトータルリターンが毀損する恐れがあります。この点を補うには為替ヘッジ付ファンドや、国内外を組み合わせた分散投資が有効です。
また、法規制の差も見逃せません。J-REITは投資法人ごとに資産の半分以上を不動産に投資する義務があり、レバレッジ(借入比率)は平均約44%です。一方で、米国REITは税制優遇を得る代わりに90%以上の利益を配当する義務が課され、借入比率は平均34%と低めです。レバレッジの違いは、景気悪化時の下落幅にも直結するので、国ごとの制度を理解して比較しましょう。
分配利回りとリスクを読み解くポイント
まず押さえておきたいのは、利回りだけでREITを選ぶと「高利回り=高リスク」の落とし穴にはまる点です。分配利回りは株価が下がれば上がるため、短期的な値下がり局面では一見魅力的に見えます。そこで「NAV倍率」と「LTV」という二つの指標を組み合わせることで、実質的な安全度を測ることができます。
NAV倍率は純資産価値に対する株価の割安度を示し、1倍を下回ると市場が資産価値を過小評価している状態です。ただし、オフィス系REITの平均NAV倍率は0.9倍前後と低い一方で、空室率悪化の懸念も織り込まれています。つまり割安に見える場合でも、将来収益の減少リスクを見極める必要があります。
LTVはLoan to Valueの略で、総資産に対する借入金比率を示します。J-REIT全体の平均は44%ですが、物流特化型の一部銘柄では50%を超えています。金利上昇局面では借入コストが収益を圧迫するため、LTVが高い銘柄ほど分配金減少のリスクが高まります。利回りと同時にLTVを確認することで、高利回りの裏に潜むリスクを可視化できます。
初心者が活用しやすい比較基準
ポイントは、複数の尺度を組み合わせて「相対評価」することです。具体的には、①分配利回り、②価格変動性(年率ボラティリティ)、③資産タイプ、④運用実績の四つを一覧表にまとめると、特徴が一目でわかります。金融庁の『指定統計 第50号投信統計』によれば、2024年度末時点でJ-REIT型投信の平均ボラティリティは年率13%、海外REIT型は17%でした。数字を並べることで、利回りだけでなく値動きの大きさも比較できるわけです。
たとえば、同じ4%利回りでもボラティリティが10%と15%では、損益の振れ幅が約1.5倍違います。そこで初心者は、まず平均以下のボラティリティで安定した利回りを確保する銘柄を選び、経験を積んでから高リスク高リターンの商品に挑戦するとよいでしょう。つまり、投資経験とリスク許容度を軸に、比較表を定期的に更新することが成功の近道です。
さらに、投資信託を活用すれば個別銘柄を選ばずに分散が可能です。2025年度もNISA制度は継続しており、成長投資枠でREIT型投信を購入すれば分配金に対する税金が非課税となります。制度を使うか否かで、手取り利回りは0.6%前後変わることもあるため、比較時には必ず税引後リターンで見るようにしましょう。
ポートフォリオ作成の考え方
まず、REITだけに偏ると景気後退時に大きな損失を被る恐れがあるため、株式や債券との組み合わせが不可欠です。一般的には「REIT10~20%、株式40%、債券40%」のような配分が推奨されますが、ここでも利回りとボラティリティを基に自分の許容範囲を設定します。
直近三年間のデータでは、J-REITと日本国債の相関係数は0.2程度にとどまり、分散効果が高いことがわかります。また、米国REITと米国株の相関は0.6前後とやや高めですが、為替を含めると日本の投資家にとってはさらに値動きが異なるため、適度に組み入れることでポートフォリオ全体のリスクを抑えつつリターンを押し上げられます。
最後に、年に一度はリバランスを行い、目標比率から大きく乖離した資産を売買してバランスを整えましょう。これにより、高値掴みや安値売りを防ぎ、長期的に安定した収益を確保できます。リバランスは感情を排した定期的なルール運用が効果的であり、初心者ほどルールを決めて機械的に実行することが大切です。
まとめ
REITは少額で不動産収益を得られる便利な商品ですが、利回りだけでなくLTVやボラティリティを加味した比較が欠かせません。国内外で制度や為替リスクが異なる点を理解し、複数指標を使った相対評価で自分に合った銘柄や投信を選ぶことが、安定運用への近道です。まずは分散効果の高い商品を中心に少額から始め、毎年リバランスを行いながら経験値を積み上げていきましょう。堅実な比較と継続的な見直しこそが、長期的な資産形成を後押ししてくれます。
参考文献・出典
- 東証REIT指数月次リポート – https://www.jpx.co.jp
- 金融庁 投信統計(指定統計 第50号) – https://www.fsa.go.jp
- MSCI ワールドREITインデックス ファクトシート – https://www.msci.com
- 国土交通省 不動産市場動向レポート2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 統計データ「資金循環統計」 – https://www.boj.or.jp

