アパート経営を始めたいけれど、どの街を選ぶべきか分からない。家賃相場や利回りの数字だけを追っても、入居者が集まらなければ収益は安定しません。そこで本記事では、立地選定で失敗しないための具体的な判断軸を、最新データと実務経験を交えて解説します。読み進めれば、初心者でも自信を持ってエリアを絞り込む手順が分かります。
なぜ立地が収益を左右するのか
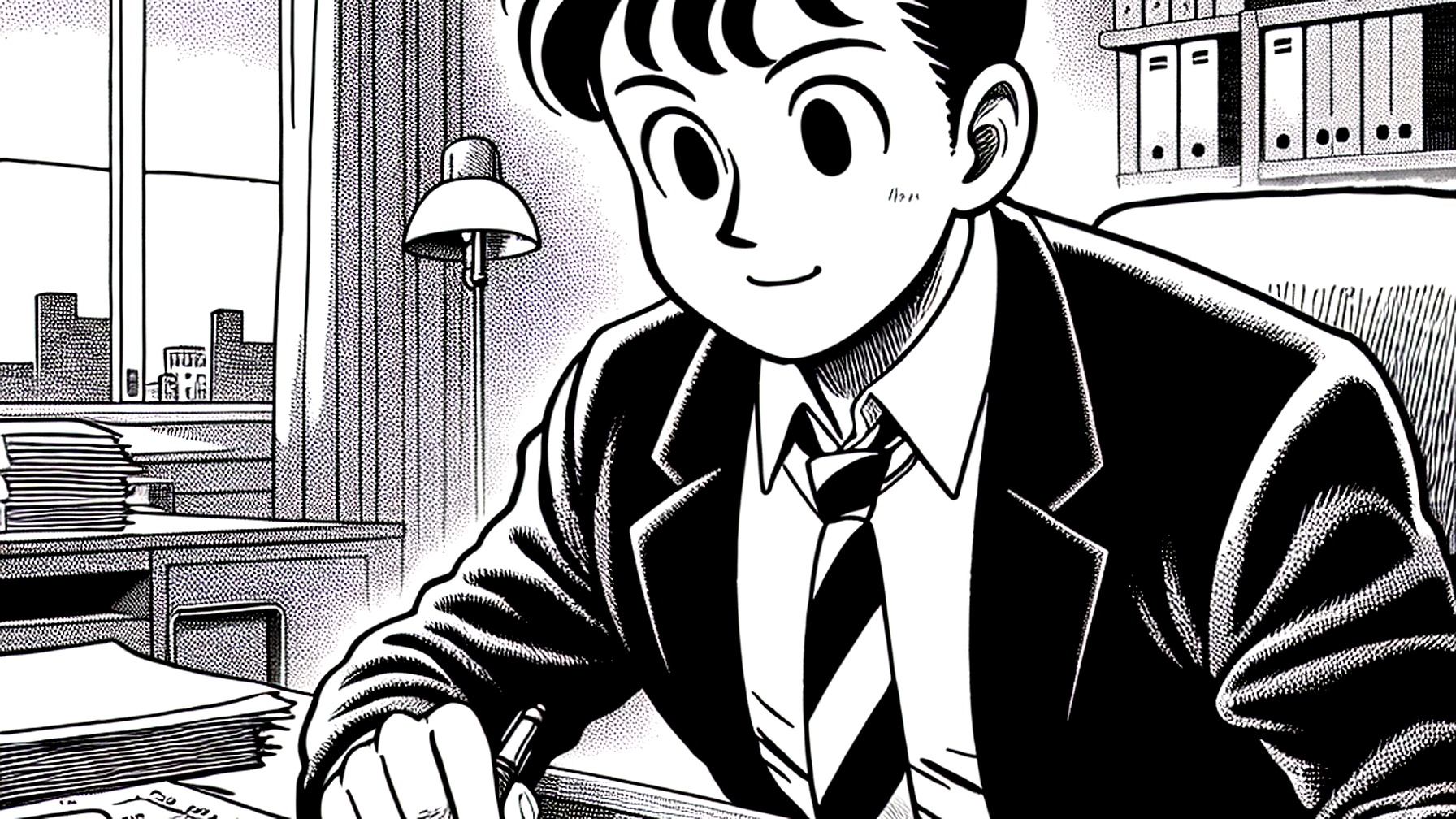
重要なのは、立地が家賃水準だけでなく空室率と修繕コストにも影響する点です。入居者の目線を想像しながら、収益全体を左右する仕組みを捉えましょう。
まず立地と収益の直接的な関係として、空室期間の長さがあります。国土交通省の2025年7月データによると、全国平均のアパート空室率は21.2%ですが、駅徒歩10分圏の物件では15%前後にとどまります。つまり同じ利回りでも駅近エリアはキャッシュフローのブレが小さいのです。一方、郊外に利回りの高い物件を購入しても長期空室が続けば、想定収益を下回るリスクが高まります。
また立地は修繕コストにも関係します。築古物件を中心に、海沿いの地域では塩害の影響で外壁や鉄部が早期に傷み、結果的に維持費が膨らむ傾向があります。内陸部であれば同程度の築年数でも補修サイクルが長くなるため、長期的には収支差が顕著に表れます。このように立地は見えにくい支出まで左右します。
経験上、立地判断を数字だけに頼ると、将来の行政計画や人口動向の変化を見逃しがちです。都市計画が進むエリアは道路拡張や商業施設の誘致で住環境が向上し、家賃上昇余地が期待できます。逆に中心街から離れた工業地域が再編される場合、転入需要が一時的に落ち込むこともあります。定性的な情報を組み合わせて判断する姿勢が欠かせません。
賃貸需要を見抜く人口動態の読み方
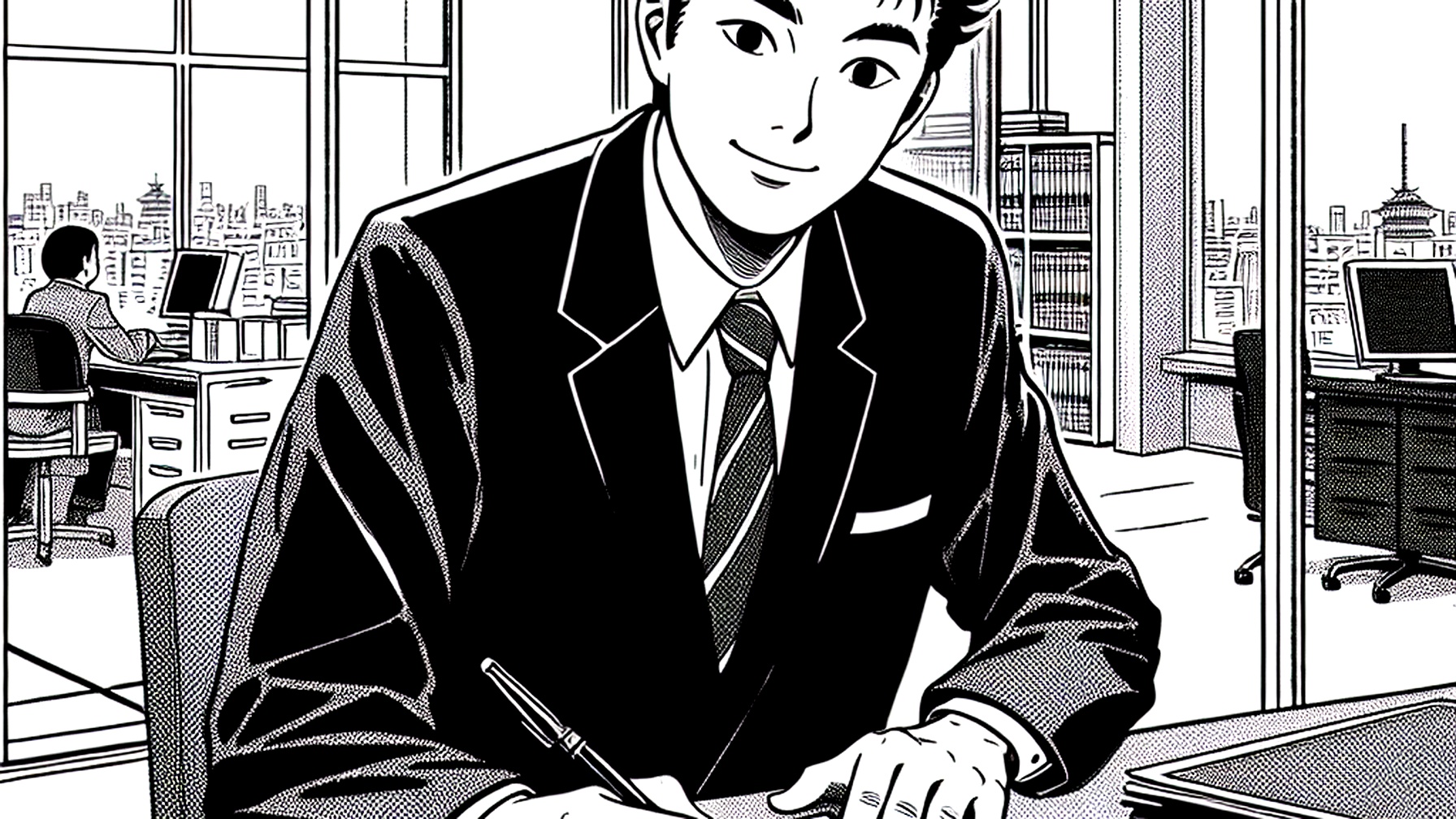
まず押さえておきたいのは、人口の増減を見るだけでは不十分という点です。年齢構成や世帯数を合わせて分析することで、将来の入居者像が具体的に浮かび上がります。
総務省の2025年8月推計では、全国の総人口は前年比0.6%減となりましたが、25〜39歳の生産年齢人口が増えた市区町村は全体の12%存在します。若年層の伸びはワンルームやコンパクトタイプの需要増につながるため、アパート経営には好材料です。表面利回りだけでなく対象世代の人数が増えているかを確認する習慣を付けると、空室リスクを抑えられます。
一方で、総人口が横ばいでも世帯人数が減っている地域は、単身者向けの需要が伸びる可能性があります。ファミリー向けから単身向けへ住戸ニーズが変わる転換期を捉えれば、築古物件を間取り変更して収益力を高める戦略も選択肢に入ります。このように人口統計はリフォーム計画とも密接に絡みます。
実は人口動態のデータは無料で詳細を取得できます。国勢調査の小地域集計を使えば駅ごとの年齢別人口が把握でき、周辺開発の資料と重ねることで将来像が精緻になります。データ取得に30分ほどかけるだけで、年間家賃数百万円の差を生む意思決定が可能になるという点を覚えておきましょう。
交通・生活インフラのチェックポイント
ポイントは、単に最寄り駅の距離を測るだけでなく、生活インフラの重なりを調べることです。日常の利便性は入居期間を延ばし、結果として収益を安定させます。
交通面で最も分かりやすい指標は通勤時間です。東京圏では総務省の社会生活基本調査によると、片道50分を超えると転居検討率が急上昇します。つまり駅からの距離が近くても都心へのアクセスが悪い路線では長期入居が見込みにくいのです。路線情報と運行本数まで確認し、通勤ドアツードア時間を推定する姿勢が求められます。
さらにスーパーや病院、保育園の分布を地図上で可視化すると、生活利便性の差が一目で分かります。たとえば新設された大型スーパーは集客力が高く、近隣家賃水準を押し上げるケースが多いです。逆に小学校統廃合が予定されている地区ではファミリー層の流出が進むことがあります。行政の公開資料で施設の新設・廃止計画を確認しておくことをおすすめします。
近年は災害リスクが立地選定で重視されています。ハザードマップで浸水想定を調べ、必要な保険料と修繕積立額を試算すると、表面利回りだけでは見えない実質利回りが見えてきます。特に海抜が低い湾岸部の物件は水害による設備故障で空室が長期化する事例が後を絶ちません。保険料が高くても安定収益を守れるか、冷静に比較することが重要です。
利回りとリスクを両立させるエリア戦略
実は、高利回りと低リスクは必ずしも相反しません。エリアを分散し、物件タイプを変えることで両立させる余地があります。
まず都市中心部では利回りが低めでも空室期間が短いという特徴があります。平均家賃が8万円、利回り5%でも年間空室1カ月以内であれば実質利回りは4.6%程度に収まります。一方、郊外で利回り8%を確保しても3カ月の空室が続くと、同様に4.6%まで下がる計算です。表面利回りだけでなく空室期間を差し引いた実質利回りを同じ土俵で比較することが不可欠です。
また、周辺エリアの再開発計画を味方につけると、購入時の利回り以上のキャピタルゲインが狙えます。たとえば地方中核市で進む駅前の再開発では、完成後に家賃が10%上昇した実例があります。完成3年前に物件を取得していた投資家は想定より早く収益が伸び、売却益も確保できました。時間軸を含めた戦略思考が成果を左右します。
リスク分散として複数エリアに小規模物件を保有する方法もあります。修繕や空室が同時に発生する確率を低くでき、資金繰りの安定感が増します。金融機関の評価が高まると追加融資を受けやすくなる点もメリットです。ただし管理会社との連携コストが増えるため、物件間の距離を車で1時間以内に収めるよう意識すると運営効率が落ちません。
2025年度の支援制度と税制を踏まえた選定
まず押さえておきたいのは、制度を活用して初期費用と運営コストを抑える視点です。適用条件を満たすエリアを選べば、表面利回りを超える実質利回りが期待できます。
2025年度の住宅ローン減税は、省エネ性能を満たす賃貸併用住宅で年間最大28万円の控除が受けられます。該当する建物は断熱性能などの基準をクリアする必要がありますが、地方でも新築アパートの多くが対応可能です。つまり省エネ基準に適合した新築物件を選べば、初年度から税引き後キャッシュフローが向上します。
さらに、国土交通省が継続実施する賃貸住宅省エネ改修補助では、既存アパートの断熱改修費用の最大三分の一(上限150万円)が補助されます。築古物件を安く取得し、この補助で性能を底上げすれば、リノベーション直後から家賃アップを図ることが可能です。補助金は年度予算がなくなり次第終了するため、計画段階で施工業者と申請スケジュールを確認しておきましょう。
税制面では、固定資産税の新築軽減措置が2025年度も継続します。床面積要件や貸室割合を守れば、竣工から3年間は税額が半減されるため、都市部の木造アパートで年間20万円前後の負担減となります。この効果を加味すると、新築と築浅の収益差が縮まり、エリア選定の自由度が広がります。制度を正しく理解し、対象エリアでの物件探しを優先することで、資金計画に余裕が生まれます。
まとめ
立地選定では人口動態、交通・生活インフラ、制度の三つを重ねて判断することが鍵です。特に空室率、通勤時間、災害リスクを具体的な数字で比較し、実質利回りを算出すれば、表面利回りに惑わされません。さらに2025年度の税制や補助金を取り入れれば、同じ物件でも収益の手取りが大きく変わります。結論として、データと現地調査を組み合わせ、制度活用まで含めた総合戦略を立てることが、アパート経営 立地選定 成功法の最短ルートです。今日から一歩ずつ情報を集め、理想の物件を見つけてください。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅統計調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp/statistics/
- 総務省統計局 人口推計 2025年8月 – https://www.stat.go.jp/data/jinsui/
- 国土交通省 都市計画現況調査 2025 – https://www.mlit.go.jp/toshi/
- 財務省 令和7年度税制改正のポイント – https://www.mof.go.jp/
- 厚生労働省 子育て環境整備データ 2025 – https://www.mhlw.go.jp/

