不動産投資を始めたいけれど、「失敗したらどうしよう」と不安を感じる人は多いものです。特にネット上には「家賃が入らない」「ローン返済が苦しい」といった体験談が並び、踏み出せずにいる読者もいるでしょう。本記事では、そうした悩みに寄り添いながら「不動産投資 リスク なぜ」という疑問に答えます。投資歴15年の筆者が、市場動向や融資、運営、制度変更まで幅広く整理し、具体的な対策まで提示します。読み終えたとき、リスクの正体がクリアになり、一歩踏み出す判断材料が手に入るはずです。
リスクはどこから生まれるのかを理解する
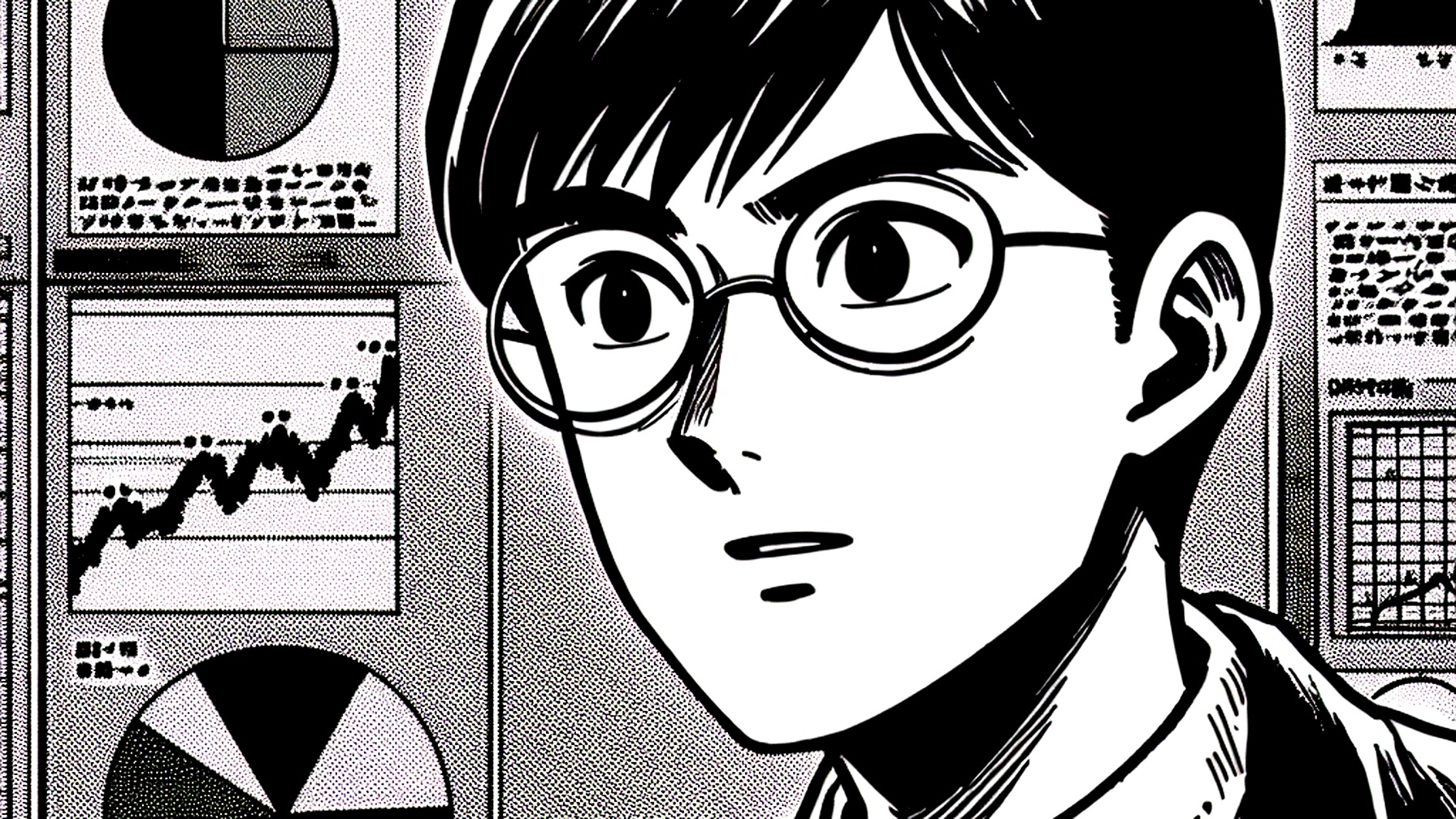
まず押さえておきたいのは、リスクは偶然ではなく仕組みから生まれるという点です。不動産は賃料と価格の両面で収益が動く実物資産です。そのため、賃貸需要、金利、法律の三要素が変動すると結果としてリスクが顕在化します。
最初の要因は賃貸需要です。国土交通省の住宅・土地統計調査(2023年最新)によると、全国平均の空室率は13.6%ですが、地方の一部では20%を超えます。需要が弱ければ家賃は下がり、入居期間も短くなります。
次に金利です。日銀のデータでは、住宅ローン変動金利は2024年末時点で平均0.6%程度でしたが、2025年9月現在は1%台前半に上昇しています。返済額が増えればキャッシュフローが圧迫され、投資家の心理的負担も増します。
最後が法制度です。例えば2024年に改正された賃貸住宅管理業法は、管理会社の登録制を強化しました。ルールが厳格化されると、オーナーは委託費用や手続き面で新たな負担を負うことになります。つまり、需要・金利・法制度の変化を読み解く力がリスク管理の出発点となるわけです。
市場リスクとどう向き合うか
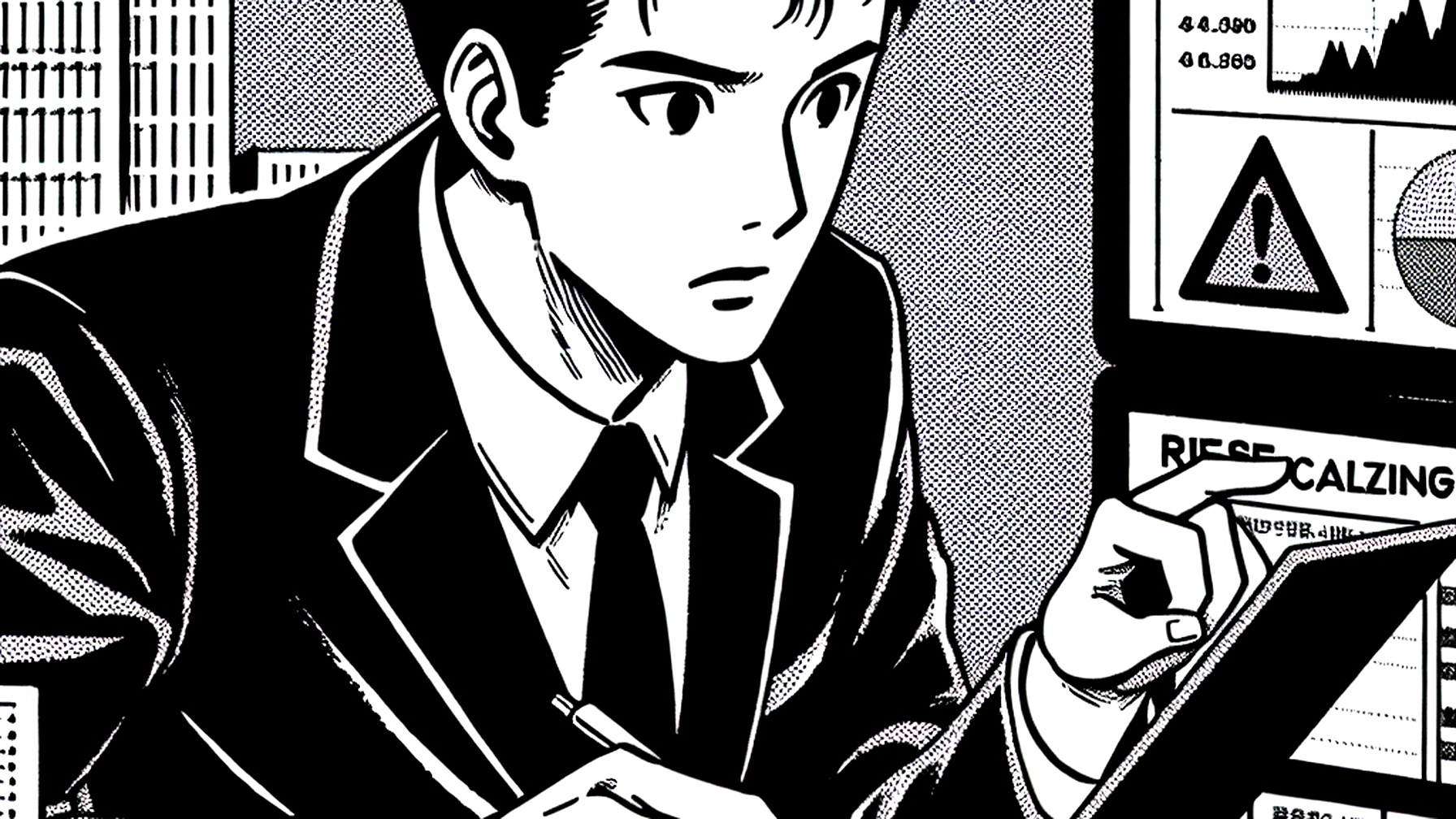
ポイントは人口動態と再開発計画を複眼的に見ることです。賃貸需要は人口の数だけでなく、世帯構成やライフスタイルでも左右されます。
2025年版の国立社会保障・人口問題研究所の推計では、全国の総人口は2030年に1億1,800万人まで減る見込みです。しかし、東京23区の単身世帯はむしろ増加が続くと予測されています。つまり、全国平均の数字だけで悲観するのは早計で、エリア別に需要を調べる姿勢が重要になります。
加えて、自治体の再開発計画を追うことで将来の賃料上昇余地を把握できます。東京都の「虎ノ門・麻布台プロジェクト」や大阪市の「うめきた2期」など、大規模再開発エリアでは基準地価が前年比10%以上上昇した事例があります。
一方で、郊外のニュータウンでは高齢化が進み、空室率が上がっています。地域経済の活力が弱いエリアは賃料が維持できず、出口戦略としての売却も難しくなる点に注意が必要です。こうしたデータを踏まえ、投資対象を都心一極集中にするか、地方中核都市に分散させるか、自身のリスク許容度で戦略を選びましょう。
ファイナンスリスクを抑える借入戦略
実は、同じ物件でも融資条件次第でリスクは大きく変わります。金融機関は物件の評価額と投資家の属性を見て融資期間と金利を決定しますが、投資家側はキャッシュフローのゆとりを確保する工夫ができます。
まず自己資金は物件価格の2〜3割を目安にすると安全度が上がります。頭金を厚くすると借入額が減り、毎月返済が軽くなるためです。返済比率は家賃収入の50〜60%以下が望ましく、70%を超えると金利上昇や空室時に赤字転落しやすくなります。
借入期間は耐用年数に合わせるのが基本ですが、余裕を持って長めに設定し、キャッシュフローを確保する方法もあります。その場合でも、繰り上げ返済用の資金を別に積み立てておくと、金利が急上昇した際に負債を圧縮できるため安心です。
日本政策金融公庫や一部地銀では、2025年度も不動産投資向け融資プランを継続しています。固定金利2%前後、期間15年以内と条件は厳しめですが、金利変動リスクを抑えたい人には選択肢となります。複数行に同時相談し、変動・固定を組み合わせてポートフォリオを作る考え方が、ファイナンスリスクの分散につながります。
運営リスクを軽減する管理のコツ
重要なのは、空室と修繕という二大コストをコントロールできる体制を整えることです。入居付けが弱い管理会社に任せきりにすると、家賃収入が途絶える期間が長くなります。
そこで、管理委託契約書の内容を細かくチェックしましょう。2021年の法改正で標準契約書が示されましたが、広告費や客付け手数料の負担割合は会社ごとに違います。募集広告の頻度や方法を数値で確認し、早期成約のインセンティブが働く仕組みを整えると空室期間を短縮できます。
次に修繕です。国土交通省の長期修繕計画標準様式によれば、外壁は12年、屋上防水は15年で大規模修繕が推奨されています。築10年を過ぎたら毎月1平方メートルあたり200〜300円程度を修繕積立金として計上すると、急な出費でキャッシュフローが崩れるリスクを下げられます。
さらに、入居者トラブルを迅速に解決する窓口も大切です。騒音やゴミ出しの苦情が放置されると退去につながり、評判が落ちます。2025年9月時点で多くの管理会社がオンラインのチャット窓口を導入しており、24時間対応の仕組みを選択すると満足度が向上し、結果として長期入居につながります。
法制度・税制が変わるリスクへの備え
ポイントは、制度変更を「読んで備える」姿勢を持つことです。不動産投資では税制優遇や建築規制が変わるたびに損益が動きます。
2025年度も住宅ローン減税は自宅用が中心で、賃貸用には適用されませんが、固定資産税の住宅用地特例は引き続き有効です。具体的には、200平方メートル以下の住宅用地は課税標準が1/6に軽減されるため、戸建てや小規模アパートの保有コストが抑えられます。
一方、都心の高層マンションを対象に「不動産取得税の重課」が検討されています。まだ法案段階ですが、高額物件ほど税負担が増える可能性があるため、投資家は最新の国会審議を確認しながら購入時期を判断する必要があります。
また、首都圏を中心に進む防災強化条例は、旧耐震基準のビルに対して耐震改修を義務化する流れです。対象物件を保有する場合、改修費が1室あたり数百万円規模になることもあり、事前に建物診断を行い、費用と工期のシミュレーションをしておくと想定外の損失を防げます。
まとめ
結論として、リスクは「知らないこと」から生まれます。賃貸需要、金利、法制度の三つをデータで把握し、借入と運営を仕組みで管理すれば、大きな失敗は避けられます。市場分析で需要の底堅いエリアを見極め、自己資金を厚めにして金利上昇に備え、信頼できる管理会社と組み、制度変更には常にアンテナを張る。こうした基本を徹底することで、不動産投資は堅実な資産形成の手段となります。今日得た知識をもとに、まずは気になるエリアの人口データと融資条件を調べ、一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅・土地統計調査(2023年) – https://www.stat.go.jp
- 国立社会保障・人口問題研究所 将来人口推計(2025年版) – https://www.ipss.go.jp
- 日本銀行 金融経済統計月報(2025年8月) – https://www.boj.or.jp
- 国土交通省 地価公示・基準地価データベース(2025年) – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 固定資産税に関する資料(2025年度) – https://www.soumu.go.jp

