不動産投資に興味はあるものの、物件価格の高騰や利回りの低下に悩む読者は少なくありません。とくに首都圏では表面利回り5%を切る案件も珍しくなく、資金効率の良い入口を探すのは容易ではないでしょう。そこで注目したいのが「競売物件」を活用した投資手法です。落札価格が市場相場より安くなる可能性が高く、自己資金を抑えながらキャッシュフローを厚くできる点が最大の魅力となります。本記事では収益物件を競売で取得する際の流れ、リスク管理、2025年度の制度活用までを網羅的に解説します。初めてでも理解しやすいよう、データと具体例を交えて順を追って説明しますので、最後までお付き合いください。
競売物件が収益物件として有利な理由
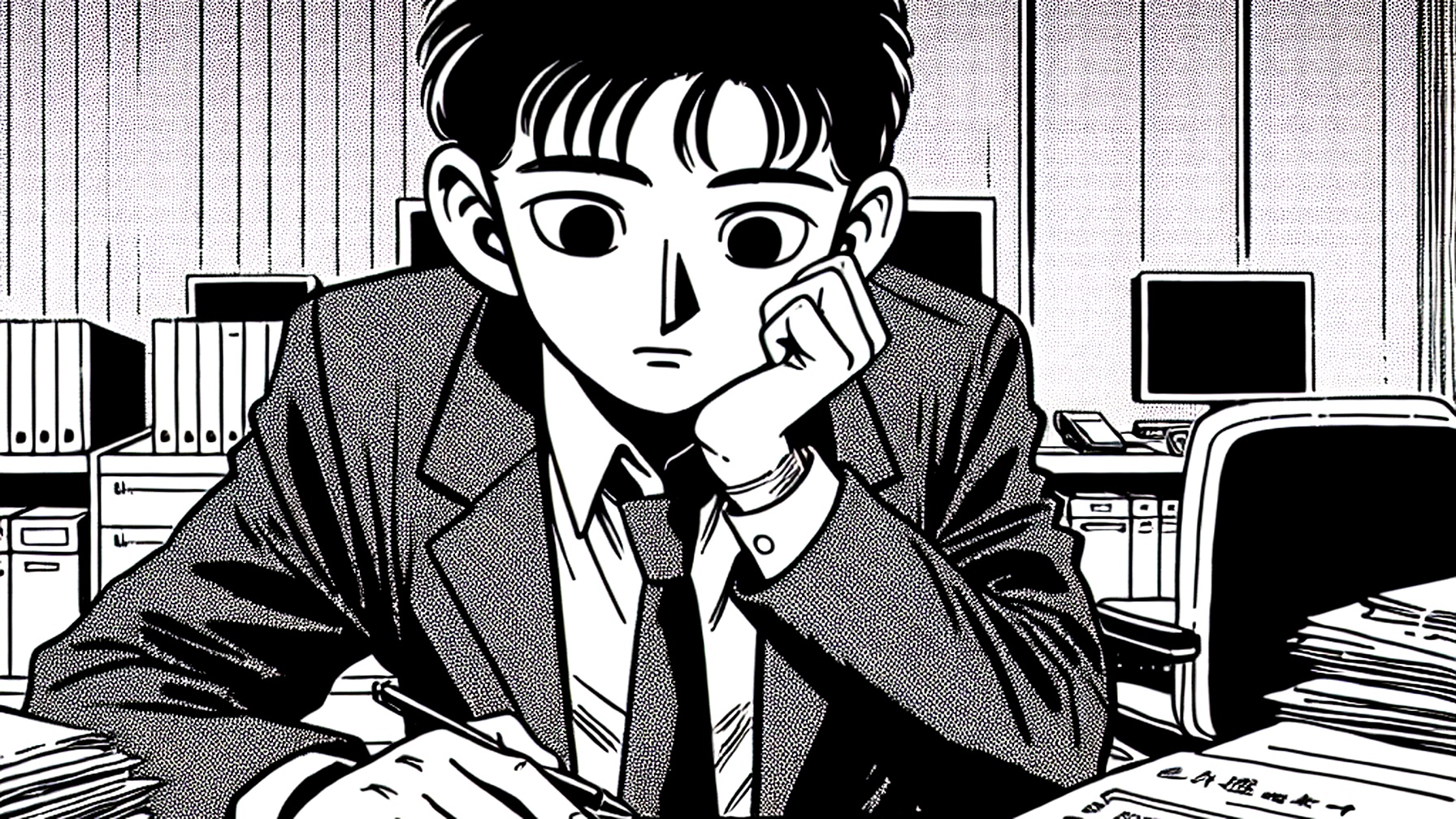
まず押さえておきたいのは、競売物件が市場流通物件と比べてどのような優位性を持つかという点です。最大のポイントは価格面で、裁判所が設定する「売却基準価額」は一般相場の7〜8割程度に収まるケースが多いとされます。
総務省「住宅・土地統計調査」によると、2024年時点の首都圏中古マンション平均価格は約4,800万円でした。一方、最高裁判所の競売統計を見ると、同エリアの平均落札価格は3,600万円前後にとどまっています。この差額を自己資金圧縮だけでなく、リフォームや広告費に再投資できる点が収益性を高める鍵になります。また、競売は物件情報が全国共通フォーマットで公開されるため、検索や比較が容易です。実は初めての投資家ほど、情報格差が少ない競売市場でチャンスをつかみやすいという側面もあります。
一方で、内覧が難しい、占有者対応が必要など固有のリスクも存在します。そこで次のセクションでは、具体的な参加手順と準備事項を整理し、リスクを最小化しながら高い利回りを得る方法を解説します。
競売に参加する流れと資金計画
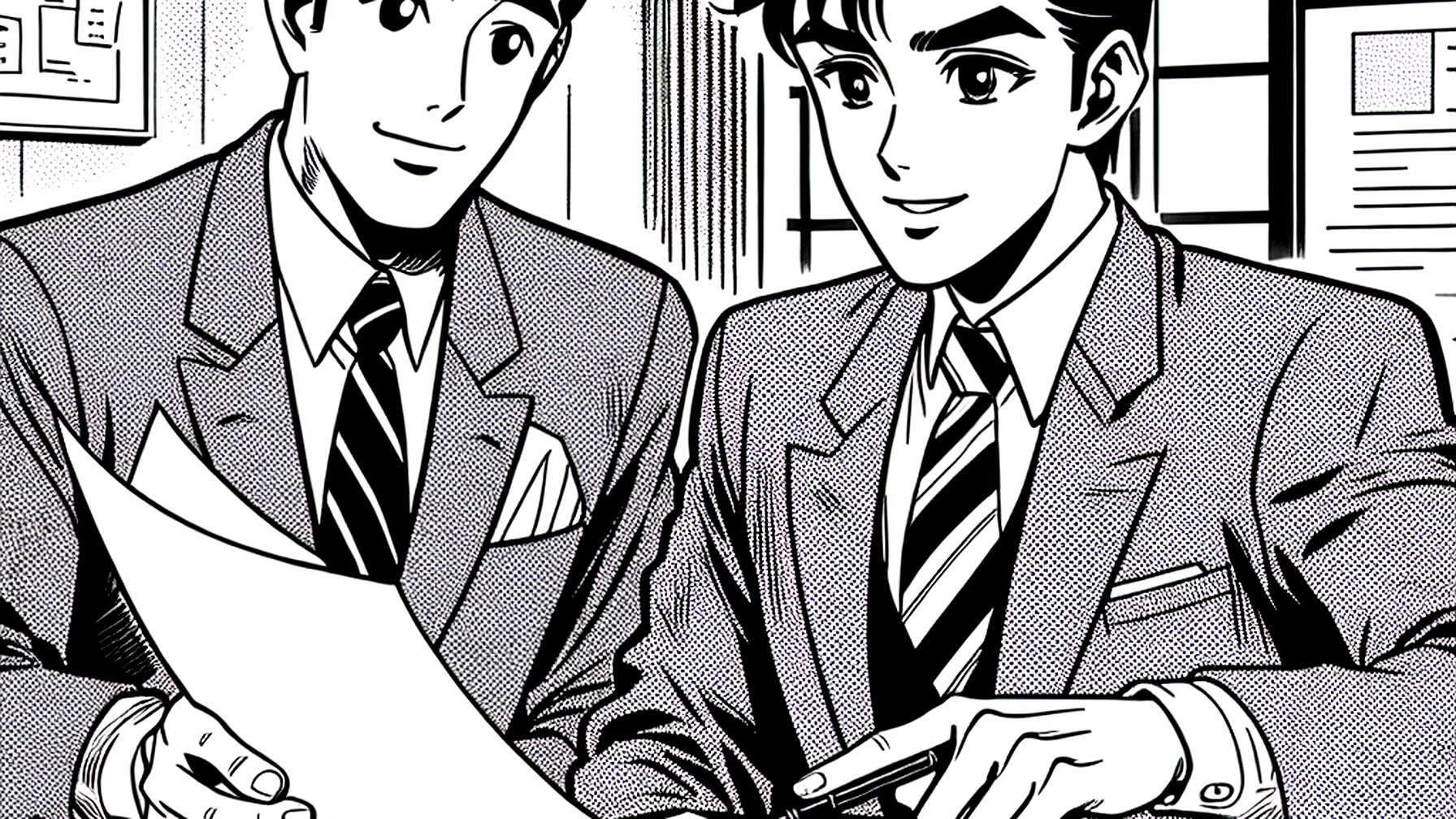
重要なのは、参加の手順を事前に理解し、資金計画を余裕を持って組むことです。競売は申込保証金の納付や入札書類の作成など、通常の売買より事務的プロセスが多くなります。
まず、法務省の「BIT(不動産競売物件情報サイト)」でエリアと種別を絞り込み、3点セットと呼ばれる調査書類を丹念に読み込みましょう。物件明細書で抵当権や差押え順位を確認し、現況調査報告書で占有状況を把握します。そして評価書をもとにリフォーム想定額を試算し、総投資額に対する想定家賃を算定します。この時点で表面利回り10%以上、実質利回り7%台を確保できるかが一つの判断基準になります。
資金面では、入札前に売却基準価額の2割程度を保証金として裁判所に納付する必要があります。落札後は通常2週間以内に全額を納付しなければならないため、融資打診は入札前に済ませておくことが必須です。地銀や信用金庫は競売案件でも融資実績があり、事前に物件概要と概算利回りを提示すると審査がスムーズに進みます。なお、自己資金比率は2〜3割が目安ですが、2025年度も続く金融庁の融資姿勢は「事業性評価重視」です。家賃相場や空室リスクを盛り込んだ事業計画書を用意し、将来の金利上昇にも耐えられる返済計画を示すことが成功の鍵となります。
リスクを可視化する調査と価格設定
ポイントは、見えにくいリスクを数値化し、落札上限額をブレずに決めることです。競売で避けたいのは、想定外の修繕や立ち退き費用が発生し、利回りが一気に低下するケースです。
まず、現地外観を確認し、外壁や屋上防水の劣化度合いを推定します。国土交通省の「長寿命化修繕計画策定ガイドライン」によれば、築25年のRC造マンションでは大規模修繕費が1戸あたり平均80万円程度見込まれます。これを基準に積立不足分を算定し、取得後3年以内に必要な支出を計上します。次に、近隣の賃料相場は不動産ジャパンやレインズの成約事例を用い、家賃帯の妥当性を検証します。家賃設定を1,000円誤ると年間収入が12万円変動するため、利回りへの影響は小さくありません。
占有者の退去交渉が必要な場合は、平均的な立ち退き料として50万円前後を想定し、期間は6か月程度を見込むのが実務的です。以上のコストをすべて含め、期待する実質利回りが達成できる上限価格を決めます。実は、この「逆算方式」を徹底できれば、入札時に感情的な競り上がりを避けられ、長期的に安定した収益が見込めるようになります。
競売物件を運営しキャッシュフローを安定させるコツ
基本的に、競売で取得した収益物件は「購入から6か月」が勝負です。この期間にリフォーム、入居付け、管理体制の構築まで完了させると、その後の運営が格段に楽になります。
リフォームでは費用対効果を意識し、キッチンや水回りは設備グレードを1ランク上げると家賃を月3,000円程度引き上げられるケースがあります。実際、レインズの2024年データでは、築20年以上のマンションでも水回りを更新した部屋は平均入居期間が1.4倍に伸びています。次に、管理会社選定では空室対策実績とレポート頻度を重視しましょう。入居率95%超の会社は広告費やオンライン内見ツールを積極投入しており、オーナー負担が減る傾向にあります。運営面では青色申告による65万円控除(電子申告の場合)や減価償却費を最大限活用し、税引後キャッシュフローを厚くすることも忘れてはいけません。
さらに、法人化による節税や資金調達力の向上を検討するのも一手です。資本金1,000万円未満で設立すれば、最長2年間は消費税免税となり、取得時の消費税還付スキームを用いる余地が生まれます。ただし、税制は毎年見直されるため、2025年度以降も適用を受けるには税理士と綿密に相談することが重要です。
2025年度の制度活用と今後の展望
実は、競売物件のリフォーム費用にも使える補助制度が存在します。国土交通省と経済産業省が共同で実施する「住宅省エネ2025キャンペーン」は、賃貸住宅の断熱改修や高効率給湯器の導入に対して最大50万円(戸当たり)の補助が受けられます。申請期間は2025年12月末までですが、予算枠に達し次第終了となるため、早めの申請が肝心です。
税制面では、不動産所得に対する損益通算や青色申告特別控除は2025年度も継続します。また、登録免許税の軽減措置は投資用物件には適用されませんが、固定資産税は新築賃貸住宅に限り3年間1/2となる特例が維持されています。築古の競売物件を取得後に建替えを検討する場合、この特例を視野に入れると長期的な利回りが向上します。
国土交通省の不動産価格指数によると、2023年から2024年にかけて全国の住宅価格は平均で6%上昇しましたが、2025年上半期は上昇幅が2%台に鈍化しています。金利も長期国債利回りが1%前後で推移しており、今後の利上げリスクをにらみつつも、割安に仕入れられる競売市場は依然として魅力的と言えるでしょう。つまり、制度を活用しながら低コストで取得し、適切な運営で利回りを高める戦略がますます重要になります。
まとめ
ここまで、収益物件を競売物件で取得するメリットと実践手順を解説してきました。市場価格より安く購入できる点は大きな利点ですが、調査不足による想定外コストが利益を食いつぶすリスクもあります。だからこそ、3点セットの読み込みと現地調査でリスクを数値化し、落札上限額を明確に設定する姿勢が欠かせません。落札後は6か月以内にリフォームと入居付けを完了し、青色申告や住宅省エネ補助金など2025年度の制度を積極的に活用しましょう。行動に移すことでしかチャンスはつかめません。まずはBITで気になる物件を検索し、シミュレーションから始めてみてください。
参考文献・出典
- 最高裁判所 競売統計データ – https://www.courts.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 2023年速報 – https://www.stat.go.jp
- 法務省 不動産競売物件情報サイト(BIT) – https://bit.sihd-bk.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 2025年6月公表値 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省・経済産業省 住宅省エネ2025キャンペーン資料 – https://jutakushiene2025.go.jp

