不動産投資に興味はあっても、「実質利回り」という言葉に戸惑う人は少なくありません。表面利回りより低い数字を見て不安になり、投資をためらう読者も多いでしょう。しかし、実質利回りを正しく理解すれば、物件の真の収益力が分かり、失敗リスクを大幅に下げられます。本記事では、なぜ実質利回りが重要なのかを基礎から解説し、2025年の最新データを踏まえて具体的な計算方法や改善策まで掘り下げます。最後まで読めば、自分に合ったマンション投資の判断軸が得られるはずです。
実質利回りとは何を示す指標か
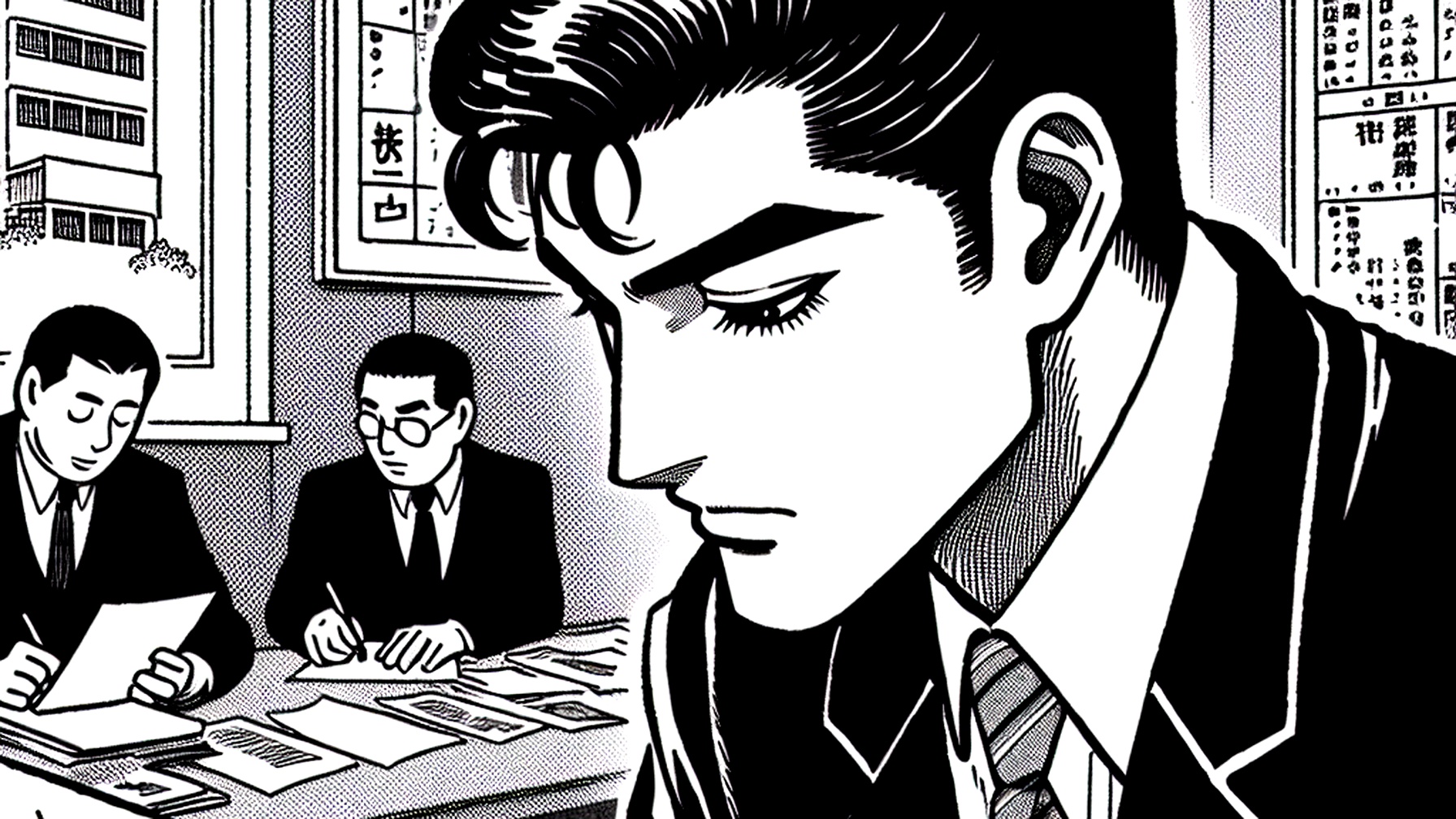
まず押さえておきたいのは、実質利回りが手元に残るキャッシュを示す指標だという点です。家賃収入から運営費用や税金を差し引いた後の利益を、物件取得総額で割って算出します。表面利回りより厳しい数字になるものの、現実的な投資判断には欠かせません。
実質利回りを計算する際は、管理費、修繕積立金、火災保険料、固定資産税などを含めます。さらに、新築時の登録免許税や不動産取得税、仲介手数料も取得総額に加える必要があります。こうした諸費用を見落とすと、収支シミュレーションが甘くなり、予期せぬ赤字を招きかねません。
日本不動産研究所の2025年9月データによると、東京23区のワンルームマンション平均表面利回りは4.2%です。一方、同条件で諸費用を考慮した実質利回りは概算で2.8%前後まで下がるケースが多いと報告されています。つまり、実質利回りを無視すると、収支が実態より1.4ポイントも高く見えてしまうわけです。
投資家にとって重要なのは、金融機関の返済や長期修繕といった支出をカバーし、安定的に黒字を維持できる数字かどうかです。実質利回りは、その安全余裕を測る物差しとして機能します。
表面利回りと実質利回りの差が生まれる理由
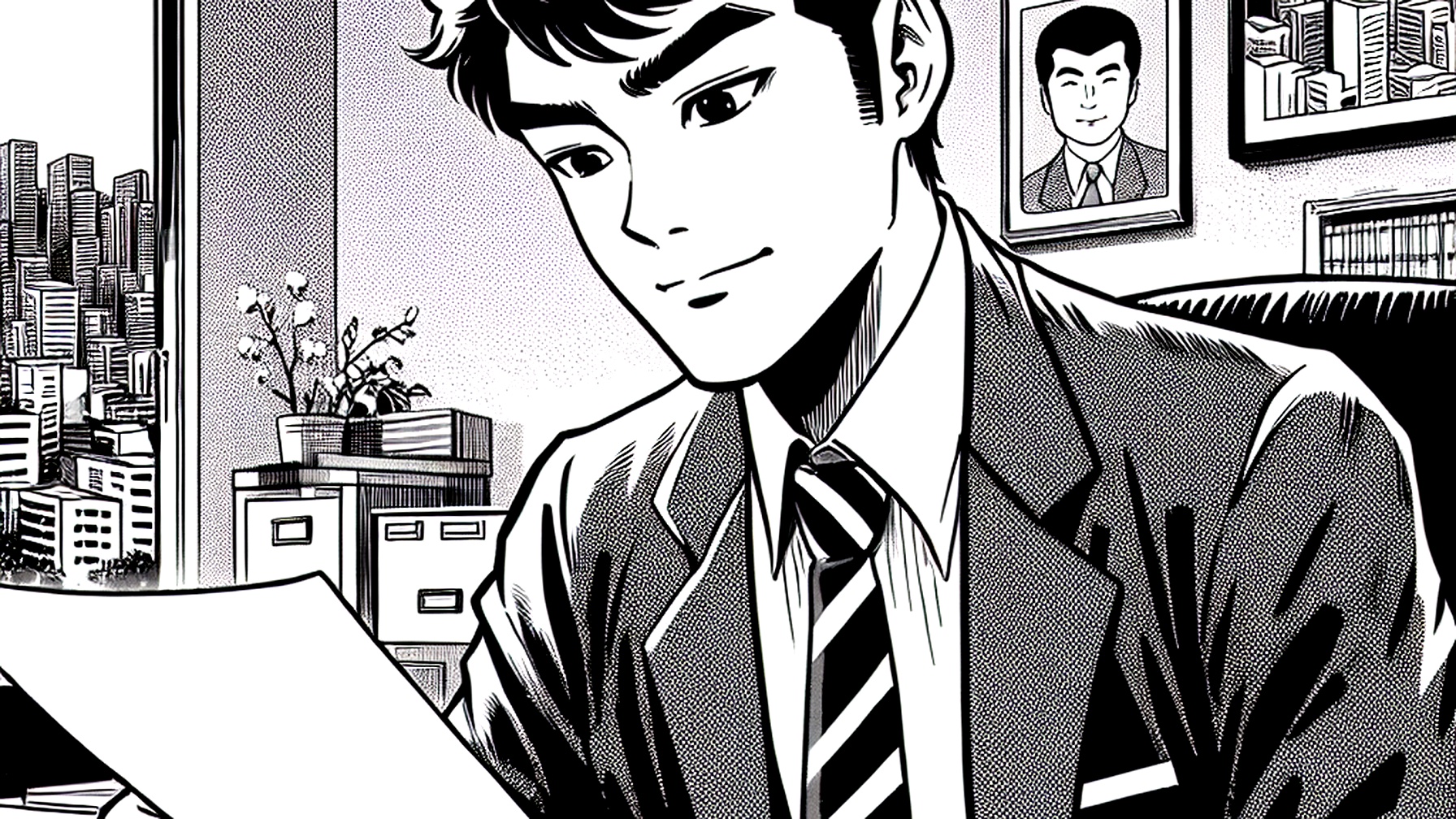
ポイントは、費用構造の複雑さが差の主因であることです。表面利回りは年間家賃収入を物件価格で割るだけなので単純です。しかし、実際の運営では多様なコストが発生し、このギャップが広がります。
例えば、管理会社に支払う委託手数料は家賃の3%から5%が一般的です。さらに、ワンルームでも月8,000円程度の管理費と修繕積立金が発生します。これらを合算すると、表面利回りが1ポイント以上目減りするのは珍しくありません。また、空室リスクを考慮して想定家賃の5%前後を損失見込みとして計上する投資家も多いでしょう。
一方で税負担も軽視できません。固定資産税は建物評価額に応じて毎年課税され、東京都心の新築ワンルームで年間9万円前後が目安です。2025年度も新築住宅に対する固定資産税1/2軽減措置が3年間適用されますが、期間限定のため4年目以降は負担が増えます。このように時間とともにコスト構造は変化します。
実質利回りを算出するとき、取得時の諸費用を均等償却して年あたりに換算する方法があります。たとえば登記費用や仲介手数料の総額90万円を30年で割ると、年3万円のコスト増となります。この計算を加えるだけで、将来の資金繰り精度が高まります。
実質利回りを高める運用と管理の工夫
重要なのは、費用を抑えるだけでなく、収入を安定させる工夫を両輪で進めることです。賃料収入を守りつつ、無駄な支出を削減すれば、実質利回りは確実に向上します。
まず家賃を下げずに空室期間を短縮する施策が有効です。具体的には、退去予告を受けた時点でネット広告を開始し、敷金礼金を柔軟に設定します。最近は家具付き短期賃貸の需要も高く、家賃を1割上乗せできる例も増えています。こうした小さな改善でも、年間家賃が10万円増えれば利回りは大きく改善します。
支出面では修繕の長期計画が欠かせません。給湯器やエアコンは10年から15年で交換が必要になるため、資金を積み立てておけば一度に大きなキャッシュアウトを防げます。また、複数物件を保有している場合、保険を一括契約に切り替えることで保険料が5%ほど下がることもあります。
さらに、金融機関との交渉は利回り向上に直結します。2025年9月時点で投資用ローンの固定金利は年2.1%前後が平均ですが、優良顧客向けに1.8%を提示する地銀も存在します。金利を0.3ポイント引き下げると、3,000万円の借入で年間約9万円の利息削減になり、実質利回りが0.3ポイント上がる計算です。
2025年の市場動向と利回りの現実
実は、成長エリアの選定も利回りに大きく影響します。2025年9月時点で東京23区の新築マンション平均価格は7,580万円と過去最高を更新しました。不動産経済研究所は、都心5区の価格上昇が全体をけん引していると分析しています。その結果、表面利回りは低下傾向にあり、利回りの底上げには運用改善がより重要になります。
一方で、郊外の再開発エリアは価格上昇が緩やかで、表面利回りが5%台の物件も見られます。ただし、人口減少リスクや賃料下落の可能性があるため、長期的な需要を見極める視点が求められます。国土交通省の都市計画現況調査でも、鉄道新線計画がある駅周辺は入居需要が堅調に推移する傾向が示されています。
マンションを選ぶ際は、将来のキャッシュフローを複数シナリオで試算することが有効です。楽観的な賃料維持シナリオに加え、賃料3%下落や空室率15%悪化のケースでも黒字を確保できるかを確認すると安全度が高まります。この作業により、実質利回りがプラスでもキャッシュフローがマイナスになる「わな」を避けられます。
結論として、市場全体の利回り低下が続く局面では、物件選びだけでなく、管理の質と金融条件が投資成否を左右します。安易に高利回りを追うより、需要の強いエリアで実質利回りを堅実に積み上げる戦略が現実的です。
実質利回りを見極めるシミュレーション手順
まず押さえておきたいのは、シミュレーションは一度で終わらせず、前提を変えて繰り返すことが肝要だという点です。収支表を複数パターン用意し、実質利回りの変動幅を把握することで不測の事態に備えられます。
手順は大きく三段階です。最初に取得総額を正確に集計し、登記費用や火災保険料を漏れなく計上します。次に、賃料、管理費、空室率、修繕費、税金を入力し、年間キャッシュフローを算出します。最後に、家賃下落や金利上昇のストレス条件を加え、実質利回りが急激に悪化しないか確認します。
Excelや無料のシミュレーターだけでなく、金融機関の担当者にチェックを依頼するのも有効です。担当者は融資審査の視点を持つため、過度に楽観的な前提を指摘してくれることが多いからです。また、2025年度時点で利用できる「住宅セーフティネット登録住宅」に該当する投資用物件では、入居者紹介支援を受けられ、空室リスクを下げる効果が期待できます。
最後に、実質利回りの目標ラインを明文化し、達成できない案件は見送るルールを設定すると投資判断がブレません。例えば、ローン返済後のキャッシュフローマージンが年10万円以上確保できるかを基準にすると、数値で合否を判断できるため冷静な投資が可能になります。
まとめ
実質利回りは、マンション投資で真に重要な「手元に残る利益」を示す指標です。表面利回りとの差は管理費や税金などの運営コストで生じ、適切に把握しなければ収支が甘くなります。家賃維持策や費用削減、低金利交渉を組み合わせれば、実質利回りは着実に改善できます。2025年の市場は表面利回りの低下が続く一方で、需要の強い立地を選び、綿密なシミュレーションを行えば安定した収益は十分に狙えます。次の物件を検討する際は、必ず実質利回りを基準にした収支表を作成し、自分のリスク許容度に合うかを確認しましょう。行動を先延ばしにせず、数字に基づいた判断で一歩踏み出すことが成功への近道です。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 都市計画現況調査 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 固定資産税関連資料 – https://www.soumu.go.jp
- 財務省 税制改正資料(2025年度) – https://www.mof.go.jp

