憧れの不動産投資を調べていると、「やっぱり新築でないと入居者が決まらないのでは」と悩む声を耳にします。しかし一方で「マンション投資 新築 いらない」という逆の意見も存在し、情報が錯綜しているのが実情です。本記事では、新築にこだわるメリットとデメリットを整理しつつ、中古を含めた戦略的な投資手法を解説します。初心者でも読み進めやすいよう基礎から説明しますので、読み終わる頃には自分に合った判断軸が持てるはずです。
新築マンション投資が抱える特徴
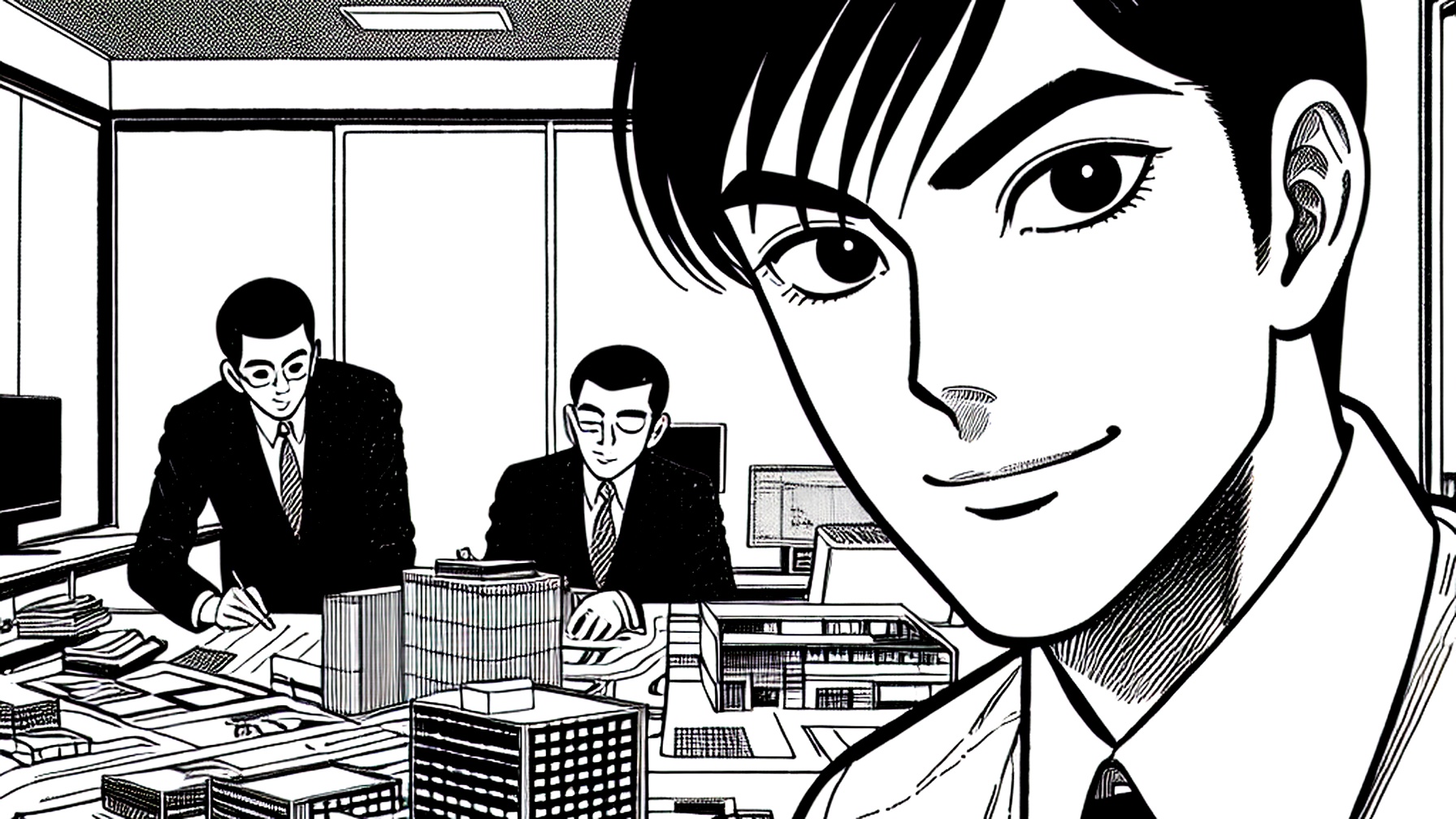
まず押さえておきたいのは、新築物件特有のコスト構造です。新築価格には広告費やモデルルーム運営費などが上乗せされ、同じ立地でも中古より2〜3割高くなる傾向があります。不動産経済研究所によると、2025年9月時点の東京23区の新築平均価格は7,580万円で前年より3.2%上昇しました。
この価格上昇は、建設費の高止まりや人件費の増加が背景にあります。家賃が比例して上がらなければ利回りは圧縮され、キャッシュフローが細くなる点が課題です。また、新築プレミアムと呼ばれる人気は入居後数年で薄れるため、長期投資では実質利回りの低下に注意が必要です。
さらに、減価償却費の節税効果が限定的である点も見逃せません。木造と異なり、鉄筋コンクリート構造の法定耐用年数は47年です。築浅ほど残存年数が長くなり、初期に計上できる償却費が少なくなるため、所得税の軽減効果は中古より小さくなります。
中古マンション投資のメリットを読み解く
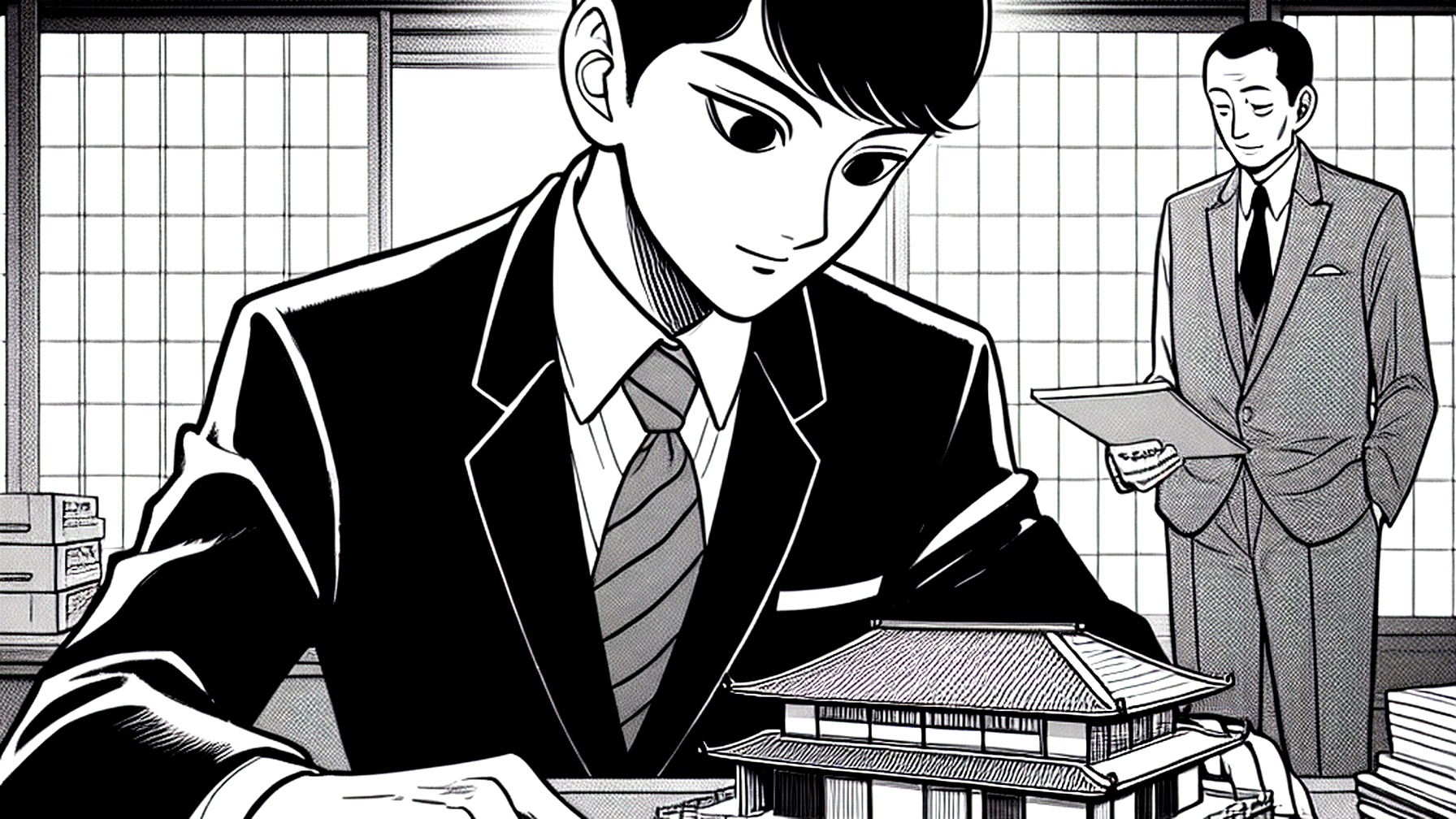
ポイントは、価格と家賃のバランスが取りやすいことです。築15〜25年程度の首都圏ワンルームでは、販売価格が新築の6割前後まで下がる一方、家賃は築5年と比べても1〜2割しか落ちない事例が多くあります。つまり表面利回りが高まりやすく、融資返済後のフリーキャッシュを確保しやすいのです。
建物の状態を不安視する声もありますが、長期修繕計画の開示が義務化されている管理組合が増え、修繕履歴を確認すればリスクは大幅に減らせます。国交省のマンション総合調査でも、築20年超の物件で大規模修繕を実施済みの割合は75%を超えました。適切に管理された中古を選ぶことで、将来の修繕負担を想定しやすくなります。
また、減価償却による節税効果が高い点は見逃せません。築20年を超えると残存耐用年数が短くなるため、加速度的に費用計上が可能です。これにより手取りキャッシュを維持したまま所得税を抑えられ、次の投資資金を早期に回収できる仕組みが構築できます。
新築にこだわらない戦略的な買い方
実は、購入時期と出口戦略を組み合わせることで、新築・中古どちらにも対応できる柔軟なポートフォリオが作れます。重要なのは、立地・客付け力・管理体制という三本柱でリスクを評価し、物件そのものの築年数に依存しすぎない視点を持つことです。
例えば、再開発が予定される駅徒歩5分圏内の築12年物件を取得し、再開発完了までの5年間で家賃上昇を狙う手法があります。竣工時のような新築プレミアムはなくても、エリア魅力の向上が家賃を底支えするため、安定収入と売却益の両方が期待できます。一方で、オリンピック開催など一時的な需要だけを当てにすると空室リスクが高まるため、長期的な人口動態やインフラ計画に基づく分析が欠かせません。
加えて、区分所有だけでなく、一棟レジデンスや小規模木造アパートへの分散投資も視野に入れるとリスクヘッジ効果が高まります。物件種別を分けることで、金利上昇や賃貸市場の変動に対する耐性を高められるため、「マンション投資 新築 いらない」という発想を超えた総合的な不動産ポートフォリオが完成します。
2025年度の税制と融資動向をチェック
まず2025年度の税制で押さえておきたいのは、住宅ローン控除の対象外である投資用ローンに対して、特別な減税措置は設けられていない点です。節税を図るなら減価償却計算と修繕費のタイミングを工夫するだけでなく、不動産所得の赤字を給与所得と損益通算できる範囲を理解しておく必要があります。
融資面では、メガバンクよりも地銀・信金が中古マンション投資に積極的です。2025年の金融庁業態別貸出統計によると、首都圏の中古区分への平均金利は2.1%前後で、借入期間は最長35年が標準的となっています。また、サステナビリティ関連融資では築年数が古い物件でも、断熱改修を条件に金利を0.2%下げる商品が登場しました。この制度は2025年度末までの契約が対象であり、活用すれば中古でも実質利回りを高められます。
なお、インフレ局面では金利上昇リスクがつきまといます。変動金利を選ぶ場合は、返済比率を家賃収入の50%以内に抑え、金利が1%上がってもキャッシュフローがプラスを維持できるか試算しておくと安心です。
リスク管理と出口戦略の考え方
基本的に、投資は買うときよりも出口で成否が決まります。新築にこだわらずとも、売却時に競争力を保つためには管理状態の維持とリノベーションの巧拙が鍵となります。特に水回りや共用部の美観は、購入検討者が最初に目にするため、資本的支出と修繕費のバランスを取りつつ計画的に改善しましょう。
空室リスクを下げるには、募集開始のタイミングと家賃設定が重要です。年明けから春にかけて転勤・入学需要が高まるため、その1〜2か月前にリフォームを終わらせておくことで、募集期間の短縮が見込めます。また、家賃を周辺相場の5%以内に抑え、フリーレント1か月を併用するなど、長く住んでもらう仕組み作りが欠かせません。
出口戦略としては、想定利回りを下げる局面で売却するより、キャッシュフローが安定している間に資産入れ替えを行う方が有利です。具体的には、売却益が出た段階で簿価残高の小さい築古を追加購入し、減価償却費を確保しながらポートフォリオを若返らせる手法が有効です。こうして買い替えを繰り返すことで、手元資金を極端に減らさずに資産規模を拡大できます。
まとめ
本記事では、新築マンション投資のコスト構造と中古マンションの実利を比較し、さらに2025年度の税制や融資動向までを踏まえた戦略的アプローチを解説しました。要は、立地・管理・価格のバランスを見極めれば「マンション投資 新築 いらない」という選択肢は十分に理にかないます。目先の新築プレミアムだけで判断せず、キャッシュフローと出口までを一貫して設計することが、長期的な資産形成への近道です。ぜひ本記事を参考に、自分の投資基準を明文化し、次の一歩を踏み出してください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 令和6年度マンション総合調査 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁 銀行業態別貸出統計(2025年上期) – https://www.fsa.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告(2024年) – https://www.soumu.go.jp
- 日本政策金融公庫 不動産投資向け融資動向レポート2025 – https://www.jfc.go.jp

