不動産投資に興味はあるけれど高額な物件を買うのは不安、そんな悩みを持つ人にとってREITは手軽な選択肢に映ります。しかし価格変動や分配金の仕組みを十分に理解せずに購入すると、思わぬ損失につながりかねません。本記事ではREIT 注意点を中心に、2025年10月時点で押さえるべき最新の市場動向とリスク管理のコツをやさしく解説します。読み終えたときには、銘柄選びから購入後のチェックまで自分で判断できる基礎力が身についているはずです。
REITの仕組みを正しく理解する
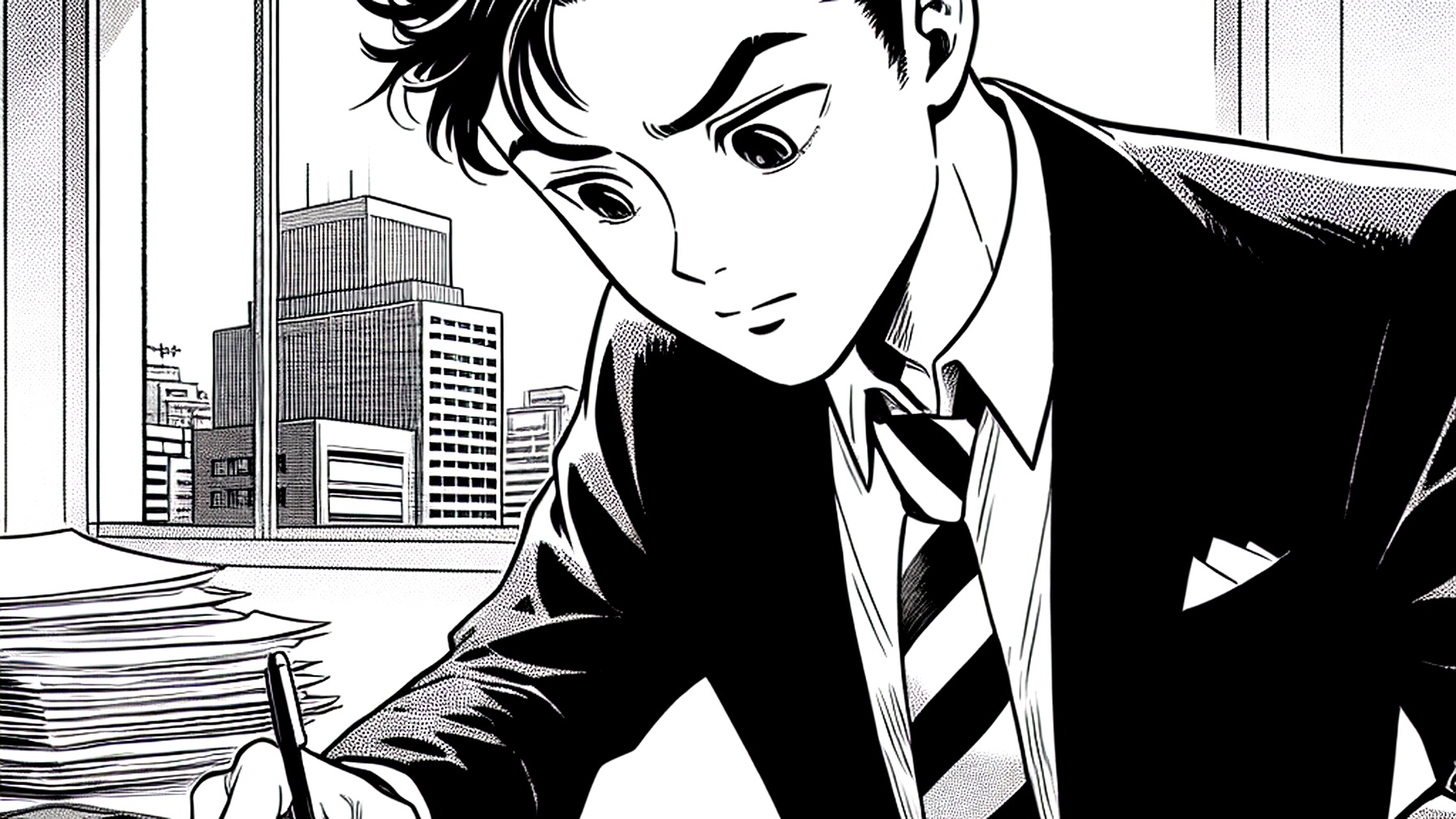
重要なのは、REITが不動産そのものではなく「不動産を束ねた投資信託」である点を認識することです。投資家は口数を購入し、運用会社は集めた資金でオフィスや住宅、物流施設などを取得し賃料収入を得ます。つまり分配金の原資は賃料と売却益であり、物件の稼働率が安定しなければ収益も揺らぎます。
次に知っておきたいのが、法律上REITは利益の九〇%超を分配すると法人税が実質ゼロになる仕組みです。高い分配利回りが魅力に映るものの、内部留保が少ないため大規模修繕や災害時の負担が直接投資家に跳ね返りやすい点は見逃せません。
また、証券取引所に上場しているため株式と同じように売買できます。流動性が高い半面、金利や為替、景気指標の発表に合わせて価格が短期的に乱高下することも珍しくありません。値動きをストレスなく受け止められる資金計画が前提となります。
最後に信託報酬です。運用報酬、物件管理費、市場外の借入コストなど複数の手数料が差し引かれた後に分配金が計算されます。目論見書で実質コストを把握し、同じ利回りでもコストの低い銘柄を選ぶと長期的なパフォーマンス差は意外と大きくなります。
2025年の市場環境と金利動向
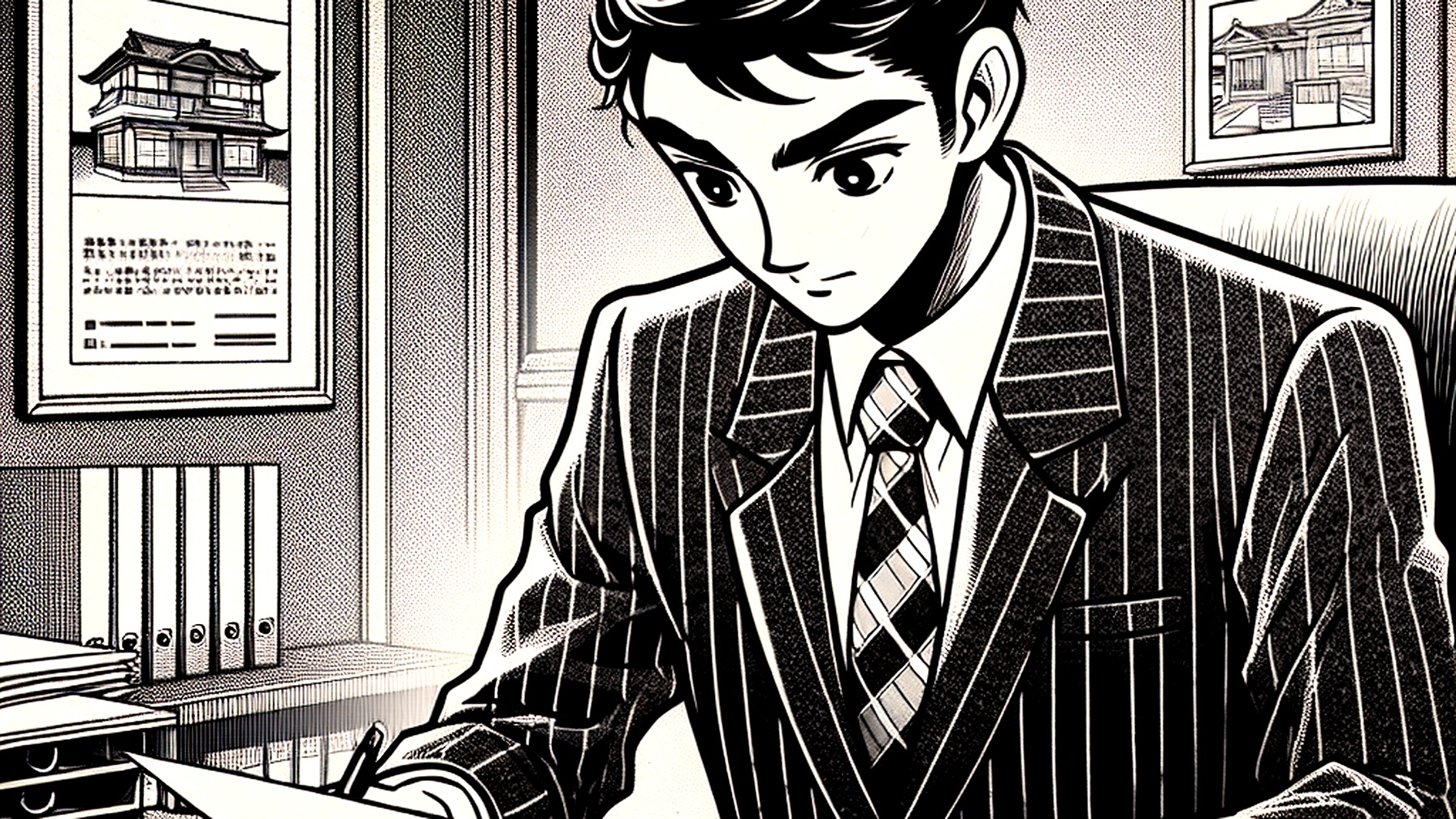
まず押さえておきたいのは、日銀が2025年春にマイナス金利を解除し、長期金利が一%台に乗せたという事実です。日本取引所グループのデータによれば、金利上昇局面では東証REIT指数が三〜六カ月ほど調整する傾向がありました。金利が上がると借入コストが増え、将来の分配金が圧迫されると市場が織り込むためです。
一方で、人口減少が続く中でも都心オフィスの空室率は二〇二四年比でほぼ横ばいにとどまりました。国土交通省の「不動産価格指数」では、住宅系REIT向け物件が前年同月比で三%上昇しており、堅調な需要がうかがえます。つまり金利に敏感な銘柄と、物件需給に左右される銘柄で値動きが分かれる局面です。
投資家としては、ポートフォリオ内の借入比率(LTV)と平均固定金利期間を確認することが欠かせません。借入比率が五〇%を超える銘柄は金利上昇リスクが高く、安定配当を求めるなら四〇%前後に抑えた銘柄を軸に組むと安心感があります。
加えて、2025年度の税制改正で創設された「個人版成長投資枠(つみたてNISAの上限拡大)」はREITにも適用されます。年間三六〇万円までの購入分配金が非課税となるため、長期保有を前提とする場合は活用価値が高い制度です。
分配金利回りに潜むリスクを見抜く視点
ポイントは、表面利回りだけでなく「分配余力」を調べることです。分配余力とは、当期純利益に加えて過年度から繰り越した利益剰余金を合算し、一口あたりで示した指標を指します。余力が多い銘柄は短期的な空室や修繕費の増加があっても分配金を維持しやすいのです。
つまり高利回りでも余力が薄い場合は、次期以降に減配リスクを抱えている可能性があります。実は、東証REIT全体の平均分配余力は2023年度末で一口当たり約一五〇円でしたが、物流特化型の一部銘柄は五〇円以下にとどまっています。投資判断では利回りと余力を必ずセットで確認しましょう。
さらに、修繕積立金の水準にも注意が必要です。国交省のガイドラインでは、築二〇年時点で建物価格の一〇%相当額を積み立てることが望ましいとされますが、実際には銘柄間で差が大きいのが現状です。積立不足のまま大規模修繕期を迎えると、追加借入や減配の形で投資家負担が表面化します。
最後に為替リスクです。外貨建てテナント契約や海外不動産を組み込むグローバルREITは、円高局面で分配金が目減りする点を頭に入れておきましょう。為替ヘッジの有無とコストを運用報告書で見極めることで、想定外の収益変動を軽減できます。
税制と法規制のチェックポイント(2025年度版)
まず、2025年度もREITの分配金は「配当所得」として課税され、上場株式と同じく源泉分離課税二〇%が基本です。先述の個人版成長投資枠を利用すれば、非課税で受け取れるため長期運用の効率が高まります。ただし、枠を超えた分は課税対象になるため配分管理が必須です。
次に覚えておきたいのが、金融商品取引法の改正で義務付けられた「ESG情報開示」です。二〇二四年十月以降、REITもサステナビリティ関連指標を有価証券報告書に記載しています。環境負荷を軽減する物件は、中長期的にテナント需要が高まりやすいため、開示内容を比較することはリスク低減につながります。
また、災害対策特別措置法により、津波浸水想定区域の物件を保有するREITは追加のリスク説明が求められています。ハザードマップを確認し、自身の耐震基準や保険加入状況までチェックすることで、地震国日本ならではのリスクを限定できます。
最後に損益通算です。REITの分配金は不動産所得ではなく配当所得に区分されるため、個人が賃貸経営で出た赤字と通算できません。節税目的で複数の投資を組み合わせる場合、この点を誤解しないよう注意が必要です。
購入前後で実践したいセルフチェック
まず押さえておきたいのは、自身の投資目的を利益目標と期間で具体化することです。分配金を年四%得たいのか、売買益を狙うのかで銘柄も売買タイミングも変わります。目的があいまいなまま高利回りに飛びつくと、期待外れの値動きに振り回されやすくなります。
次に実行したいのが、投資額を「生活防衛資金の六カ月分を残した余剰資金」に限定するルール設定です。REITは上場商品である以上、市場暴落時には三割近い下落も起こり得ます。余裕資金で臨むことで狼狽売りを避け、長期の複利効果を享受できます。
購入後は、四半期ごとに運用報告書と分配金の推移を確認し、LTVや空室率が許容範囲を超えていないかをチェックします。目安として、LTVが五〇%を超えた場合、追加購入を見送りポートフォリオを見直すと安全です。
最後に情報源の分散です。会社発表だけでなく、国交省の統計や日経平均との相関、金融庁の行政処分情報など公的データを合わせて読む習慣をつけると、バイアスの少ない判断ができます。
まとめ
REIT 注意点を整理すると、仕組み・市場環境・分配余力・税制・セルフチェックの五点を理解することが損失回避の鍵だと分かります。結論として、高利回りの数字だけを追うのではなく、借入比率や修繕積立、法改正への対応まで多面的に確認する姿勢が不可欠です。今日紹介した視点を手元の銘柄リストに当てはめ、まずは少額から実践し経験値を積み上げてみましょう。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁 金融機関モニタリングレポート – https://www.fsa.go.jp
- 総務省 統計局 消費者物価指数 – https://www.stat.go.jp
- 日銀 経済・物価情勢の展望 – https://www.boj.or.jp

