不動産投資に興味はあるものの、「現物マンションを買うべきか、それともREIT(リート)で小口から始めるべきか」と迷う人は少なくありません。まとまった資金がなくても投資できるREITと、資産形成の王道とされるマンション投資では、必要な知識やリスクが大きく異なります。本記事では二つの投資手法を比較しながら、初心者でも実践できる始め方を具体的に解説します。読むことで、自分に合った投資スタイルが見つかり、行動に移す自信が得られるはずです。
REITとマンション投資の違いを押さえる
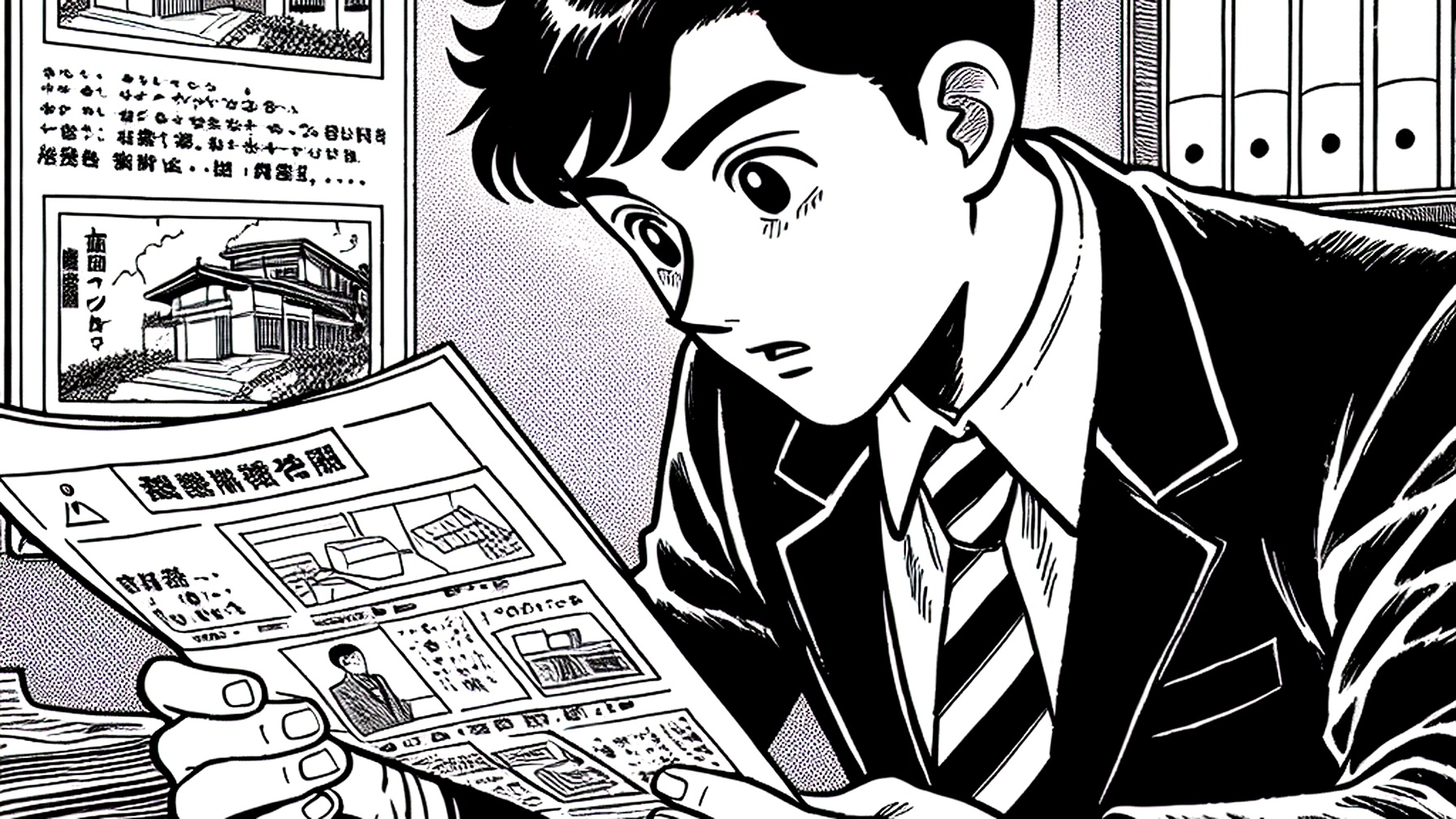
重要なのは、両者の特徴を整理して投資目的と照らし合わせることです。REITとは複数の不動産をまとめた投資信託で、証券取引所で株式のように売買できます。一方でマンション投資は実物資産を保有し、賃料収入と資産価値の上昇を狙う方法です。
まず流動性に注目しましょう。東京証券取引所の売買代金データによると、2025年上期のJ-REIT平均出来高は一日約1,200億円でした。価格はリアルタイムで変動し、売却もクリック一つで完結します。一方、マンション売却には平均3〜6か月かかり、仲介手数料や登記費用も必要です。
リスク構造も異なります。REITは投資先物件が分散されているため、一棟の空室が配当に直ちに影響するわけではありません。しかし株価のように値動きがあり、景気後退時に価格が20〜30%下落する局面も過去に観測されています。マンション投資は空室や家賃下落が直撃しますが、長期保有でインフレヘッジとして機能しやすい点が魅力です。
費用面では、REITは購入手数料がネット証券なら0.1%前後と小さく、管理は運用会社に委任されます。これに対しマンション投資は管理費・修繕積立金や固定資産税が毎年発生します。つまり、自分で手間をかける意欲と時間があるかが選択の分かれ目になります。
まず知りたいREITの仕組みと始め方
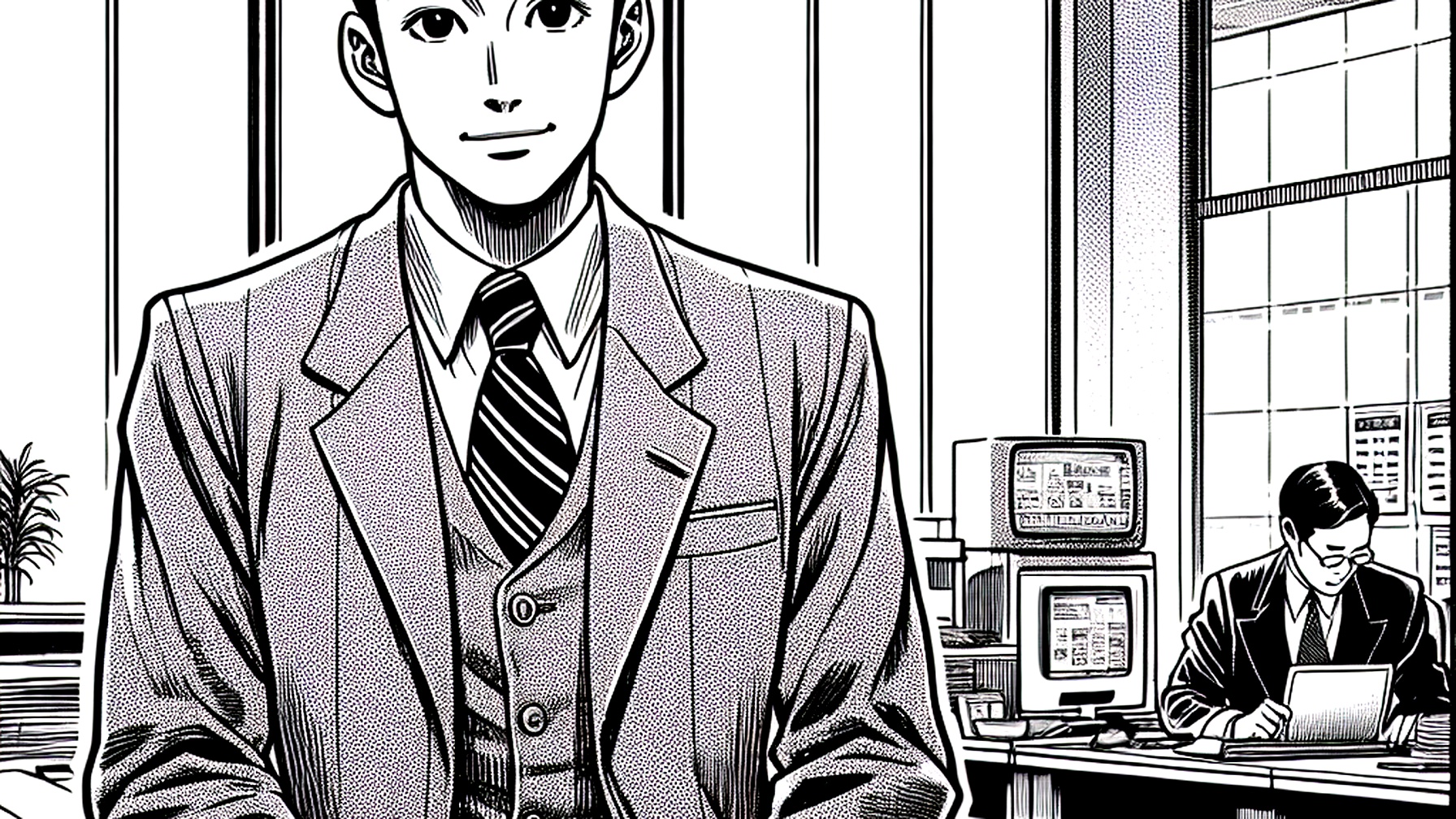
ポイントは、証券口座を開設してから商品を選ぶまでの流れを理解することです。REITは投資法人がオフィスや住宅、物流施設などを保有し、その賃料収入を原資に年2回配当を行います。金融庁の開示資料によれば、2025年3月期のJ-REIT平均分配利回りは年4.2%でした。
実際の始め方はシンプルです。ネット証券で総合口座を作り、株式と同じ画面で銘柄コードを入力して発注します。最少投資額は1口およそ5万〜20万円なので、ポートフォリオを組みやすい点が魅力です。投資信託型の「REIT指数ファンド」を使えば1万円以下でも分散投資が可能です。
銘柄選びでは資産タイプとLTV(負債比率)をチェックしましょう。オフィス特化型は景気敏感ですが利回りが高く、住宅特化型は賃料変動が小さい分、利回りは低めです。また、日本取引所グループの統計ではLTVが50%を超えると金利上昇時に分配金が圧迫されやすい傾向があります。資料の注記を読んで安定感を判断してください。
最後に税金です。分配金は20.315%の源泉徴収で完結し、確定申告は不要です。ただしNISA(少額投資非課税制度)の成長投資枠を使えば、2025年度は年間240万円まで配当が非課税になります。制度を活用するかどうかで、最終利回りが大きく変わる点を覚えておきましょう。
マンション投資で押さえるべき3つの視点
まず押さえておきたいのは、立地・資金計画・運営体制の三本柱です。立地については国土交通省の地価LOOKレポートで需給を確認し、駅から徒歩10分以内・人口増加エリアを優先します。実際、2025年の新築マンション平均価格は東京23区で7,580万円と高騰していますが、ワンルーム投資なら2,500万円前後でも選択肢があります。
資金計画では自己資金2割が目安です。日本政策金融公庫の調査では、自己資金比率が20%未満のオーナーは返済比率が40%を超えるケースが増え、キャッシュフローが圧迫されがちです。金利1.5%で35年ローンを組むと、1,000万円借入あたり月返済は約3万円です。家賃設定と返済額を慎重にシミュレーションすることが欠かせません。
運営体制としては管理会社選びが成否を分けます。空室期間が1か月短縮されるだけで年間利回りが約0.5%向上する試算もあります。管理委託料は家賃の5%程度が相場ですが、24時間対応や原状回復費の割引などサービス内容を比較し、総合コストで判断しましょう。
税務面では、減価償却による所得圧縮効果が期待できます。鉄筋コンクリート造(RC)の法定耐用年数は47年で、築20年の中古なら残存期間27年を償却可能です。これにより給与所得と損益通算でき、所得税と住民税の負担を軽減できます。ただし2025年度の税制改正では、個人の不動産所得に関する大きな変更は見送られており、現行ルールが継続しています。
資金計画とリスク管理の実践ポイント
実は、REITとマンション投資いずれにも共通するのがキャッシュフローの可視化です。REITの分配金シミュレーションは、購入価格と利回り、目標保有口数から年間収入を逆算します。価格変動リスクを示すβ値や標準偏差を利用し、下落局面への耐性を確認するのが効果的です。
マンション投資では、家賃下落率1%刻みで30年分のキャッシュフロー表を作成し、空室率10%と20%の二通りで比較します。さらに、固定資産税や修繕費を物件価格の年間1〜2%で計上すれば、想定外の支出に備えられます。銀行の融資審査でも、このような詳細シミュレーションが提出できると評価が高まります。
金利上昇リスクも無視できません。日本銀行は2025年4月に長期金利誘導目標を0.75%に引き上げました。変動金利ローンを利用する場合、金利が1%上がると返済額は15〜18%増えるケースがあります。固定期間選択型や全期間固定を組み合わせることで、リスクを分散できます。
最後に出口戦略です。REITは目標利回りを下回ったら売却し、他銘柄へリバランスするだけで完了します。マンション投資では、市場価格が融資残高を上回ったタイミングで売却する「アッパーレフト戦略」が基本です。査定価格と返済残高を半年に一度確認し、売却までの想定期間を短縮させることで、下落局面の損失を抑制できます。
2025年度の税制優遇と最新市場動向
ポイントは、現時点で利用できる確実な制度だけを押さえることです。まずNISAの非課税枠拡大はREIT投資家にとって大きな追い風で、成長投資枠240万円は2025年度も継続します。また、マンション投資では不動産取得税の課税標準が「固定資産税評価額×3%」と軽減される措置が2026年3月31日まで延長されました。
住宅ローン控除は自宅取得向け制度であり、投資用マンションは対象外ですが、所得税・住民税の節税策としては青色申告が効果的です。65万円の控除を受けるためには複式簿記で帳簿を付け、期限内に申告する必要があります。国税庁の統計によると、青色申告を利用する個人大家の平均節税額は年18万円となっています。
市場動向では、不動産経済研究所のデータで東京23区の2025年新築マンション価格が前年より3.2%上昇し、供給戸数は微減しています。インバウンド需要が回復し、都心部のホテルコンバージョン案件が増えたことで、J-REITのホテルセクターも分配金を伸ばしています。一方、地方ワンルーム市場では転出超過が続くエリアもあり、需給の二極化が鮮明になっています。投資判断ではエリア別人口動態と企業立地動向を必ず確認してください。
まとめ
結論として、少額から始めたい人や流動性を重視する人にはREIT、長期で資産を積み上げたい人や節税効果を求める人にはマンション投資が向いています。両者の違いを理解し、資金計画とリスク管理をセットで考えることが成功の近道です。まずは証券口座開設や物件情報収集といった小さな行動から始め、半年以内に試験的な投資を実行してみましょう。実践を通じて得られる経験こそが、将来の大きなリターンにつながります。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp
- 日本取引所グループ – https://www.jpx.co.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 地価LOOKレポート – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp

