不動産投資に興味はあるものの、まとまった自己資金がなくて踏み出せない。そんな悩みを抱える方は多いはずです。実は不動産市場には「REIT 中古」という二つの選択肢があり、少額から始めつつ物件オーナーになる道も残されています。本記事では、両者の違いを丁寧に整理し、2025年10月時点の最新ルールを踏まえながら、初心者でもムリなく資産形成へ進むための手順を解説します。
REITと中古物件投資を比べる視点
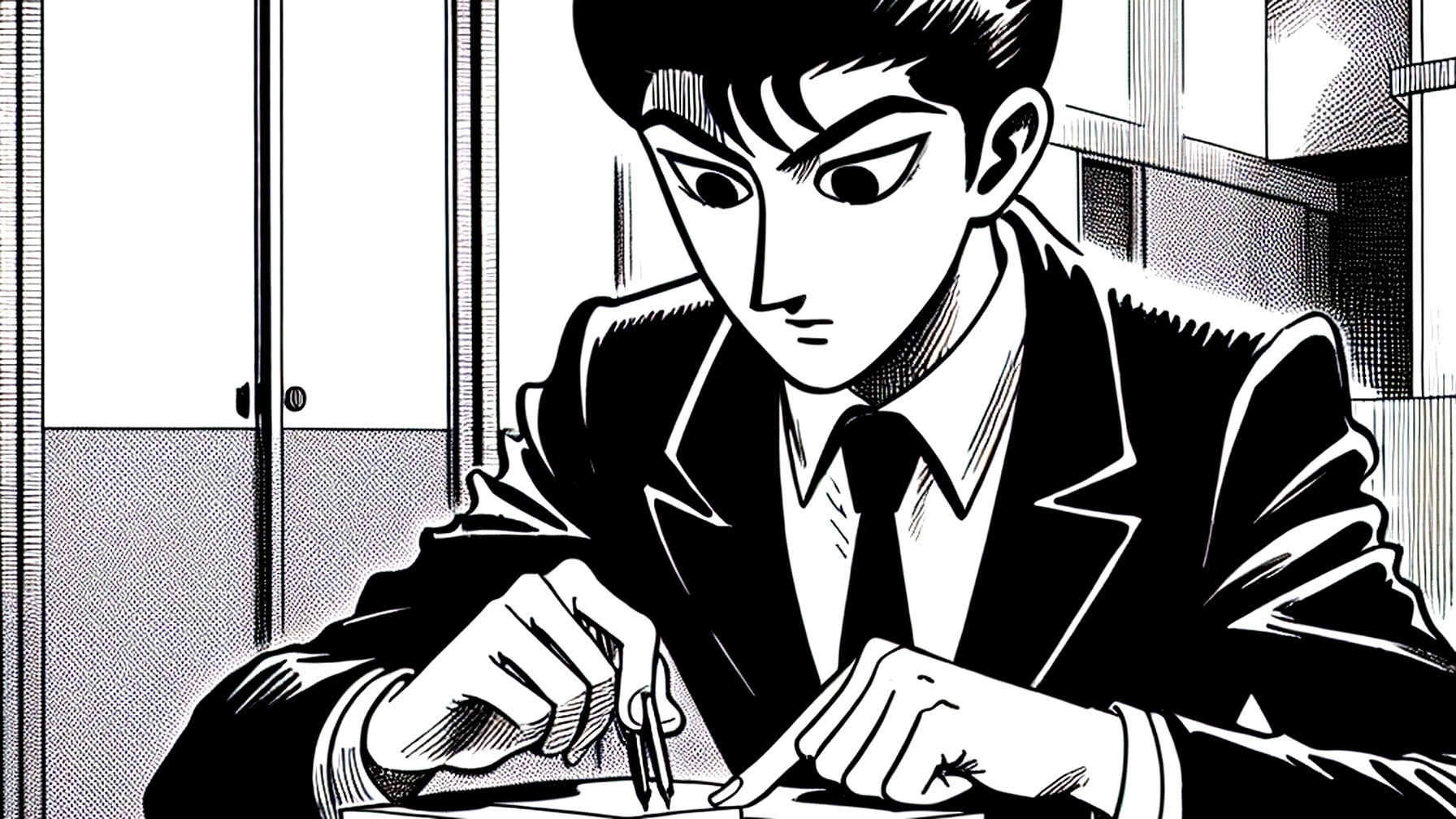
まず押さえておきたいのは、REIT(不動産投資信託)と中古物件投資が、似て非なる仕組みだという点です。REITは証券取引所で取引される投資商品で、1万円前後の少額から分散投資ができます。一方、中古物件は現物不動産を直接所有するため、まとまった自己資金が必要ですが、レバレッジを活用すれば収益率を高められます。
次に確認したいのは、流動性の差です。REITは株式と同様に平日であれば即日売買できますが、中古物件は売却まで数か月かかるケースが一般的です。つまり、市場価格が下落してもREITなら素早く撤退できますが、現物では長期目線が欠かせません。この違いが投資家のリスク許容度を左右します。
また、価格決定要因にも相違があります。REITは保有物件の純資産価値に加えて、長期金利や投資マネーの流入出が影響します。中古物件は立地条件、築年数、周辺賃料水準といった個別要因で評価が変わります。つまり、経済全体の動向を読むのが得意ならREITが向き、物件調査を厭わないなら中古がフィットしやすいのです。
最後に管理の手間を比較しましょう。REITでは運用・管理はプロに一任できます。しかし中古物件では管理会社の選定や修繕対応など、オーナーとしての判断が不可欠です。時間を確保できるかが重要な分かれ道になります。
REIT 中古の魅力とリスク
ポイントは、両者に共通してインカムゲイン(分配金・家賃収入)がある一方、リスク構造が異なることです。REITの魅力は分散効果です。2025年9月末の東証REIT指数は約1,900ポイントとコロナ前水準を回復し、平均分配利回りは4.1%となっています。複数のオフィスや住宅、物流施設を間接的に保有できるため、空室リスクが平準化されます。
しかし、REITは金利上昇に弱い側面があります。日本銀行のマイナス金利政策が解除された2024年以降、長期金利が1.2%前後で推移し、利回り低下懸念が定期的に市場を揺らしています。価格変動が株式並みに激しい点は、メンタル面での負担になりやすいでしょう。
一方、中古物件投資の強みは自分で収益改善策を打てる点です。例えば築25年の区分マンションでも、アクセントクロスや照明を更新し、募集賃料を月5,000円上げる余地があります。国土交通省「住宅市場動向調査2024」によると、築20年以上でもリフォーム実施で家賃が平均6.3%上昇した例が報告されました。自助努力で利回りを押し上げられるのは大きな魅力です。
ただし、突然の設備故障や退去リスクは避けられません。しかも修繕費は予測しづらく、管理会社からの緊急連絡に対応する手間もあります。さらに、将来的な人口減少で郊外エリアの空室期間が長期化する可能性も指摘されています。リターンと引き換えに、手間と時間を受け入れる覚悟が要ると言えるでしょう。
キャッシュフローと資金計画の立て方
実は、REITでも中古物件でも収益の源泉はキャッシュフロー管理にあります。まずREITの場合、証券口座に入る分配金は税引き前で4%前後です。ここから所得税15.315%、住民税5%が源泉徴収され、手取りは約3.2%になります。NISA成長投資枠を活用すれば年間240万円までの投資は非課税となるため、2025年度の枠はぜひ使い切りたいところです。
中古物件では、家賃収入から管理費や修繕積立金、ローン返済を差し引いた純キャッシュフローを重視します。たとえば表面利回り8%の1,500万円区分マンションを、自己資金300万円・金利2%・期間25年で購入した場合、年間の返済額は約76万円です。管理費等を差し引くと手取りは年間約40万円、自己資金利回りは13%程度になります。つまり、レバレッジ効果でREITを上回る利回りが実現しますが、金利上昇時には返済負担も増える点に注意が必要です。
重要なのは、空室や修繕で家賃が半年止まる悲観シナリオも試算することです。収支シミュレーションでは「空室率20%」「修繕費年5%」など保守的な条件を盛り込み、マイナスキャッシュフローでも耐えられるかを確認してください。そのうえで、自己資金は物件価格の20%前後、別途100万円の予備費があれば、金融機関の融資審査にも通りやすくなります。
税制と2025年度の制度活用ポイント
まず、2025年度もREIT分配金は株式配当と同じ申告分離課税扱いで、税率は20.315%です。総合課税で住民税を申告不要とする選択も可能ですが、所得水準が高い場合は注意が必要です。また、REITは「みなし配当控除」の対象外なので、個人投資家は配当控除を使えません。NISA口座で購入した場合は非課税になりますから、活用余地は大きいでしょう。
中古物件では、不動産所得として青色申告が使えるかが節税の鍵です。3棟10室基準を満たせば事業的規模となり、65万円の特別控除を受けられます。2025年度税制改正で、この基準や控除額に変更はありません。さらに、減価償却費が節税インパクトを高めます。木造なら築22年超の中古物件で短期償却が可能になり、課税所得を大きく圧縮できます。
一方で、2025年度も「住宅省エネ改修特例」は継続しており、一定の省エネリフォーム工事を行うと固定資産税が1/3減額されます(工事完了翌年度のみ)。ただし、工事費50万円以上などの条件があるため、実施前に市区町村窓口で確認しましょう。終了時期は2026年3月31日工事完了分までと明記されているため、スケジュール管理が欠かせません。
初心者が踏み出すための具体的ステップ
まず、小口で市場感覚をつかみたい人にはREITがおすすめです。ネット証券の積立機能を利用し、毎月1万円ずつインデックス型のリートETFを購入すれば、相場変動を経験しながら配当実績も確認できます。価格変動への耐性が身につけば、次の段階へ進みやすくなるでしょう。
一方、現物を保有したい人は情報収集と融資枠の確保から始めてください。金融機関の事前審査を通して与信枠を把握し、その範囲内で利回り計算を行うと失敗しにくくなります。物件検索はポータルサイトだけでなく、仲介会社の未公開情報も視野に入れると選択肢が広がります。
物件を見学する際は、昼と夜の雰囲気、エントランス清掃状況、ゴミ置き場の管理状態を確認しましょう。こうした細部が入居率を左右します。また、同エリアで直近3か月以内に成約した賃料水準を調べ、募集賃料が適正かを検証することが大切です。
最後に、購入後の運営フローを事前に決めておくと安心です。管理会社への委託範囲、修繕積立のルール、確定申告のスケジュールをリスト化し、家賃入金と支出をクラウド会計ソフトで可視化してください。こうした準備が、長期的な資産拡大につながります。
まとめ
REIT 中古のいずれを選ぶかは、資金量、時間、リスク許容度という三つの軸で整理すると判断しやすくなります。REITなら少額で分散投資しつつ、高い流動性で柔軟に動けます。中古物件は手間と融資リスクを引き受ける代わりに、レバレッジ効果と節税メリットで高い実質利回りを狙えます。まずは自分のライフスタイルと資産目標を照らし合わせ、今日できる小さな一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2024 – https://www.mlit.go.jp
- 財務省 個人所得課税の概要(2025年度) – https://www.mof.go.jp
- 日本取引所グループ 東証REIT指数月次レポート2025年9月 – https://www.jpx.co.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合議事要旨(2025年7月) – https://www.boj.or.jp
- 総務省 統計局 住宅・土地統計調査2023 – https://www.stat.go.jp

