急な金利上昇でローン負担が増えるのでは、と不安に感じる投資家は少なくありません。特に初めての方は「このタイミングでマンション投資を始めても大丈夫なのか」という疑問を抱えがちです。本記事では、金利が上向く局面でも一棟買いを選択するメリットと注意点を整理し、キャッシュフローを守りながらリスクを抑える具体策を解説します。読了後には、市況を味方につけて長期の資産形成を進める視点が得られるでしょう。
金利上昇期に何が起こるのか
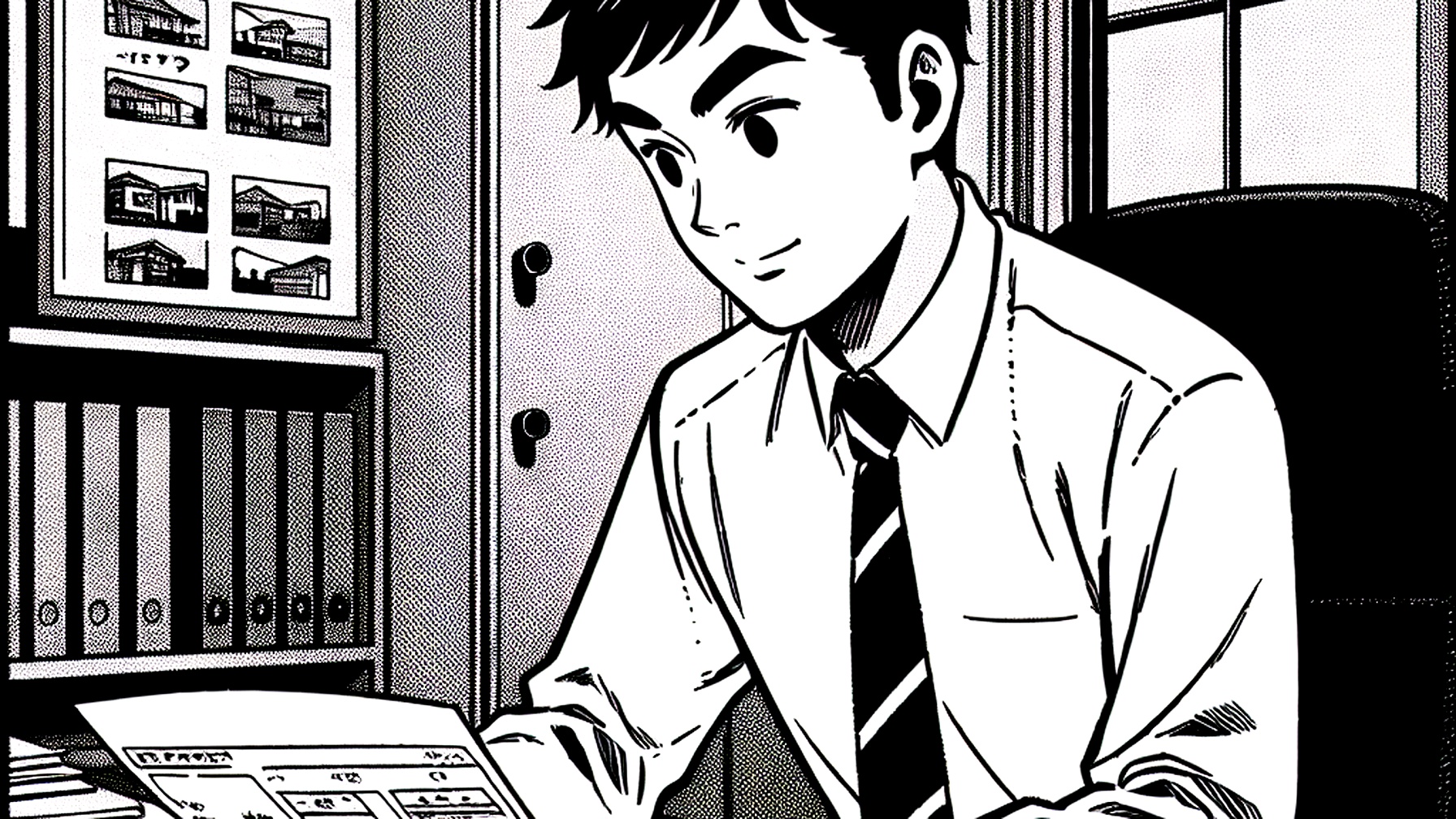
まず押さえておきたいのは、金利が上がると融資コストが直ちに増える一方で、物件価格や賃料にも連動する力が働く点です。日本銀行が2024年3月にマイナス金利を解除して以降、主要地銀の投資用ローンは変動で年1.7〜2.3%が一般的となりました。これは2023年と比べておよそ0.4ポイント上昇していますが、長期固定に比べればまだ低水準です。
次に、金利上昇は買い手の資金繰りを圧迫し、一定の売り急ぎを誘発します。つまり売り手市場だった都心部でも価格交渉の余地が生まれやすくなります。不動産経済研究所によると、2025年10月の新築マンション平均価格は東京23区で7,580万円と高止まりが続くものの、築20年超の一棟レジデンスは利回り上昇の期待から流通量が増加しています。
一方で、金利が上がるからといって賃料がすぐ下がるわけではありません。総務省の住宅・土地統計調査では、23区の平均家賃は過去10年で年1%程度の緩やかな上昇を維持しています。つまり、返済額より賃料の伸びが鈍い場合でも、運営コストを抑えたうえで購入価格を調整できれば、収益性は十分確保できるというわけです。
結論として重要なのは、金利上昇が「全面的な逆風」ではなく、購入交渉と資産入れ替えの好機でもあるという事実です。適切なシミュレーションと長期視点があれば、むしろ競争が緩和された市場で優良物件を押さえられる可能性が広がります。
一棟買いのメリットとリスク
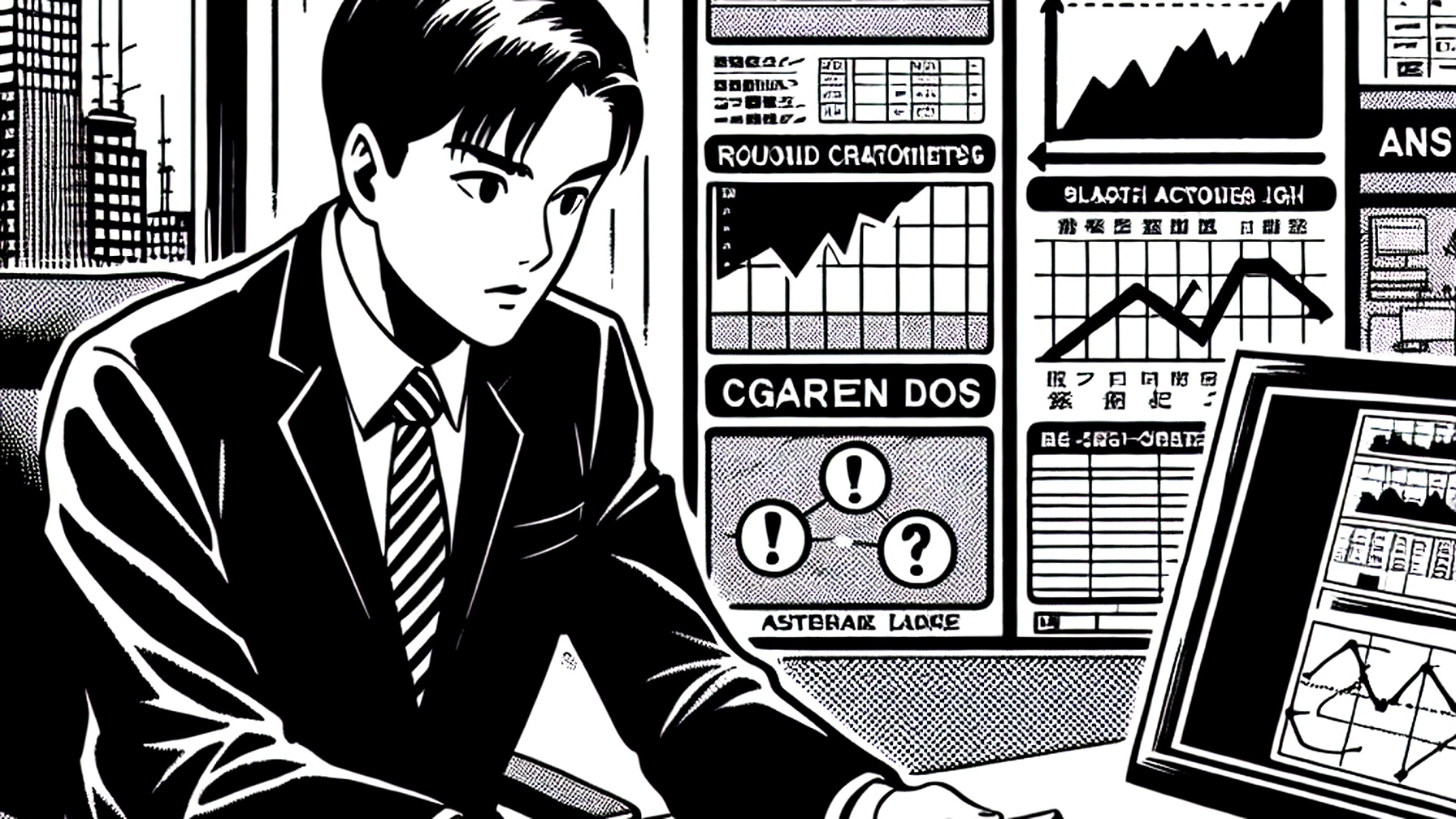
ポイントは、区分所有と比べた場合の規模の経済と管理自由度の高さです。一棟買いでは土地建物を一括で所有するため、外壁修繕や設備更新の判断を自分で下せます。その結果、早期に投資を回収しやすい改装戦略を採れることが魅力です。
また、収入源が複数戸に分散されることで、空室が出ても全体収入への影響を緩和できます。例えば10戸中1戸が空いても家賃収入は9割維持されます。しかし区分1戸のみの所有だと、空室期間はゼロ収益となりキャッシュフローが急減します。家賃の安定度は融資審査でも評価されやすく、結果的に長期固定金利を引き出しやすい面も見逃せません。
一方で、購入金額は数億円規模になるため、レバレッジが高くなりがちです。金利が1%変動するだけで年間返済額は数百万円動く可能性があります。さらに、建物全体の老朽リスクや入居者トラブルへの対応も自己責任となるため、管理会社選定や設備更新計画の精度が求められます。
つまり、一棟買いは収益性と裁量権を得る代わりに、資金計画と運営体制の構築が不可欠です。特に金利上昇期では、返済負担の増加を見越した長期のシナリオづくりが投資成功のカギとなります。
金利上昇局面でのキャッシュフロー管理
実は、金利上昇による負担増は「返済額の変動」「修繕積立の不足」「空室期間の長期化」が重なると深刻化します。まず、毎月の返済額を計算する際は金利上昇幅を1.5〜2ポイントまで織り込むと安全です。例えば融資額2億円、期間25年、金利2%が4%へ上昇した場合、月返済は約84万円から105万円へと21万円増えます。この差額を家賃収入で吸収できるかが分岐点になります。
次に、築年数が15年を超えると大規模修繕の周期が迫ります。外壁と屋上防水で1戸当たり30万〜40万円の負担を見ておくと現実的です。2025年度の税制では、修繕が長期修繕計画に基づく場合、資本的支出として減価償却が可能である点がキャッシュフローの下支えになります。
さらに、管理会社と連携して早期の募集と家賃設定を行うことが空室期間の短縮につながります。住宅情報サイトの掲載写真やVR内覧を活用することで、繁忙期以外でも成約率を高められるデータがあり、実務レベルでは広告費の最適化が欠かせません。
重要なのは、これら三つのコスト要因を年度ごとにシミュレーションへ反映させ、手元流動性が不足しないラインを明確にすることです。想定利回りが8%でも、実効利回りが5%を下回れば追加資金が必要になるケースもあるため、慎重な試算が求められます。
2025年度の融資動向と実務ポイント
まず、2025年度は金融庁の指針により、投資用不動産ローンの「総収入に対する元利返済比率(DSCR)」を重視する姿勢が定着しています。具体的には、家賃収入が返済額の1.2倍以上あることを融資条件とする地域銀行が増えました。つまり、表面利回りよりも実質利回りと空室リスクの説明が重要になります。
また、環境性能への評価も高まっており、断熱改修を行った一棟マンションには金利優遇を設ける金融機関が目立ちます。2025年度の「省エネ改修促進税制」は投資用物件も対象で、一定の省エネ基準を満たすと固定資産税が3年間10%減額されます。期間は2026年3月申請分までなので、工期を逆算した資金計画が必須です。
融資交渉では、固定と変動を組み合わせたミックスローンを提案することで、金利上昇リスクを部分的に固定化しつつ、返済負担の平均化が図れます。例えば総借入額の70%を20年固定、残り30%を変動にする方法です。この比率は金利情勢や自己資金の厚みに応じて調整します。
加えて、投資家自身の属性強化も欠かせません。決算書や確定申告でキャッシュフロー計算書を作成し、将来の修繕引当を数値化すると、金融機関からの信頼度が高まります。結果として借入期間の延長や金利優遇を引き出せる可能性が広がるでしょう。
成功する物件選びと出口戦略
基本的に、金利上昇期ほど「キャッシュフローと資産価値の両立」を見極める目が問われます。まず立地ですが、人口流入が続くエリアかどうかを総務省の住民基本台帳移動報告で確認しましょう。東京23区でも千代田・港・中央区はほぼ横ばいですが、品川区や江東区は再開発効果で増加が続いています。
次に、建物構造と築年数は表面利回りだけでなく耐用年数と修繕履歴で評価します。鉄筋コンクリート造(RC)は法定耐用年数47年ですが、実務上は60年以上の使用例も珍しくありません。築30年でも配管更新済みであれば、修繕コストが抑えられ実質利回りが高まることがあります。
出口戦略としては、保有継続と売却の二本立てで準備することが安心につながります。金利がさらに上昇し売却利回りが上がる局面では、同規模投資家に対しバリューアップ後の物件を譲渡する選択肢があります。逆に、金利が下がれば借り換えで返済コストを下げ、キャッシュフローを増やしながら長期保有を続けられます。
最後に、マンション投資 金利上昇期 一棟買いを成功させるには、「市場環境の変化を前提とした複数シナリオ」を常に更新し、物件の競争力を維持する施策を途切れさせない姿勢が求められます。そうすることで、長期的に安定したインカムゲインと将来のキャピタルゲインを同時に狙えるのです。
まとめ
本記事では、金利上昇が進む2025年の不動産市場で一棟マンションを取得する際の視点を整理しました。金利負担は確かに増えますが、価格交渉の余地拡大や税制優遇、分散効果といったプラス要素も同時に存在します。要は、資金計画と修繕計画を具体的な数値で把握し、融資条件を柔軟に組み合わせることがポイントです。今こそ、市場が揺れるタイミングを学びとし、堅実なキャッシュフローと出口戦略を備えた投資行動を始めてみてはいかがでしょうか。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 日本銀行「金融政策決定会合議事要旨」 – https://www.boj.or.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 金融庁「投資用不動産向け融資に関する監督指針」 – https://www.fsa.go.jp
- 国土交通省「省エネ改修促進税制の概要(2025年度)」 – https://www.mlit.go.jp

