家賃収入を得たいけれど空室が怖い、投資信託のように手軽に不動産へ投資したい、そんな二つの願いを同時に抱える方が年々増えています。実際、総務省の家計調査によると不動産所得を持つ世帯は2024年時点で過去10年比1.4倍に伸びました。しかし「シェアハウス」「REIT」「税金」という三つのキーワードが絡むと、制度や確定申告の複雑さに尻込みしてしまう人も多いはずです。本記事では、2025年10月時点で有効な制度を前提に、初心者でも理解しやすい形でシェアハウス投資とREITの特徴、税金の仕組み、さらに両者を組み合わせた資産形成戦略を解説します。読み終える頃には、ご自身のリスク許容度に合わせた次の一手が明確になるでしょう。
シェアハウス投資の基本と市場動向
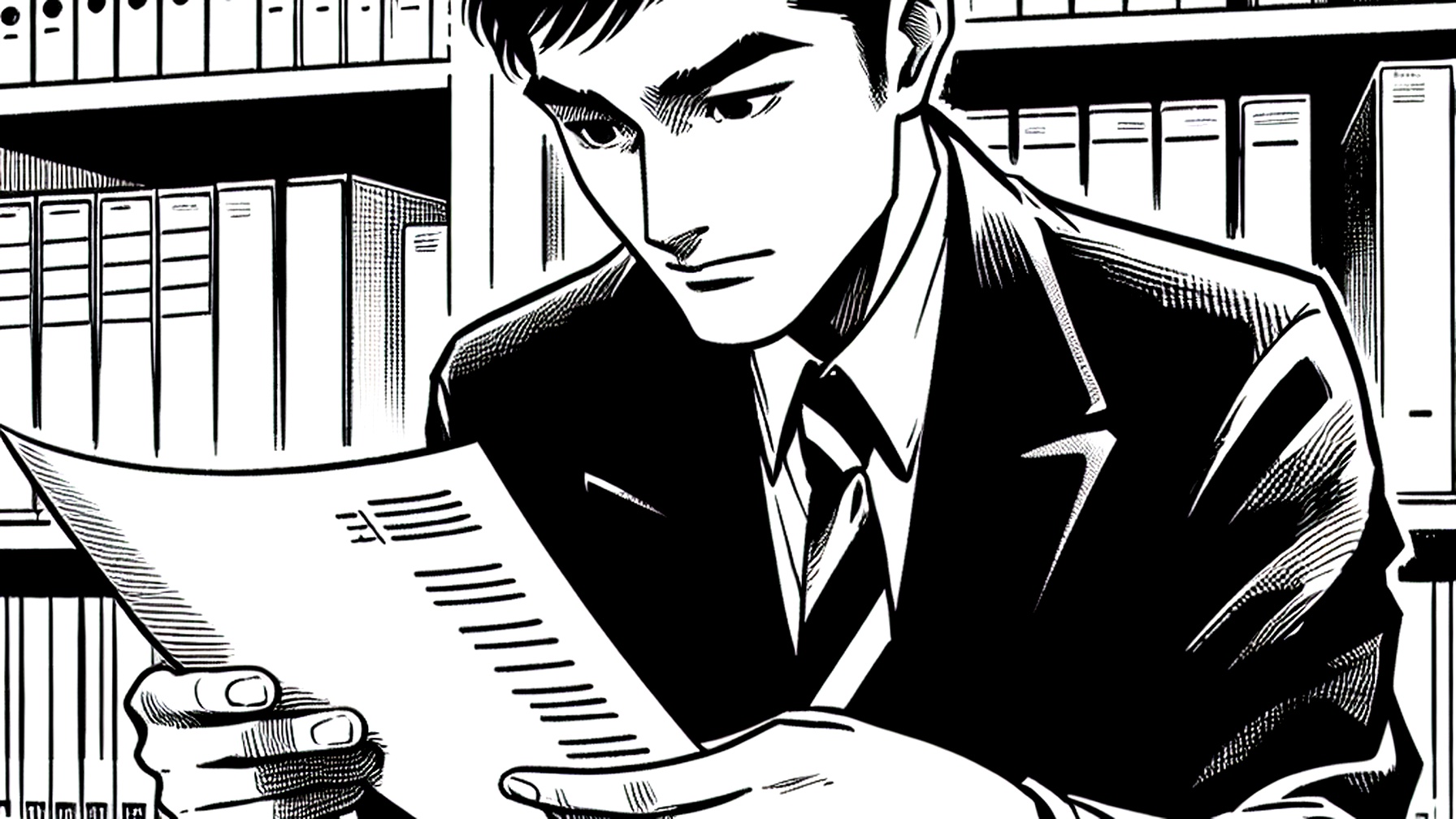
まず押さえておきたいのは、シェアハウスが通常の賃貸マンションとはまったく異なる収益構造を持つ点です。個室は狭く共用部を広く取る設計のため、延べ床面積あたりの賃料単価が高まり、表面利回り8〜12%を確保しやすいことが魅力です。一方で、入居者同士のトラブルや管理運営の手間が増えるという特徴もあります。
国土交通省「賃貸住宅市場調査2024」によれば、シェアハウス戸数は全国で約7.3万室とニッチながら堅調に推移しています。特に20〜30代の単身者が都心へのアクセスとコミュニティを重視する流れが追い風になっています。それでも供給が過剰でないため、共用部を丁寧にメンテナンスすれば平均入居期間は2.8年とワンルーム並みに確保できる点がポイントです。
運営面では、家具家電付きで短期契約を許容するぶん、原状回復費や備品更新費がかさみます。そこで損益計算では、入居率90%でも年間5%の修繕積立を見込むなど保守的なシミュレーションが不可欠です。また消防設備や旅館業法該当性のチェックなど法令順守コストも考慮しましょう。
実際の購入価格は立地が同じワンルーム比で2割前後高い傾向がありますが、複数戸を一括で取得するため金融機関から見れば運営効率が良い不動産と判断されやすく、住宅ローンではなくアパートローンを活用した場合でも金利1.8〜2.5%の枠が付くことが多いです。つまり、表面利回りと金利差が4%以上確保できれば、キャッシュフローは安定しやすいと言えます。
REITで不動産に間接投資するメリット
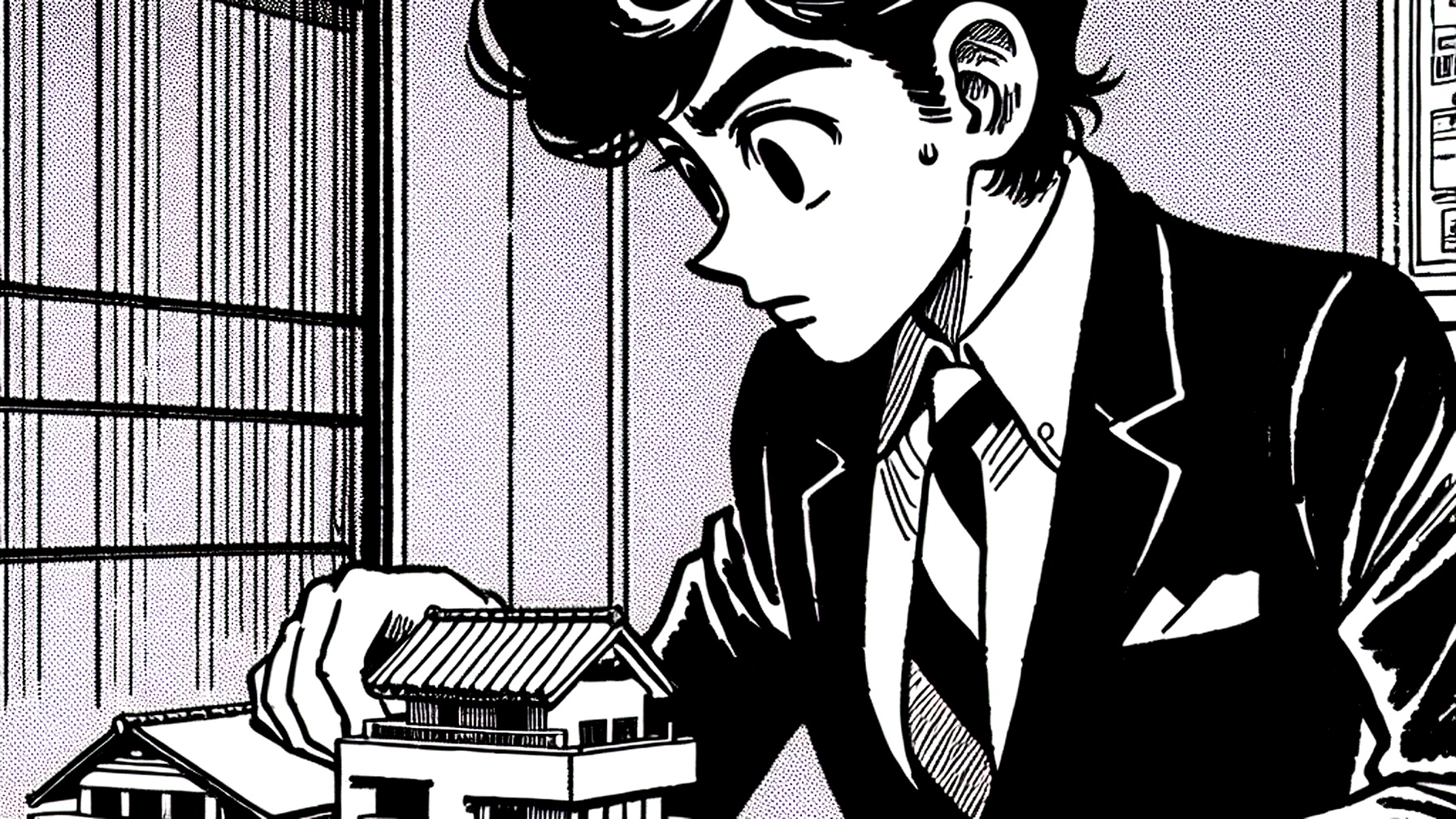
重要なのは、REIT(不動産投資信託)が物件を直接所有しなくても賃料収入と売却益を分配してくれる金融商品である点です。東京証券取引所のデータでは、2025年8月末時点のREIT全体の平均配当利回りは3.7%で、長期国債利回りとの差は約2ポイントあります。これにより、株式より値動きが小さく、預金より高い収益を期待できる投資対象として注目されています。
REITの最大のメリットは流動性です。証券口座があれば株と同じように1口から取引でき、数万円単位で分散投資が可能です。さらに上場廃止リスクが極めて低く、現物不動産のように売却手続きに数カ月かかる心配もありません。またプロの運用会社がテナント募集や修繕計画を担うため、投資家は運用ノウハウを必要としません。
ただし価格変動リスクは市場環境に左右されやすく、例えば2023年の長期金利上昇局面ではJ-REIT指数が一時10%下落しました。金利上昇は借入コストを圧迫し、分配金の減少につながるためです。一方でオフィス型、住宅型、物流型など用途が分かれているため、複数銘柄を組み合わせればリスクを抑えられます。
税制面では、分配金が株式配当と同じく「配当所得」に区分され、特定口座なら20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。NISA口座を使えば年間240万円まで非課税(2025年度時点)で投資できるので、長期保有の効率が高まります。
税金の仕組みと節税のポイント
実は、シェアハウスとREITでは課税のタイミングと控除枠が大きく異なります。まずシェアハウスの家賃収入は「不動産所得」に分類され、総収入から必要経費を差し引いた額に対し累進課税が適用されます。経費には減価償却費、管理委託料、修繕費、共用部の光熱費などが認められ、適正に計上すれば課税所得を抑えられます。
減価償却費の計算では、鉄骨造や木造で耐用年数が変わります。例えば築10年の木造シェアハウス(法定耐用年数22年)の場合、簡便法により残存耐用年数は12年となり、年間償却率は1/12です。取得価額3,600万円なら毎年300万円を経費化できるため、給与所得と損益通算を行うと実効税率を10%以上下げられるケースもあります。
一方REITは、売却益が出た時点で「譲渡所得」、分配金が「配当所得」となり、原則として源泉徴収で完結します。損益通算は株式譲渡損となら可能ですが、給与所得や不動産所得とは通算できません。したがって、高額所得者が節税目的でREITを選ぶ場合は、損出しやNISA活用が中心となる点に注意が必要です。
住宅ローン控除は自宅取得が前提なのでシェアハウスには適用されませんが、2025年度も引き続き「固定資産税の新築住宅軽減(3年間1/2)」は利用可能です。木造2階建て以下で床面積50〜280㎡のシェアハウスなら適用対象となるため、取得初期のキャッシュフロー改善に寄与します。さらに地方自治体によっては空き家活用支援補助金を設けており、上限100〜200万円が交付される事例もあるため、事前確認が重要です。
シェアハウスとREITを組み合わせたポートフォリオ戦略
ポイントは、現物と金融商品を組み合わせることでリスクと流動性を補完し合うことです。例えば手元資金1,000万円のうち700万円を自己資金として都心近郊のシェアハウスを2.5%の金利で購入し、残り300万円を住宅型REITに分散投資するとします。シェアハウスでは実質利回り6%(税引き前)を見込み、REITでは配当利回り3.5%を想定します。
このケースでは、年間賃料収入が420万円、REIT配当が10万円程度となり、ローン返済と経費差し引き後のキャッシュフローは約120万円です。さらにREITはいつでも売却できるため、突発的な修繕費が発生した際の流動性確保に役立ちます。つまり、シェアハウスの高利回りとREITの換金性を両立させることで、安定収益と柔軟性を同時に得ることができます。
また金融庁の「資産形成シミュレーション2025」によれば、過去20年間で現物不動産とREITの相関係数は0.35と低く、組み合わせることでポートフォリオ全体の変動幅を平均15%削減できたと報告しています。少額から段階的に買い増しを行えば、ライフイベントに応じたリバランスもしやすくなります。
資金調達面では、シェアハウスの融資契約を先にまとめる方が得策です。金融機関は既存借入を重視するため、先にREITを購入しても与信に大きな影響は出ませんが、逆だと自己資金が減り融資額が下がる恐れがあります。タイミングを意識した順序が成功のカギとなります。
2025年度に活用できる優遇制度
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続される「住宅用建物消費税還付スキーム」がシェアハウスにも適用可能な点です。課税事業者になり、短期賃貸区画を設けることで仕入税額控除を受け、物件価格の消費税額の一部を還付できます。ただし適用判断は税務署が厳格に審査するため、専門家の同席が欠かせません。
また環境性能向上の取り組みが重視されており、断熱等級5以上の新築シェアハウスには「こどもエコ住まい支援事業(2025年度版)」の補助金が設けられています。補助額は最大60万円ですが、交付申請は着工前に行う必要があります。省エネ設備を導入することで、電気代削減と入居者満足度向上、そして物件評価額の上昇が見込めるため、長期的な収益改善にもつながります。
一方REITについては、2025年から始まった新NISAの「成長投資枠」を利用すると、年間240万円まで非課税で購入できます。配当再投資も非課税で複利効果が高まるため、20年間保有した場合の実質利回りは課税口座より1.2倍になると試算されています。
地方創生の観点からは、空き家をシェアハウスへ転用する際に固定資産税が最大5年間1/2になる自治体も増えています。たとえば福岡市は2025年度予算で同制度を継続し、対象物件は市内中心部から公共交通機関で30分以内に限られるものの、取得コストと税負担を大幅に抑えられます。
まとめ
シェアハウスは高利回りと実物資産ならではのコントロール性、REITは少額・高流動性という長所を持ちます。税金面では、シェアハウスが経費計上と減価償却で節税余地を生み、REITはNISAを活用して非課税運用が狙えます。さらに2025年度は省エネ補助金や消費税還付など活用可能な制度がそろっています。まずは自己資金とライフプランを確認し、手間をかけられる範囲でシェアハウスを選ぶか、時間を節約してREITを軸にするか、あるいは両者を組み合わせるかを検討してください。行動に移す際は、税理士や不動産の専門家に相談し、最新情報をアップデートしながら計画をブラッシュアップすることが成功への近道になります。
参考文献・出典
- 国土交通省 賃貸住宅市場調査2024 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 家計調査年報2024 – https://www.stat.go.jp
- 東京証券取引所 J-REIT指数月報2025年8月 – https://www.jpx.co.jp
- 国税庁 所得税基本通達2025 – https://www.nta.go.jp
- 金融庁 新NISA制度概要2025 – https://www.fsa.go.jp
- 不動産経済研究所 REIT市場動向レポート2025 – https://www.fudousankeizai.co.jp

