親から突然「そろそろ相続のことも考えてほしい」と言われ、どう準備すればいいのか戸惑う人は少なくありません。相続税の負担を抑えつつ、家族に安定した収入源を残す方法として注目されるのがアパート経営です。しかし「本当に安全なのか」「空室が続いたらどうするのか」と不安は尽きないでしょう。本記事では、筆者が実際にアパートを建てて運営している体験談を交えながら、相続対策としてのメリットと安全性を確かめるポイントを具体的に解説します。最後まで読むことで、失敗を避けながら家族を守る方法が見えてきます。
アパート経営が相続対策になる理由
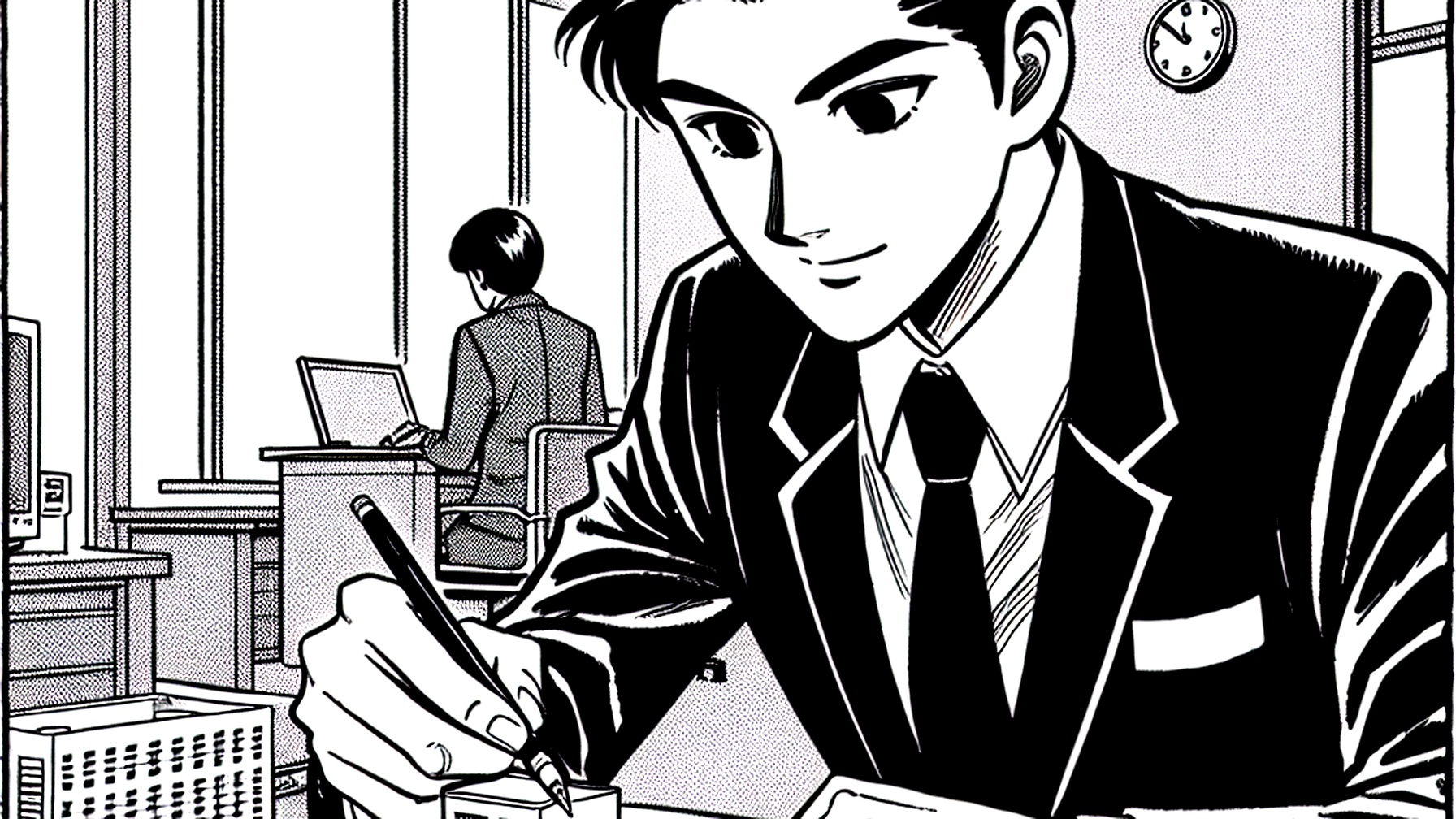
まず押さえておきたいのは、土地と建物の評価方法が異なるため、アパート経営は合法的に課税額を圧縮できる点です。相続税では土地の評価が路線価、建物は固定資産税評価額で計算され、いずれも実勢価格より低くなる傾向があります。
実は、賃貸用の建物や敷地にはさらに「貸家建付地」や「貸家評価減」と呼ばれる調整が加わります。つまり、更地のまま相続するよりも、アパートを建てて賃貸に出した方が課税上の圧縮効果が大きくなるわけです。
2025年度も継続する「小規模宅地等の特例」を活用すると、一定の面積までは80%の評価減が認められます。課税価格が1億円を下回るケースも多く、現金で相続するより負担は大幅に軽くなります。また、毎月の家賃収入があるため、納税資金を自ら生み出せる点も強みです。
ポイントは、評価減だけに目を奪われず、長期の収支シミュレーションを作成して家計のキャッシュフローを確認することです。後述する安全設計と組み合わせることで、相続税対策と資産運用の両立が可能になります。
私が実践した初期計画と安全設計
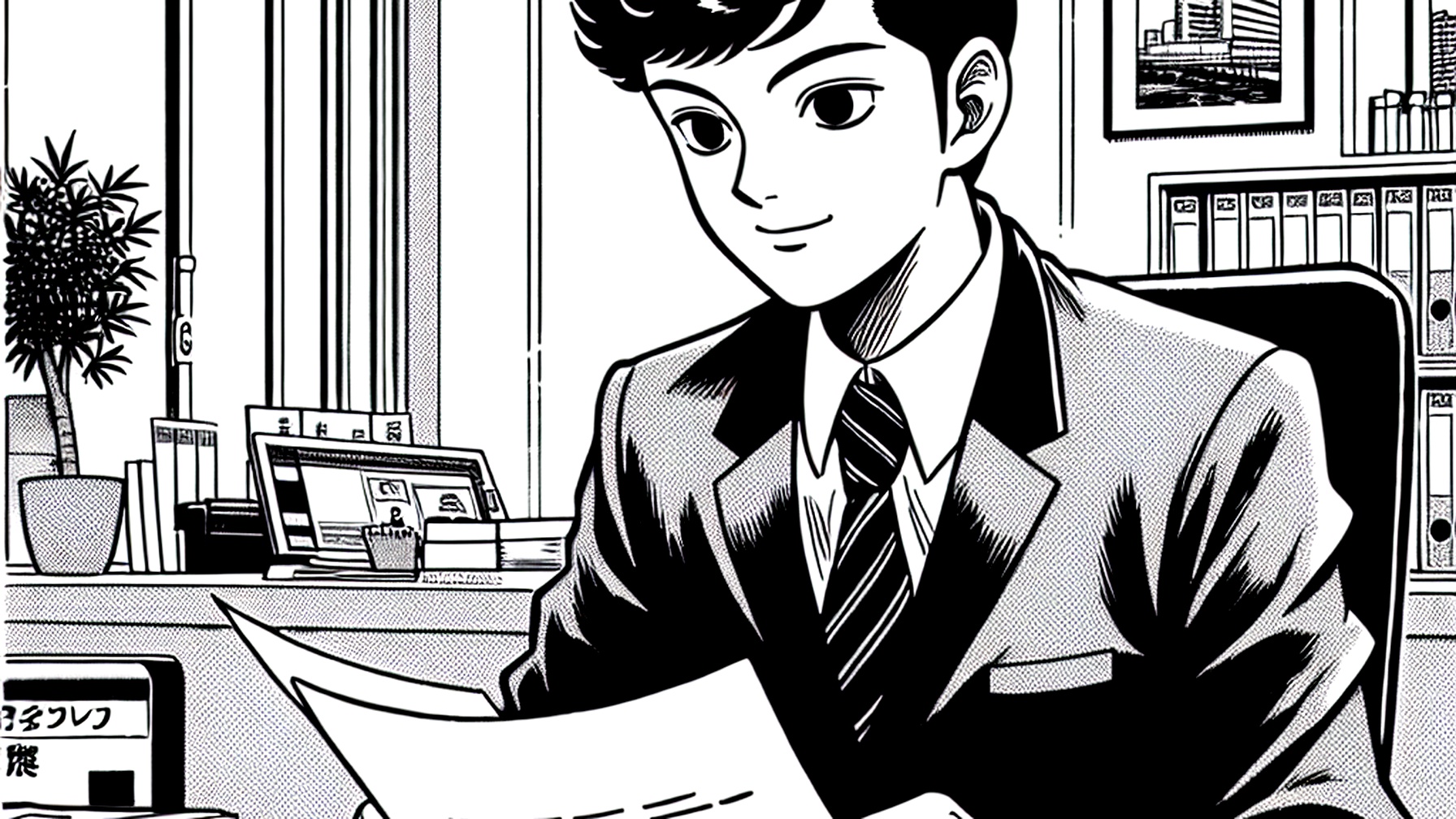
重要なのは、建てる前に「最悪のシナリオ」を具体的に想定することでした。私は金融機関に提出する事業計画書とは別に、空室率30%、金利上昇2%、修繕費年額15万円増という厳しい条件で再試算しています。
まず自己資金を物件価格の25%用意し、残債が家賃年収の7倍を超えないようにしました。これにより、金利が1%上がっても返済比率が家賃収入の50%を下回る安全圏を維持できます。また、家計とは別に毎月2万円を修繕積立に回し、10年後の大規模修繕費に備えました。
一方で、工事費用の削減だけを追う行動は避けました。安すぎる建築会社を選ぶと、後で雨漏りや断熱不足のクレームが発生し、結果的に入居率を下げる危険があります。私は大手ハウスメーカーと地元工務店の見積もりを比較し、構造保証10年と設備保証5年が付くプランを選択しています。
さらに、融資の契約書には「期間中の一括返済手数料無料」という条項を入れてもらいました。万が一、相続後に物件を売却する必要が生じても、違約金なしで残債を清算できるためです。このように、出口戦略まで織り込んだ設計が安全性を高めます。
入居率を守る運営術と最新データの活用
まず、安定運営には正確なマーケットデータが欠かせません。国土交通省住宅統計によると、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で、前年比0.3ポイント改善しました。地域差が大きいものの、需要が微増しているエリアでは適切な賃料設定が空室対策となります。
私が管理会社と共有している指標は、周辺5キロ圏内の平均賃料と成約スピードです。平均賃料を5%下回り、内覧から契約までの期間を10日以内に収めると、空室期間が短くなる傾向があります。これを実現するため、築年数に応じたリフォーム計画を前倒しで実施しています。
また、デジタル内覧システムを導入した結果、遠方からの転勤者にもアプローチでき、実際に2部屋がオンライン契約に至りました。ネット広告費用は月3万円ほどですが、空室が1カ月短縮されるだけで家賃6万円分の収入が増え、費用対効果は明らかです。
一方で、無理な家賃値下げは避けるべきです。値下げ幅が大きいと、次の更新時にも減額交渉を招きやすく、長期の家賃下落につながります。私の体験では、共用部の照明をLED化し、Wi-Fiを無料提供するなど付加価値を加える方が入居者満足度を維持できました。
税務と法律で失敗しないためのポイント
まず、税務上のミスは損失額が大きいため、毎年の決算時に税理士へレビューを依頼しています。特に減価償却の耐用年数を誤ると、将来の課税所得が急増する危険があるからです。
2025年度の税制では、消費税の仕入税額控除に関するインボイス制度が完全施行されています。登録番号を持つ業者との取引でないと控除が受けられないため、建築後の修繕や清掃も業者選定が重要になります。これは賃貸経営に新たなコスト意識をもたらしました。
一方、民法改正による賃貸借契約の敷金返還ルールも定着しました。トラブルを防ぐため、原状回復ガイドラインを契約書に添付し、入居時の室内写真をクラウド保存しています。退去精算がスムーズになり、裁判沙汰を回避できました。
相続発生後は、遺産分割協議で不動産をどう扱うかが感情面の火種になります。私は生前に家族会議を開き、「配偶者に50%、子ども二人に25%ずつ共有名義」とする遺言を作成しました。これにより、相続開始後の争いを防ぎ、金融機関の借り換え審査も円滑に進みました。
体験談から学ぶリスクと向き合う姿勢
ポイントは、成功例だけでなく失敗しかけた場面にも学びがあることです。私は竣工後3年目に給水管の漏水事故を経験し、20万円の修繕費が発生しました。火災保険のオプションに水濡れ特約を付けていたため、自己負担は1万円で済みましたが、保険未加入なら収支に大打撃だったでしょう。
また、近隣に大規模マンションが建設された際は、募集家賃を据え置いた結果、2カ月間の空室が生じました。これを機に、毎年春と秋に周辺開発計画を市役所で確認し、競合の動きを先取りする習慣ができています。
心構えとして、「リスクは必ず発生するもの」と捉えることが安全運営につながります。備えがあれば慌てずに対応でき、結果的に家族への負担も減ります。私自身、家族信託の相談や認知症リスクに備える任意後見契約まで検討し、運営の継続性を確保しました。
最後に、体験談はあくまで一例です。物件の立地や家族構成で最適解は変わります。専門家の意見を聞きつつ、自分の許容範囲を明確にしておくことが、長期にわたる安全経営の鍵となります。
まとめ
本記事では、アパート経営が相続対策として有効な理由から、筆者自身の安全設計、入居率維持の工夫、税務・法律面の注意点、そして体験談に基づくリスク管理までを紹介しました。結論として、評価減や家賃収入だけでなく、出口戦略と家族間の合意形成まで含めた総合設計が不可欠です。読者の皆さんも、まずは長期の収支計画と家族会議から始め、専門家と連携しながら一歩を踏み出してみてください。家族を守りながら資産を育てる未来がきっと開けるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅局住宅統計調査 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 相続税に関するFAQ – https://www.nta.go.jp
- 中小企業庁 インボイス制度特設サイト – https://www.chusho.meti.go.jp
- 法務省 民法改正に関する解説 – https://www.moj.go.jp
- 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 – https://www.retio.or.jp

