不動産に興味はあるけれど、物件を買うほどの資金や時間はない――そんな悩みを抱える人は多いものです。REIT(リート)なら比較的少額から参加でき、証券口座を通じた手軽な資産運用が可能になります。本記事では「始め方 REIT 資産運用」の基本を、仕組みから実践的なポートフォリオ構築まで丁寧に解説します。読後には、自分に合ったリスク管理の方法と2025年度の最新制度を踏まえた投資プランを描けるようになるはずです。
REITの仕組みと市場規模を押さえる
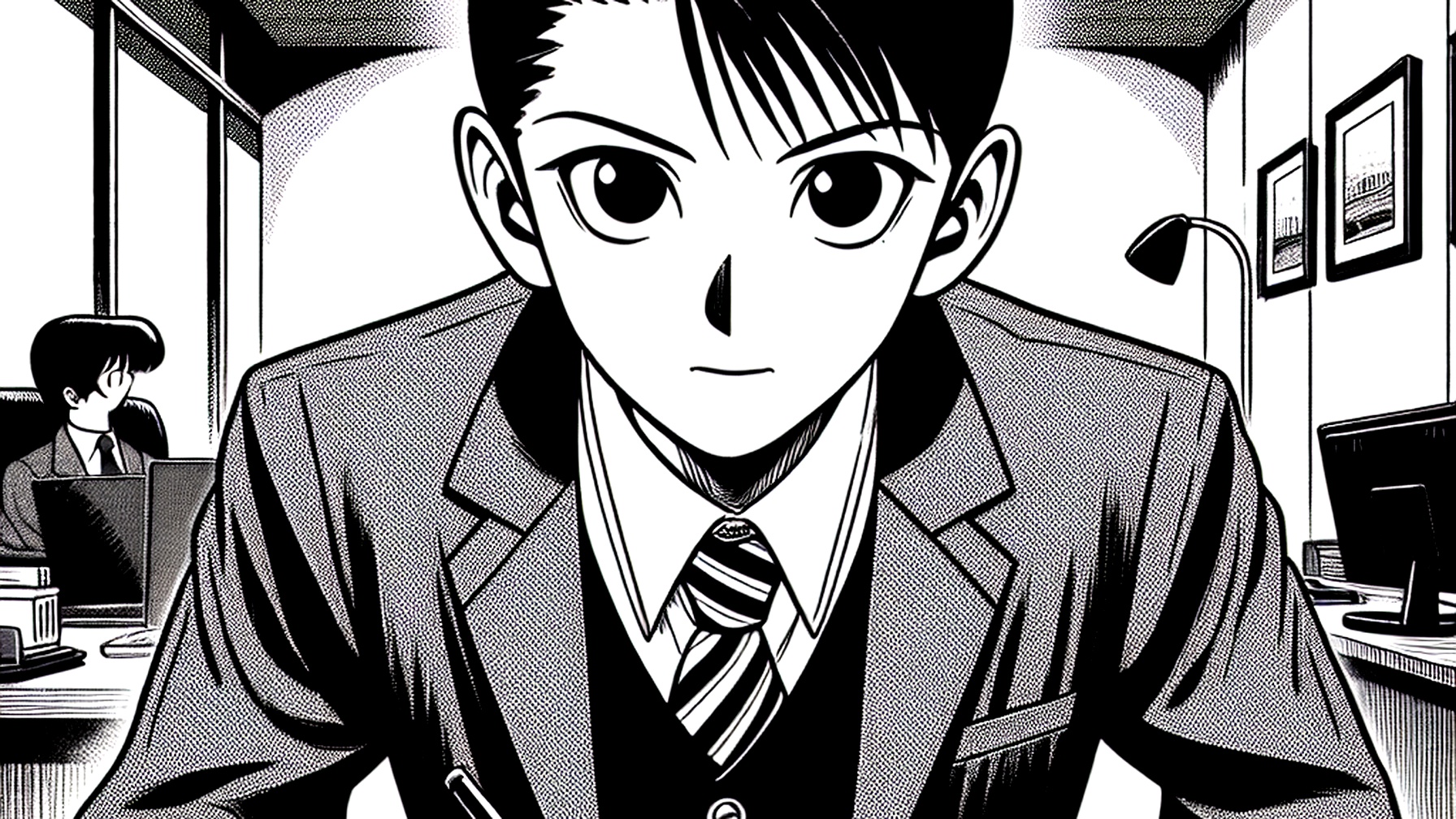
まず押さえておきたいのは、REITが「不動産投資信託」の略称であり、多数の投資家から集めた資金でオフィスビルや物流施設などを保有し、その賃料や売却益を分配する仕組みです。株式と同様に証券取引所で売買できるため、流動性が高く、少額から取引を始めやすい点が大きな特徴になります。
日本取引所グループの統計によると、2025年9月末時点で国内REIT総資産は約22兆円に達し、上場銘柄数は64本に拡大しました。つまり、国内だけでも多様な物件タイプや運用戦略を選べる環境が整っています。また、米国をはじめとする海外REITも証券口座で購入できるため、地理的な分散投資も視野に入ります。
重要なのは、REITが「投資信託」である以上、内部の運用会社が物件管理を代行することです。個別物件の修繕やテナント対応を自分で行う必要がないので、不動産運用に割く時間が限られる会社員や主婦層でも参入しやすいと言えます。一方で、物件の選定や運営の質は運用会社の手腕に左右されるため、財務指標だけでなくマネジメント体制にも目を向けることが欠かせません。
REITを資産運用に組み込むメリットとリスク
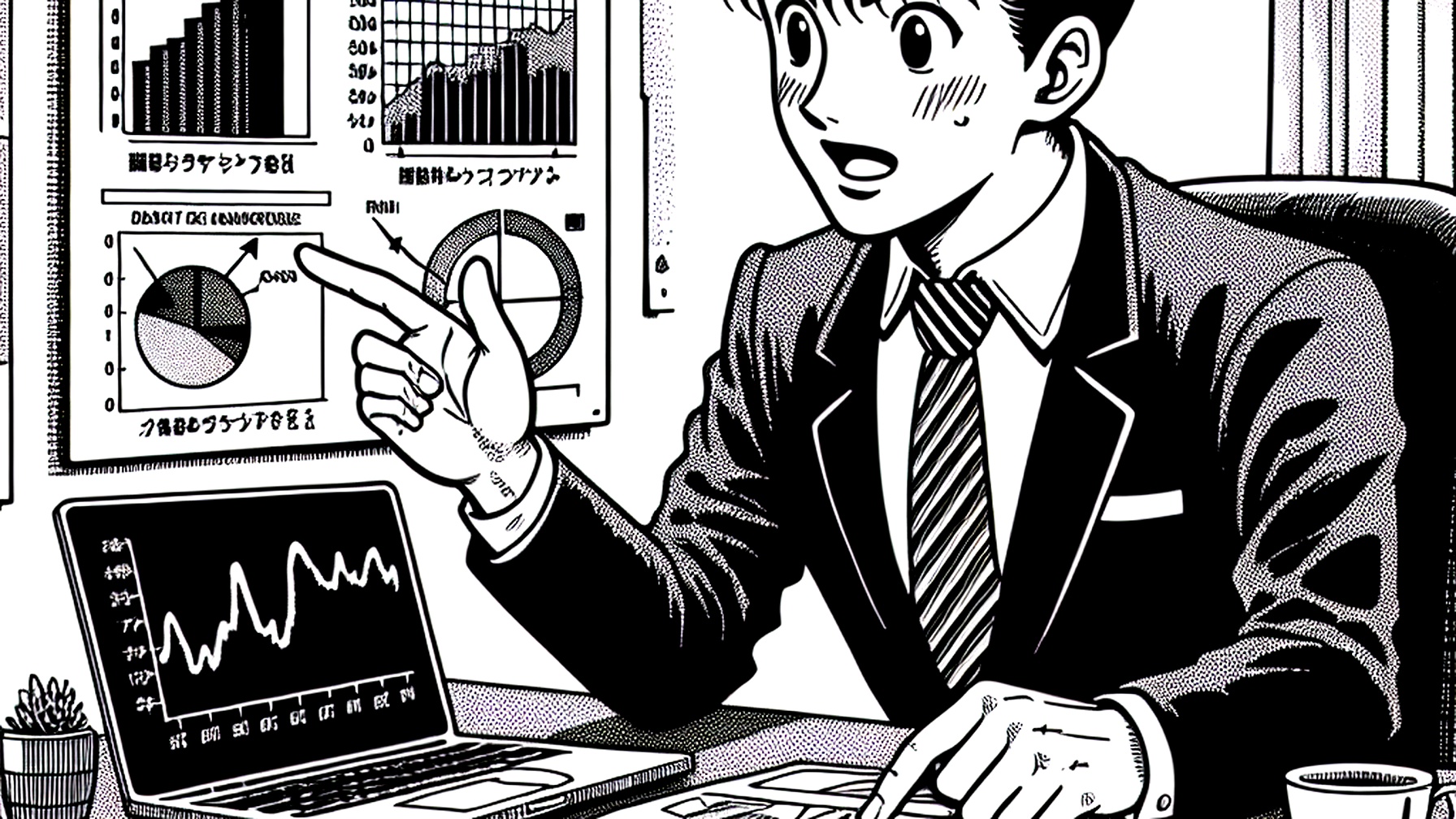
ポイントは、REITが「高配当」と「分散効果」の両面を持つことです。総務省家計調査によれば、リートの平均分配利回りは2025年9月時点で3.7%前後と、東証株式平均配当利回りの約2.3%より高い傾向があります。この分配金は四半期または半年ごとに受け取れるため、定期収入を重視する投資家には魅力的です。
一方で、不動産価格や金利動向の影響を受けるリスクがあります。日本銀行の金融政策が変更され長期金利が上昇すると、REITの資金調達コストが増え、分配金が減る可能性があるからです。また、オフィス系REITの場合、テレワークの定着で空室率が高まると賃料収入が下がります。つまり、物件タイプごとの市場環境を見極める目が求められます。
さらに、株式市場の急落時にはREIT価格も連動して下落しやすい点が忘れられがちです。価格変動を抑えたいなら、住宅やヘルスケア特化型など景気連動性の低いセクターを組み合わせると効果的です。過去十年のデータを振り返ると、物流系REITは景気後退局面でも比較的安定した賃料を維持しており、ポートフォリオの防御ラインとして機能しました。
証券口座開設から銘柄選定までの始め方
実は「始め方 REIT 資産運用」と聞いても、手順自体は株式投資と大きく変わりません。まずは証券会社で総合取引口座を開設し、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると確定申告の手間が軽くなります。次に、少額投資非課税制度である新NISAを活用すると、年間240万円までの買付分配金が最長無期限で非課税となる点が大きな利点です。
銘柄選定では、利回りだけでなく「NAV倍率(純資産価値倍率)」と「LTV(負債比率)」を併せて確認します。NAV倍率が1倍前後なら資産価値に対して公平な価格水準と判断しやすく、LTVが50%を超える高レバレッジ銘柄は金利上昇局面で高リスクになります。また、決算説明資料を読み、過去五期の稼働率推移や修繕計画まで目を通すと運用の安定度を測れます。
ここで注意したいのは、分配金利回りが高く見えても、一過性の物件売却益が含まれている場合がある点です。運用報告書のキャッシュフロー計算書に目を向け、営業活動によるキャッシュフローが安定的かを判断しましょう。つまり、数字の裏側を読み解く姿勢が長期的な成功には不可欠です。
ポートフォリオ構築と運用継続のコツ
重要なのは、REIT単体ではなく他資産とのバランスを取ることです。金融庁の資産形成シミュレーションでは、国内外株式70%、債券20%、REIT10%のモデルポートフォリオが、過去20年間でリスク調整後リターンを最大化した事例が示されています。ただし、年齢や家計状況によって適切な配分は変わるため、自分のリスク許容度を定量的に測ることが先決です。
運用を継続する際は、四半期ごとに基準価額と分配金の推移を記録し、目標利回りから乖離した場合はリバランスを検討します。特に海外REITを保有する場合、為替ヘッジの有無がトータルリターンを大きく左右するので、ヘッジコストと期待利回りのバランスを見極めてください。
また、分配金を受け取った後に再投資を行う「DRIP(分配金再投資)」戦略を取り入れると、複利効果が期待できます。国内REITではDRIP制度を公式に設けていない銘柄が多いため、受取後に自動買付設定を行うか、手動で買い増しする仕組みを作るとよいでしょう。つまり、運用ルールをあらかじめ決めておくことで、市場変動時に感情的な売買を避けられます。
2025年度の税制優遇と最新注意点
まず押さえておきたいのは、2025年度も新NISAが継続し、成長投資枠で年間240万円までのREIT投資が非課税対象になることです。非課税保有限度額は1,800万円のまま据え置かれているため、長期でコツコツ買い増す戦略が有効です。加えて、iDeCo(個人型確定拠出年金)では国内外REITファンドが選択肢に含まれており、掛金全額が所得控除となる点も見逃せません。
一方で、2025年度税制改正大綱では「法人課税の見直しに伴うJ-REIT特例措置の延長」が議論され、分配金控除制度は現行のまま2030年度まで延長される予定です。したがって、現時点で急いで売却する必要はありません。ただし、政府が掲げるGX(グリーントランスフォーメーション)方針を背景に、環境性能が低い物件を多く抱えるREITは追加投資負担の影響を受けるリスクがあります。
さらに、金融庁は2025年4月から「サステナビリティ情報開示基準」をREITにも適用しました。運用報告書にエネルギー消費原単位やCO₂削減目標の達成状況が義務付けられたため、環境指標を公開していない銘柄は今後の資金流入が鈍る可能性があります。つまり、銘柄選定の際には財務指標に加えてESG開示状況も確認することが不可欠になりました。
まとめ
ここまで「始め方 REIT 資産運用」の全体像を見てきました。REITは少額から不動産の賃料収入を得られる一方、金利や市場環境の影響を受けやすい資産です。仕組みを理解し、利回り・LTV・NAV倍率など複数の指標で銘柄を吟味し、株式や債券と組み合わせたバランス運用を意識しましょう。2025年度の新NISAや分配金控除延長を活用すれば、税負担を抑えた長期投資も可能です。自分のリスク許容度を見極め、定期的にポートフォリオを点検する習慣をつけることが、安定した収益への近道となります。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 不動産市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁 資産形成シミュレーション – https://www.fsa.go.jp
- 総務省 家計調査年報 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 2025年金融システムレポート – https://www.boj.or.jp

