不動産投資信託(REIT)で資産を拡大してきたものの、毎年の税金計算がわずらわしいと感じていませんか。特に分配金や売却益の扱いは、株式投資とは微妙に異なり、経験者でも戸惑う場面があります。本記事では「REIT 経験者向け 税金」に焦点を当て、2025年10月時点で有効な制度を踏まえながら、税負担を抑える具体策を解説します。仕組みを理解し、正しい申告と制度活用を行えば、手取り収益は大きく変わります。読み終えたとき、あなたの税務戦略が一段レベルアップするはずです。
REITの課税体系を整理する
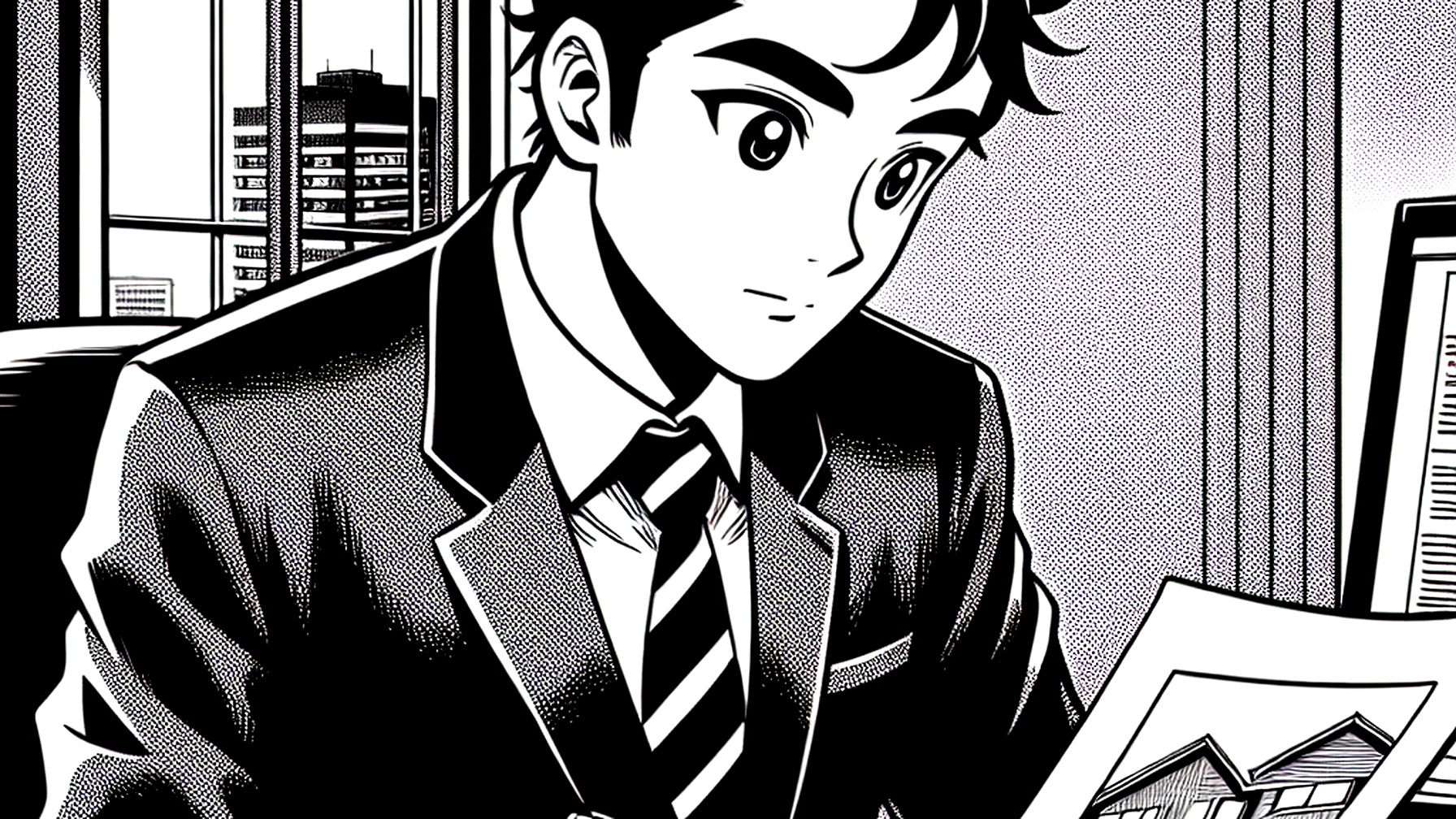
まず押さえておきたいのは、REITの利益に課される税の種類です。分配金は「配当所得」に区分され、上場株式と同じく源泉徴収20.315%が原則です。一方で、投資口の売却益は「譲渡所得」となり、こちらも分離課税20.315%が適用されます。つまり、表面的な税率は株式と共通ですが、損益通算の範囲や控除の有無で最終負担が変わります。
さらに、分配金には法人税がほぼ課されない仕組みが採用されています。J-REITは利益の90%超を分配することで、法人段階の課税が実質免除となるためです。投資家は個人段階で課税されるだけで済み、二重課税が低減されています。ただし、そのメリットを最大化するには、口座区分や確定申告の方法を選び直す必要があります。
国税庁の統計によれば、2024年度に源泉徴収のみで済ませた上場株式等の配当所得は約4兆円です。REIT分配金もこの流れに含まれ、多くの投資家が申告不要を選択しています。しかし、所得水準や医療費控除の有無によっては、総合課税へ切り替えたほうが有利なケースも出てきます。経験者こそ、毎年の試算を怠らないことが重要です。
分配金の税務処理を最適化するコツ
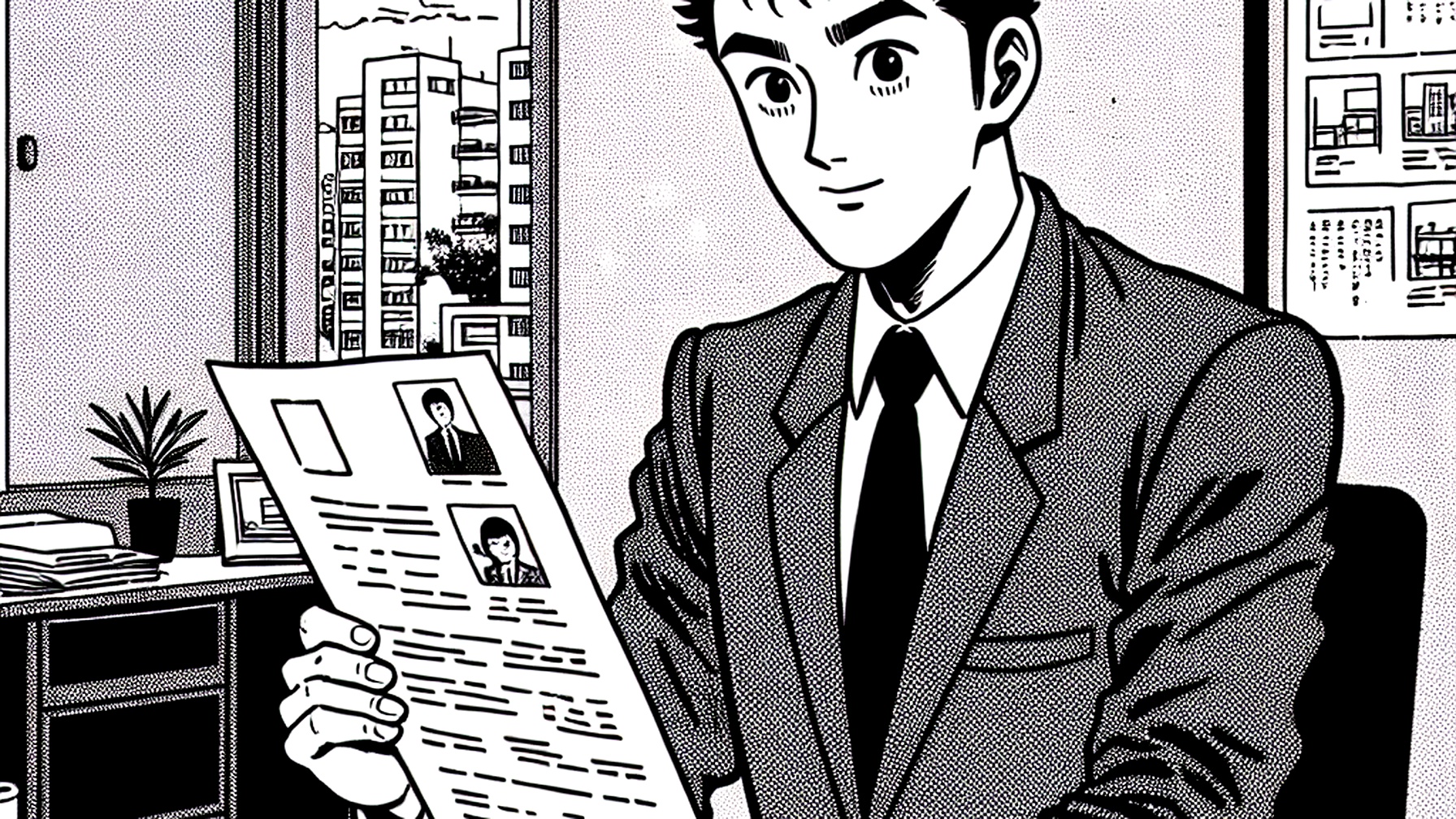
ポイントは、源泉徴収で完結させるか確定申告で取り戻すかを判断するフレームです。源泉徴収だけなら手間はかかりませんが、所得控除が多い年には「還付」の好機が潜んでいます。たとえば、小規模企業共済やふるさと納税で課税所得が大きく減る場合、総合課税を選択し配当控除の恩恵を受けると実効税率を下げられます。
ここで注意したいのが「配当控除率」です。J-REIT分配金は株式配当に比べ控除率が低く、所得税部分に限定されています。とはいえ、住民税は申告不要を選び、所得税のみ総合課税とする「住民税申告不要制度」を組み合わせれば、控除を確保しつつ住民税率を抑えることが可能です。
実は、医療費控除や住宅ローン控除を使う年も狙い目です。控除で課税所得が大幅に下がると、総合課税へ切り替えても税率5%区分に落ち込むことがあります。そのうえで源泉徴収分との還付が生じれば、手取りが数万円増える例も珍しくありません。毎年1月に「源泉徴収票」と「特定口座年間取引報告書」を並べ、利回りではなく税率を比較する習慣をつけましょう。
売却益・損失と損益通算の活用法
重要なのは、譲渡損失をいかに活かすかという視点です。REIT投資口の売却損は、同一年に発生した上場株式やETFの売却益と相殺可能です。さらに、相殺しきれない損失は翌年以降3年間繰り越せます。この仕組みは「譲渡損失の繰越控除」と呼ばれ、2025年度税制でも継続が決定しています。
たとえば、2025年にREITで50万円の損失が出ても、株式で50万円の利益があれば課税額はゼロになります。損が利益を打ち消すため、税率20.315%を負担せずに済みます。繰越控除を使う際は、確定申告が不可欠です。特定口座源泉徴収ありの設定でも、自動相殺は行われない点に気をつけましょう。
また、分配金と譲渡損失は損益通算の対象外です。分配金は配当所得、売却益は譲渡所得と課税区分が異なるためです。株式と同じ感覚で「配当と損失を相殺できるはず」と勘違いしやすいので注意してください。損失を翌年に繰り越す価値を測るため、含み損のある銘柄を年末に売却して損出しする手法も活用できます。手放したい銘柄を整理しつつ、翌年の税負担を軽くする一石二鳥の戦略です。
NISA・iDeCoとREIT投資の税効果
まず、2024年に刷新された新NISAは、2025年も恒久制度として続きます。年間360万円、通算1,800万円の投資枠が用意され、売却益と分配金が非課税です。REIT銘柄も投資対象に含まれるため、経験者ほど枠のフル活用が求められます。一般口座で運用している銘柄を順次NISA枠に移すと、将来の税負担を大幅に減らせます。
一方で、企業年金がない個人事業主やフリーランスの方はiDeCo(個人型確定拠出年金)も有力です。掛金が全額所得控除となるため、積立時点で税軽減を享受できます。現行制度ではREIT専用ファンドの品ぞろえが限定的ですが、国内外REITに分散投資するバランス型商品が増えてきました。分配金非課税のうえ、60歳以降の受け取りも公的年金控除や退職所得控除を利用できるので、多段階で税優遇が重なります。
ただし、NISA・iDeCoともに非課税枠の再利用はできません。NISAで売却後に枠を使い切ると、再投資は翌年以降になります。iDeCoは60歳まで原則引き出せない流動性の制約があるため、生活資金とのバランスを考慮して掛金を設定しましょう。
2025年度の税制改正ポイント
ポイントは、特定口座年間取引報告書の電子データ連携強化です。2025年分の確定申告から、Myナンバー連携により証券会社の取引情報が自動入力されます。手入力の手間が減る一方、申告漏れが検出されやすくなるため、計算ミスには注意が必要です。
また、税制改正大綱では「投資促進税制」の一環として、個人が保有する上場株式等の配当課税の負担軽減を議論中です。ただし、2025年10月時点で具体的な税率変更は決定しておらず、REITの源泉税率20.315%は据え置きとなります。不確実な情報に基づき行動するのではなく、決定次第公式情報を確認してから対応しましょう。
加えて、地方税電子化の進展により、翌年2026年度から住民税の申告不要制度もオンライン選択が可能になる予定です。紙の申告書を提出していた投資家は、今年のうちにe-Taxと連携する「eLTAX」の準備を進めておくとスムーズです。
まとめ
結論として、REIT投資の税金対策は「分配金の課税区分」「損益通算の可否」「非課税制度の活用」を正しく組み合わせることで最大効果を発揮します。源泉徴収で完結させる年と、確定申告で還付を狙う年を切り替える柔軟性が、経験者の手取りを押し上げます。
税制は毎年細かく更新されるため、金融庁や国税庁の公式情報を定期的にチェックし、最新ルールに合わせて戦略を微調整してください。行動としては、年末までに含み損ポジションの精査、NISA枠の埋め合わせ、そしてe-Tax環境の整備を進めることをおすすめします。税知識を味方につけ、REIT投資のリターンをさらに高めましょう。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp
- 総務省 eLTAX – https://www.eltax.lta.go.jp
- 財務省「令和6年度税制改正大綱」 – https://www.mof.go.jp
- 東京証券取引所 J-REITデータ – https://www.jpx.co.jp
- 独立行政法人 確定拠出年金情報サービス – https://www.dcnenkin.go.jp

