新築アパートへの投資は、築浅プレミアムや最新設備の魅力から「初心者でも始めやすい」と語られがちです。それでも、ローン返済が計画どおり進むのか、空室が長引かないかといった不安を抱く人は少なくありません。実は、建築コストの高騰や人口動向の変化など、表面化しにくいリスクが複数存在します。本記事では、2025年10月時点の最新データを用いながら、新築アパートに潜む代表的なリスクと対策を基礎から解説します。読み終えるころには、物件選定や資金計画で何に注目すべきかが具体的にイメージできるはずです。
なぜ新築アパートに注目が集まるのか
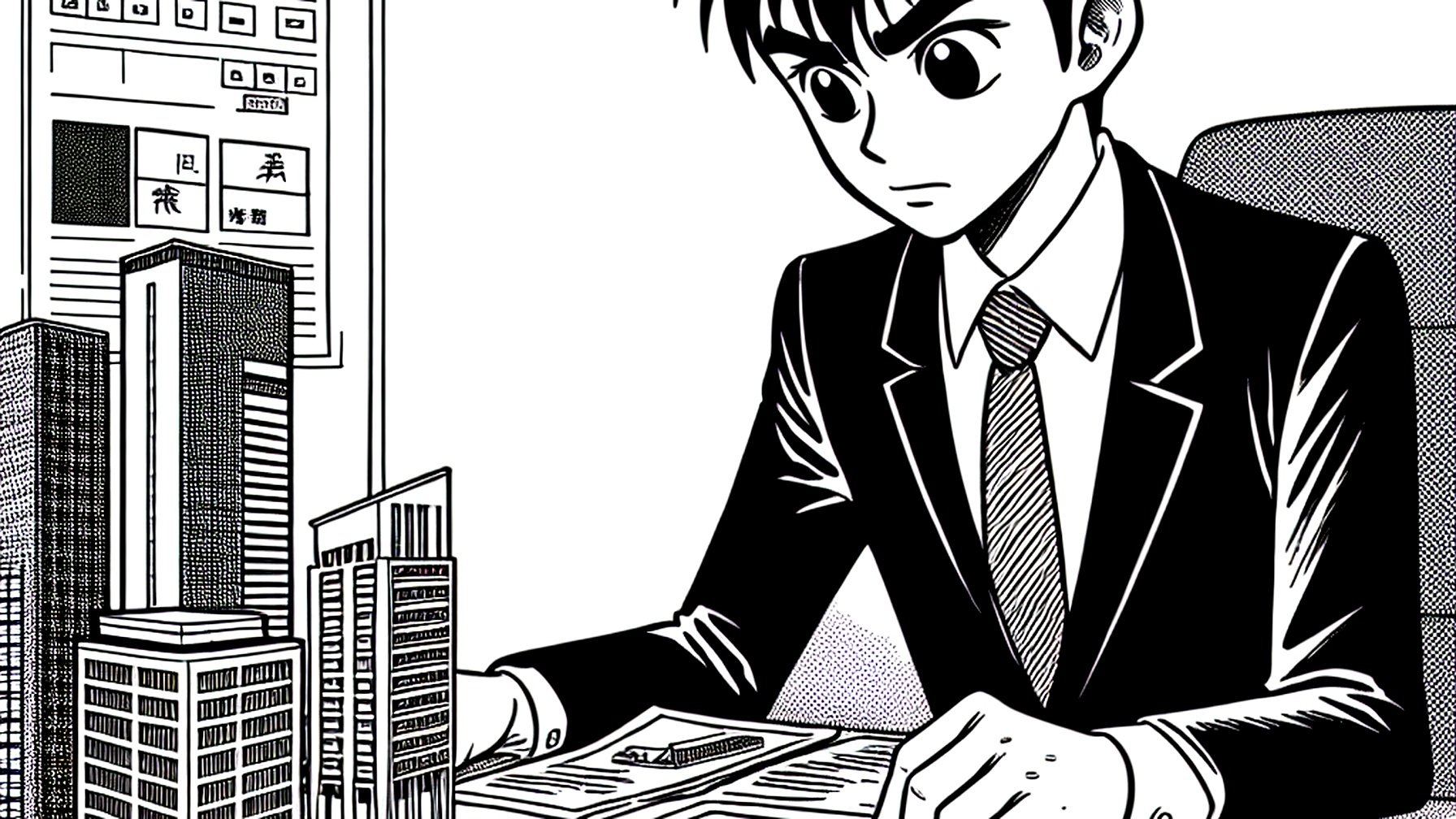
まず押さえておきたいのは、新築アパートが投資家の関心を集める背景です。利点を理解したうえでリスクを比較すると、判断の精度が高まります。
新築物件は減価償却期間が長く、初期数年間の節税効果が見込めます。また、銀行の融資審査では築年数が浅いほど評価が高く、金利も抑えやすい傾向があります。さらに、最新の住宅設備を備えているため、広告では「高額賃料でも入居が決まりやすい」と強調されがちです。
一方で、広告の主な情報源は販売会社や施工会社です。そのため、想定家賃がやや楽観的になったり、修繕費の計上が後回しになったりするケースが散見されます。言い換えると、利点が前面に出るほどリスクが見えづらくなる構造が存在します。
2020年代後半は地方圏で人口減少が続き、国立社会保障・人口問題研究所の推計では2030年までに30代以下の転入超過が見込める都市は全国の15%前後にとどまります。つまり、立地や需給を厳密に見極めないと空室率が高まりやすく、メリットが一転してデメリットになる可能性があります。これが次章で扱う利回りの「見かけとのズレ」につながります。
表面利回りの罠と実質利回り
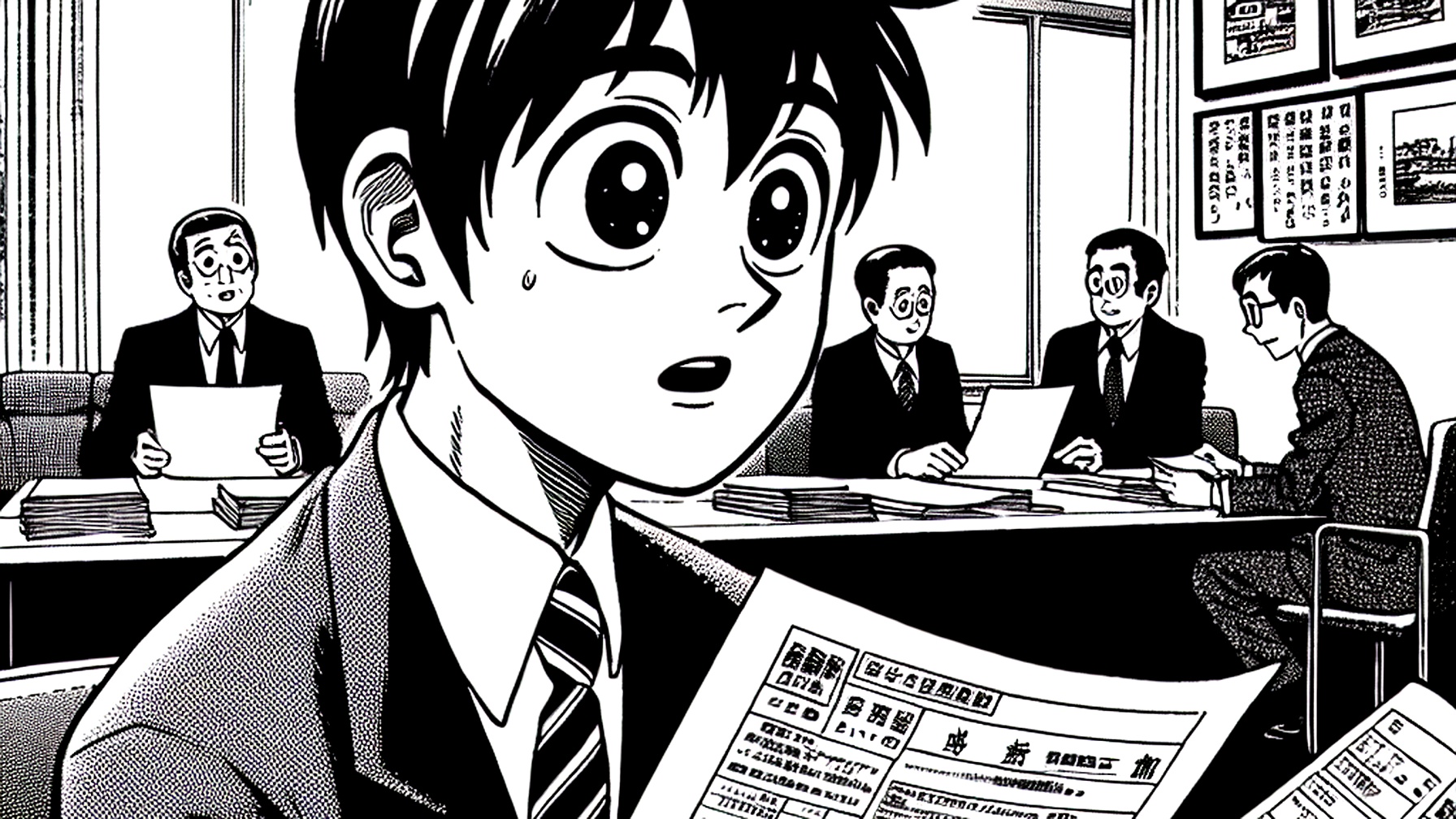
ポイントは、広告に記載された表面利回りと、最終的に手元へ残る実質利回りが大きく異なる点です。数値の差を理解しないまま購入すると、キャッシュフローが赤字に転落しかねません。
表面利回りは「年間想定家賃÷購入価格」で算出されます。例えば家賃600万円、物件価格1億円なら6%です。しかし維持費や空室ロスを差し引くと、実質利回りは4%台に下がることが珍しくありません。維持費には管理会社への手数料、固定資産税、保険料、長期修繕積立が含まれ、毎年家賃収入の15〜20%を占めるのが一般的です。
さらに、国土交通省住宅統計によると2025年8月時点の全国アパート空室率は21.2%です。仮に空室率を15%と想定しても、年間家賃は510万円に減ります。ここから設備更新費を年30万円見込むと、実質利回りは約3.8%まで低下します。この数値をローン金利と比較し、金利1.9%で借りる場合でも手元に残るのはわずかです。
つまり、原価償却分だけでなく空室や修繕も織り込み、厳しめのシナリオでシミュレーションを作ることが不可欠です。机上の数字より「手残り」が縮む現実を受け入れたうえで、投資を判断する必要があります。
空室リスクを左右する要素
空室率の変動は収益性に直結しますが、立地だけを見ても不十分です。人口動態、物件仕様、管理体制が相互に影響し合うためです。
まず人口動態ですが、エリア全体の人口減少に加え、世帯構成の変化を確認しましょう。例えば地方中核都市であっても単身世帯が減少しファミリー層が微増している地域では、1K中心の新築アパートが過剰供給になりがちです。また、高齢化が進む地区では階段のみの三階建て物件が敬遠され、エレベーター付きの物件より長期空室になりやすい傾向があります。
次に物件仕様です。2025年以降、断熱等級5以上が標準化しつつあります。基準を満たさない建物は賃料が下落しやすく、将来的なリフォーム費用も増えます。仕様を確認する際は、断熱性能、ネット環境、宅配ボックスの有無など、入居者が重視するポイントを網羅的にチェックしてください。
最後に管理体制です。入居募集を一社専任にすると広告露出が少なくなる場合があり、空室期間が伸びる恐れがあります。複数仲介会社へ情報が流れる「一般媒介」に切り替える、内覧時の清潔感を保つなど、オーナー主導の工夫が欠かせません。これら三つの視点を総合してはじめて、空室リスクを実態に近い形で把握できます。
建築コスト上昇と資産価値の推移
実は、建築費の高騰と二次流通市場の価格ギャップが出口戦略を難しくしています。完成後数年で売却したい場合、この差が重くのしかかります。
財務省「建築資材価格指数」によれば、2021年から2025年までの4年間で主要資材は平均18%値上がりしました。同じ設計でも2025年着工分は、2021年着工分より1戸あたり80万円前後高くなる計算です。建築会社は価格転嫁を余儀なくされ、その結果、販売価格が利回りの計算に合わなくなるケースが増えています。
一方、中古市場では築5年程度でも「新築プレミアム」が剝がれ、成約価格が新築時より10〜15%下落する例が目立ちます。日本銀行の不動産市況レポート(2025年6月)でも、首都圏の木造アパート平均売買価格は築浅期に急落する傾向が示されています。高い建築費で購入し、数年後に売却すると損失が出やすいのはこのためです。
つまり、長期保有を前提にしても出口価格を現実的に見積もり、想定利回りを上回る収益が得られるかを確認しなければなりません。加えて、設備更新費を積み立てておくことで資産価値を維持し、売却時の評価減を抑えやすくなります。
2025年度の制度とリスク対策
2025年度に利用できる制度や金融商品の特徴を把握すると、リスク軽減策が見えてきます。ここでは賃貸住宅に適用可能な代表例を紹介します。
まず、2025年度も継続している「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、一定の省エネ基準を満たす賃貸住宅の改修費を一部補助します。新築時点で高断熱仕様にしておくと、将来の改修費を抑えやすく、補助対象になりやすい点は見逃せません。また、地方税法の特例により、省エネ性能認定を受けた賃貸住宅は固定資産税が新築後3年間おおむね半額になります。取得時に証明書の取得費用を惜しまないほうが、実質利回りを底上げできます。
金融面では、2025年10月現在、民間銀行のアパートローン金利は変動1.4〜2.1%が中心です。長期固定型でも1%台後半が登場し、金利上昇リスクを抑えられます。返済比率を家賃収入の50%以下に設定すると、空室率が25%程度まで悪化しても返済が滞りにくくなります。
最後に保険です。火災保険に加え、家賃保証会社と連携することで滞納リスクを低減できます。ただし保証料は家賃の3〜5%を占めるため、利回り計算に組み込むことを忘れないでください。制度や商品を組み合わせ、リスクヘッジを多層化することで、投資の安定性が大きく向上します。
まとめ
この記事では、新築アパート投資に潜む代表的なリスクを五つの視点から整理しました。表面利回りと実質利回りの差、空室率を左右する複合要因、建築費高騰による出口価格のギャップ、そして2025年度に活用できる制度や金融商品の要点を押さえることで、リスクを可視化できます。投資判断の前には、厳しめの収支シミュレーションと複数シナリオの検証を行いましょう。そうすれば、不確実な市場環境でも安定したキャッシュフローを確保できる可能性が高まります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査(2025年8月速報) – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査(2023年) – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 不動産市況レポート(2025年6月号) – https://www.boj.or.jp
- 財務省 建築資材価格指数(2025年4月) – https://www.mof.go.jp
- 国土交通省 長期優良住宅化リフォーム推進事業(2025年度案内) – https://www.mlit.go.jp/housing/reform

