物価がじわじわ上がるいま、預金だけで資産を守るのは心もとないと感じる人が増えています。そこで注目されるのが「不動産投資 インフレ対策 デメリット」というテーマです。しかし、家賃が上がるなら安心という単純な話でもありません。本記事ではインフレ下で不動産に投資する利点と落とし穴を分かりやすく整理し、2025年9月時点の制度やデータを踏まえて具体的な判断材料を示します。読み終えたころには、自分に合う戦略を描けるはずです。
なぜインフレ局面で不動産投資が語られるのか
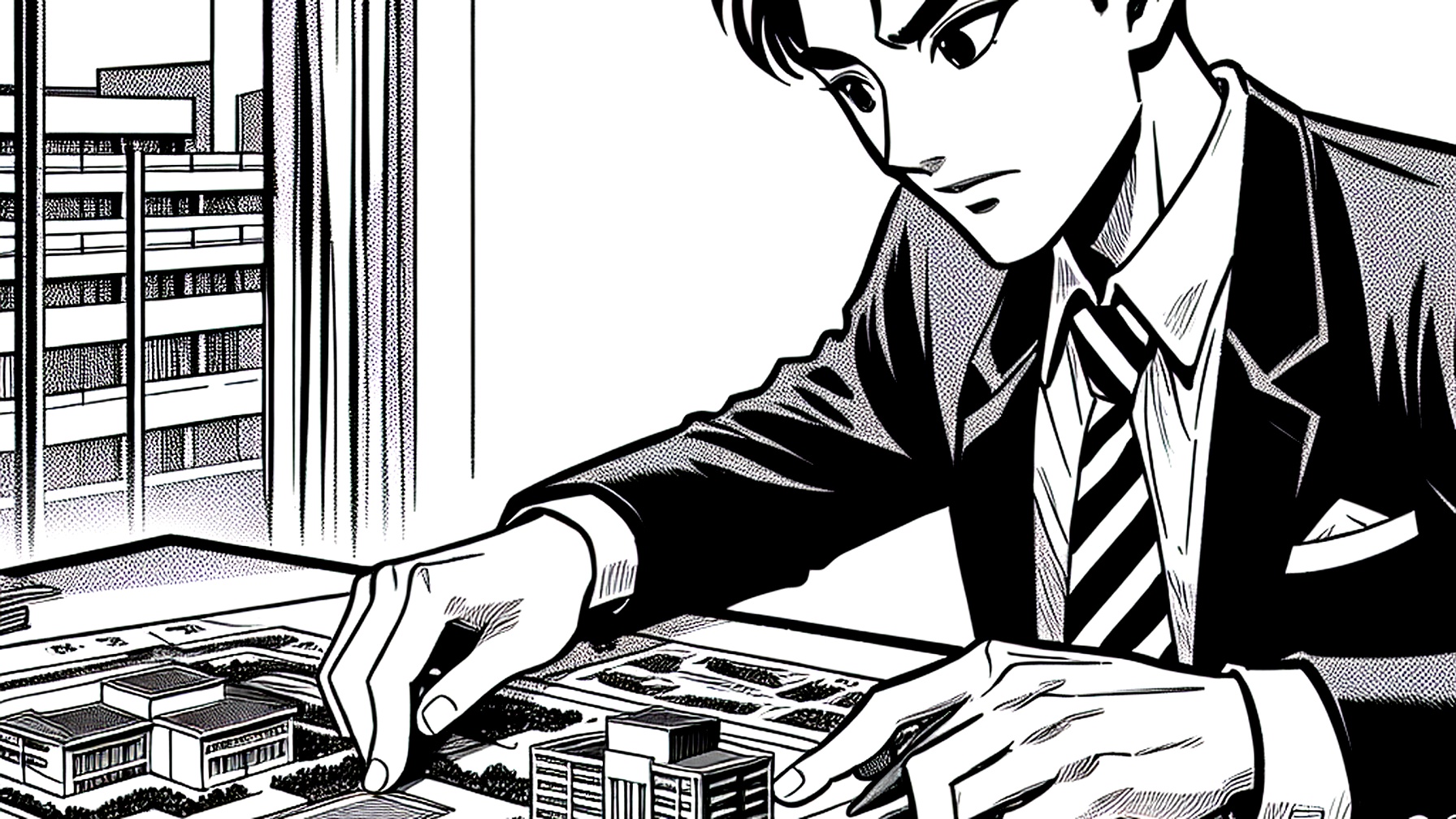
まず押さえておきたいのは、不動産の賃料や物件価格がインフレに連動しやすいという構造です。総務省の消費者物価指数では2025年7月時点で住宅関連サービスが前年同月比2.8%上昇し、同期間の預金金利平均0.02%を大きく上回りました。つまり現金を銀行に置くより、家賃収入を得るほうがインフレを転嫁しやすいのです。
しかし、賃料は地域や物件タイプによる差が大きいです。都市部ワンルームは空室率が低く、家賃改定が年1回程度行われる一方、地方のファミリー向け物件は人口減少で値上げが難しいケースもあります。また、不動産は現物資産であるがゆえにインフレ時の代替需要を集めやすく、それが投資マネーを呼び込み価格を押し上げる循環も生みます。
金融面でも効果があります。インフレが進むと実質的な債務負担が軽くなるので、固定金利で長期ローンを組んだ投資家ほど利息の相対負担が減る仕組みです。固定金利1.9%で30年借り、物価が平均3%で上がるシナリオなら、返済額は名目固定でも実質的には目減りします。
インフレ対策として得られる三つの効果
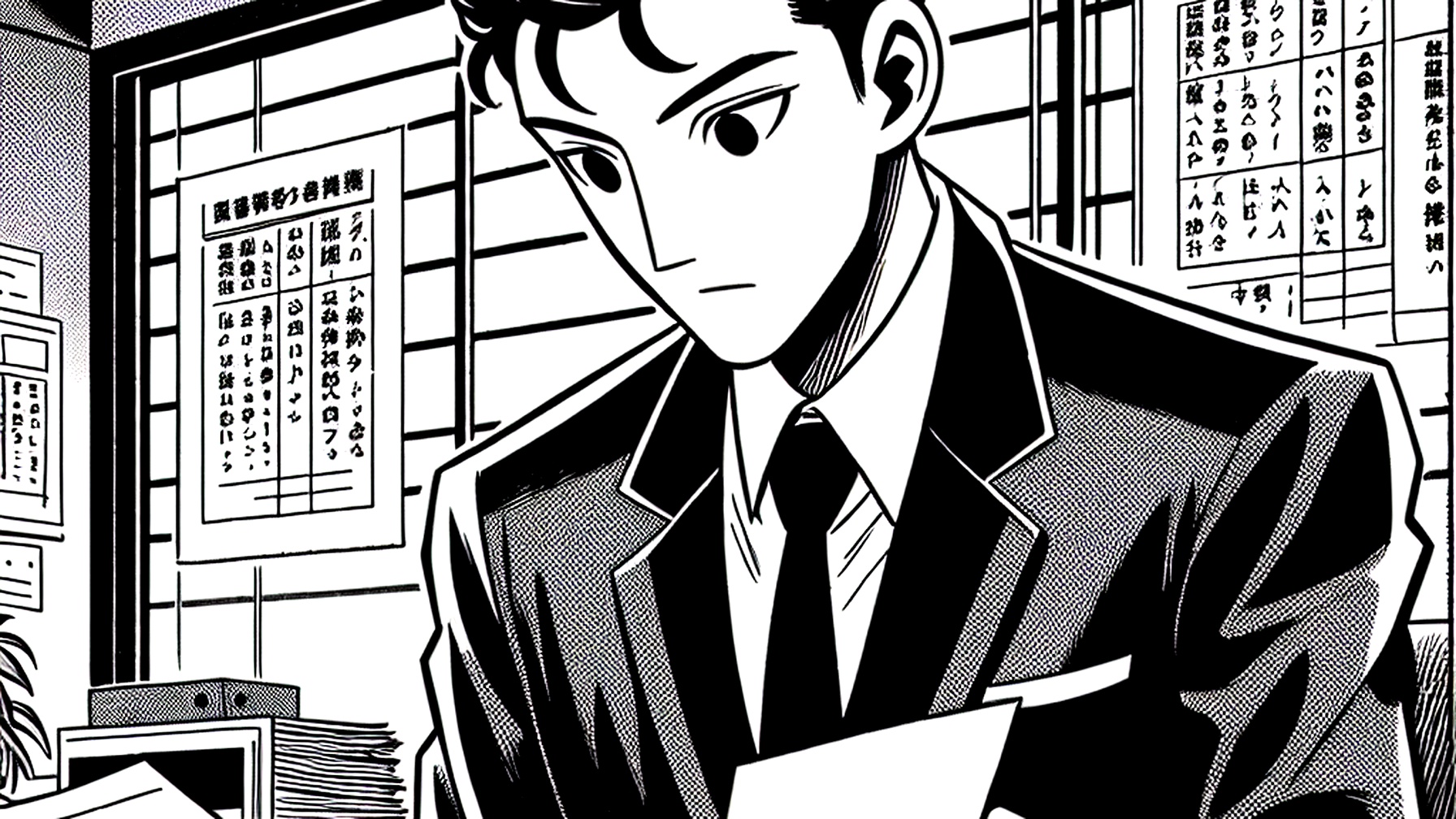
重要なのは、インフレ局面で不動産がもたらす主な効果を具体的に理解することです。大きく分けると「現金価値の目減り回避」「家賃収入の上昇ポテンシャル」「節税メリット」の三点になります。
第一に現金価値の目減り回避です。インフレ率が年3%続くと、10年後には100万円の購買力が約74万円相当に縮みます。一方、同じ期間で物件価格や家賃が3%ずつ上昇した場合、キャッシュフローはほぼ実質維持されるため、資産全体として購買力を守りやすくなります。
第二に家賃収入の上昇ポテンシャルがあります。東京都心の築浅ワンルームでは2022〜2024年に平均家賃が約4%上がり、さらに2025年上半期も2%上昇しました(国土交通省・不動産取引価格情報)。家賃が上がると利回りが高まり、売却価格にも反映されるため、キャピタルゲイン(値上がり益)も期待できます。
第三は節税メリットです。2025年度も「住宅ローン減税」が賃貸併用住宅で適用可能で、最大控除額は年額21万円、控除期間は13年間となっています。また、不動産所得は減価償却費を計上できるため、現金支出がなくても課税所得を圧縮できます。このように複数の節税策を組み合わせることで、インフレ率以上の純利益を確保する事例も少なくありません。
見落としがちなデメリットとリスク
一方で、インフレだからといって無条件に不動産投資を選ぶと痛い目に遭います。ポイントは「流動性の低さ」「維持コストの上昇」「金利上昇の影響」の三つです。
流動性の低さは現物資産の宿命です。急に現金が必要になっても、売却には平均3〜6か月を要し、価格も買い手次第になります。特に築古や利便性の低い物件は、インフレ下でも買い手の選別が厳しく、売却価格が伸びない可能性があります。
次に維持コストの上昇です。物価が上がると修繕費や管理費も高くなります。2025年4月の建設労働者賃金は前年比4.5%上昇し、クロス張り替えや設備交換の見積もりが1割高くなったという報告もあります。家賃が上がってもコスト増が並走すれば、手残りが減る点に注意が必要です。
最後に金利上昇リスクがあります。インフレを抑制するために日本銀行が政策金利を引き上げれば、変動金利ローンの返済額が増えます。2025年7月にメガバンクの変動金利は平均0.825%まで上昇し、2023年比で0.25ポイント高くなりました。借入5,000万円、残期間25年の場合、月返済は約5,600円増えます。小さく見えても複利的にキャッシュフローを圧迫する要因です。
デメリットを抑える実践的な対策
実は、前述のリスクを完全に避けることは難しいものの、適切な対策で影響を小さくできます。ここでは現役投資家が実践する方法を三つ紹介します。
まず、ローンは固定金利と変動金利を組み合わせる戦略が有効です。例えば購入時に調達額の7割を固定、3割を変動にしておくと、金利上昇局面ではダメージを抑えつつ、低金利メリットも一部享受できます。住宅金融支援機構「フラット35(2025年度)」は団信込み年1.79%で融資が可能なため、長期の安定負債として利用する投資家が増えています。
次に、修繕積立シミュレーションを厳しめに設定します。マンション管理センターのデータでは、築20年の分譲マンションの大規模修繕費は平均240万円ですが、建築資材の高騰を考慮して2割上乗せしたモデルを作れば、インフレによる追加負担にも耐えやすくなります。
さらに、出口戦略の複線化が欠かせません。売却だけでなく、親族への相続や個人から法人へ移す「ローリング」も視野に入れると、相場が不安定でも選択肢を確保できます。法人保有に切り替える際は、譲渡所得税を圧縮できるタイミングを税理士と綿密に計算することが大切です。
2025年度の制度と市場動向
基本的に、制度の活用はインフレ対策の効果を底上げします。2025年度時点で有効な主要制度は、住宅ローン減税のほか、「固定資産税の住宅用地特例」「所得税の損益通算」などです。住宅用地特例は小規模住宅用地200㎡までの課税標準が6分の1に軽減され、結果として保有コストを抑えられます。
市場動向も押さえておきましょう。国土交通省「不動産価格指数」によると、首都圏の住宅総合指数は2025年6月時点で前年同月比4.1%上昇し、地方中核都市は2.2%の伸びにとどまりました。インフレ全体が均一に進んでいるわけではなく、エリア格差が拡大しています。
また、賃貸住宅管理業法が2024年6月に全面施行され、管理業務の外部委託では登録事業者に限られるようになりました。これにより管理手数料が平均0.2ポイント上昇したケースもありますが、サービスの質が上がり空室期間が短縮したという報告もあり、コストと効果を秤にかける必要があります。
以上のように、制度と市場の最新情報を随時確認しながら、インフレ対策としての不動産投資をアップデートする姿勢が求められます。
まとめ
ここまで、不動産投資がインフレ局面でどのように機能するかを利点と欠点の両面から見てきました。現金価値の目減りを抑え、家賃と物件価格の上昇を味方につけるメリットは大きい一方、流動性や維持コスト、金利変動といったデメリットが存在します。結論として、インフレ対策で成功する鍵は「エリア選定」「資金計画」「長期的なリスク管理」の三本柱です。今日からできるのは、固定と変動を分けた借入シミュレーションを作り、修繕積立を現実的な数字で見直すこと。実践を通じて、物価上昇に負けない資産形成を目指しましょう。
参考文献・出典
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 住宅金融支援機構 フラット35金利情報 – https://www.jhf.go.jp
- 不動産取引価格情報検索 – https://www.land.mlit.go.jp
- 一般社団法人 マンション管理センター – https://www.mankan.or.jp

