家賃収入で資産を増やしたい。でも周囲には「アパート経営で大損した」と嘆く知人もいる──そんな声をよく耳にします。立地や融資条件が似ていても、成功する人と失敗する人の差は意外に小さな判断の積み重ねです。本記事では、アパート経営 失敗する人に共通する思考パターンをひも解き、具体的な対策を提示します。投資初心者でも理解できるよう、資金計画・空室対策・税務の基本を最新データとともに解説しますので、読み終える頃には“負けパターン”を避ける術が身につくでしょう。
失敗を招く三つの思い込み
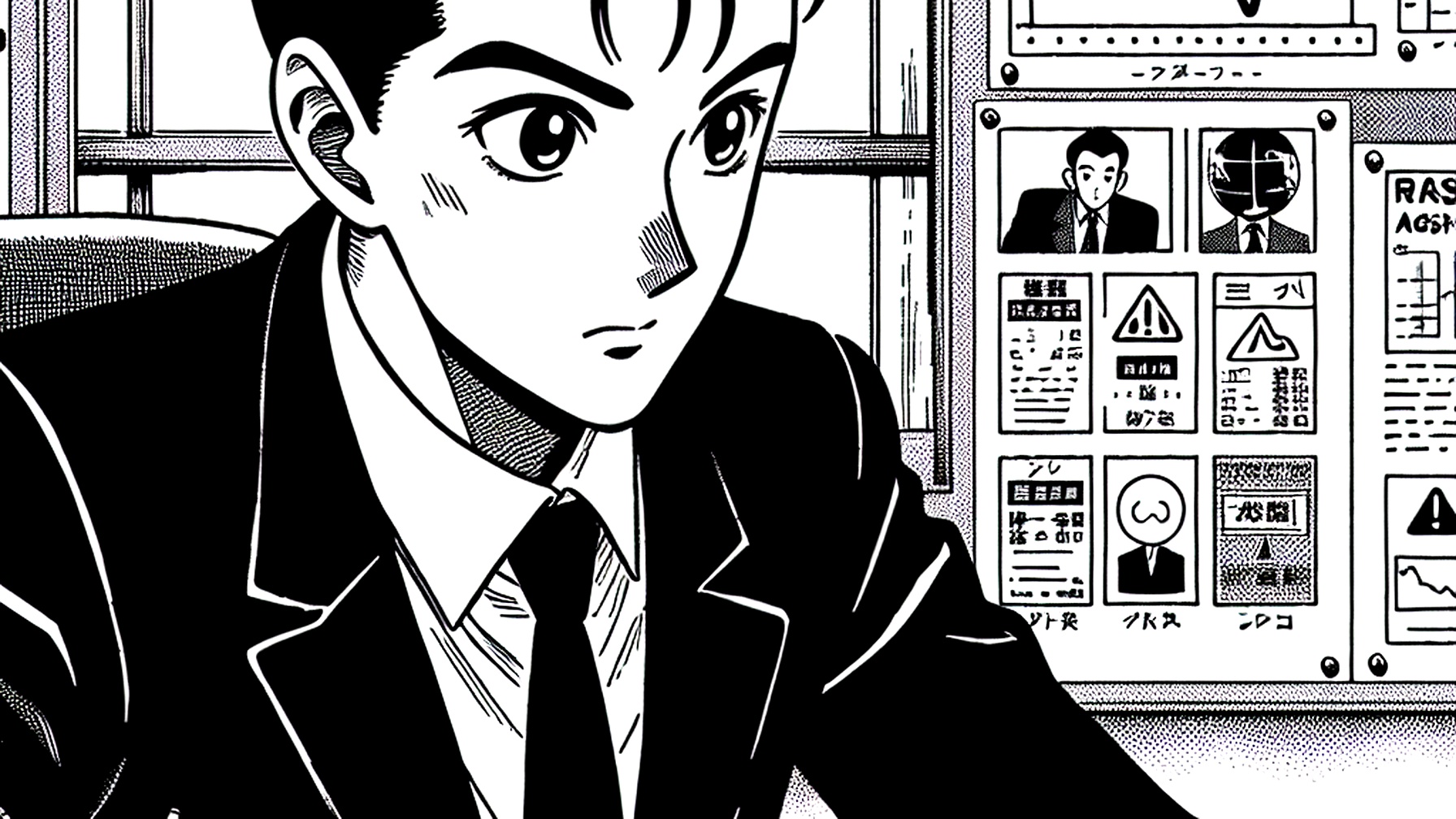
まず押さえておきたいのは、失敗を呼び込む人が抱えがちな三つの思い込みです。第一に「人口が多い地域なら必ず埋まる」という過信、次に「金利は当面上がらない」という願望、そして「管理会社に任せれば安心だろう」という委任依存です。
国土交通省の住宅統計(2025年8月)によると、全国平均のアパート空室率は21.2%ですが、都市部でも築25年以上の木造アパートでは30%を超える地域が珍しくありません。つまり人口だけでは埋まらない現実が存在します。また、日本銀行が示す長期金利見通しは0.5%前後で推移しているものの、2023年からの緩やかな上昇傾向は続いており、2%近い上昇シナリオも想定しておくべきです。さらに管理会社の質は千差万別で、委託契約書を精査しないと広告費や修繕費が膨らむリスクがあります。
一方で、こうした思い込みを早期に修正できれば、損失を最小限に抑えられます。具体的には、空室率の地域差を細かく調べる、市場金利の感度分析を行う、契約前に管理会社の実績を確認する、といった基本動作を徹底することが肝要です。
資金計画が甘いとどうなるか
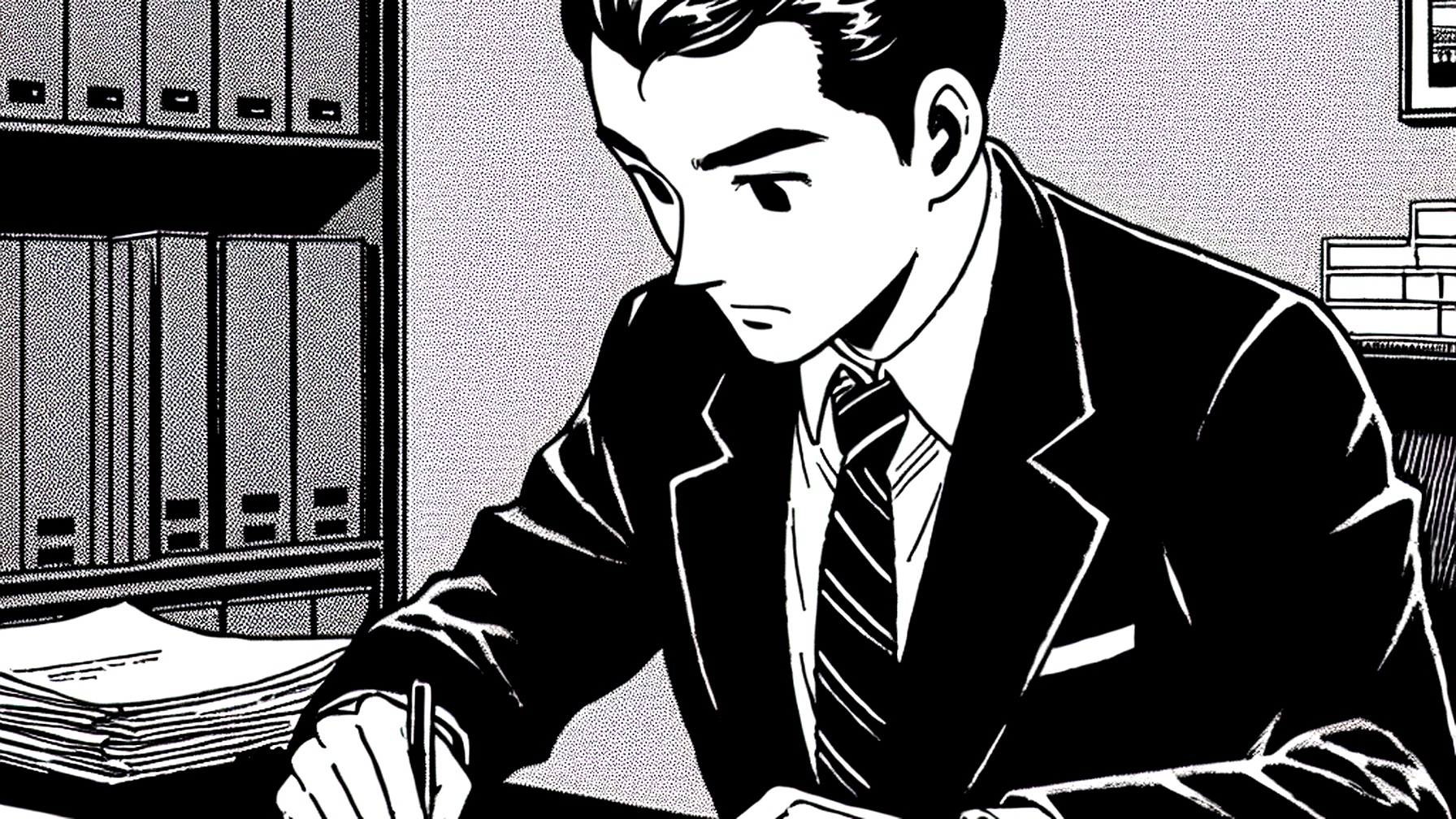
重要なのは、キャッシュフローを厳しめに試算する姿勢です。表面利回りだけで判断し、自己資金も少なくフルローンを組むと、金利上昇や修繕費の高騰に耐えられません。
たとえば、2%金利で8,000万円を35年返済した場合の毎月返済額は約26万円ですが、金利が3%に上がると3万円弱負担が増えます。空室が1室増えただけで収支が赤字化するケースも多く、アパート経営 失敗する人の半数以上が「返済に追われてリフォーム資金が捻出できない」という悪循環に陥っています。
実は、自己資金を物件価格の20%用意し、さらに家賃収入の半年分を予備費として確保すると、多くのトラブルを吸収できます。これは金融機関の融資審査でもプラスに働き、固定金利で0.2〜0.3%の優遇を受けられる可能性が高まるため、長期的なリスクヘッジにもなるのです。
空室対策と賃貸管理のリアル
ポイントは、空室リスクを“発生してから”ではなく“購入前”に織り込むことです。築古アパートは利回りが高く見えますが、入居募集に苦戦した途端に手残りが激減します。
リクルート住まい研究所の2024年調査では、入居者が物件を選ぶ基準として「インターネット無料」が62%と最多で、次いで「宅配ボックス」が48%でした。築20年以上でもこれらの設備を導入すれば、平均入居期間が1.4年延びたとのデータもあります。導入コストは1戸あたり10万円前後で済むケースが多く、長期の空室に比べれば負担は軽微です。
また、管理会社を選ぶ際は「募集力」と「維持管理力」を分けて評価する姿勢が求められます。募集はリーシング専門会社、日常管理は地元密着会社という分業も近年増えており、2025年時点で大手ポータルサイト掲載率が90%以上の会社は成約スピードが1.3倍という調査結果があります。こうした定量的指標で比較することで、感覚的な依頼先決定を避けられます。
税務と法規を軽視するリスク
実は、税務戦略を怠ると利益は簡単に目減りします。不動産所得は累進課税で、所得が900万円を超えると税率33%。減価償却を適切に計上しなければ、多額の税負担が発生します。
さらに、2025年度の相続税評価見直しでは、貸家建付地の評価減が一部縮小されました。節税目的でアパートを建てるだけでは評価額を十分に引き下げられないケースが増えています。税理士に相談し、青色申告特別控除65万円や小規模宅地等の特例を組み合わせて総合的にプランニングする必要があります。
法規面では、2024年4月に改正されたインボイス制度が賃貸事業にも影響を与えています。課税売上1,000万円超のオーナーは適格請求書発行事業者の登録が必須となり、対応を怠れば仕入税額控除が受けられません。こうした制度変更を追えていない人ほど資金繰りが悪化し、途中売却を余儀なくされる傾向が強いのです。
2025年の市場動向と成功のポイント
まず、2025年10月時点での大局観を整理しましょう。出生数の減少は続く一方で、単身世帯は増加しています。内閣府の「令和6年版高齢社会白書」によると、65歳以上単身世帯は2030年に900万世帯を超える見込みです。高齢単身者が望むのは、バリアフリーや地域医療が近い物件であり、都会のワンルームとはニーズが異なります。
そこで、エレベーターなしの3階建て木造アパートより、家賃を抑えた1階中心の平屋タイプや、駅近で設備を刷新したリノベーション物件が注目されています。国土交通省の「既存住宅流通促進事業」(2025年度)では、一定の耐震性と省エネ性能を満たすリフォームに対し、最大120万円の補助が継続中です。条件を満たせば工事費を圧縮でき、競争力向上に直結します。
また、ネット募集の主戦場がSNSに移りつつあり、短尺動画による内見代替が若年層に浸透しました。管理会社任せにせず、オーナー自身が物件の魅力を発信することで、入居決定率が2割向上した事例も報告されています。時代の変化を味方に付ける積極姿勢が、長期的な安定経営へとつながるでしょう。
まとめ
アパート経営 失敗する人の多くは、思い込みで物件を選び、資金計画を甘く見積もり、税務や法改正を後回しにしています。本記事で示したように、空室率や金利を厳しくシミュレーションし、設備投資と管理体制をデータで判断し、税務戦略を専門家と練るだけで失敗確率は大幅に下がります。今すぐできる行動は、保有物件のキャッシュフローを再計算し、管理会社の募集実績を数値で確認することです。小さな一歩が将来の大きな損失を防ぎ、安定した家賃収入への近道になると覚えておきましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年8月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 2025年7月 – https://www.boj.or.jp
- 内閣府 令和6年版高齢社会白書 – https://www8.cao.go.jp/kourei
- リクルート住まい研究所 2024年 賃貸契約者動向調査 – https://suumo.jp/edit/research
- 財務省 税制改正の概要 2025年度版 – https://www.mof.go.jp
- 中小企業庁 インボイス制度Q&A 2025年改訂版 – https://www.chusho.meti.go.jp

